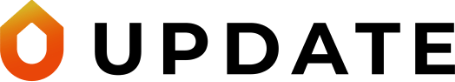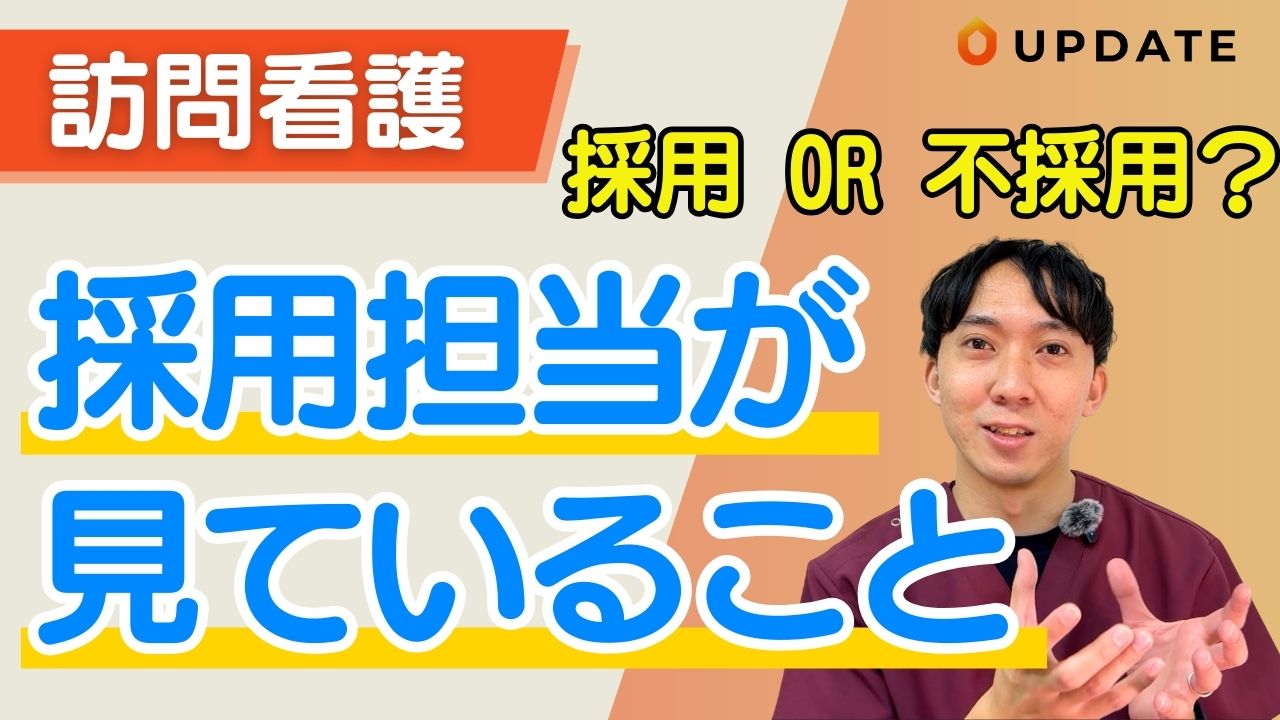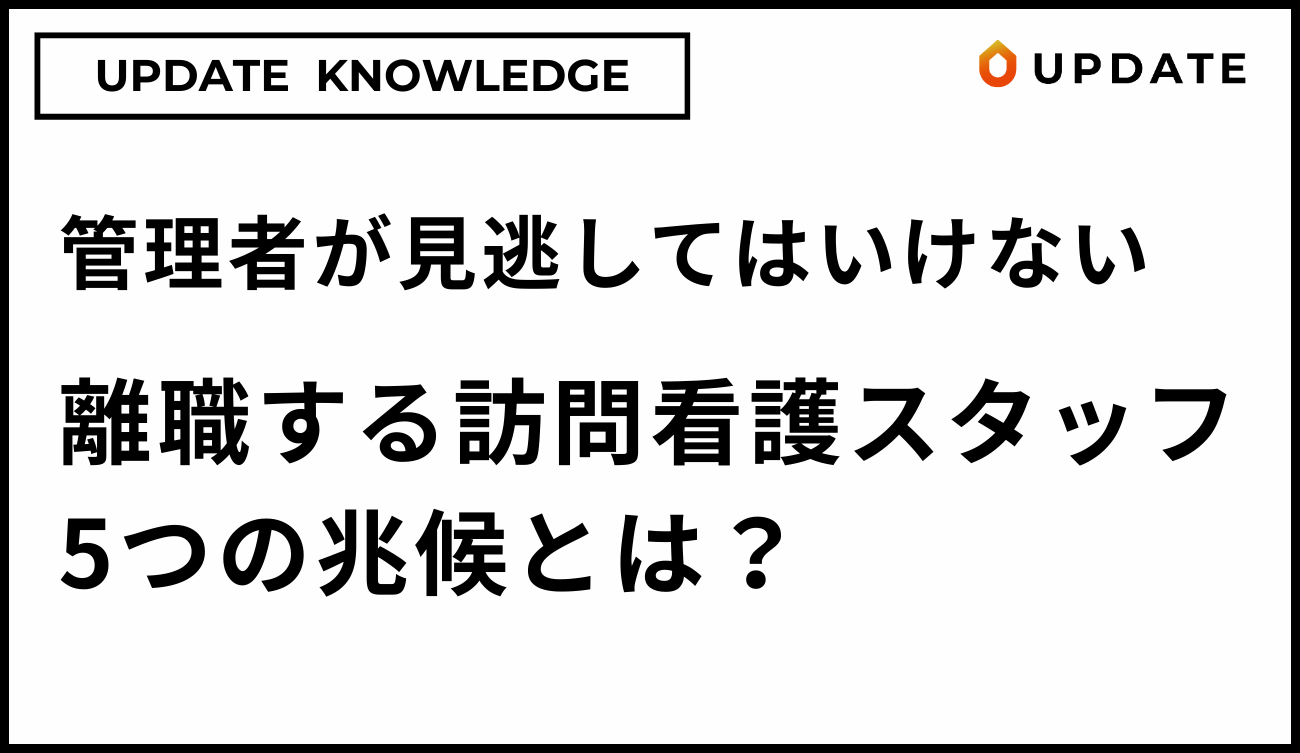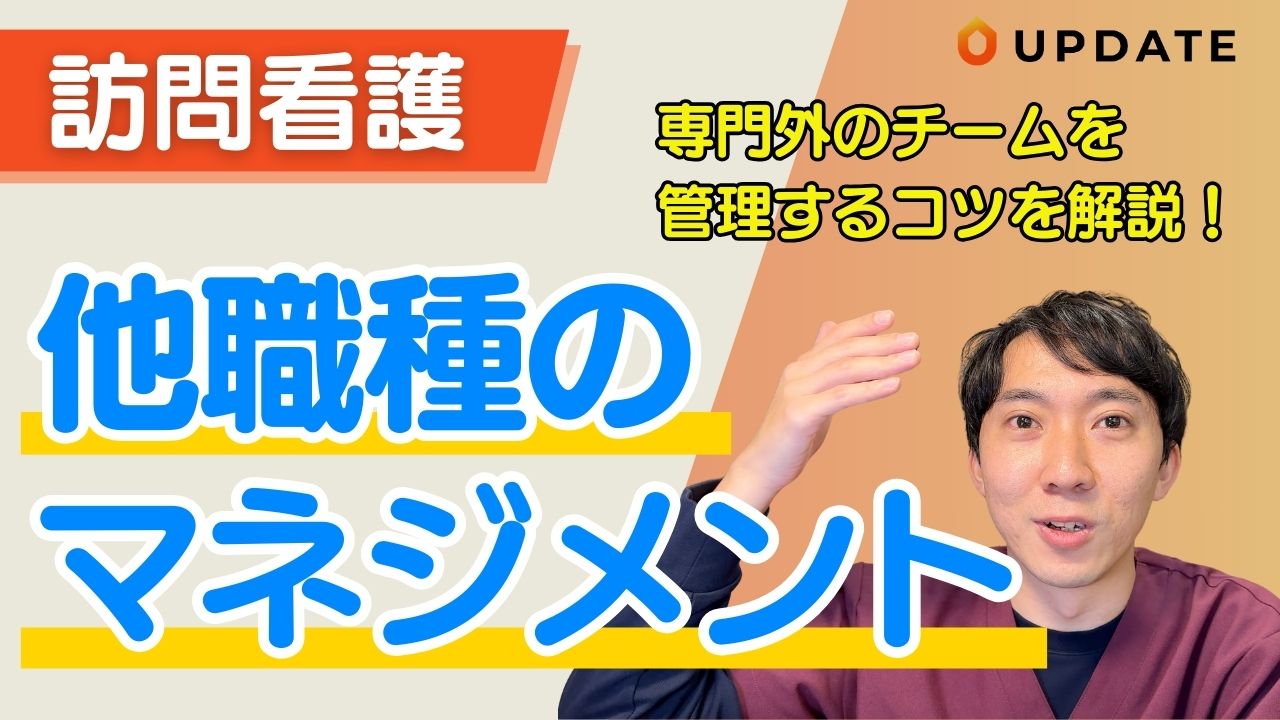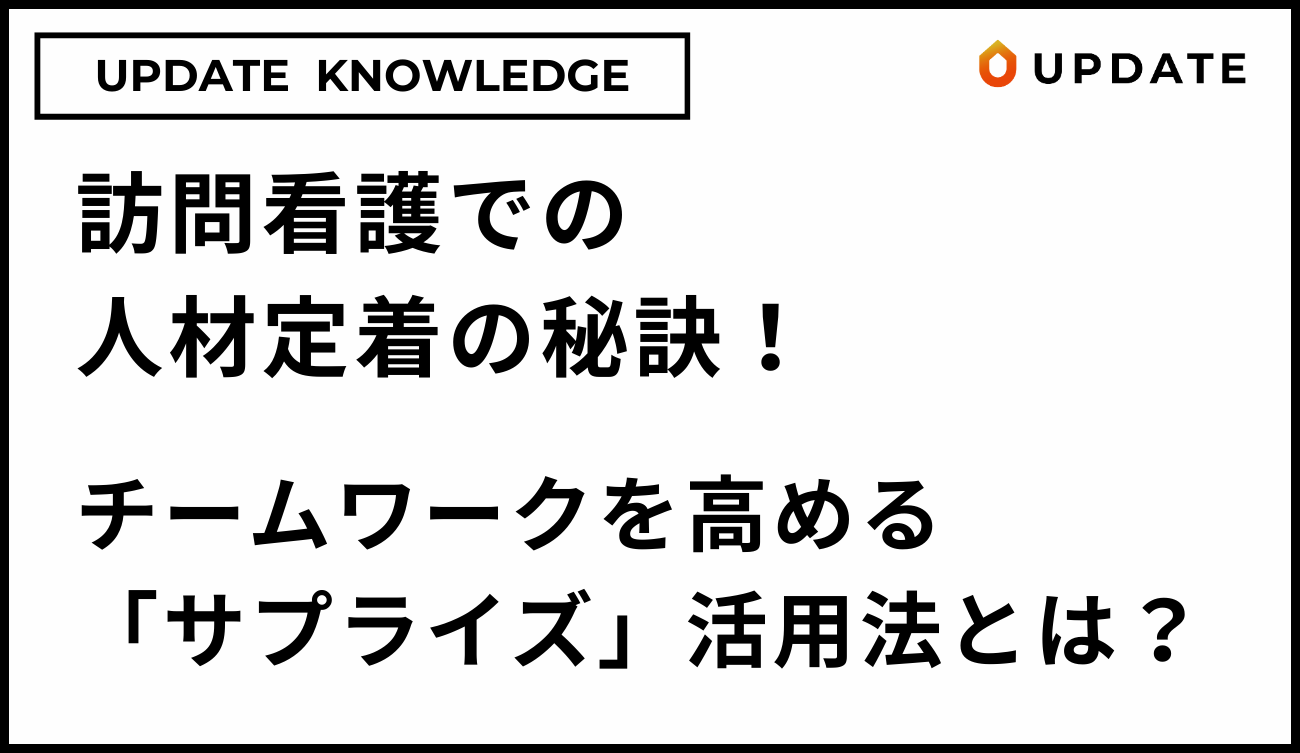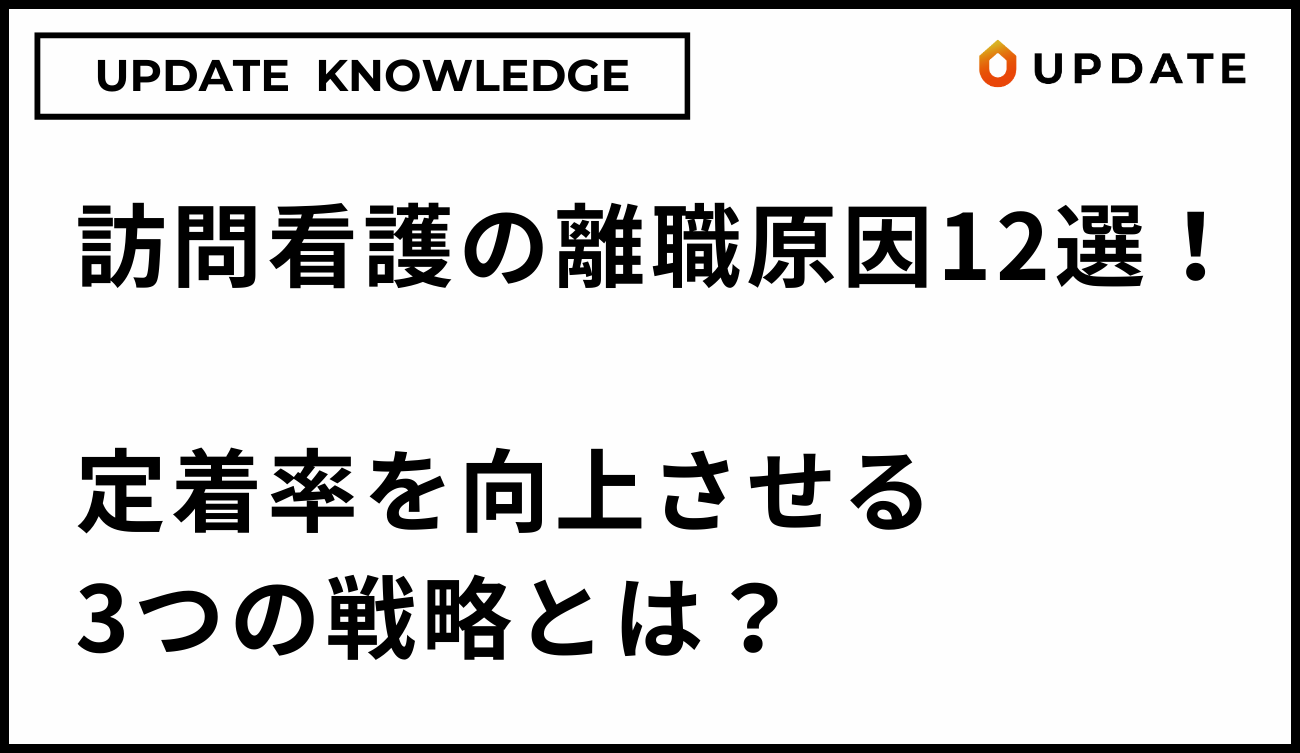訪問看護専門管理加算とは?算定要件・導入手順について解説
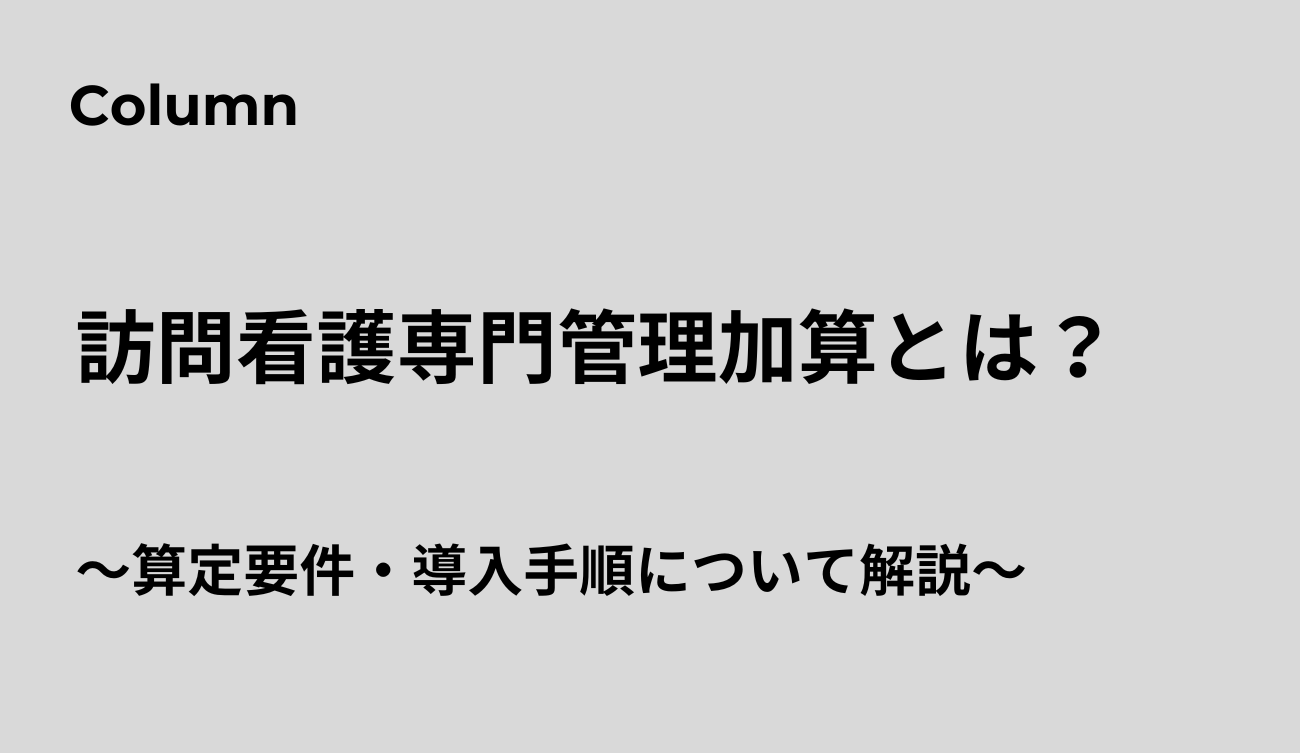
訪問看護における専門管理加算は、質の高いケア提供体制を構築し、より重度な医療ニーズに応えるための評価制度です。加算の取得には、専門性を有する看護師の配置や、適切な訪問・管理体制の整備、関係者への同意取得といった多角的な準備が求められます。また、加算制度の理解不足やスタッフの業務負担など、運用面での課題も見逃せません。
本記事では、専門管理加算の種類と要件、必要な体制整備、運用上の注意点までを網羅的に解説し、管理者・経営者が実務に活かせる視点で整理しています。

株式会社UPDATE 代表取締役(看護師・保健師・MBA) ケアプロ訪問看護ステーション東京にて新卒訪問看護師としてキャリアスタート。その後、訪問看護の現場・マネジメント経験の他、薬局や訪問看護運営するスタートアップ企業で40拠点・年商65億規模の経営を行い、上場企業へのグループインを実現。現在は医療職マネジメント人財を育成するためマネジメントスクールを運営中。
■経歴
2013年 慶應義塾大学 看護医療学部 卒業
2013年 ケアプロ株式会社入社
2019年 株式会社UPDATE(旧:ヘルスケア共創パートナー株式会社) 創業 代表取締役(現職)
2021年 GOOD AID株式会社 取締役(事業譲渡により退任)
2023年 セルフケア薬局 取締役(吸収合併により退任)
2023年 まちほけ株式会社 代表取締役(事業譲渡により退任)
■得意領域
医療系事業の組織マネジメント
教育体制構築
採用戦略・体制構築
教育体制構築
新卒訪問看護師の育成
管理職の育成
■保有資格・学位
看護師
保健師
経営学修士(MBA)
目次
訪問看護の専門管理加算とは

専門管理加算は、医療的ケアが必要な利用者様に対し、専門性の高い看護師が計画的に訪問管理を行う体制を評価するため、令和6年度介護報酬改定で新設された加算です。緩和ケアや褥瘡管理、人工肛門・膀胱ケアの専門研修を修了した看護師、または特定行為研修修了者が対象となり、一定の要件を満たすことで加算の算定が可能になります。
訪問看護ステーションの提供体制をより高度化し、在宅医療の質を維持・向上させるための重要な制度設計といえます。
参照:令和6年度介護報酬改定における改定事項について|厚生労働省
専門管理加算(イ)の算定要件と対象利用者様
専門管理加算(イ)は、緩和ケアや褥瘡ケア、人工肛門・人工膀胱ケアに専門的な研修を受けた看護師が、対象となる利用者様に対して計画的な管理を実施した場合に算定できる加算です。月1回の加算が認められており、単位数は250単位と設定されています。訪問看護ステーションにおける専門性の高いサービス提供を促進し、医療的ケアの質的向上と継続的支援体制の確保を目的としています。
算定要件
加算を受けるには、当該ケア領域において厚生労働省が定めた専門研修を修了している看護師が、月1回以上の頻度で訪問し、計画的な管理を実施していることが必要です。
ここでの「計画的管理」には、状態変化の予測に基づくケア計画の策定や、再発予防を見据えた継続的な観察・記録が含まれます。ステーション全体での連携体制と情報共有も加算算定の持続には不可欠です。
算定対象者
対象となる利用者様は、次のいずれかに該当する方です。
・悪性腫瘍の鎮痛療法または化学療法を受けている方
・真皮を超える褥瘡のある方(もしくは真皮までの褥瘡で在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定している方)
・人工肛門や人工膀胱の周囲にびらん等の皮膚障害が持続的・反復的に生じている方
・その他、人工肛門または人工膀胱に関連する合併症を有する方
これらに該当するケースでは、専門管理加算(イ)の要件に基づき、適切な申請と運用体制の整備が求められます。
専門管理加算(ロ)の算定要件と対象利用者様
専門管理加算(ロ)は、特定行為研修を修了した看護師が、医師の指示に基づく「手順書」に従い、特定の医療的ケアを要する利用者様に対して計画的な管理を実施した場合に算定される加算です。月1回、250単位が加算されるしくみであり、高度な医療管理を地域で支える体制づくりを後押しする評価項目です。
算定要件
この加算を算定するには、厚生労働大臣が指定する研修機関で定められた「特定行為研修」を修了した看護師が、訪問看護の現場において「手順書」に準拠した管理を行っていることが条件です。
対象となる研修には、在宅・慢性期領域パッケージ研修を含み、呼吸器管理・ろう孔管理・創傷管理・輸液管理に関連する内容が含まれます。手順書の記載内容には、対象となる病状や実施内容、報告・連絡体制などが明記されている必要があります。
算定対象者
算定対象となるのは、医師または歯科医師が交付した手順書に基づき、次のいずれかの特定行為を必要とする利用者様です。
・気管カニューレ、胃ろう・腸ろうカテーテル、膀胱ろうカテーテルの交換
・褥瘡や慢性創傷の壊死組織の除去
・陰圧閉鎖療法
・高カロリー輸液の投与量調整
・脱水に対する補液管理
これらのケアが定期的に必要な方に対し、専門管理加算(ロ)を適切に活用することで、在宅医療体制の質と安全性を両立することが可能となります。
専門性の高い看護師の定義と確保戦略
専門管理加算を適切に算定するには、加算対象となる「専門性の高い看護師」を計画的に確保・配置する必要があります。以下では、専門性の要件、採用市場の動向、社内育成の具体策について整理します。
専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了者の要件整理
専門性の高い看護師には、特定行為研修修了者、専門看護師、認定看護師、ならびに緩和ケアや褥瘡ケア等に特化した研修修了者が該当します。特定行為研修修了者は、一定の実務経験と厚労省指定研修機関での研修受講が必要です。
専門看護師は大学院修士課程での単位取得と実務経験が条件で、がん看護や在宅看護など14分野で活躍しています。認定看護師は5年以上の実務経験に加え、A課程(2026年度まで)またはB課程の修了が要件とされ、多様な専門領域に対応しています。
採用市場動向と人材紹介サービス活用策
専門性を備えた看護師は全国的に希少であり、採用競争は年々激化しています。特に訪問看護分野では、特定行為研修修了者の確保が難航しやすく、即戦力人材を求める事業所が増加しています。採用戦略としては、専門職に特化した人材紹介サービスの活用が有効です。
求人要件の明確化と研修支援体制の提示は、転職希望者への訴求力を高めます。また、紹介会社と連携し、選考時に専門分野の実務経験や資格取得状況を事前確認することで、ミスマッチ防止につながります。
関連記事:訪問看護マネジメントでの「採用力」とは?適切な人材を見極める3つのポイントを徹底解説!
既存スタッフ育成と研修費用計画
中長期的な視点では、既存スタッフの育成が最も安定した人材確保策となります。加算要件を踏まえ、特定行為研修や日本看護協会が主催する専門研修への受講支援を制度化することが求められます。業務調整による学習時間の確保や研修費用の法人負担は、職員のモチベーション維持にも直結します。
また、国や自治体が提供する研修費補助制度の活用も有効です。人材育成を経営戦略の一部として位置付けることで、組織全体の専門性が底上げされ、持続的な加算取得にもつながります。
「しっかり組織マネジメントの基礎を学びたい!」という方向けに、UPDATEでは『訪問看護特化の組織マネジメント基礎講座』を開催しています。無料の体験クラス動画もご用意してますので、興味のある方はぜひご覧ください。
無料体験クラス「組織に合わない言動を放置する悪影響と、効果的なフィードバック」
加算取得までの準備フロー

専門管理加算の取得にあたっては、ステーションの体制整備から自治体への届出、利用者様への説明・同意取得まで、段階的な準備が求められます。以下では、加算取得に必要な運用準備の流れを3つの視点で解説します。
体制基準ギャップ分析と改善スケジュール
加算取得の第一歩は、現状の体制と基準とのギャップを把握することです。対象となる看護師の配置状況や研修修了実績、訪問頻度や記録体制など、基準と照らし合わせながら確認を進めます。
見落とされやすいのが、管理的支援や報告フローといった裏方業務の整備です。ギャップが明らかになった時点で、計画的な改善スケジュールを作成し、各業務の責任者を明確にしたうえで運用を始めると、申請の段階でも混乱が生じにくくなります。
自治体提出書類一覧と作成ポイント
加算取得には、自治体への届出書類の提出が必須です。提出書類には、訪問看護事業所指定申請書、介護給付算定にかかる体制届出書、事業所の体制や研修実績に関する様式などが含まれます。
これらは厚生労働省や各自治体のサイトからダウンロードが可能で、記入漏れや記載ミスがあると差し戻しの対象となるため、ダブルチェック体制の構築が重要です。また、書類作成時には「計画的な管理内容」や「看護師の配置根拠」を具体的に記載することで審査がスムーズになります。
利用者様同意取得と計画書作成の流れ
加算を算定するには、加算内容を利用者様やご家族に丁寧に説明し、同意書を取得するプロセスが欠かせません。特に専門管理加算では、看護師の専門性や実施内容に対する理解を得たうえで、ケアマネージャーとも連携して訪問看護計画書を作成する必要があります。
同意取得時には専門用語の多用を避け、図解や具体例を用いた説明が有効です。計画書作成後は、主治医からの指示書を受け取り、サービス担当者会議などで内容を共有しながら、実施に向けた運用体制を整えます。
加算取得時によくある課題と解決策

専門管理加算の取得には、多様な体制整備とスタッフの意識統一が求められますが、現場では人材や業務バランス、情報共有に関する課題が発生しやすい傾向があります。以下では、事業運営において直面しやすい3つの実務課題とその対処法を整理します。
専門性を有する看護師が少ない事業所の対応策
専門管理加算の要件を満たすには、特定行為研修や専門領域研修を修了した看護師の配置が必須です。しかし、特に中小規模のステーションでは該当人材が不在、あるいは配置数が不足しているケースも多く見受けられます。
解決策としては、専門性を有する看護師の採用を長期目標に据えつつ、短期的には外部研修機関との提携や自治体補助金の活用を進めることが現実的です。また、すでに在籍する看護師のスキルアップ計画を明文化し、組織全体で研修受講を支援する体制を構築することが重要です。
教育時間確保と訪問件数維持の両立
研修受講や加算に伴う記録・管理業務が増えることで、スタッフの稼働時間が圧迫され、訪問件数が維持できないという課題も生じます。これに対応するためには、勤務シフトの見直しと、繁忙期に備えた代替支援体制の整備が有効です。
具体的には、研修日は事前に予定として確保し、他スタッフとの連携で業務を分担する仕組みを設けます。また、記録業務についてはICTシステムの導入やテンプレート化を進めることで、業務の標準化と時間短縮が可能となります。
スタッフ理解促進とモチベーション管理
加算取得は管理者だけでなく、現場スタッフ全員の理解と協力が不可欠です。しかし、制度の内容や業務増加に対する懸念から、職員の間に温度差が生まれることもあります。この対策として、加算に関する勉強会を定期的に実施し、制度の意義や現場への影響、得られるメリットを具体的に共有することが大切です。
さらに、研修受講者や積極的に取り組むスタッフへの評価制度を導入することで、モチベーションを維持・向上させ、加算運用の定着につなげていくことが期待されます。
まとめ
専門管理加算の取得は、看護の専門性を可視化し、訪問看護ステーションの信頼性やサービスの質を向上させる大きな機会です。一方で、要件の複雑さや人材確保の課題に直面する事業所も少なくありません。加算制度の正確な理解と、全体最適を意識した組織設計が運用の鍵となります。制度対応を通じて現場の専門性強化と経営の安定を両立させることが重要です。
UPDATEでは、訪問看護での実践的なマネジメントが学べる『訪問看護マネジメントスクール』を提供しております。経営マネジメントに関してお悩みの方は、ぜひお気軽にお問合せください。