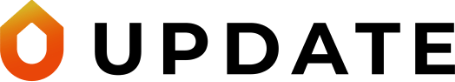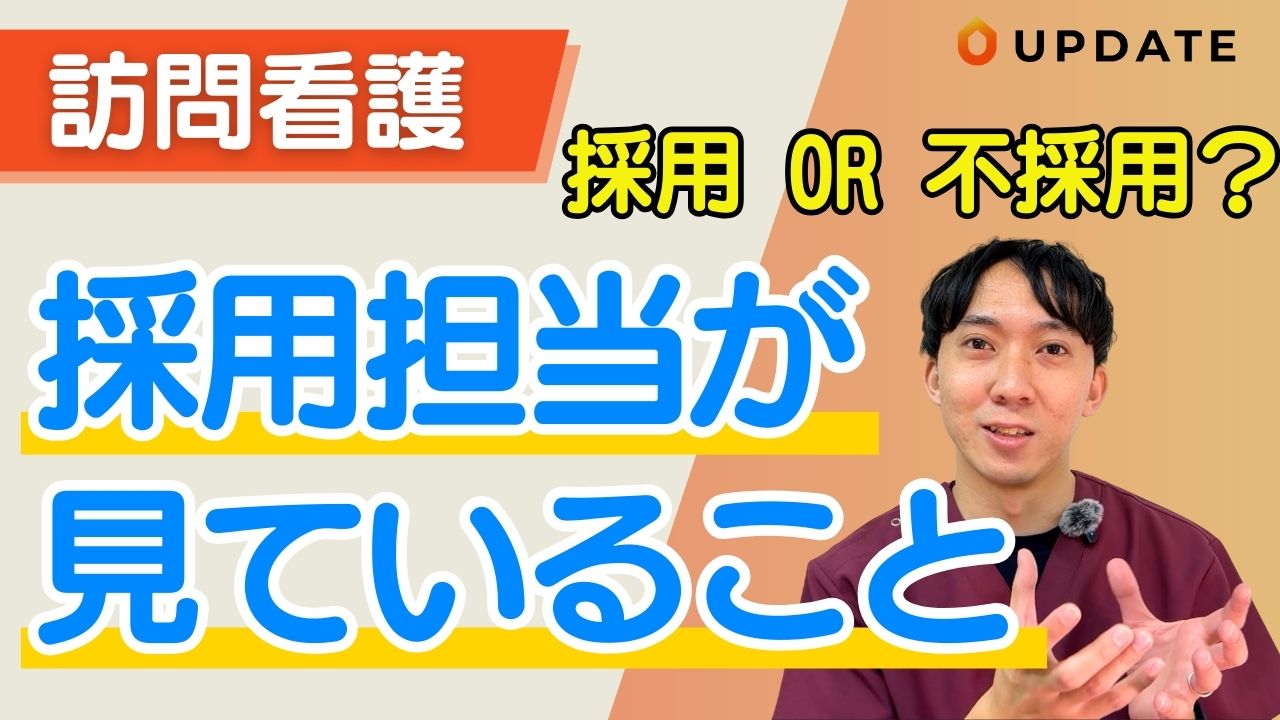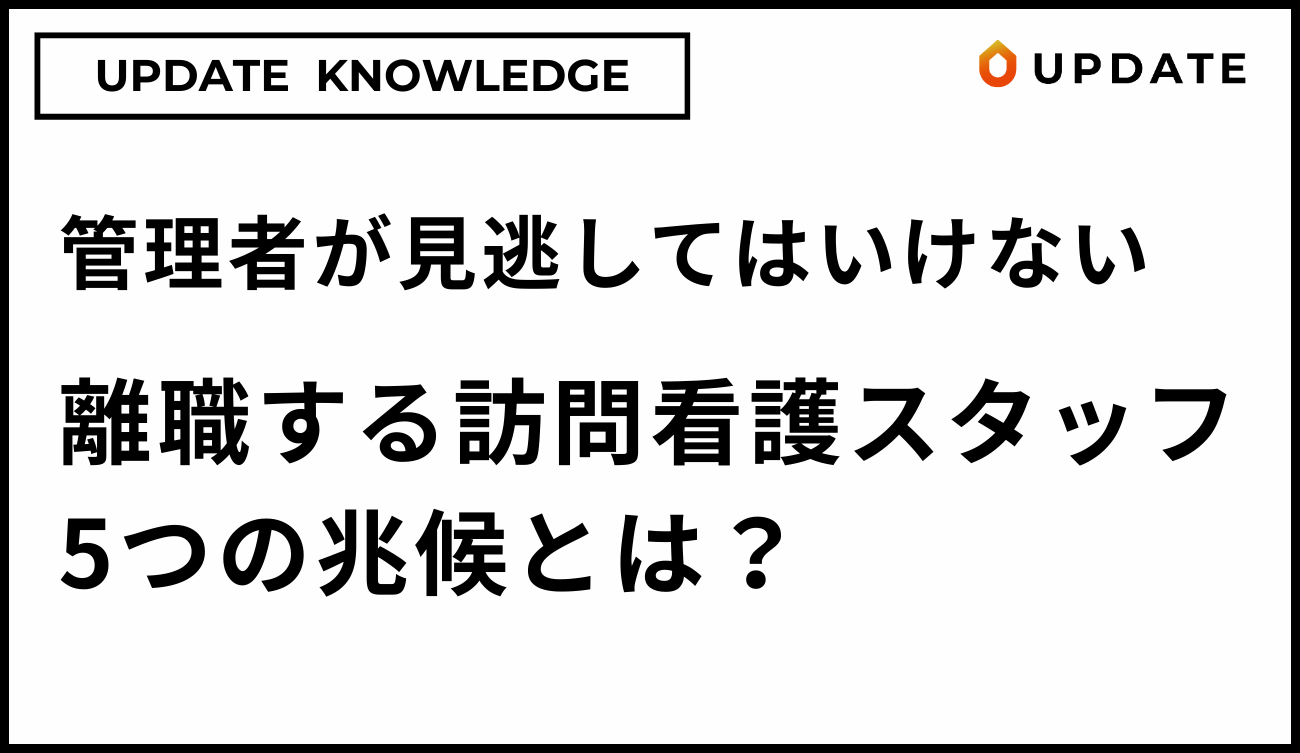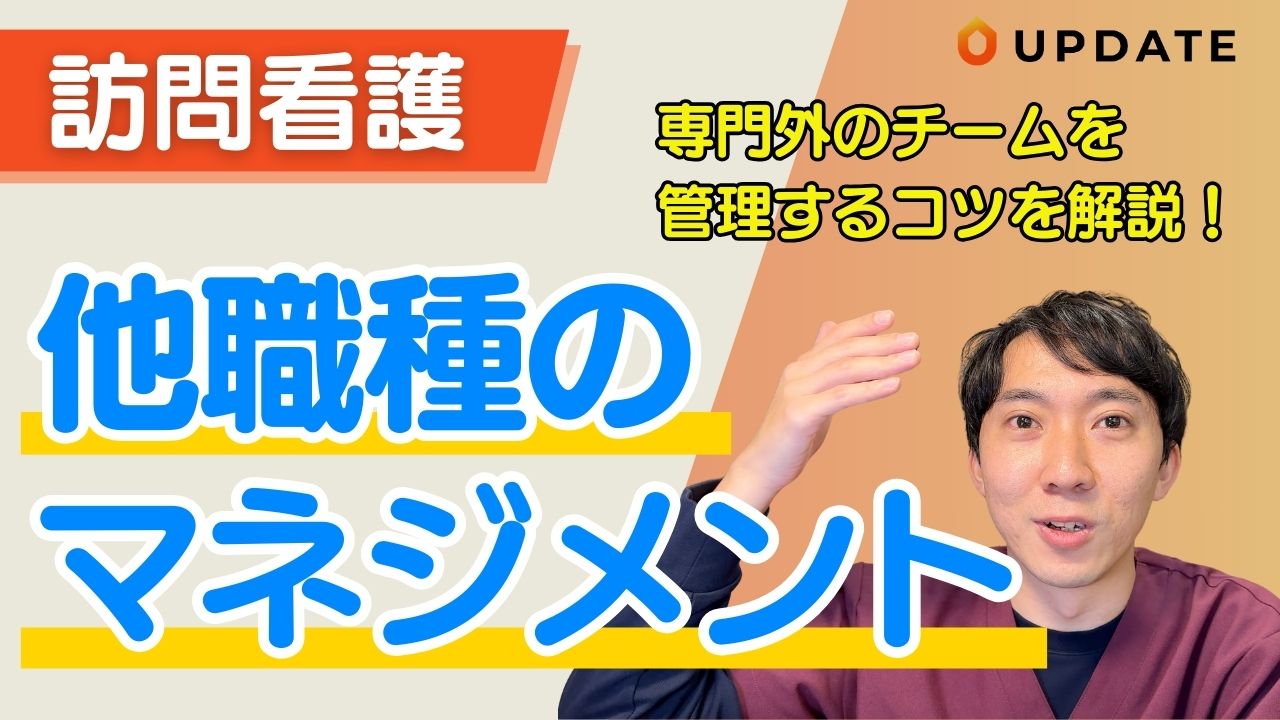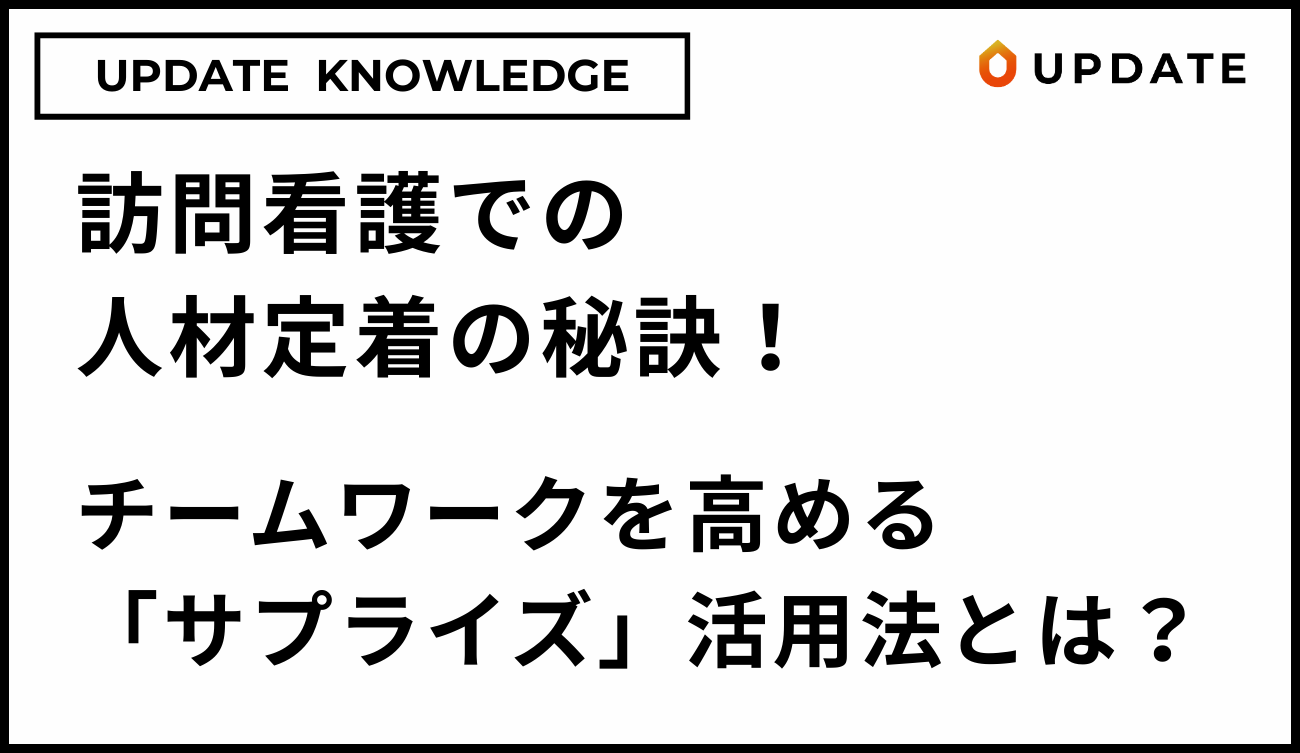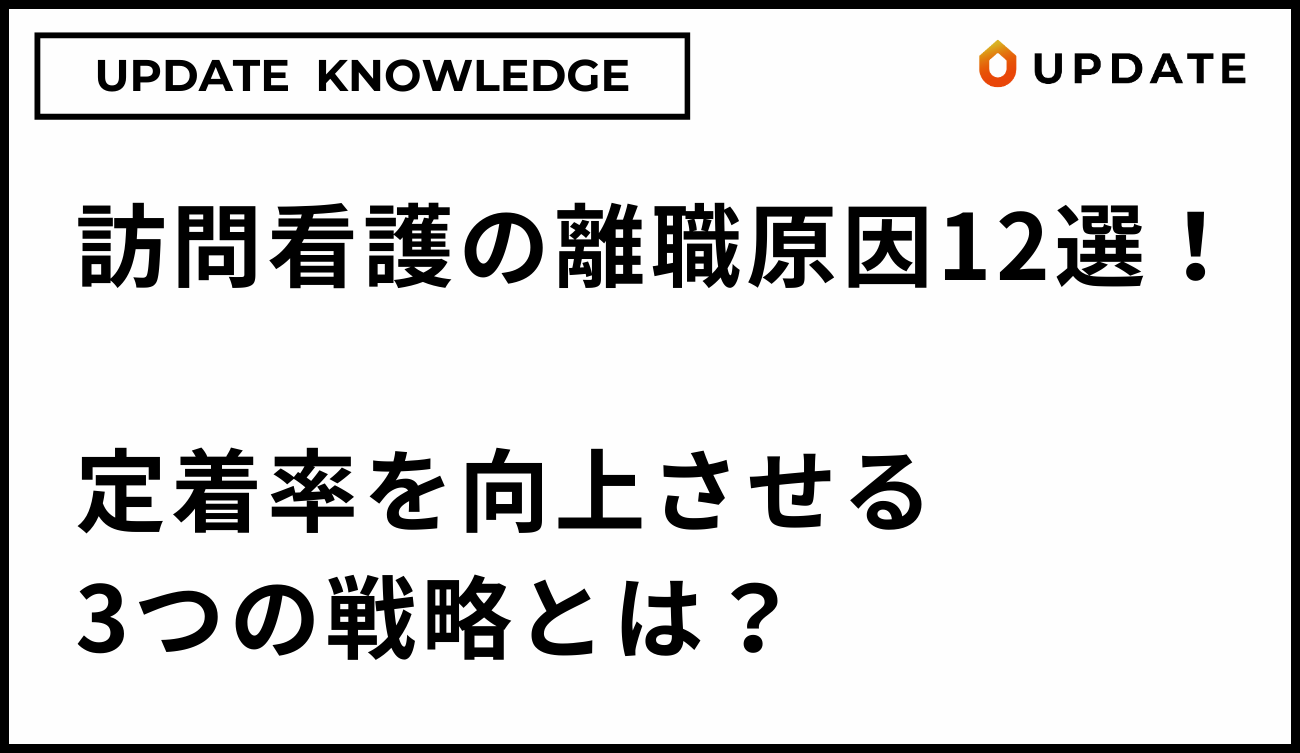機能強化型訪問看護ステーションとは?管理療養費1・2・3について
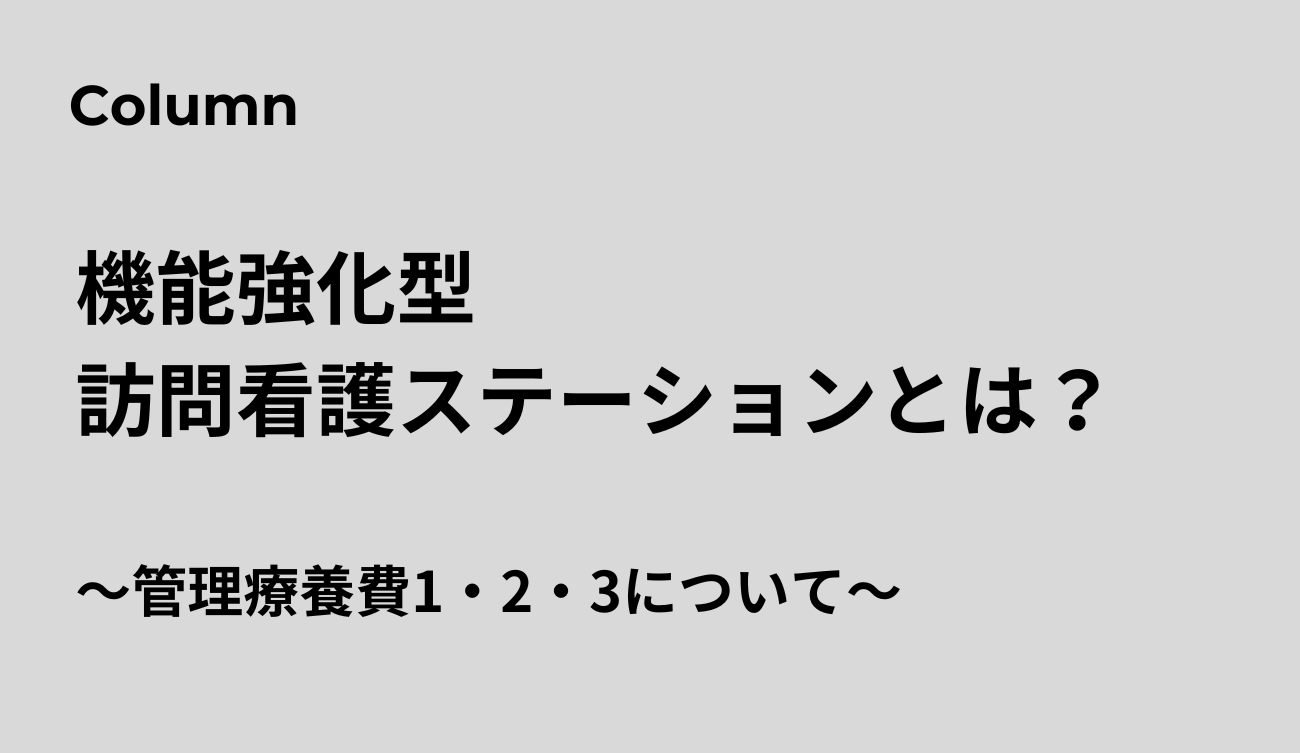
地域包括ケアの中核を担う訪問看護において、機能強化型ステーションへの移行は、今後の運営を左右する重要な戦略のひとつです。2025年、さらには2040年に向けて在宅療養者の増加が確実視される中、高度なケアへの対応力と持続可能な体制構築が求められています。
機能強化型訪問看護管理療養費の算定には複数の要件が存在し、それらを段階的に整備していくことが必要不可欠です。本記事では、各療養費区分の要件から、体制整備、届出の実務対応、さらには経営的なメリットに至るまで、管理者・経営者視点で整理・解説いたします。

株式会社UPDATE 代表取締役(看護師・保健師・MBA) ケアプロ訪問看護ステーション東京にて新卒訪問看護師としてキャリアスタート。その後、訪問看護の現場・マネジメント経験の他、薬局や訪問看護運営するスタートアップ企業で40拠点・年商65億規模の経営を行い、上場企業へのグループインを実現。現在は医療職マネジメント人財を育成するためマネジメントスクールを運営中。
■経歴
2013年 慶應義塾大学 看護医療学部 卒業
2013年 ケアプロ株式会社入社
2019年 株式会社UPDATE(旧:ヘルスケア共創パートナー株式会社) 創業 代表取締役(現職)
2021年 GOOD AID株式会社 取締役(事業譲渡により退任)
2023年 セルフケア薬局 取締役(吸収合併により退任)
2023年 まちほけ株式会社 代表取締役(事業譲渡により退任)
■得意領域
医療系事業の組織マネジメント
教育体制構築
採用戦略・体制構築
教育体制構築
新卒訪問看護師の育成
管理職の育成
■保有資格・学位
看護師
保健師
経営学修士(MBA)
機能強化型訪問看護とは

機能強化型訪問看護とは、在宅療養を必要とする重症度の高い利用者様や、急変リスクを抱える方への迅速な支援を目的に、質の高い医療的ケア体制を強化した訪問看護ステーションの形態です。
24時間対応や緊急訪問体制の整備、多職種との連携体制を含めて、地域での看護提供体制を支える役割が求められます。制度上は、機能強化型訪問看護管理療養費のⅠ〜Ⅲいずれかを算定可能とするための要件を満たす必要があります。
機能強化型訪問看護ステーションの要件等
以下が「機能強化型訪問看護ステーション」の要件です。
| 機能強化型1 | 機能強化型2 | 機能強化型3 | |
| ターミナルケアの実施や、重症児の受入れ等を積極的に行う手厚い体制を評価 | 地域の訪問看護の人材育成等の役割を評価 | ||
| 月の初回の額 | 13,230円 | 10,030円 | 8,700円 |
| 看護職員の数・割合 | 常勤7人以上(1人は常勤換算可)、6割以上 | 5人以上(1人は常勤換算可)、6割以上 | 4人以上、6割以上 |
| 24時間対応 | 24時間対応体制加算の届出 + 休日、祝日等も含めた計画的な訪問看護の実施 | ||
| 重症度の高い利用者の受入れ | 別表7の利用者 月10人以上 | 別表7の利用者 月7人以上 | 別表7・8の利用者、精神科重症患者又は複数の訪看STが共同して訪問する利用者 月10人以上 |
| ターミナルケアの実施、重症児の受入れ | 以下のいずれか・ターミナル 前年度20件以上・ターミナル 前年度15件以上+ 重症児 常時4人以上・重症児 常時6人以上 | 以下のいずれか・ターミナル 前年度15件以上・ターミナル 前年度10件以上+ 重症児 常時3人以上・重症児 常時5人以上 | ー |
| 介護・障害サービスの計画作成 | 以下のいずれか・居宅介護支援事業所を同一敷地内に設置+特に医療的な管理が必要な利用者の1割程度について、介護サービス等計画又は介護予防サービス計画を作成・特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所を同一敷地内に設置+サービス等利用計画又は障害児支援利用計画の作成が必要な利用者の1割程度について、計画を作成 | ー | |
| 地域における人材育成等 | 以下のいずれも満たす・人材育成のための研修等の実施・地域の医療機関、訪問看護ステーション、住民等に対する情報提供又は相談の実績 | 以下のいずれも満たす ・地域の医療機関や訪看STを対象とした研修年2回 ・地域の訪看STや住民等への情報提供・相談の実績 ・地域の医療機関の看護職員の一定期間の勤務実績 | |
| 医療機関との共同 | ー | ー | 以下のいずれも満たす・退院時共同指導の実績・併設医療機関以外の医師を主治医とする利用者が1割以上 |
| 専門の研修を受けた看護師の配置 | 専門の研修を受けた看護師が配置されていること | 専門の研修を受けた看護師が配置されていること(望ましい) | |
[経過措置]令和6年3月31日において現に機能強化型訪問看護管理療養費1に係る届出を行っている訪問看護ステーションについては、令和8年5月31日までの間に限り、専門の研修を受けた看護師の配置に係る基準に該当するものとみなす。
機能強化型訪問看護管理療養費1の算定要件
機能強化型訪問看護管理療養費1の算定を目指すには、訪問看護ステーションとしての提供体制を高水準で整備する必要があります。まず、常勤換算で看護職員7名以上(うち6名は常勤)を確保し、看護職員比率を60%以上とする人員体制が基本要件となります。加えて、24時間対応体制加算の届出を行い、緊急時の支援体制を構築しておくことが前提です。
その上で、ターミナルケアや重症児への対応実績、別表7該当利用者の一定数以上の受け入れ、地域との連携や相談支援実績、さらに人材育成に関する研修の実施が求められます。また、営業日外でも訪問看護が提供可能な体制整備と、専門研修を修了した看護師の配置も評価対象です。
機能強化型訪問看護管理療養費2の算定要件
機能強化型訪問看護管理療養費2を算定するには、一定の基準を満たした提供体制と実績が必要です。まず、看護職員数は常勤換算で5人以上(うち常勤職員が4人以上)、かつ看護職員比率が60%以上であることが求められます。また、24時間対応体制加算の届出を行っていることが前提となります。
加えて、前年度のターミナルケア件数が15件以上、もしくは10件以上かつ重症児利用者が常時3人以上、または重症児が5人以上在籍していることが条件となります。該当する利用者も月平均7人以上確保が必要です。さらに、居宅介護支援事業所や相談支援事業所との協働実績、地域への情報提供、人材育成のための研修実施といった地域貢献の姿勢も求められます。
機能強化型訪問看護管理療養費3の算定要件
機能強化型訪問看護管理療養費3は、訪問看護の地域的役割や人材育成の視点が重視された区分であり、比較的柔軟な要件で算定が可能です。常勤の看護職員を4人以上確保し、うち看護職員の割合を6割以上に保つことが基本条件です。加えて、24時間対応体制加算の届出を行い、緊急対応力のある運営体制を整備することが求められます。
その上で、地域における情報提供や相談支援の実績、年2回以上の研修実施、地域の保健医療機関職員の勤務受け入れ実績、共同訪問や退院支援の加算件数など、地域連携と教育機能が問われます。また、敷地内に医療機関がある場合は、主治医の偏りを避けた運用も必要です。
機能強化型移行で得られる経営メリット

機能強化型訪問看護ステーションへ移行することで、経営基盤の強化と地域内での存在価値向上を両立できます。以下では、具体的な4つの観点から得られるメリットについて解説します。
サービス拡大による利用者様支援機会
機能強化型への移行は、受け入れ可能な利用者様の幅を広げる大きな契機となります。とくに、ターミナルケアや医療的ケアが必要な重症児など、高度な支援を要する方への対応力が強化されるため、他ステーションとの差別化が可能です。
対応領域が広がることで、医師やケアマネージャーからの紹介数が増え、支援機会の拡充につながります。結果として、地域で支援を必要とする層に対する受け皿としての機能を果たし、ステーションとしての社会的意義がより明確になります。
地域内での信頼性と連携強化効果
地域内での認知と信頼の獲得は、経営的にも継続性を左右する重要な要素です。機能強化型として届出を行うことで、地域の保険医療機関や他の訪問看護ステーションとの多職種連携が強化され、対外的な信頼性が高まります。
情報提供や研修の開催などを通じて、地域医療の中での役割が明確化され、安定した紹介ルートが築かれます。特に二次医療圏での機能強化型配置が進む中で、地域連携の中核として評価されることは、長期的な経営視点からも大きな優位性となります。
人材採用・定着促進に与える影響
人材の確保と定着は、多くの訪問看護ステーションにとって共通の課題です。機能強化型への移行により、質の高いケアを提供する職場であることを内外に示すことができ、採用面での訴求力が向上します。
研修制度の整備や専門性を高められる環境は、職員のモチベーションや定着率にも良い影響を与えます。また、管理療養費の加算による原資確保は、給与面での改善や業務環境の整備にも反映されやすく、組織としての魅力が高まります。
収入構造安定化と投資回収シミュレーション
収入面では、機能強化型訪問看護管理療養費の算定により、通常よりも高い報酬単価を確保できます。たとえば、月初回の訪問時における療養費は、通常型に比べて最大5,000円以上の差が生まれるため、利用者様数に比例して収益が積み上がる構造です。
これにより、人件費や広告費といった固定コストへの投資に対しても、回収計画を立てやすくなります。特に中長期の視点で見た場合、稼働率の変動に対する耐性が向上し、経営の安定性が強化されることが期待されます。
訪問看護ではスタッフや組織のマネジメントがとても重要です。
ぜひ以下から無料のマネジメント講座もご視聴ください。
訪問看護特化の『組織マネジメント基礎講座』
無料体験クラス「組織に合わない言動を放置する悪影響と、効果的なフィードバック」
要件達成に向けた組織体制の整え方
機能強化型訪問看護ステーションへの移行を成功させるには、制度上の算定要件を満たすだけでなく、それを支える体制構築が不可欠です。以下では、採用・教育・体制構築・研修の4つの視点から、組織整備の具体的な取り組み方を整理します。
看護職員採用・育成の考え方
機能強化型の要件を満たすためには、看護職員の常勤配置や専門性の確保が前提となります。特に、精神科や重症児対応が可能な人材や、専門研修修了者の配置が求められるケースも多く、人材の採用段階から明確な選考基準と人材要件を定めておく必要があります。
育成面では、訪問看護における初期教育と継続研修を分けて設計し、スキル向上と定着率を両立させる工夫が重要です。キャリアパスの提示や、外部研修への参加支援も、職員の成長意欲を引き出す要素になります。
関連記事:訪問看護マネジメントでの「採用力」とは?適切な人材を見極める3つのポイントを徹底解説!
24時間対応体制構築ステップ
24時間対応体制の確保は、機能強化型の届出要件の中でも中心的な項目です。体制整備には、看護師のシフト計画、オンコール業務の負荷分散、緊急時対応マニュアルの整備が求められます。
まずは、夜間・休日を含めた年間稼働スケジュールを作成し、無理のないローテーションを設計することが優先されます。また、ICTを活用したリアルタイムの連絡体制と情報共有手段の導入により、質を担保した夜間訪問が可能となります。加えて、対応履歴を蓄積しPDCAを回すことで、継続的な運用改善にもつながります。
ICT活用と記録・情報連携強化
機能強化型ステーションでは、記録の正確性と情報連携の速さが運営効率と利用者支援の質を左右します。電子カルテや訪問スケジュール管理システムの導入は、記録の効率化だけでなく、外部連携にも好影響を与えます。
例えば、オンコール対応中の看護師がタブレット端末から利用者情報を即時に確認できれば、判断や報告の精度が向上します。訪問看護計画書や報告書の共有もクラウド上で行うことで、医師やケアマネージャーとの連携もスムーズになります。これらの仕組みは、運営全体の見える化にも貢献します。
外部研修と学習機会確保
訪問看護職員が持続的に成長できる環境整備も、組織の安定運営には欠かせません。特に、機能強化型の要件では地域への研修提供や実習受入の実績も評価対象となるため、内部研修に加えて外部との協働も意識する必要があります。
具体的には、地域の医療機関や大学と連携し、学生や若手職員の受入体制を整えること、地域住民や関係職種への公開研修の開催が挙げられます。また、専門研修受講に対する勤務調整や費用補助といった制度設計も、人材の定着やスキルアップの促進に寄与します。
関連記事:訪問看護の法定研修について徹底解説!
届出から運用までの実務フロー

機能強化型訪問看護管理療養費の算定を目指すうえでは、届出から実運用までを見据えた計画的な準備が求められます。以下では、必要書類の準備から体制構築、モニタリング、監査対応まで、実務フローの各段階における留意点を整理します。
地方厚生局への届出書類準備
機能強化型訪問看護管理療養費の届出は、厚生労働省が指定する様式に沿って作成し、ステーション所在地を管轄する地方厚生局に期日までに提出する必要があります。
令和6年度の例では、提出期間が5月2日~6月3日とされており、郵送やメール提出時のファイル名や件名の指定にも注意が必要です。届出様式は複数存在し、申請区分(機能強化型1・2・3等)ごとに使い分けが求められるため、提出前の精査が不可欠です。
内部チェックリストとスケジュール管理
届出準備の段階では、要件該当状況や添付書類の有無を確認する内部チェックリストの活用が有効です。特に看護職員数、研修実績、地域連携の記録など、要件証拠の明文化が重要になります。提出期限から逆算したスケジュールを作成し、法人内の複数部署との連携やリマインド体制を整備することで、抜け漏れのない準備が可能になります。
算定開始後のモニタリング指標
算定開始後は、各要件の継続的な充足を確認する仕組みが必要です。たとえば、別表7・8該当利用者数の月次確認や、ターミナルケア件数、情報提供・研修実施状況など、定量的な指標を設定し、定例会議等で進捗管理を行います。要件から外れた場合のリスク対応計画も、あらかじめ準備しておくことで安定運営に寄与します。
監査・指導に備える社内体制
機能強化型の届出後は、地方厚生局や指導監査課からの実地確認や資料提出を求められる場合があります。そのため、記録・帳票類の保管ルールを明文化し、業務日報や実績報告書の整備を徹底することが重要です。特に加算算定に関する根拠資料は、いつでも提出できるよう電子化やフォルダ管理を行うと対応力が高まります。
まとめ
機能強化型訪問看護への移行は、単なる届出業務にとどまらず、職員体制、連携構築、ICT活用、教育機会の確保など多方面にわたる体制整備が求められます。一方で、地域での信頼獲得や収入基盤の安定、採用強化といった多くの経営的メリットも期待できます。要件への対応を計画的に進めながら、現場と管理者が一体となって地域に根ざした高品質な訪問看護体制を構築していくことが重要です。
UPDATEでは、訪問看護での実践的なマネジメントが学べる『訪問看護マネジメントスクール』を提供しております。経営マネジメントに関してお悩みの方は、ぜひお気軽にお問合せください。