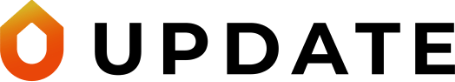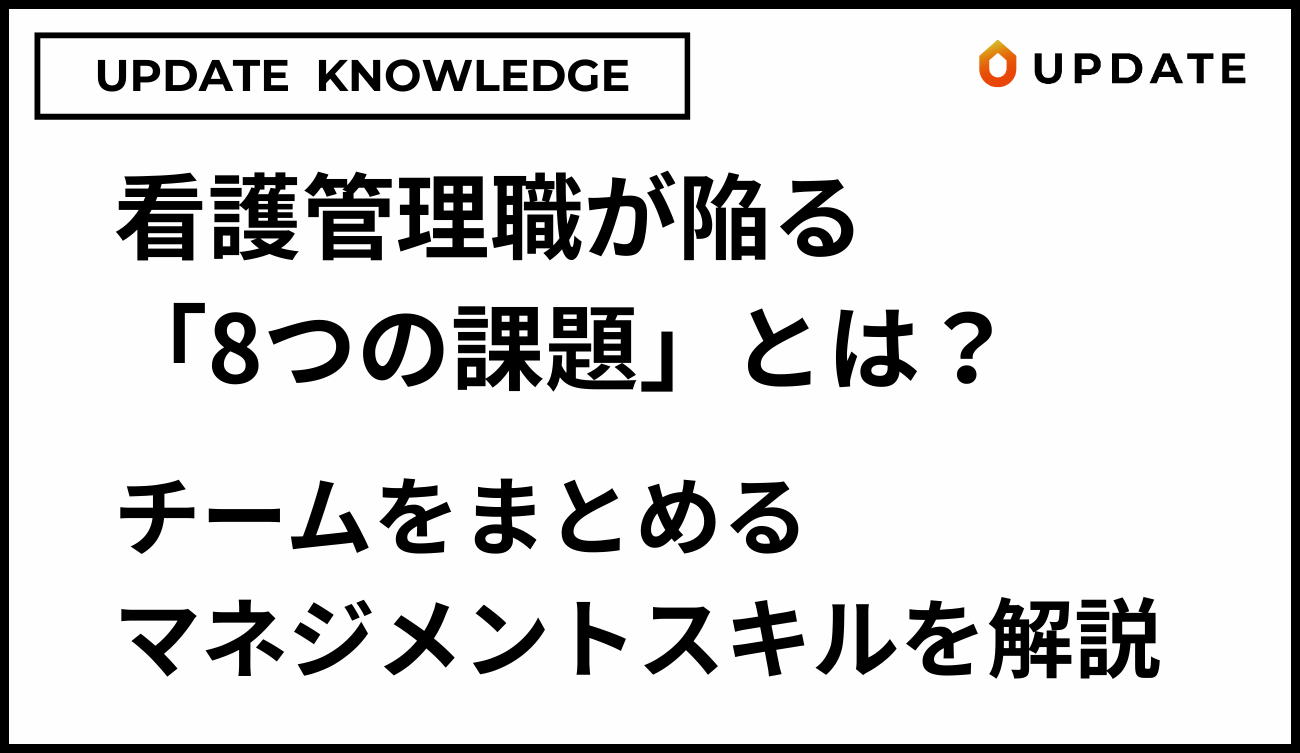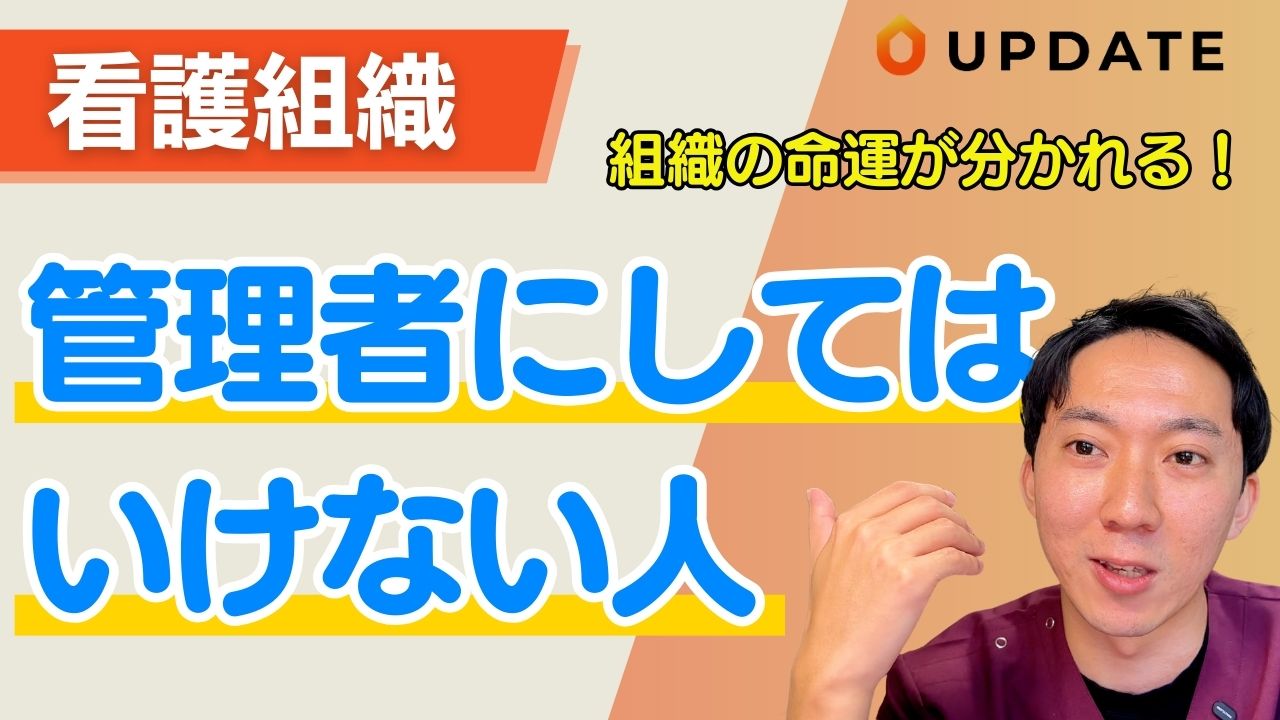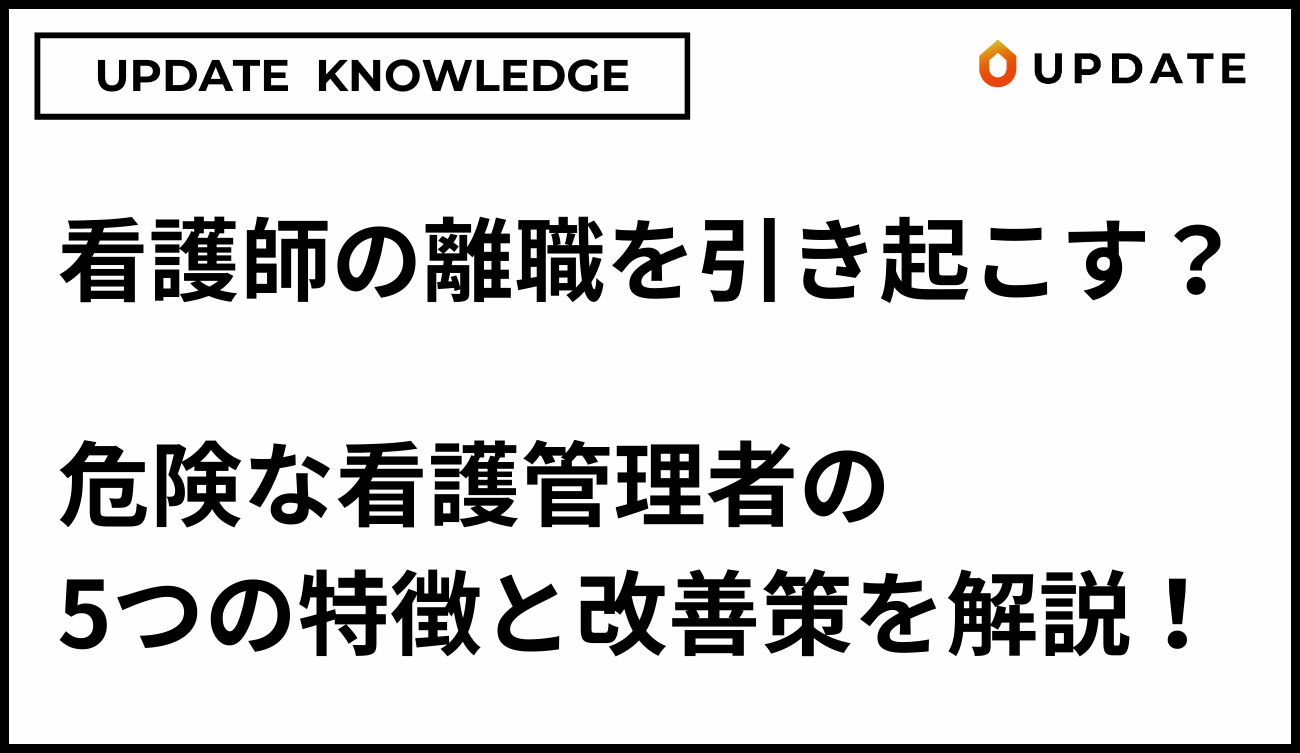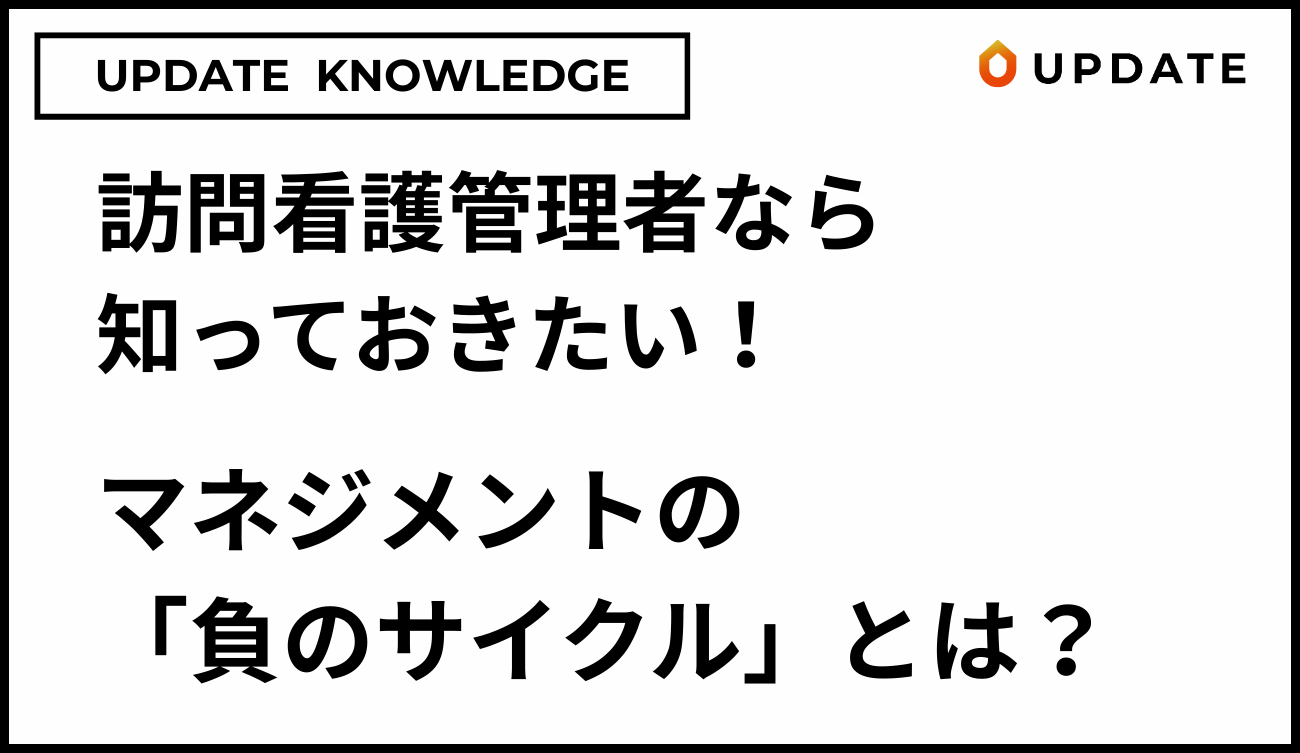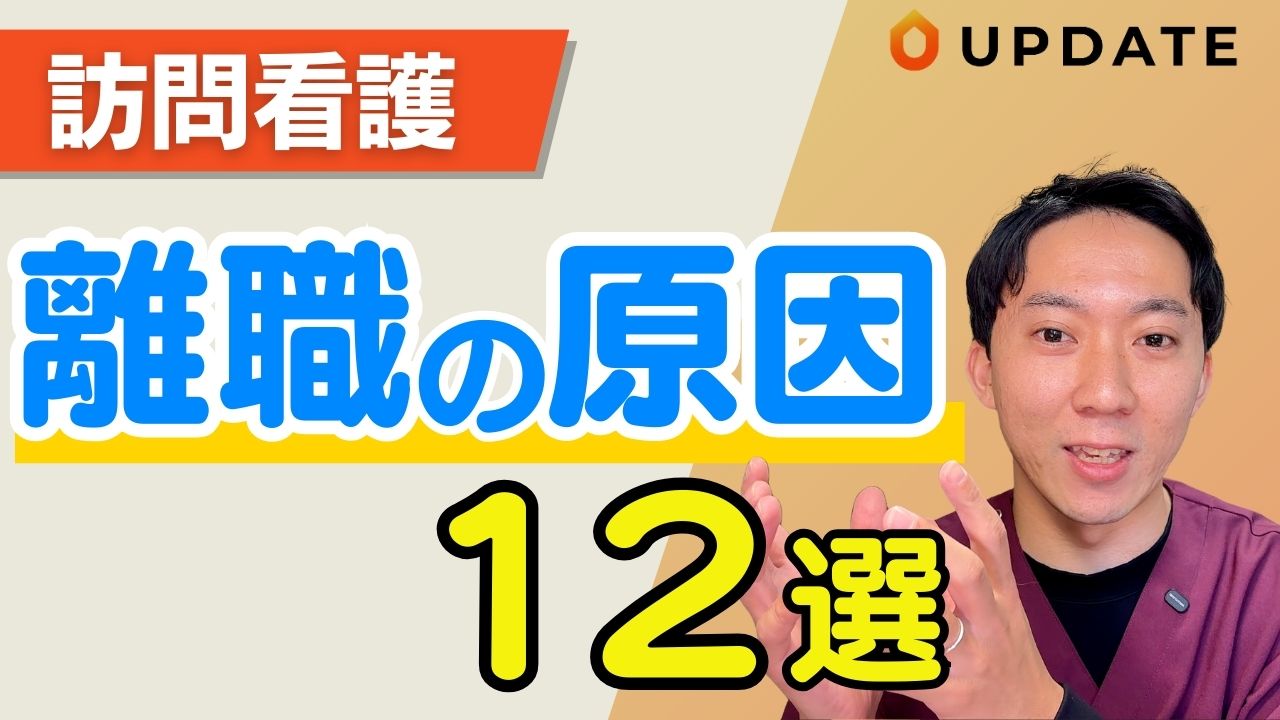【管理者研修受講者インタビュー】地域を支えるサービス拡大に向けたマネジメントの体制強化|医療法人和光会 福井郁子様
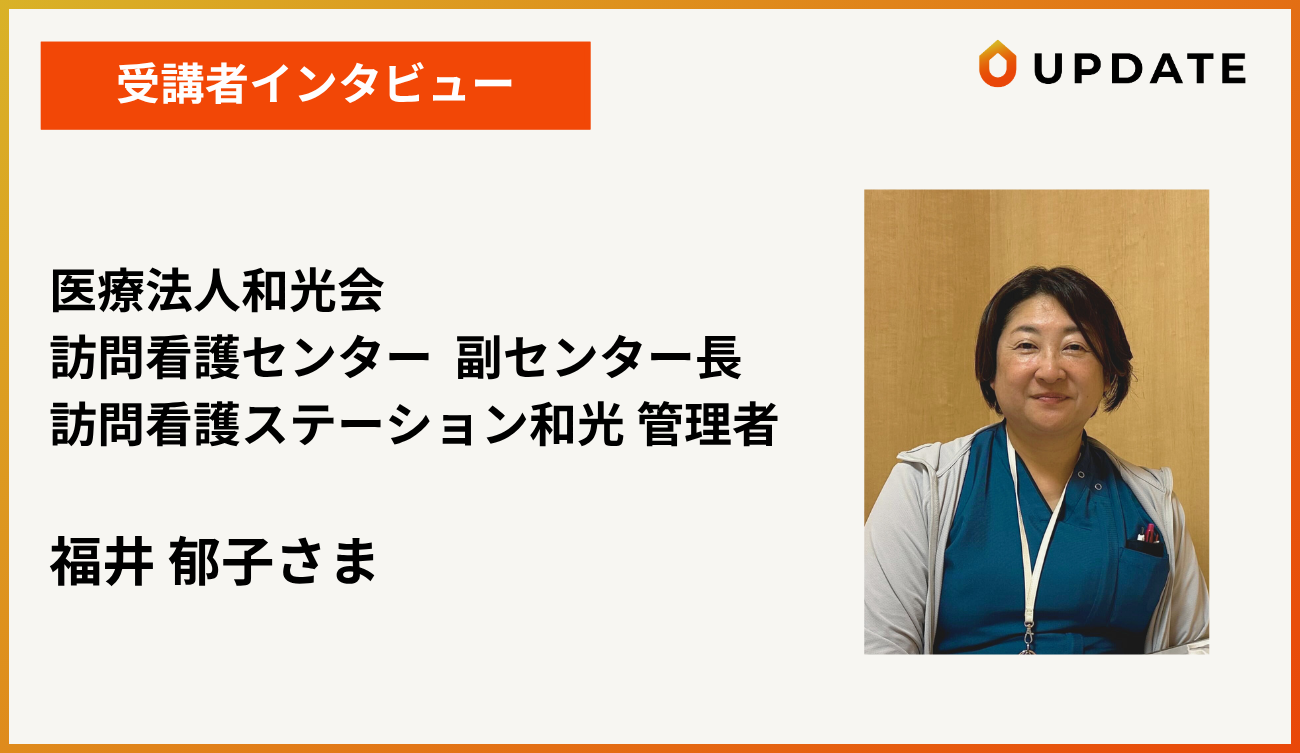
今回の【訪問看護管理者研修】基礎から学ぶ組織マネジメント講座受講者インタビューでは、医療法人和光会 訪問看護センターの福井郁子さんにお話を伺いました。
福井さんは和光会グループの副看護部長や訪問看護センター副センター長として、訪問看護ステーションや看多機などの組織のマネジメントに携わられています。
本記事では、福井様がUPDATEの講座受講を悩まれた末に決断された背景や、率直なご感想、また今後のビジョンについてお伺いしました。受講を迷われている方は、ぜひ最後までお読みください。
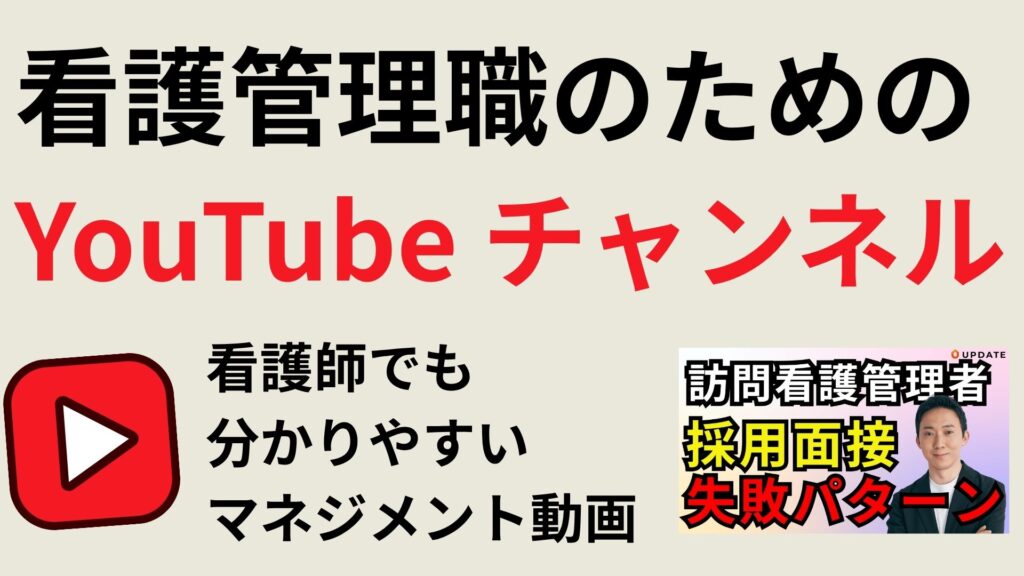
株式会社UPDATE 代表取締役(看護師・保健師・MBA) ケアプロ訪問看護ステーション東京にて新卒訪問看護師としてキャリアスタート。その後、訪問看護の現場・マネジメント経験の他、薬局や訪問看護運営するスタートアップ企業で40拠点・年商65億規模の経営を行い、上場企業へのグループインを実現。現在は医療職マネジメント人財を育成するためマネジメントスクールを運営中。
■経歴
2013年 慶應義塾大学 看護医療学部 卒業
2013年 ケアプロ株式会社入社
2019年 株式会社UPDATE(旧:ヘルスケア共創パートナー株式会社) 創業 代表取締役(現職)
2021年 GOOD AID株式会社 取締役(事業譲渡により退任)
2023年 セルフケア薬局 取締役(吸収合併により退任)
2023年 まちほけ株式会社 代表取締役(事業譲渡により退任)
■得意領域
医療系事業の組織マネジメント
教育体制構築
採用戦略・体制構築
教育体制構築
新卒訪問看護師の育成
管理職の育成
■保有資格・学位
看護師
保健師
経営学修士(MBA)
目次
受講者様ご紹介
- 業種:訪問看護
- 役職:副看護部長/訪問看護センター 副センター長/訪問看護ステーション 所長
- 職種:看護師
- 受講形態:個人向け研修
- 受講講座:【訪問看護管理者研修】基礎から学ぶ組織マネジメント講座
インタビュー内容
UPDATEの訪問看護管理者研修はどこで知りましたか?
ZESTというスケジュール管理ツールを使ってるのですが、たまたまその企業から無料セミナーのお知らせがあって、小瀨さんの講演を聞いたのが最初のきっかけでした。
人財確保に悩むなかで、色々な記事を読むと『管理者のカリスマ性』に関する話が良く出てくるんです。でも、すぐにカリスマ性が持てるわけでもないし、「何が自分たちに足りないんだろう?」って気になっていました。
そんな時に小瀨さんが登壇するセミナーの案内が届いて、普段受けないんですが参加してみて、すごく面白かったんですよね。まさに、自分が課題にしていることばかりで。
受講を申し込む前に心配なことはありましたか?
はい。すごい悩んだんですよ。
回数もそれなりにあるし、参加する人がみんなプロフェッショナルな人たちばかりだったら場違いじゃないかな?って想いはありました。
でも、カリキュラムを見た時に、すごく自分が課題としていることがいっぱいあったのと、無料のセミナーも時間が短かったのでやっぱり深く学びたいなと思って申し込みました。
受講前は具体的にどのような課題感がありましたか?
今管理しているステーションの前に、同じ法人内の他のステーションで5~6年管理者していたんですね。そこは今より規模が小さくて、1つ発信するとそれなりに伝わるような規模数だったんです。
だけど、今のステーションは倍くらいのスタッフ数で、もちろん全員が同じ時間に集まるのも難しいし、今までのままでは通用しないなと思ってたんです。
特に、私から主任へ、主任からリーダーへ、リーダーからスタッフへと伝達してもらう中で、隅々まで自分の考えや想いが伝わらないことが課題でした。
あとは、組織マネジメントをちゃんと学んだことがなかったので、新たに学ぶことができたら違ったアプローチができるかなという想いもありました。
基礎から学ぶ組織マネジメント講座を受講された率直な感想を教えてください。
最初は緊張していたのですが、小規模な開催だったことと他の参加者さんもフレンドリーな方で安心しました。
『組織マネジメント』って聞くと、一般企業の研修のようなイメージがありました。でも今回は、『訪問看護ステーションの組織マネジメント』ということで現場に近い内容が多かったので、すごく分かりやすかったんですよね。
なおかつ、メンバーへの伝え方やどのように動いたらよいかの具体策が非常に取り入れやすかったです。「明日からやってみよう!」というような内容が非常に多かったので、実践に活かしやすかったです。
あと、最後に必ず質疑応答や振り返りをやるじゃないですか。その時に、少しモヤっとすることを率直に相談できて、一緒に解決していくというのがすごく毎回楽しかったです。本当に楽しかったんですよ。毎週待ち遠しくて。
事業所での今の悩みも相談に乗ってくれてアドバイスをもらいながら解決できたのが、すごくよかったと思いますね。なので、UPDATEさんとしては大変かもしれないですが、今後も少人数に限定しての開催だととてもイイかなと思いました。

学びが深かったことや、組織・ご自身の成果につながったことはありますか。
講座で学んだ『ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)』の必要性は、スポーンと腑に落ちました。私たちの立場では理事長や常務とよく話をしたり、『MVV』について触れる機会が多いのですが、その意味や解釈をメンバーに伝えてなかったと講座を受けて思ったんですね。
実際にはスタッフも同じ方向性や想いで仕事をしているんだけど、『MVV』となるとすごくかけ離れたようなものという意識を持っていたので、私たちがしっかりつないであげなきゃって思うようになりました。そこで早速、現場での実践と『MVV』を紐づけるような研修を実施しました。
また、講座でもあった「誰をバスに乗せるのか?」という視点は大事なので、採用の時に『MVV』と、『MVVに関連する実践』を盛り込んだ面談用パワポを事業所ごとに創り、見学に来てくれた方に伝えるようにしています。
他には、『コミュニケーション・ライン』ですよね。マネジメントメンバー間での連携で、上手く行かずもやもやすることがあったのですが、「マネジメントの三角形を作って、右腕・左腕を創りなさい」という内容に「なるほど!」と思いました。
私の場合は、優秀な主任たちがいて右腕・左腕になってくれているにも関わらず、主任やリーダーを支え助ける右腕・左腕が誰なのかというところまで考えてなかったなと。
それから、例えば、主任の相談しやすい人・心強い人って誰かを確認するようになって、それぞれで右腕・左腕を育てていく重要性を教えるようになりました。なので、最近、組織の中で『右腕』『左腕』って言葉がよく使われるようになってきました。(笑)
あと、『パスゴール理論』。講座を受けた時に指導の仕方について悩んでいて、人それぞれ「私の指導の仕方」「○○さんの指導の仕方」ってあるじゃないですか。
でも、それぞれのやりたい指導の仕方でいいのかなって、もやもやしていました。でも、パスゴール理論を教えてもらって、人の力量とタスクの重要度によって教える側が変わらなきゃいけないんだなって学べたのが大きかったですね。
ちょうど主任さんもメンバーの指導に悩んでいたので、パスゴール理論を教えたらすごく腑に落ちてくれたんです。こういった知識を学ぶと、自分たちが変わることができて、実際の指導も良くなっていくんだろうなと思いました。
【訪問看護管理者研修】基礎から学ぶ組織マネジメント講座をご検討中の方に、今なら無料の体験クラス動画や特別プレゼントもご用意しています。
あなたも今すぐお受け取りください。
UPDATEマネジメントスクールはどのような方におすすめですか?
やっぱり、訪問看護の管理者さんや次世代の管理者さんですかね。看護業界って看護についてはたくさん学ぶ機会があるけど、管理者さんになっても組織マネジメントについて学ぶ機会ってないじゃないですか。なので、管理職の方や、管理者になる予定の方は、学べるといいと思いますね。
あとは、やっぱり『人に対するアプローチ』がマネジメントで一番重要だと思うので、組織の中の人・メンバーとの悩みが多い方ですかね。役職がついた方は、当然人に関する悩みも多いと思うので、講座で色んなアプローチの引き出しを見つけて実践でチョイスしながら使えるようになるといいと思います。
最後に、福井さんや医療法人和光会さんの今後のマネジメントの抱負を教えてください!
講座の中で小瀨さんが『訪問件数は届けたケアの数』という話をされていて、本当にそうだなと思ったんですよね。つい件数って『負担』というイメージでネガティブに思われがちですが。
和光会は地域社会への貢献を本当に大事にしていて、この地域の高齢者や障害を持った方、精神疾患や小児疾患をお持ちの方など、色んな人たちがこの地域で生活していけるように私たちがいる。自宅での生活が難しかったら、有料老人ホームや看多機を使いながら、この地域で暮らし続ける。この地域から離れなかったら、家族の絆も途切れることないんだろうなってすごく思うんですよ。
遠くに行ってしまったらなかなか会いにいけないかもしれないけど、毎日でもすぐに顔を出せたり。和光会グループは色んな事業を展開しているので、私自身がそういった場面や瞬間によく立ち会わせていただいている。
だからこそ、この地域にきちんと根差して、色んな選択肢で支えられるように事業を広げていくことにすごく自分も共感していますし、今後もそのようなサービスを提供していきたいです。
もちろん、事業を拡大していけば、そこで活躍するメンバーや管理職も育てていく必要があるので、そこは私のミッションだと思っています。自分が経験したことを惜しみなく伝えて、この地域を支えていける人材を育てていければと思います。
企業紹介|医療法人和光会 様
『どんなときも、安心して笑顔で暮らせる地域社会の創造』をビジョンに掲げ、岐阜県を中心に様々な医療福祉サービスを展開されています。人財育成にも力を入れられていますので、岐阜県で活躍したい方はぜひ和光会様のホームページもご覧ください。
企業HP:https://www.wakokai.or.jp/