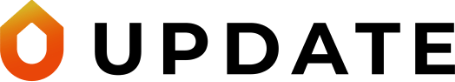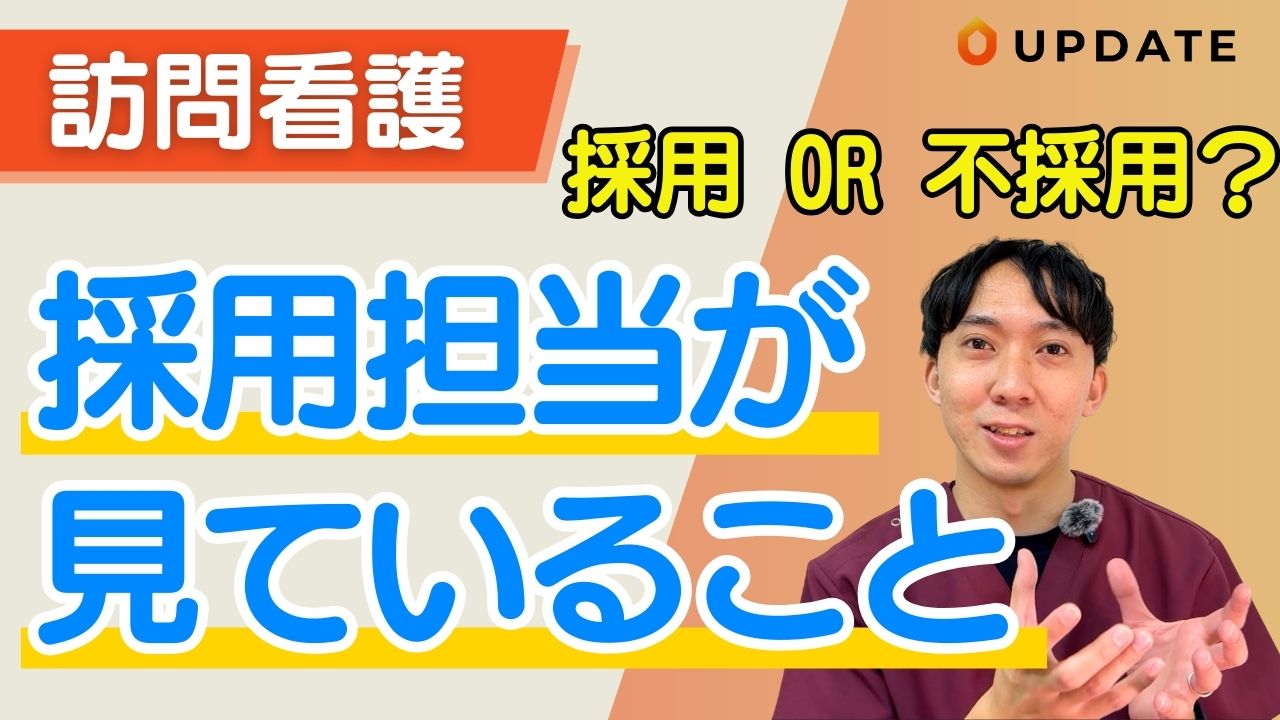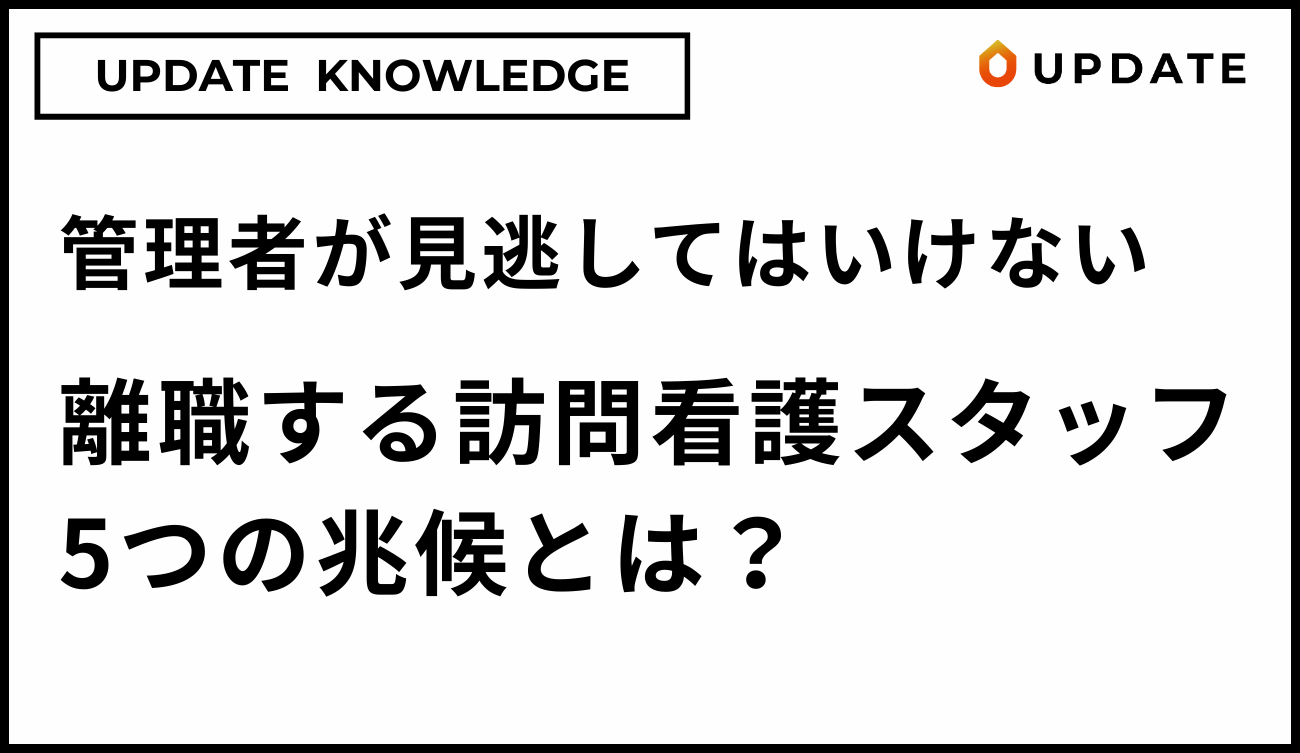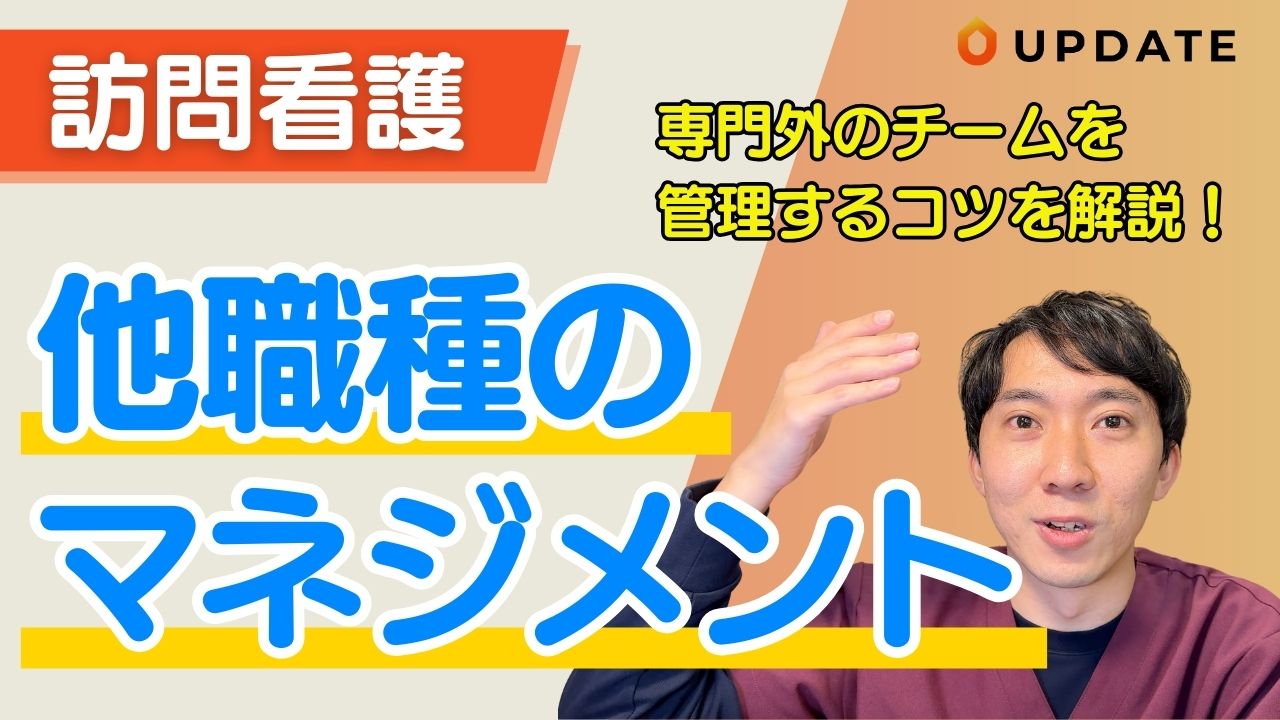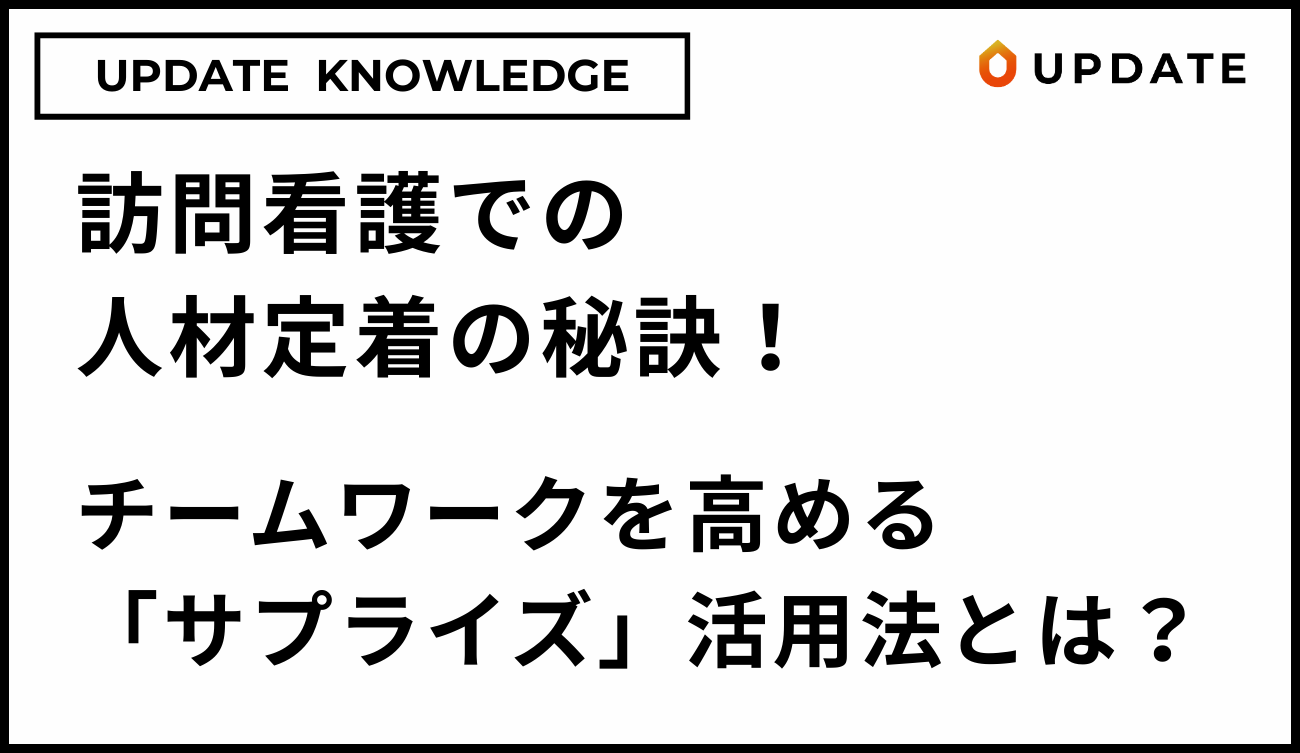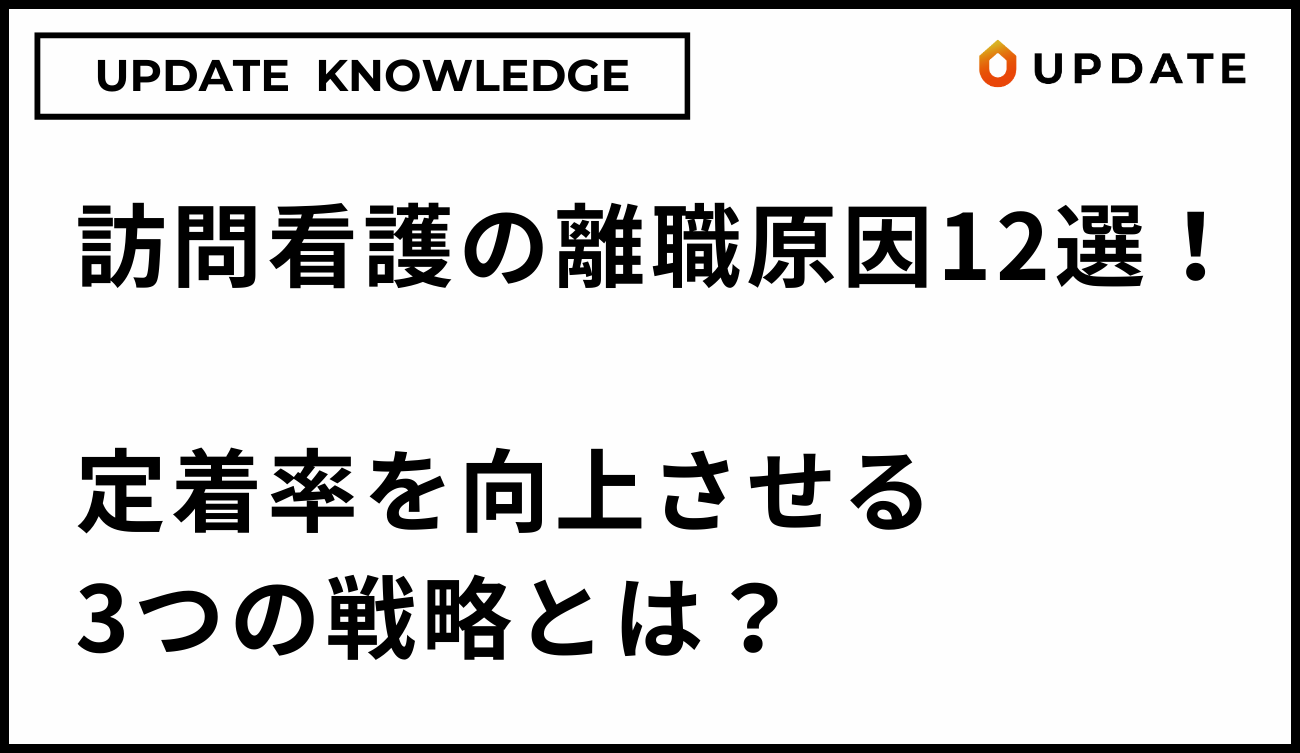訪問看護の教育体制とは?未経験看護師が安心して働ける職場の選び方を徹底解説!
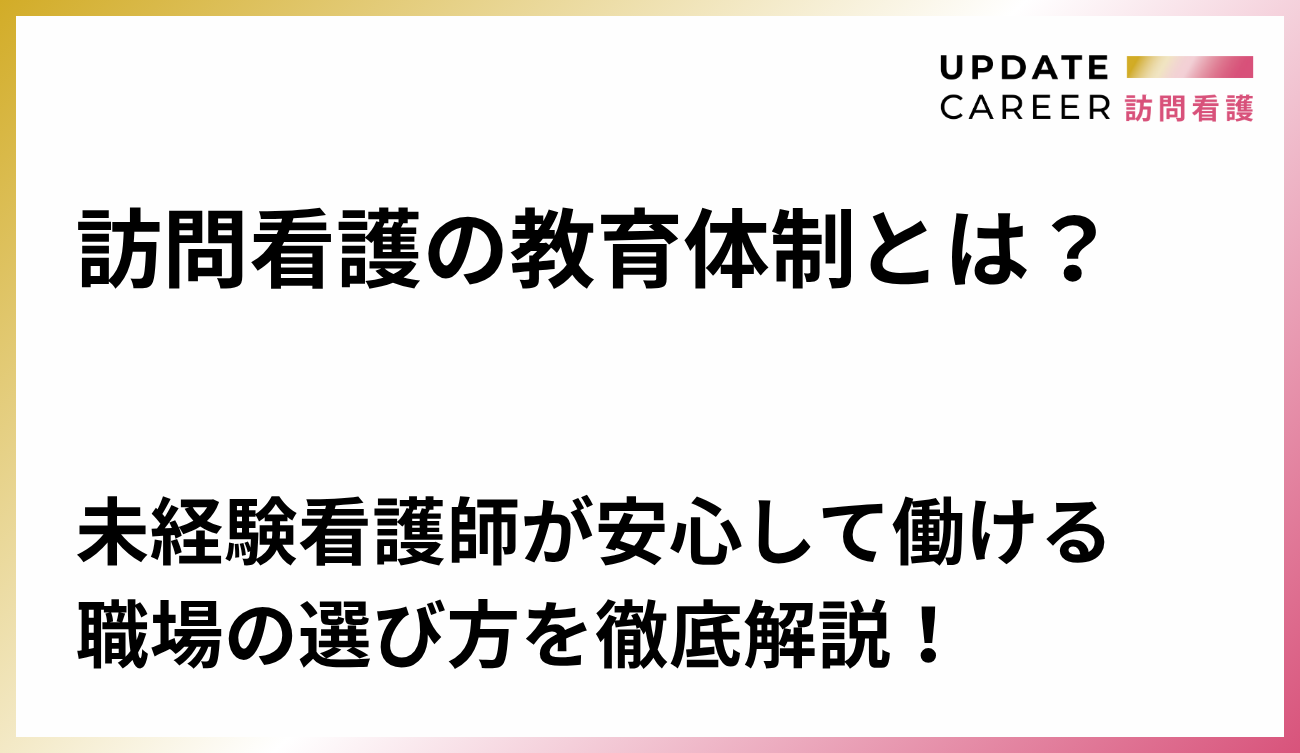
「訪問看護に興味はあるけど、教育体制は整っているの?」
「訪問看護が未経験でも大丈夫?」
などの不安を感じていませんか?
訪問看護と病院では、教育体制に大きな違いがあります。さらに、訪問看護ステーションごとに体制やサポート内容が異なるため、事前の見極めが重要です。
本記事では、訪問看護における教育体制の特徴や、未経験でも安心して働ける職場の選び方を詳しく解説します。
この記事を読めば、訪問看護の教育についての不安が解消し、自信をもって新たな一歩を踏み出せるでしょう。ぜひ最後までお読みください。

株式会社UPDATE 代表取締役(看護師・保健師・MBA) ケアプロ訪問看護ステーション東京にて新卒訪問看護師としてキャリアスタート。その後、訪問看護の現場・マネジメント経験の他、薬局や訪問看護運営するスタートアップ企業で40拠点・年商65億規模の経営を行い、上場企業へのグループインを実現。現在は医療職マネジメント人財を育成するためマネジメントスクールを運営中。
■経歴
2013年 慶應義塾大学 看護医療学部 卒業
2013年 ケアプロ株式会社入社
2019年 株式会社UPDATE(旧:ヘルスケア共創パートナー株式会社) 創業 代表取締役(現職)
2021年 GOOD AID株式会社 取締役(事業譲渡により退任)
2023年 セルフケア薬局 取締役(吸収合併により退任)
2023年 まちほけ株式会社 代表取締役(事業譲渡により退任)
■得意領域
医療系事業の組織マネジメント
教育体制構築
採用戦略・体制構築
教育体制構築
新卒訪問看護師の育成
管理職の育成
■保有資格・学位
看護師
保健師
経営学修士(MBA)
目次
訪問看護と病院の教育体制の違いとは?

訪問看護と病院では、教育体制が大きく異なります。
病院では組織的な教育プログラムが確立されているケースが多い一方、訪問看護では先輩と一緒に利用者さんのご自宅に訪問し、現場で学ぶ教育が一般的です。
日本看護協会のデータ(2022年時点)によると、訪問看護ステーションで働く常勤スタッフの数は、「5~10人未満」が40.6%で最も多く、次いで「5人未満」が27.3%です。
このように少人数で運営しているステーションが多く、教育体制への整備が難しいという現状もあります。
病院と訪問看護における、教育体制の違いを以下の表にまとめました。
| 項目 | 病院 | 訪問看護 |
| ラダー制度 | ・日本看護協会が定めるクリニカルラダー制度(JNAクリニカルラダー)が使われることが多い・病院ごとのキャリアラダー制度を導入していることが多い | ・事業所ごとに独自のクリニカルラダーを導入している場合がある・訪問看護のキャリアラダーは全国的には一般的ではない |
| 研修・勉強会 | ・院内研修や部署ごと勉強会が充実している ・外部研修費用の補助が得られる場合もある | ・内部研修が行われず現場密着型の実技指導のみのこともある・ ステーションにより格差が大きい・外部研修参加は自己負担の場合もある |
| 指導体制 | ・複数の先輩によるチーム教育 ・ プリセプター(+エルダー制度)を導入している・ いつでも先輩が病棟にいるため、質問しやすい ・新卒の場合同期が多く、同期の間で情報共有しやすい | ・同行訪問による実践な指導を行う・個別のスキルや成長のペースに合わせて指導を進める ・ 現場に先輩がいないことが多く、質問したい時は電話する必要がある・小規模の事業所では、同期のような横のつながりが少なく、情報共有しにくことがある |
| 教育期間 | ・プリセプターやラダー制度などのプログラムに沿った期間 | ・個人の習得度に応じて柔軟に指導期間を調整する・ 同行訪問期間が職場により異なる |
クリニカルラダー制度とは、看護師の能力開発や評価を行うシステムです。日本看護協会が定めるJNAクリニカルラダーは、全国レベルで共通した看護実践能力の指標として活用されています。
全国の病院では一般的に、JNAクリニカルラダーを使用しています。
訪問看護でも、都道府県や組織ごとに独自のクリニカルラダーが活用されている場合がありますが、導入していない事業所も少なくありません。
キャリアラダー制度とは、看護師の成長段階に応じて必要なスキルや知識を明確にし、段階的なキャリアアップを支援する制度です。
多くの病院で導入されており、看護師の専門性向上と定着率向上に効果を発揮しています。
訪問看護では、東京訪問看護ステーション協会や長崎県看護協会にて、訪問看護のためのキャリアラダーが作成されています。しかし、全国的には一般的ではないのが現状です。
参考文献:日本看護協会 2024年度診療報酬・介護報酬改定等に向けた訪問看護実態調査 p.11
教育体制が充実している訪問看護ステーション5つの特徴

教育体制が充実している訪問看護ステーションには、共通する特徴があります。
未経験でも不安なく働ける事業所を選ぶためには、以下の5つの特徴を参考にするとよいでしょう。
1.研修プログラムが整っている
体系的な研修プログラムが整っていることで、未経験でも安心して訪問看護師としての基礎を固められます。
具体例は以下のとおりです。
- クリニカルラダー制度の導入による段階的なスキル評価
- チェックリストや進捗管理表を活用した研修内容の見える化
- 新人の習得度に応じた個別カリキュラムの調整
例えば「基礎技術習得チェックリスト」では、バイタルサイン測定・褥瘡ケア・在宅医療機器の取り扱いなど、訪問看護に必要な技術を項目別に整理します。
習得度を見える化すれば、指導者間での引継ぎがしやすくなります。
また、指導される側にとっては自信になり、習得した技術と未習得の技術を整理できるでしょう。
2.同行訪問での指導が手厚い
訪問看護が未経験の場合、同行訪問での指導が手厚いステーションを選ぶことが大切です。
以下のポイントを押さえて事業所を選ぶとよいでしょう。
- 3ヶ月程度の同行訪問期間を確保している
- 指導内容が「見学 → 部分実施 → 全面実施」と段階的である
- さまざまなケースの利用者さんから幅広く学べる体制を整えている
最初は指導者の訪問に同行し、看護技術や利用者・ご家族とのコミュニケーション方法を学びます。
その後、指導者の見守り下で部分的な処置を行い、3か月目には全面的にケアを実施します。
同行訪問での手厚い指導があるステーションを選び、実践的なスキルを確実に身につけましょう。
3.継続的なフォローアップ体制がある
未経験からチャレンジした訪問看護師にとって、一人立ちしたばかりの段階では、まだ不安を感じているでしょう。
一人で訪問できるようになった後も継続的なサポートがあれば、不安が徐々に解消され、自信をもって訪問できるようになります。
心強いサポート体制として、以下が挙げられます。
- プリセプター制度やチームでのサポート体制
- 一人立ち後の定期的な個別面談
- 定期的な勉強会やケースカンファレンスでの事例検討
個別面談では「悩んでいるケース」や「技術的に向上したい分野」などのテーマで話し合い、具体的な改善策を検討します。
ケースカンファレンスでは、事例を通じてチーム全体で最適なケア方法を検討します。
このように、新人スタッフが一人で問題を抱え込まないよう工夫しているステーションを選ぶとよいでしょう。
4.eラーニングシステムや外部研修を導入している
eラーニングシステムや外部研修を導入しており、事業所内にとどまらない学びが得られるかどうかもチェックすべき特徴の一つです。
特にeラーニングには、以下のメリットがあります。
- 24時間いつでも学べるため、勤務形態に左右されない
- スマートフォンやタブレットで移動中にも活用できる
- 映像教材+テスト形式で、理解度を客観的に把握できる
また、外部研修に参加するための費用補助や勤務シフトの調整など、継続学習をサポートする制度の有無を確認しましょう。
このような制度があるステーションは、成長を支える意識が強いといえます。
eラーニングシステムや外部研修を活用しているステーションを選び、継続的に学ぶことで、訪問看護師として成長していけるでしょう。
5.教育体制や訪問看護サービスを一緒に創る姿勢がある
新人看護師の意見や提案を積極的に取り入れる風土があり、柔軟性の高い教育・訪問看護サービスを行っているかどうかも重要なポイントです。
以下の特徴を持つステーションは、柔軟性の高い運営を行っている傾向があります。
- 管理者と現場スタッフの距離が近い
- 教育体制に現場の声を反映している
- スタッフ全員が改善への意識をもっている
このような環境であれば、新人看護師も教育対象であると同時に、教育を一緒に創る存在として尊重されるでしょう。
新人看護師が一方的に教育を受けるだけでなく、事業所全体をより良くしようという主体的な意識をもつことも大切です。
訪問看護経験者による無料キャリア相談・転職支援はコチラから!
訪問看護の教育現場「1日の流れ」とは?
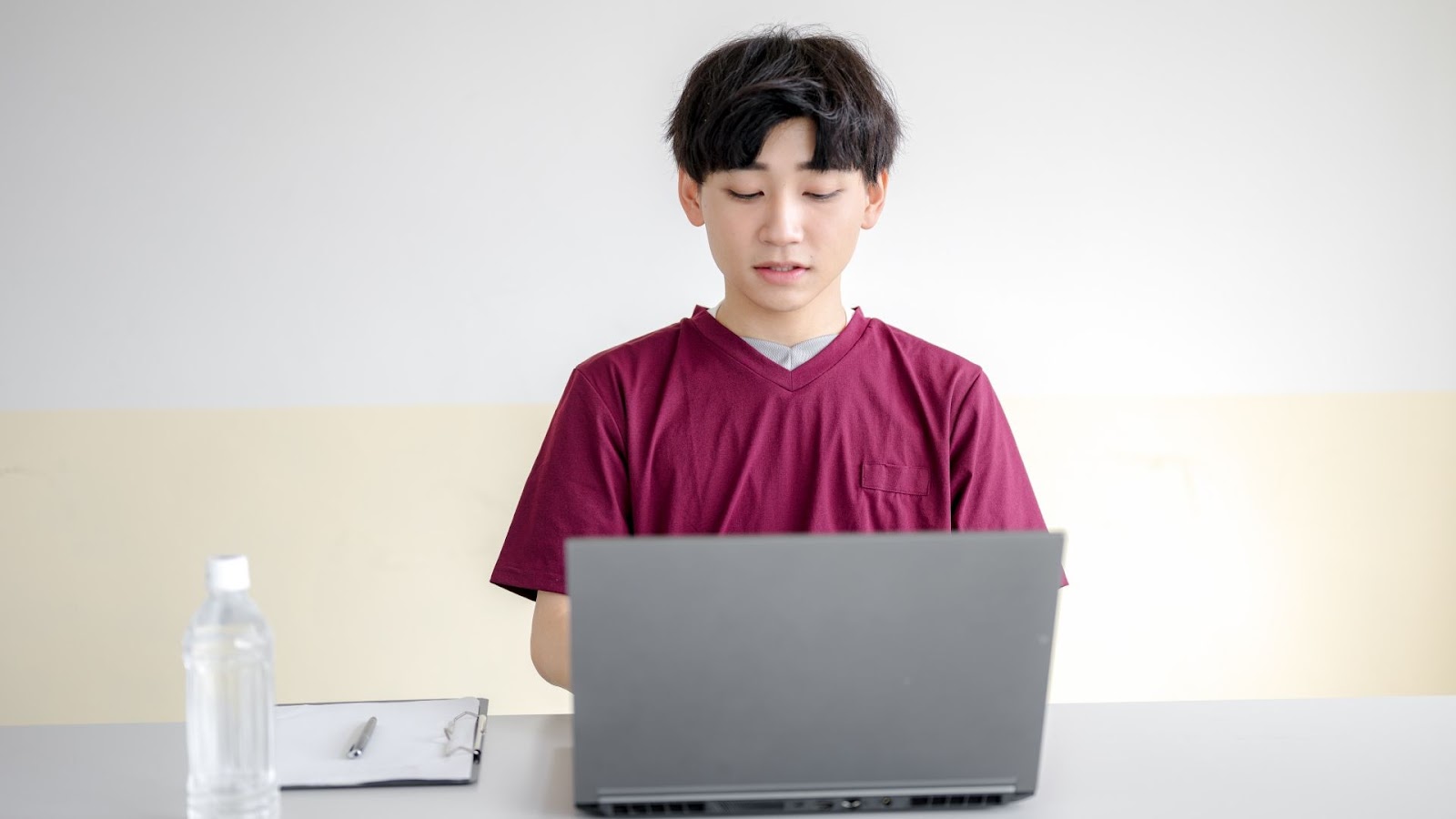
訪問看護における教育期間中の1日の流れを知ることは、働くイメージを具体化するうえで役立ちます。
本章では、同行訪問中のスケジュール例と、その中で確保されるべき移動・休憩・記録時間の配慮について詳しく解説します。
実際の現場感を把握することで、転職後のギャップを感じにくくなり、安心してスタートを切れるでしょう。
同行訪問期間中の1日のスケジュール例
教育期間中の1日は、朝礼での情報共有から始まります。利用者さんに必要なケアを確認し、指導者と一緒に訪問スケジュールを決定します。
【同行訪問期間中の基本的な流れ】
8:30 出勤・朝礼・情報収集
9:00 午前中の同行訪問(2〜3件)
12:00 昼休憩 (1時間)
13:00 午後の同行訪問(2〜3件)
17:00 記録作成と翌日の準備
18:00 退勤
1件あたりの訪問時間は30~60分程度です。
訪問件数は段階的に増やしていき、最初は1日2〜3件から始めて、慣れてきたら1日4〜6件まで徐々に増やしていくのが一般的です。
最初は先輩看護師が行うケアや利用者さん・家族との関わり方を見学して学びます。その後、部分的にケアを行い、慣れてきたら全面的なケアを行います。
ケアを実践するなかで生じた疑問を、同行訪問期間中にできるだけ先輩に質問しましょう。
移動・休憩時間の確保状況
訪問看護の教育期間中は、移動や休憩がしっかり確保されているかどうかが、働きやすさを左右します。
未経験の看護師にとっては、「土地勘がなくて迷いそう」「休憩を取りづらいのでは?」などの不安もあるでしょう。
これらの不安を軽減するためには、移動時間や訪問の間隔に余裕をもたせたスケジュールを組んでいる事業所を選ぶことが重要です。
具体的には以下の点を確認しましょう。
- 移動時間を通常より長めに設定し、余裕をもった移動や確認作業が可能
- 事業所から最も遠い利用者宅への移動にかかる時間
- 移動手段
- 昼休憩は法定どおりに取得できる体制
日本看護協会の調査では、事業所から最も時間がかかる利用者宅への移動時間(片道)は、「30~59分」が53.0%で最も多いというデータがあります。
職場見学の際には1日のスケジュール例や移動にかかる時間を確認し、無理のない勤務体制かをみておくと安心です。
参考文献:日本看護協会 2024年度診療報酬・介護報酬改定等に向けた訪問看護実態調査 p.9
記録時間の確保状況
訪問看護では、利用者ごとにケア内容を正確に記録する必要があります。
多くのステーションでは、スマートフォンやタブレットなどのICTツールを導入し、訪問中に記録を完了できるよう工夫しています。
ただし、訪問看護計画書や訪問看護報告書の作成は勤務時間外に及ぶことがあります。
記録がスムーズに進められる環境は、日々の業務負担の軽減につながります。
面接時には、記録作業の効率化に向けた取り組みや残業の発生状況などを、具体的に確かめると良いでしょう。
訪問看護の教育体制を見極めるための3つのチェックポイントとは?
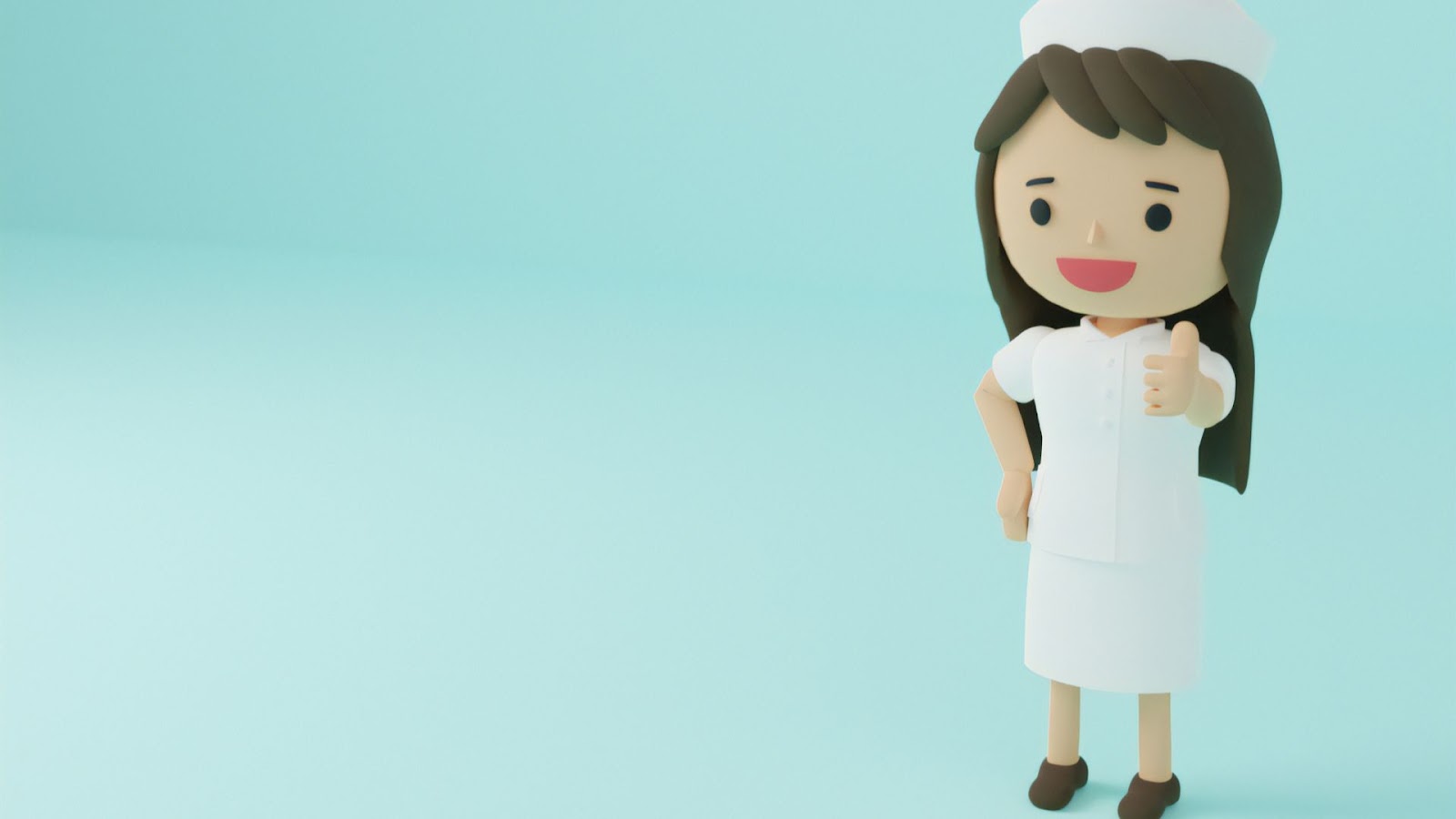
教育体制が整っているか判断するのに、どのようなポイントをチェックすればよいかわからず悩んでいる方は少なくないでしょう。
本章では、訪問看護の教育体制を確認するうえで押さえておくべき3つのチェックポイントを紹介します。
1. 教育プログラムの具体性を確認する
教育プログラムが具体的であることは、事業所が教育にどれだけ力を入れているかの指標となります。
チェックすべきポイントは以下のとおりです。
- クリニカルラダーやラダー制度の導入
- 同行訪問の期間や具体的な内容(病院経験者なら3ヶ月程度が目安)
- 同行前のオリエンテーションの内容
- 教育担当者の役職・指導経験・訪問看護の実績
- 継続学習の機会(部署勉強会、eラーニングなど)
これらの内容を面接時や説明会時に質問することで、実際に機能しているかを見極められます。
詳細に答えられない場合は、実際の教育体制に不安が残る可能性もあります。
特に、立ち上げ段階にあるステーションでは、教育体制が整っていないこともあるでしょう。その場合は、自分がそれでも飛び込みたいと思える環境か、熟考することが大切です。
新人スタッフと一緒に教育体制を作り上げていく姿勢が感じられる事業所かどうかもチェックしましょう。
2. サポート体制の手厚さをチェックする
教育プログラムだけでなく、サポート体制やフォロー体制の有無も重要なポイントです。
特に、一人立ち直後や急変時には、相談できるスタッフがいると安心できます。
以下のようなサポート体制があるかを確認しましょう。
- プリセプターやメンター制度の有無
- 一人立ち後の定期的な面談・フィードバック
- 緊急時の相談体制(電話・駆けつけ支援など)
- チーム全体でサポートしあう文化の有無
実際に制度が機能しているかを見極めるためには、スタッフ同士の連携や相談しやすい雰囲気かも確かめましょう。
3. 実績となる数字を確認する
教育体制やサポート体制がどれほど整っていても、実際に新人が定着していないようでは、実効性があるとはいえません。
そこで、離職率や復職率などの過去の実績にも注目することが大切です。
具体的には、以下のデータを調べましょう。
- 新人受け入れ実績
- 離職率
- 所属看護師の資格保持状況(例:認定看護師・訪問看護認定看護師など)
- 産休・育休取得者の数と復職率
これらの実績が一定の基準を満たしていれば、働きやすく教育体制が定着している職場だと判断できます。
面接や説明会で、ステーションの管理者に直接質問するのも一手です。
株式会社UPDATEでは、訪問看護の教育体制に不安がある方に、訪問看護経験が豊富なキャリアアドバイザーが具体的な相談を行ったうえで、キャリア・転職を支援します。
転職のご意向がなくても、「まずは訪問看護の実際を知りたい」、「自分でもチャレンジできるのか相談したい」という方ともカジュアルに面談ができます。気になる方は、以下のフォームよりお気軽にご相談ください。
『UPDATE CAREER 訪問看護』による、無料のキャリア相談・転職相談のお申込みはこちらから
訪問看護の教育体制に関するよくある質問Q&A

訪問看護の教育体制について、未経験の看護師が抱きやすい疑問とその回答を以下にまとめました。
Q1. 訪問看護の教育期間はどのくらいですか?
教育期間の長さは事業所によって異なりますが、臨床経験のある看護師であれば3ヶ月間の同行訪問が一般的な目安です。個人の習得度に応じて期間を延長できる柔軟な体制をとっている事業所もあります。
長期間病棟で勤務していたベテランの看護師でも、訪問看護特有のスキルが求められるため、一定の同行訪問期間が設定されています。
同行期間だけでなく、教育の中身や指導の段階も確かめておきましょう。面接時には、実際の教育フローや一人立ちまでのステップを詳しく聞くことをおすすめします。
Q2. 一人での訪問が不安です。緊急時のサポートはありますか?
一人で訪問する際の不安は誰しもが抱えるものです。多くの訪問看護ステーションでは、緊急時の連絡体制やフォロー体制が整備されています。
たとえば、以下の仕組みがあるかをチェックしましょう。
- 緊急時に先輩看護師に電話相談できるシステム
- 必要に応じた駆けつけ支援
- チャットやアプリを活用した情報共有
孤立感を防ぐためにも、これらの体制が機能しているかは重要なポイントです。
特に、現場に一人で向かうことに対して不安がある方は、サポート体制の充実度を重視して職場を選ぶとよいでしょう。
Q3. 教育体制の充実度を見抜くために、面接時に聞くべき質問例を教えてください
教育体制の実態を見極めるためには、面接時や説明会時に質問することが重要です。以下の質問を準備することで、具体的な情報を引き出せます。
- 「同行訪問の期間・内容はどのようになっていますか?」
- 「一人立ちまでのステップはどのように設けられていますか?」
- 「教育担当者の経験年数や訪問看護歴はどれくらいですか?」
- 「専門性の高い資格を保有しているスタッフはいますか?」
- 「一人立ち後の面談やフィードバックはどの頻度で行われていますか?」
- 「訪問件数はどれくらいから始まりますか?」
これらの質問を通して、具体的な教育方針や現場の支援体制を確認しましょう。
関連記事:看護師の勉強会のテーマは何がいい?選び方と例を解説|NsPace Career
訪問看護の教育体制を理解することがキャリアチェンジへの第一歩!

訪問看護における教育体制を正しく理解し、安心できる職場を選ぶことは、未経験からのチャレンジで失敗しないための大切な一歩です。
教育体制が整っている訪問看護ステーションで、実践的な学びと丁寧なフォローを受けられれば、未経験からでも段階的にスキルを身につけられるでしょう。
特に、同行訪問・研修制度・面談サポートなどが充実している事業所を見極めることが、安心して働くための重要なポイントです。
本記事で紹介したチェックポイントや職場選びの視点を踏まえて訪問看護ステーションを探せば、安心して長く働ける事業所に出会えるでしょう。
株式会社UPDATEでは、訪問看護の教育体制について不安をお持ちの方に対し、訪問看護の現場を熟知したキャリアアドバイザーが丁寧にお話を伺い、あなたに最適なキャリア・転職をサポートします。
「すぐに転職したいわけではないけれど、訪問看護の現場について詳しく知りたい」「未経験の自分でも訪問看護にチャレンジできるか相談してみたい」という方のご相談もお受けしています。少しでもご興味をお持ちの方は、以下のフォームからお気軽にご相談ください。
訪問看護経験者による無料キャリア相談・転職支援はコチラから!