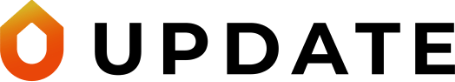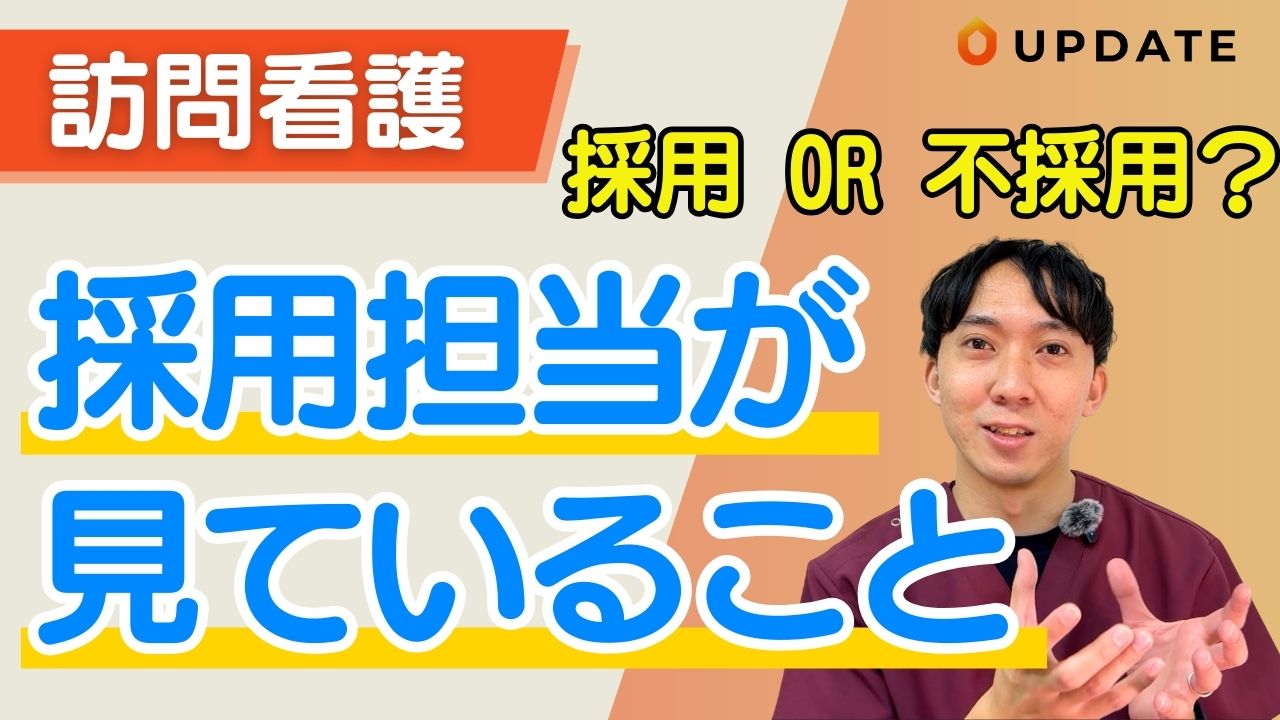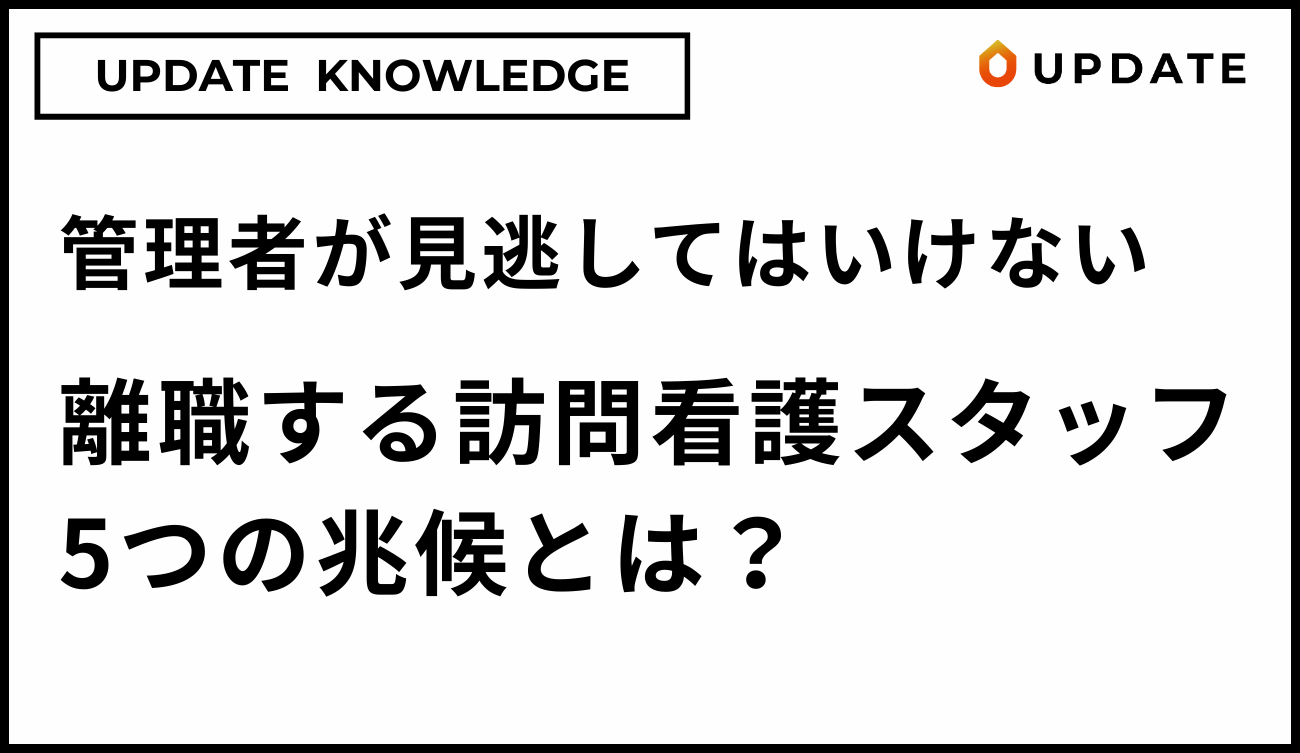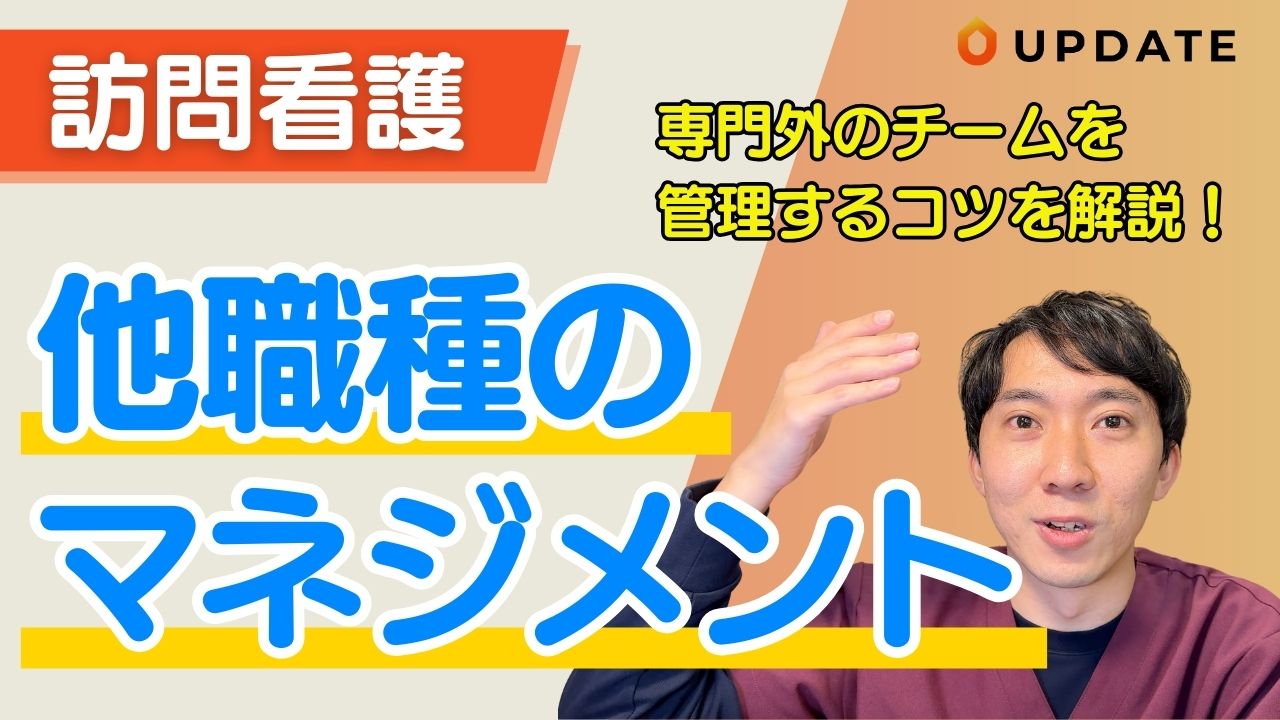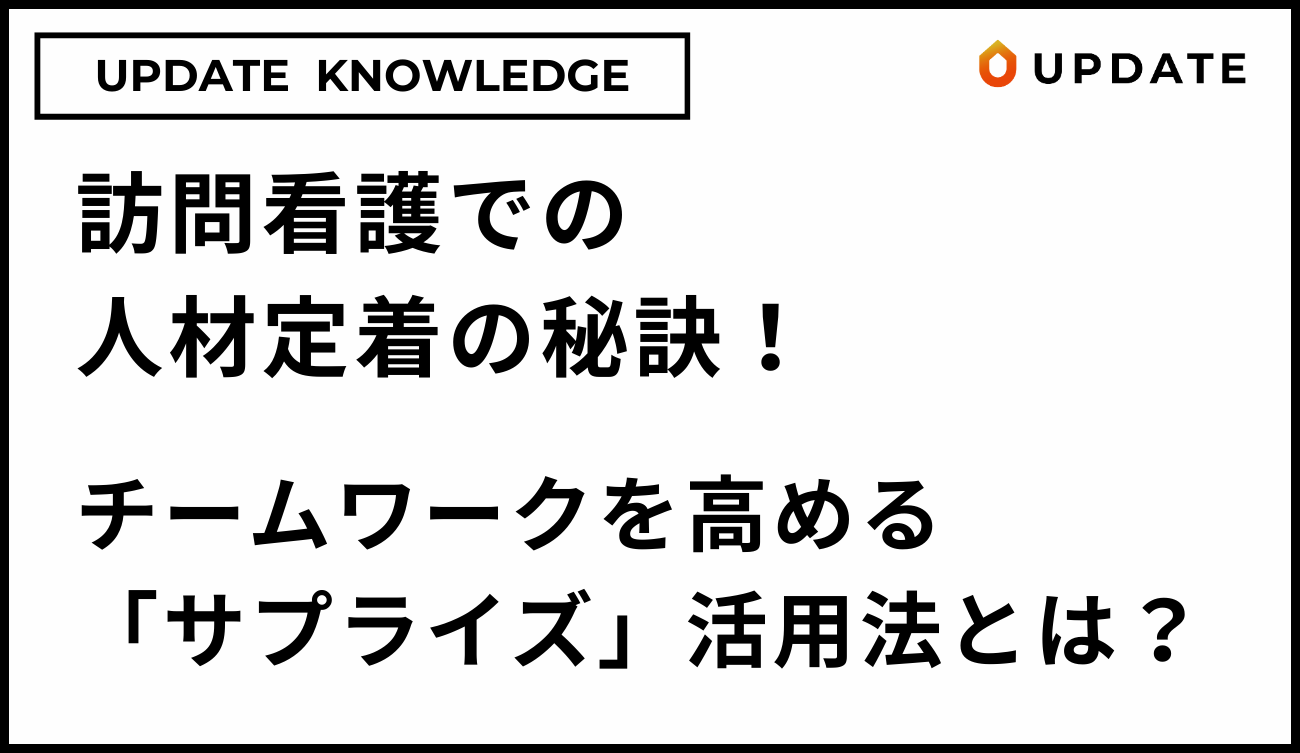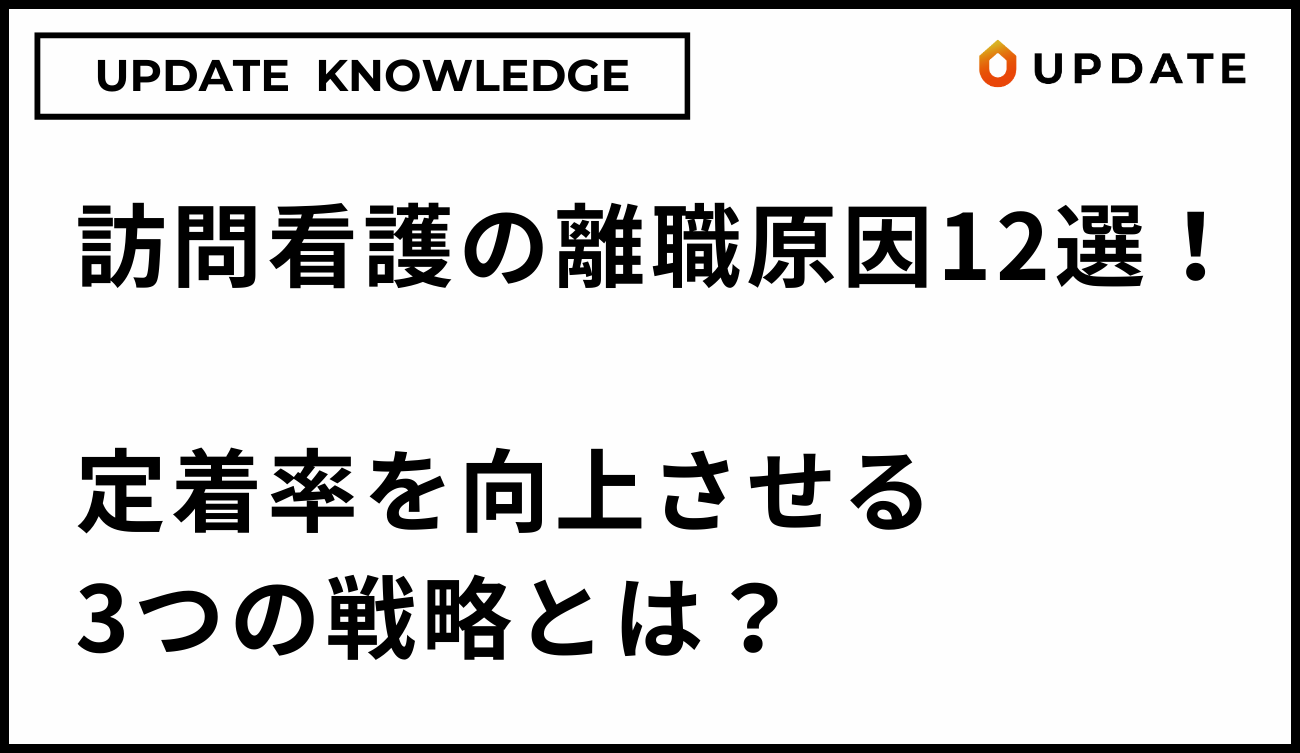訪問看護での教育体制と構築の手順|成功のポイントも紹介!
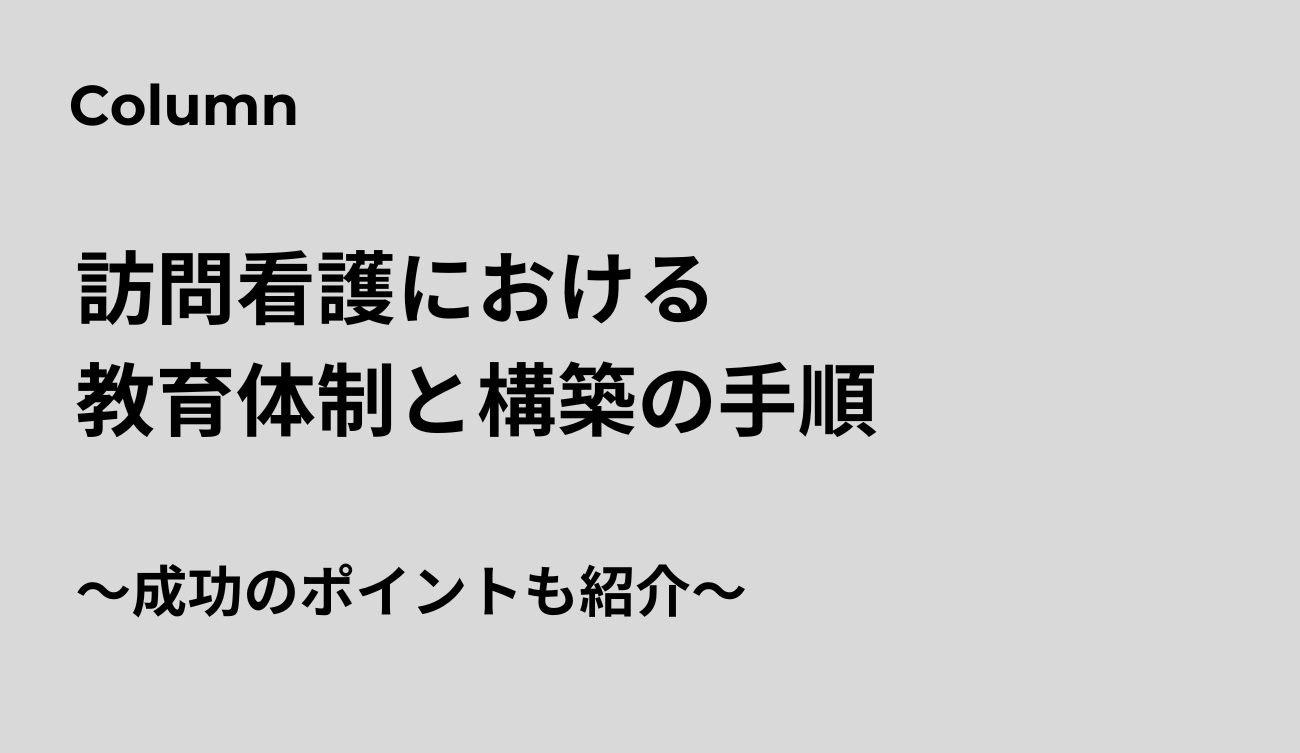
訪問看護は、在宅医療のニーズが高まる中でその役割はますます拡大しています。その中核を担うスタッフの育成には、体系的な教育体制が欠かせません。実務に直結する知識や技術を着実に習得できる体制があれば、看護サービスの質が安定するだけでなく、スタッフの離職率の低下にもつながります。
本記事では、訪問看護事業での教育体制の必要性や具体的な導入手順・成功させるためのポイントを詳しく解説します。新人教育で必須となる研修制度も紹介するので、人材定着に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
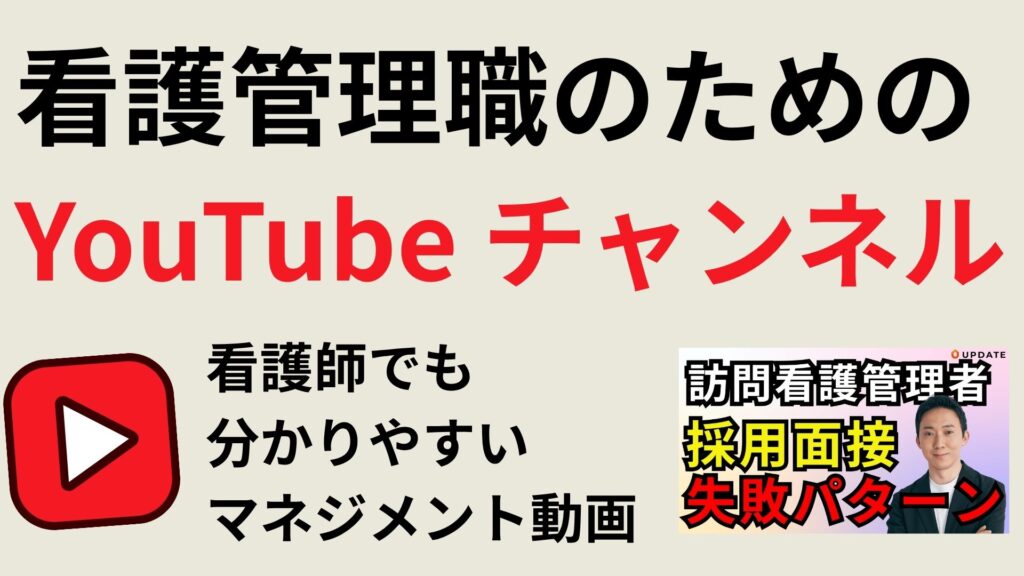
株式会社UPDATE 代表取締役(看護師・保健師・MBA) ケアプロ訪問看護ステーション東京にて新卒訪問看護師としてキャリアスタート。その後、訪問看護の現場・マネジメント経験の他、薬局や訪問看護運営するスタートアップ企業で40拠点・年商65億規模の経営を行い、上場企業へのグループインを実現。現在は医療職マネジメント人財を育成するためマネジメントスクールを運営中。
■経歴
2013年 慶應義塾大学 看護医療学部 卒業
2013年 ケアプロ株式会社入社
2019年 株式会社UPDATE(旧:ヘルスケア共創パートナー株式会社) 創業 代表取締役(現職)
2021年 GOOD AID株式会社 取締役(事業譲渡により退任)
2023年 セルフケア薬局 取締役(吸収合併により退任)
2023年 まちほけ株式会社 代表取締役(事業譲渡により退任)
■得意領域
医療系事業の組織マネジメント
教育体制構築
採用戦略・体制構築
教育体制構築
新卒訪問看護師の育成
管理職の育成
■保有資格・学位
看護師
保健師
経営学修士(MBA)
目次
訪問看護事業に教育体制が必要な理由
訪問看護は個別性の高いサービスであるため、スタッフの知識と技術のばらつきが品質を決める大きな要素です。そこで教育体制を整えることで、一定水準のサービス提供が可能となり、トラブルやミスのリスクも軽減されます。ここでは、訪問看護事業に教育体制が必要な理由を詳しく解説します。
サービス品質の向上
訪問看護では、スタッフ一人ひとりが現場で的確に判断・行動できる力を持つことが不可欠です。教育体制があれば、看護サービスの基準や対応方法を統一でき、経験や個人差によるサービスの質のばらつきを防げます。
利用者様にとって安心して利用できる環境が整うと、信頼性が向上し、事業所の評価にもつながります。このように、スタッフのスキルの底上げは、サービスの安定提供に効果的です。
人材定着率の向上
教育体制が整っている事業所は、スタッフにとって安心して働ける環境です。入職時から段階的に学べる仕組みがあれば、新人でもスムーズに現場に適応でき、定着しやすくなります。
また、整った教育体制によりキャリアアップの道筋が見えることで、スタッフの成長意欲も高まるため、キャリアへの不安による離職につながりません。結果的に、安定した人材確保と組織力の向上が期待できます。
関連記事:訪問看護師が辞める理由とは?負担軽減の解決策について紹介!
専門性の強化による他事業所との差別化
訪問看護で専門性を持つことは大きな強みです。教育体制を通じて特定分野に強いスタッフを育成すれば、他の事業所と差別化が図れるため、利用者様や医療機関からの信頼を獲得しやすくなります。
また、小児や精神・終末期など、専門的なケアに対応できる体制は、地域ニーズへの対応にもつながります。教育によって強みを明確にし、選ばれる事業所を目指しましょう。
リスクマネジメントの強化
訪問看護は1人で利用者様に対応する場面が多く、非常時にも独断での判断が必要になるため、対応力の差がトラブルにつながることもあります。教育を通じて、感染症対策や緊急時の対応・記録の正確な取り扱いなどを定期的に学べる体制を整えることで、リスクの早期発見や予防が可能になります。
スタッフの知識と意識の向上は、安心・安全な質の高い看護サービスの提供を実現し、利用者様とその家族の信頼を得やすくなるでしょう。
業務効率と経営の安定化
業務フローの標準化や知識の共有が進むことで、スタッフの負担が軽減し、日々の業務効率が向上します。教育体制により、全員が全ての業務に対応できる体制が整えば、急な欠勤や人手不足にも柔軟に対応可能です。また、スタッフが効率的に働ける環境は、結果的に収益性や事業継続性にもよい影響を与えます。
訪問看護事業所に義務付けられている研修

訪問看護事業所では、法令に基づき、スタッフに対する研修の実施が義務付けられています。研修内容は、法令やガイドラインに沿ったものが求められ、事業所内でも定期的に実施されます。内容は事業所の規模や地域によって異なることがありますが、主に義務付けられている法定研修の内容は以下の通りです。
- 訪問看護師のスキル向上に関する研修
- 感染予防や衛生管理に関する研修
- 個人情報保護やプライバシー配慮に関する研修
- 倫理的配慮や法令遵守に関する研修
- 認知症に関する研修
- 非常災害時の対応に関する研修
- 医療事故に関する研修
これらの研修は、業務に必要な知識や技術を維持・向上させるために大きな役割を果たします。特に、訪問看護の専門的なスキルや医療安全に関する研修は、看護サービスの質向上だけでなく、医療事故を未然に防ぐ役割も果たすため、訪問看護では欠かせない内容です。
各事業所で行われている教育体制の主な内容

各事業所での教育体制の整備によって、スタッフ一人ひとりが安心して働ける環境が生まれ、看護サービスの質の維持や業務効率化につながります。ここでは、現場で実施されている代表的な教育制度を紹介します。
新人研修プログラム
訪問看護では、入職時の新人研修がとても大きな役割を持ちます。現場では多様な疾患や生活背景を持つ利用者様に対応するため、即戦力で動けるようになるためには一定の準備やスキルが必須です。新人研修では、以下のような内容が重視されています。
- 専門知識と看護技術
- 安全性と品質
- コミュニケーションスキル
- 在宅ケアの実践
- チームでの連携
- リスクマネジメント
さらに、訪問マナーや記録の書き方・緊急時の対応などを段階的に学び、基礎看護技術の確認も実施されます。また、評価やフィードバックも定期的に行われるため、経験の浅い看護師でも安心です。内容はOJTに加え、オリエンテーションや講義形式・同行訪問など多様で、実践的な力を養うことができます。
クリニカルラダー制度
クリニカルラダーとは、看護師の「実践能力」や「マネジメント能力」「臨床実践能力」などのスキルを段階的に可視化・評価し、スキルアップを支える制度です。多くの事業所で導入されており、成長を促す枠組みとして機能します。
段階ごとに求められる知識や技術が明確にされており、目標が明文化されているため、自分に必要な学びを計画的に進められます。また、評価や定期的なフィードバックは、看護師本人のモチベーション向上だけでなく、管理者や教育担当者の正確な情報把握にもつながります。
メンター・プリセプター制度
新人や経験の浅い看護師を支える制度として効果を持つのが、経験豊富な先輩看護師が指導役となるメンター・プリセプター制度です。業務上の不安や困りごとを相談できる相手がいることで、精神的な安心感が生まれ、業務にも集中しやすくなります。
メンターは技術指導だけでなく、組織内のルールや人間関係も伝える役割を担い、新人の早期離職防止にもつながります。また、指導役となる先輩看護師にとっても、指導力やマネジメント能力の向上を目指せる点もメンター制度のメリットの1つです。
関係性を築くことが目的であるため、月に数回の面談や同行訪問など継続的なサポートが実施されます。
外部研修
より専門的な知識や技術を習得するためには、外部研修の活用が効果的です。事業所内では扱えない領域の学びを取り入れることで、看護の幅が広がり、利用者様への対応力も向上します。
訪問看護に関連する学会や地域の研修会・企業などが、管理者やスタッフ向けに、様々な研修を提供しているため、事業所内では扱えない内容を選択して参加できます。提供されている研修の内容は「小児訪問看護」や「地域の認知症療養者のための多職種連携」から、「保険請求業務」や「診療報酬改定研修」など様々です。
また、受講後の学んだ内容の事業所内での共有によって、組織全体のスキルアップにもつながります。
eラーニングシステム
eラーニングは、インターネットを利用した学習方法です。パソコンやスマートフォンを用いて時間や場所にとらわれず学習できるため、多忙な訪問看護師でも空き時間を使って学習できる大きなメリットがあります。
多くの事業所では、基礎看護技術や感染対策・法令遵守など幅広い分野のコンテンツが用意され、反復して学べる仕組みも整っています。
また、受講状況や理解度の管理ができるため、管理者側にとっても教育の進捗を把握しやすい方法です。柔軟な学習環境を整えることで、スタッフも学びを継続しやすくなります。
「しっかり組織マネジメントの基礎を学びたい!」という方向けに、UPDATEでは『訪問看護特化の組織マネジメント基礎講座』を開催しています。無料の体験クラス動画もご用意してますので、興味のある方はぜひご覧ください。
無料体験クラス「組織に合わない言動を放置する悪影響と、効果的なフィードバック」
訪問看護による教育体制構築の手順
訪問看護で、継続的に高い質の看護サービスの提供を維持するには、体系的な教育体制の整備が不可欠です。現場の実情に即した教育計画を策定し、スタッフが安心して学び続けられる仕組みの構築が、組織の成長と安定的な運営につながります。ここでは、訪問看護での教育体制構築の手順を解説します。
1.現状の分析と教育目標の設定
教育体制を築くには、まず事業所の現状を正確に把握しましょう。組織全体のスキルレベルや課題を洗い出し、現場に求められる知識や能力を明確にします。その上で、到達すべき人材像や教育目標を定めることで、今後の教育の方向性が具体化します。
2.教育プログラムの設計
次に目標に基づき、各レベルに応じた教育プログラムを設計します。必要な知識やスキルを分類し、新人向け・中堅向けなど段階的な学習内容の整理を行うことで、計画的な成長を促せます。また、OJTとOff-JTを組み合わせて、実務力と理論をバランスよく身につけられる体制を構築しましょう。
3.リソースの確保
教育の質を保つには、指導役や時間・教材などのリソースの確保が欠かせません。社内に経験豊富なスタッフがいない場合には、外部講師の導入も検討しましょう。また、業務に支障が出ないように研修時間を適切に確保し、環境面にも配慮する必要があります。十分なリソースが整えば、教育活動がスムーズに進みます。
4.年間研修計画の作成とスタッフへの周知
教育内容が決まったら、年間を通じた研修スケジュールを作成します。研修のタイミングや対象者を明確にし、スタッフが無理なく参加できるように設定しましょう。さらに、事前に全員に内容を周知しておくことで、研修に対する意識を高め、モチベーションの向上につながります。
5.研修の実施と記録
計画に基づき研修を実施したら、参加状況や内容・学習成果などを記録しましょう。記録があれば、後から個別の進捗確認や制度の見直しがしやすくなります。OJTの際も、簡単な記録様式を用意すると、教育の成果が曖昧にならず、継続的な育成につながります。
6.評価と改善
教育の成果を定期的に評価し、問題点を洗い出して改善につなげます。受講後のアンケートや面談を通じて、スタッフの反応や理解度を把握し、必要に応じて内容や方法を見直しましょう。このサイクルを繰り返すことで、より実践的で効果的な教育体制に成長します。
訪問看護による教育体制を成功させるコツ

訪問看護による教育体制を成功させるポイントは、明確な目標と柔軟な運用です。現場に即した設計とスタッフの理解を得ることで、教育の定着と組織全体の成長につながります。ここでは、訪問看護の教育体制を成功させるコツを紹介します。
具体的で分かりやすい教育目標を設定する
教育の成果を引き出すには、誰にでも理解できる具体的な目標設定が効果的です。抽象的な表現では到達点が見えにくいため、学習の意欲にも影響を与えかねません。
例えば「報告・連絡・相談の質を向上させる」ではなく、「訪問後1時間以内に記録を完了できるようになる」のように、行動レベルまで落とし込むことで達成度が明確になります。目標が明確であれば、学ぶ側も主体的に取り組めます。
外部研修を活用する
社内だけではカバーできない知識やスキルを補うには、外部研修が効果的です。専門的なテーマや最新の知識、技術など限られたリソースでは伝えにくい内容も、外部講師やセミナーを通じて効率的に学ぶことができます。
また、外部研修の活用は教育担当者の負担軽減にもつながるため、全体の教育バランスを保ちやすくなります。
定期的にフィードバックを行う
教育の効果を維持・向上させるためには、スタッフへの定期的なフィードバックも欠かせません。一方的な指導ではなく、進捗や理解度を確認しながらコミュニケーションを取ることで、学習内容が定着しやすくなります。
フィードバックの場では改善点だけでなく、よかった点も伝えることでスタッフの自己肯定感が上がり、業務にも意欲的に取り組むようになります。また改善点は指摘するだけではなく、次のステップにどうつなげるかを共有しましょう。こまめな振り返りが、教育体制の質を大きく左右します。
訪問看護による教育体制構築時の注意点
訪問看護の教育体制を構築する際には、スタッフの負担を避けなければなりません。そのため、無理のないスケジュールでの研修計画を立てることが大切です。過度な負担をかけると、効果的な学びが得られないだけでなく、スタッフのモチベーションも低下してしまいます。
また、スタッフがより実践的な知識を身につけやすいよう、研修内容は実務に直結したものに絞るのがおすすめです。業務に必要なスキルを重点的に学ぶことが、教育体制の成功につながります。各スタッフの成長速度に合わせた進行を心掛け、研修後も相談しやすい職場環境を作るなど、継続的なサポートを行いましょう。
まとめ
訪問看護での教育体制の整備は、質の高い看護サービス提供と経営の安定に直結します。現場で必要とされる知識やスキルを継続的に習得できる環境が、人材の定着や差別化にもつながります。訪問看護事業所の持続的な発展に向けて、成功につながる教育体制を構築していきましょう。
UPDATEでは、人材が定着する訪問看護事業所の経営に向けて実践的なマネジメントが学べる『訪問看護マネジメントスクール』や『人事・組織構築コンサルティングサービス』を提供しています。なかなか人材が定着しないことで事業所運営に困っている方はぜひ一度、お気軽にお問合せください。