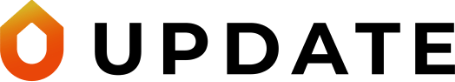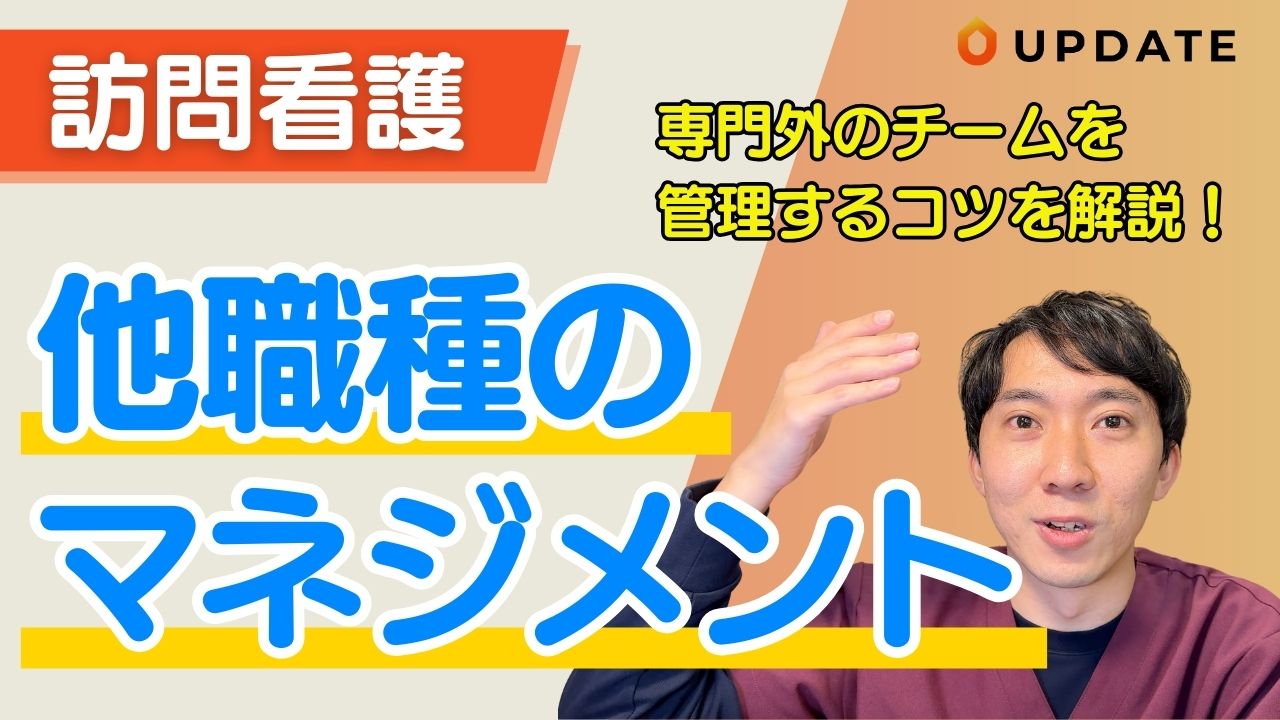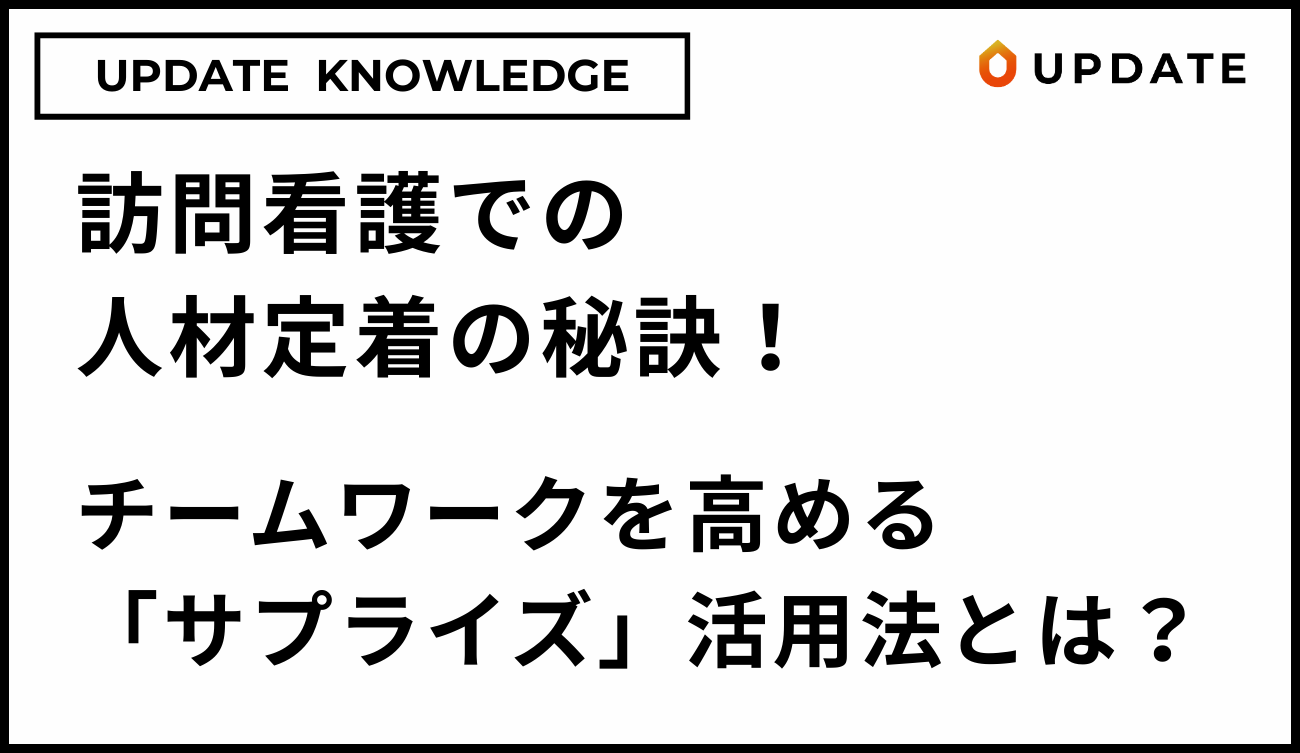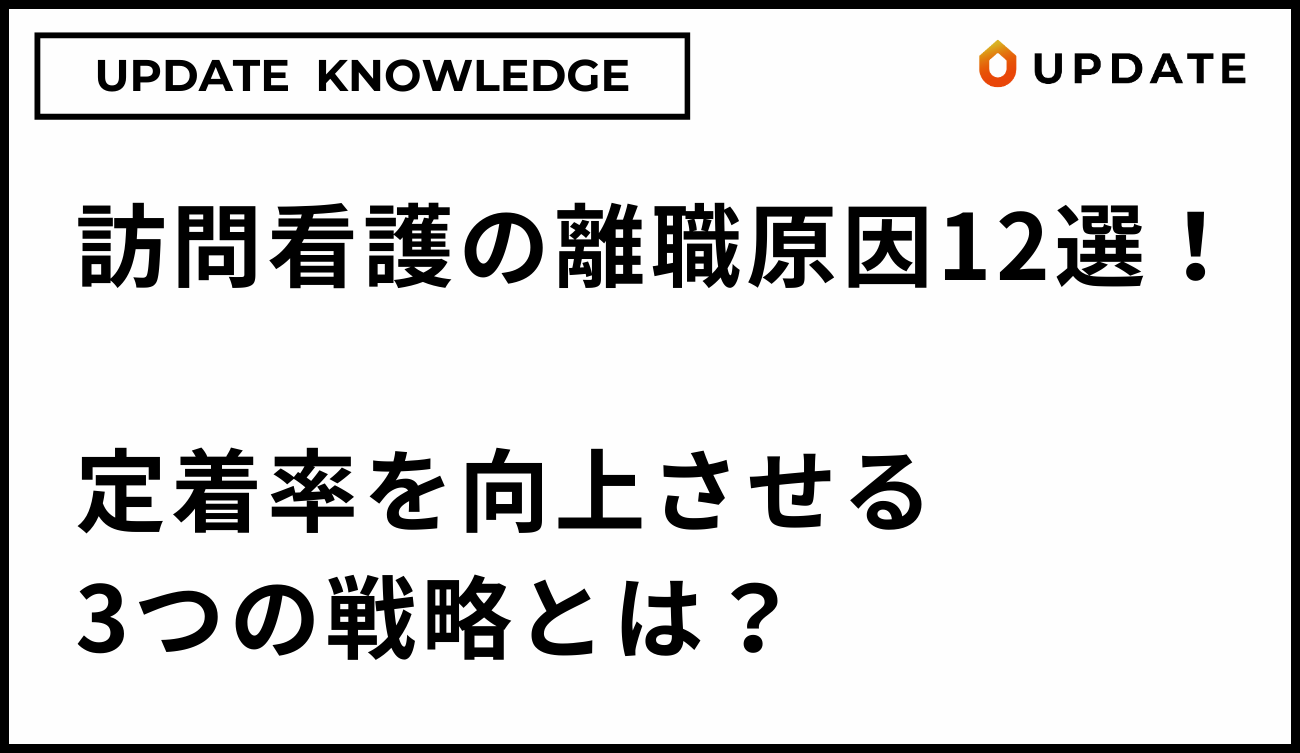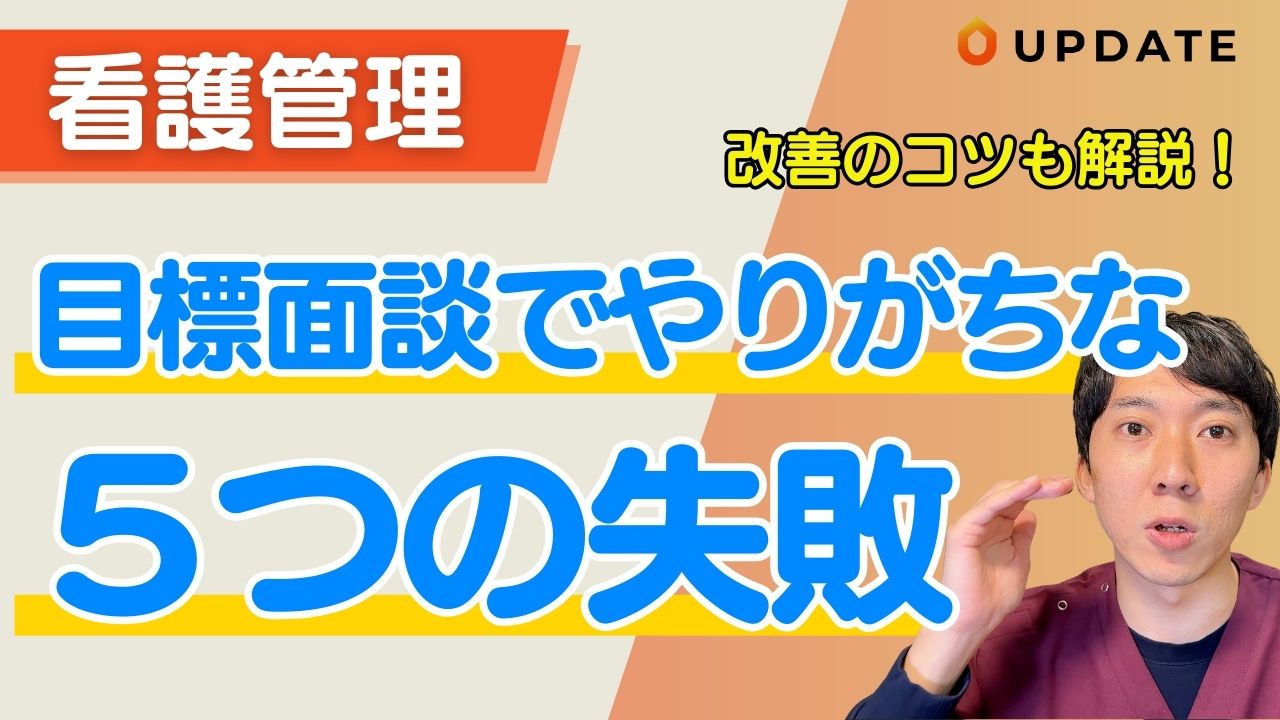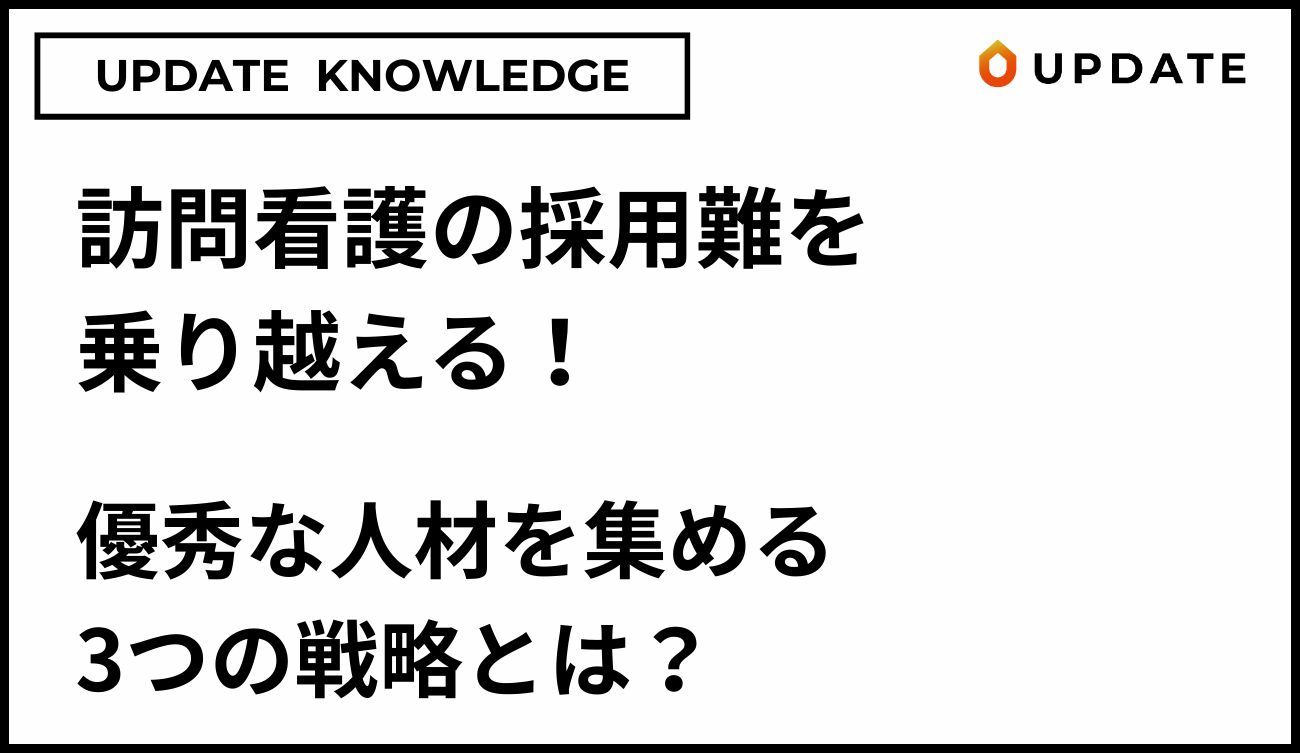訪問看護師の離職率・退職理由とは?スタッフが定着する5つの対策を徹底解説!
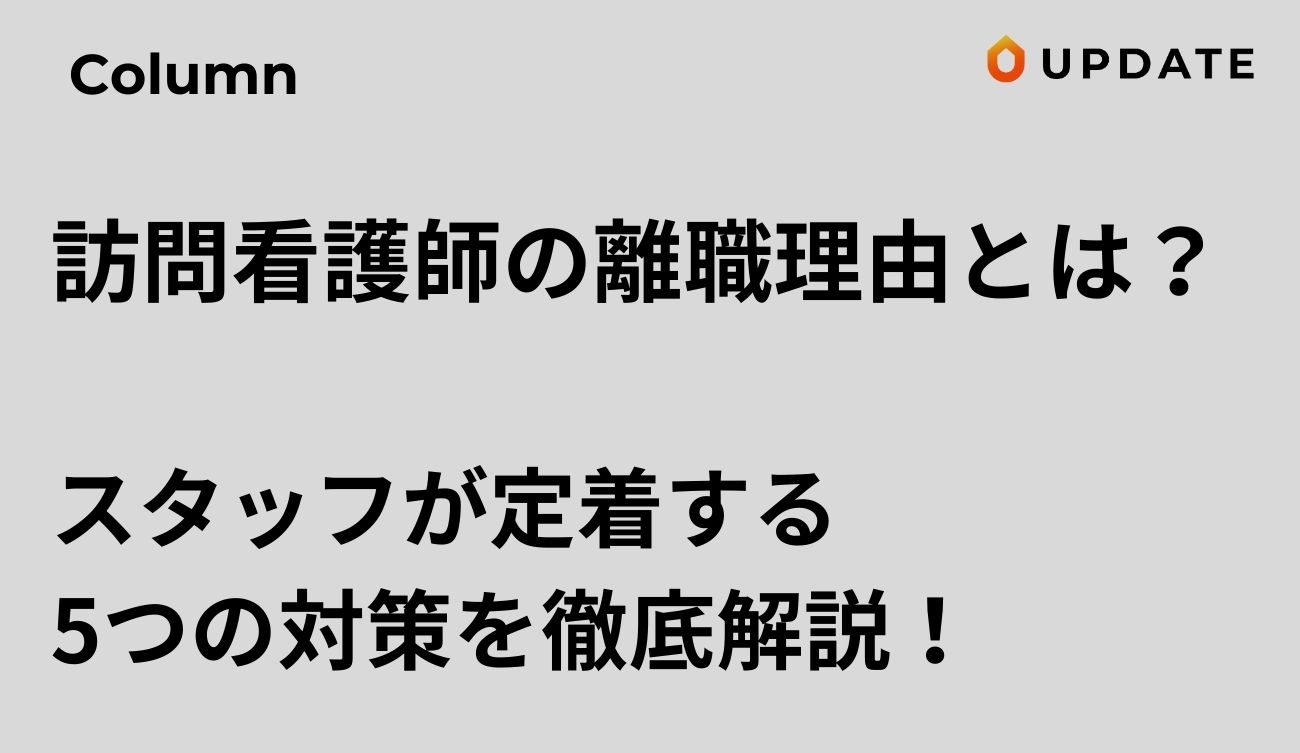
訪問看護ステーションを運営するなかで、
「新しいスタッフがすぐ辞めてしまう」
「スタッフが安定せず業務が回らない」
と悩んでいませんか?
訪問看護はやりがいがある一方で、精神的・肉体的な負担や職場環境の問題に悩み、退職を選択するスタッフも少なくありません。
スタッフの離職が相次ぐと現場が回らなくなり、ステーションの管理者が窮地に立たされる場面は少なくないでしょう。
本記事では、訪問看護スタッフの離職率・退職理由や、離職防止のための具体策について詳しく解説します。
記事を読み進めることで、スタッフの離職を防ぎ、経営を安定化させるためのヒントが得られるでしょう。ぜひ最後までお読みください。
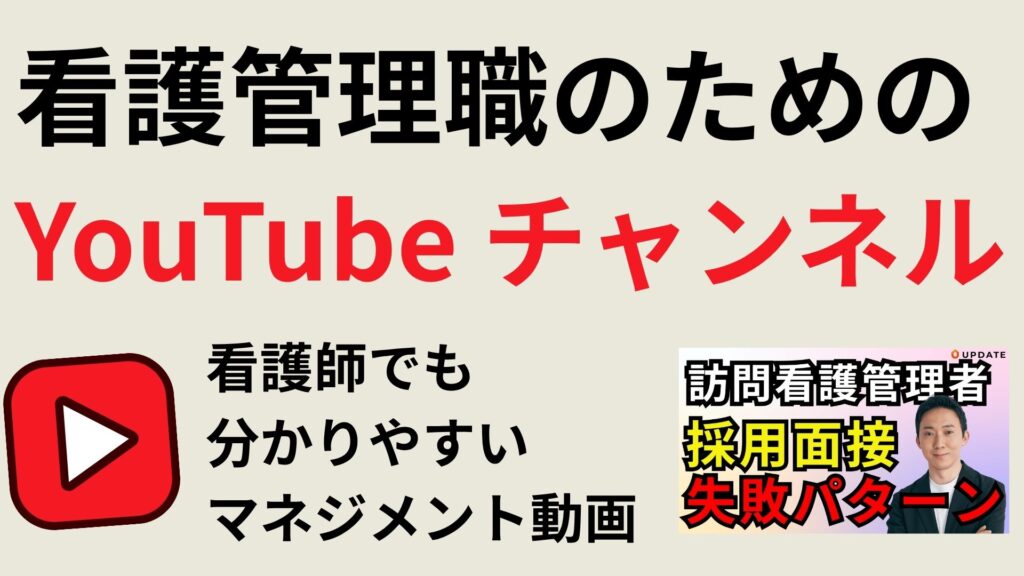
目次
訪問看護師の主な3つの離職理由とは?

訪問看護スタッフの離職は、精神的な負担や肉体的な負担、オンコール対応の厳しさなどの要因が重なって生じます。本章では、各要因について詳しく解説します。
理由1.精神的な負担が大きい
訪問看護の現場では、終末期ケアやお看取りなどで緊張が続き、精神的な負担が大きくなりやすい傾向があります。
教育体制が整っていない場合、新人スタッフが単独訪問に対し不安を感じることもあるでしょう。
さらに、訪問先の環境が医療施設と異なり、十分な設備がない場合、看護師が工夫を求められる場面も少なくありません。このような状況が続くことで、心身の負担が限界に達し、辞職を考えるケースが考えられます。
理由2.肉体的な負担が大きい
訪問看護は一日に複数の利用者宅を回るため、移動による疲労を感じる場合があります。訪問後には記録や事務作業が残り、勤務時間内に業務を終えることが難しい現場もあります。
移動や残業による疲労が慢性化すればモチベーションが低下し、健康面にも悪影響を及ぼすかもしれません。
このように肉体的な負担が大きい点も、離職を検討するきっかけとなります。
理由3.オンコールがもたらす影響
オンコール対応は、訪問看護の業務の中でも特に看護師に負担を与える要素の一つです。対応頻度が高まると、十分な休息が取れなくなる恐れがあります。
精神的な緊張感が続き、睡眠不足や疲労感が蓄積すれば、心身の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、オンコール対応はプライベートの時間を削るため、家族や友人との関係にも支障をきたすかもしれません。
このようにオンコールの頻度が多いと、仕事と生活のバランスを崩し、働く意欲を損なう可能性があります。
訪問看護スタッフの離職率はどれくらい?
神奈川県の調査によると、2023年度における訪問看護ステーションの看護職員(神奈川県内)の離職率は 16.7%でした。前年度(2022年度)の18.1% に比べて1.4%の改善がみられています。
また、少し古いデータではあるものの、全国訪問看護師の離職率(2007年度)は15.0% でした。これは同時期の病院看護師の離職率(12.6%)よりもやや高い結果となっています。
訪問看護の離職率は、病院よりやや高い傾向にあることがわかります。
参考:令和5(2023)年度 看護職員就業実態調査結果 (訪問看護ステーション)
訪問看護の伸び悩みに関するデータ p.2
訪問看護スタッフの離職がステーション経営に与える影響
訪問看護スタッフの離職は、ステーションの経営に直結する問題です。採用や教育にはコストと時間がかかるため、離職が相次ぐと負担が増し、経営を圧迫します。
人員不足が続けば新規利用者の受け入れを制限せざるを得ず、売上減少やサービス低下につながるため注意が必要です。
さらに、離職は残されたスタッフへの負担を増やし、職場の雰囲気を悪化させる要因となります。結果として、サービスの質を維持できず、事業運営が不安定になるでしょう。
現場の課題を解決するには、管理者がマネジメントを体系的に学ぶことが重要です。
私たちUPDATEの訪問看護特化、基礎から学ぶ組織マネジメント研修では、人材定着や経営改善に役立つ知識を実践的に学べます。
訪問看護40拠点・12年以上の現場経験を持つ代表・小瀬が、リアルな失敗談とともに、成果につながるノウハウをお伝えします。
受講者の方々からは、
「現場に近い内容でわかりやすかった」
「明日からやってみようと思える具体策がわかった」
などのお声も多数!
スタッフからもっと信頼される管理者になるために、あなたも一歩踏み出してみませんか?
ぜひ以下のバナーより、無料体験講座をご覧ください。

訪問看護師の離職を防ぐための3つの方針
離職防止策を考えるうえで、現場の負担や不安軽減に向けた方針づくりが必要です。
東京都福祉局の調査によると、訪問看護ステーションのスタッフ定着に必要な要素として、常勤看護師の66.2%が「給与・賃金」と回答しました。次いで「人材育成支援」が48.3%、「OJT(職場内研修)」が35.7%でした。
このデータから、給与だけでなく、訪問看護師としての成長を支える仕組みも重視されていることがわかります。本章では、離職防止のための3つの方針を解説します。
参考:東京都福祉局 Ⅳ.訪問看護の人材確保・定着に関する調査 p.24
方針1.給与や待遇の改善をする
給与や待遇の改善は訪問看護師の定着率向上に重要です。オンコール対応や長時間労働、移動などの負担に対して、報酬が見合わないと感じるケースが多いためです。
管理者は報酬体系をコストではなく投資と捉えましょう。
報酬を高めるだけでなく、貢献や働き方にあった評価が重要です。公平な評価制度の導入により、働きがいとモチベーション向上が期待できます。
また柔軟な働き方を支援すれば、育児や介護との両立を可能にします。これにより職場満足度が向上し、離職率の低下につながるでしょう。
方針2.人材育成支援を充実させる
教育や研修が整っていないと、新人や若手が不安を抱きやすく、早期離職の一因となる場合があります。
訪問看護では、病棟と違い単独訪問によるケアを行なう機会が多くあります。病院での看護とは異なり、すぐにはサポートを得られないケースもあるでしょう。
そのため、対応に不安を感じたり、「成長できているだろうか?」と焦りを感じたりする場合があります。
これらのことから、経験やスキルに合わせた教育プログラムを整備したり、スキルアップの機会を整えたりする工夫が必要です。
また、東京都福祉局の調査では、黒字経営の事業所ほど研修が充実している傾向があると報告されています。この結果からも、教育に力を入れることで人材が定着し、安定した運営につながるといえるでしょう。
参考:東京都福祉局 Ⅳ.訪問看護の人材確保・定着に関する調査 p.23
方針3.スタッフ間のコミュニケーションを活性化する
人間関係が原因での退職を防ぐには、スタッフ間のコミュニケーションを活性化する取り組みが欠かせません。円滑なコミュニケーションは、信頼関係を構築し、チーム全体の士気を高める重要な要素です。
定期的なミーティングや意見交換の場を設け、個々のスタッフが抱える問題を共有しやすい環境をつくれば、相互理解が深まります。
これにより職場内の協力体制が強化され、働きやすさが向上し、退職率の低下にもつながるでしょう。
関連記事:訪問看護はきついって本当?訪問看護師を辞める理由と対策を解説|すべらない転職
「しっかり組織マネジメントの基礎を学びたい!」という方向けに、UPDATEでは『訪問看護特化の組織マネジメント基礎講座』を開催しています。無料の体験クラス動画もご用意してますので、興味のある方はぜひご覧ください。
無料体験クラス「組織に合わない言動を放置する悪影響と、効果的なフィードバック」
訪問看護スタッフの定着率を高める具体策5選
訪問看護師の定着を促すためには、方針を現場で具体策として落とし込むことが重要です。
続いて、管理者が実務で取り入れやすい5つの方法を紹介します。
対策1.給与や待遇を見直す仕組みづくり
管理者は経営と人材定着の両立を意識し、給与体系や待遇を見直すことが求められます。
改善のための対策例は以下のとおりです。
- オンコール手当や残業代の適正化
- 公平で透明性のある評価制度
- 資格取得や研修への支援
- 経験やスキルに応じた昇給制度
努力が正当に評価される環境が整えば、離職率の低下につながります。
対策2.ワークライフバランスを支援する制度設計
スタッフが安心して長く働ける事業所づくりのためには、ワークライフバランスを重視した制度設計が欠かせません。
子育てや介護と仕事の両立がしやすい制度が整っていれば、ライフステージが変わっても働き続けられるでしょう。
具体的な取り組み例として、以下が挙げられます。
- 訪問件数やオンコール回数の適正化
- ローテーション制や夜勤専従スタッフの配置
- 有給休暇やリフレッシュ休暇取得を推進
- フレックス勤務や短時間勤務制度の導入
無理なく働ける環境の整備が、スタッフの離職を防ぎ、質の高いケアの継続につながります。
対策3. ICTシステムの導入
業務負担の軽減には、ITシステムや業務支援ツールの導入が効果的です。
記録やスケジュール管理などの事務作業は、スタッフが負担に感じやすい訪問看護の特徴の一つです。業務効率化のためには、電子カルテやスケジュール管理システムを導入するとよいでしょう。
例えば、スマートフォンやタブレット端末を活用すれば、訪問先でリアルタイムに情報入力できます。これにより、帰社後の事務作業を大幅に削減できるでしょう。
効率的な業務体制を整えることで、看護業務に集中できる環境が生まれ、スタッフの働きやすさにつながります。
介護業界のデジタル化を強力にサポートするツールについては、こちらをご覧ください。
【介護DX】2024年最新版!介護業界の業務効率を劇的に向上させる管理ツールと利用例を解説|cyzen
対策4.スキルアップ・研修制度の整備
幅広い知識と判断力が求められるため、学ぶ環境の不備により不安やストレスが増し、離職につながる場合があります。とくに経験の浅い若手看護師は、「この先やっていけるのか」という焦りを感じやすいでしょう。
またスキルアップの機会も、スタッフの安心感やモチベーションを支えるうえで欠かせません。
スキルアップや研修制度の整備に関する取り組み例は、以下のとおりです。
- 経験年数やスキルに合った教育を行なう
- 定期的な院内・社内研修を実施する
- 外部講習や関連学会の告知をする
- 資格取得をサポートし、キャリア形成を後押しする
研修制度の充実により、スタッフは「成長できる職場」という安心感を得られ、人材定着につながるでしょう。
対策5.相談・連携しやすい環境づくり
訪問看護は一人での業務が多く、孤独感や不安を感じやすい仕事です。そのため、上司や同僚に気軽に相談できる雰囲気を作ることが大切です。
具体的な取り組み例として、以下が挙げられます。
- 定例のカンファレンスやミーティングを開催する
- スタッフとの個別面談で、安心して相談しやすい環境を整える
- 雑談や社内イベントなど、交流の場を意図的に設ける
日頃から風通しの良い職場作りを意識すれば、スタッフの安心感が高まり、離職防止につながります。
まとめ:訪問看護スタッフの離職理由を理解し、定着率を高めよう
訪問看護師が離職する背景には、精神的・肉体的な負担やオンコール対応などの要因があります。
管理者は3つの要因を理解し、定着率を高める工夫を取り入れることが重要です。
離職防止は一つの施策だけで解決できるものではなく、経営視点を踏まえた総合的な取り組みが求められます。
相次ぐ離職を食い止めて、スタッフの定着を促すためには、管理者自身がマネジメントを体系的に学ぶことが欠かせません。
私たちUPDATEの訪問看護特化、基礎から学ぶ組織マネジメント研修では、人材定着や経営改善に役立つ実践的なノウハウを提供しています。
受講者の方々からは、
「モヤっとする現場の悩みを解決できた」
「組織の適切な配置や役職採用での注意点がわかった」
「メンバーへのフィードバック方法や関わり方がわかった」
などのご感想をいただいています。
現在、無料体験講座を配信中です。さらに受講者特典として、特別プレゼントもご用意しています。
以下のバナーより、ぜひお受け取りください。