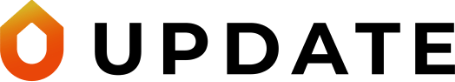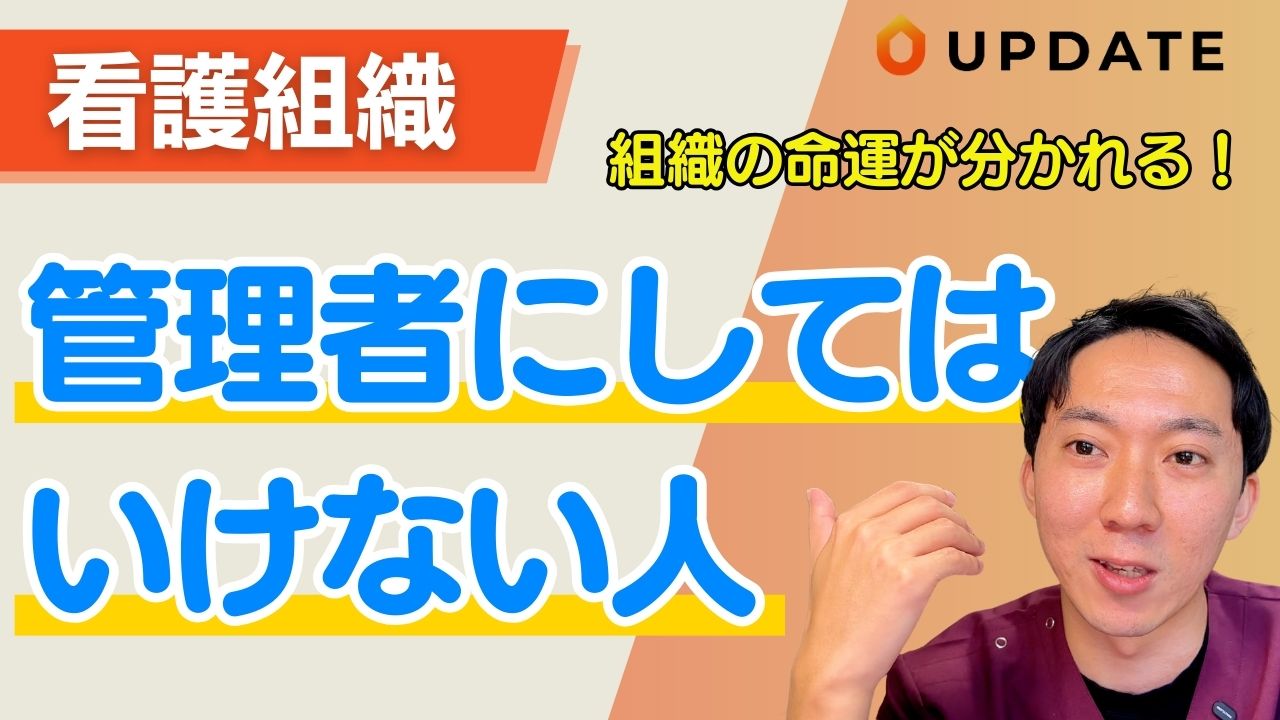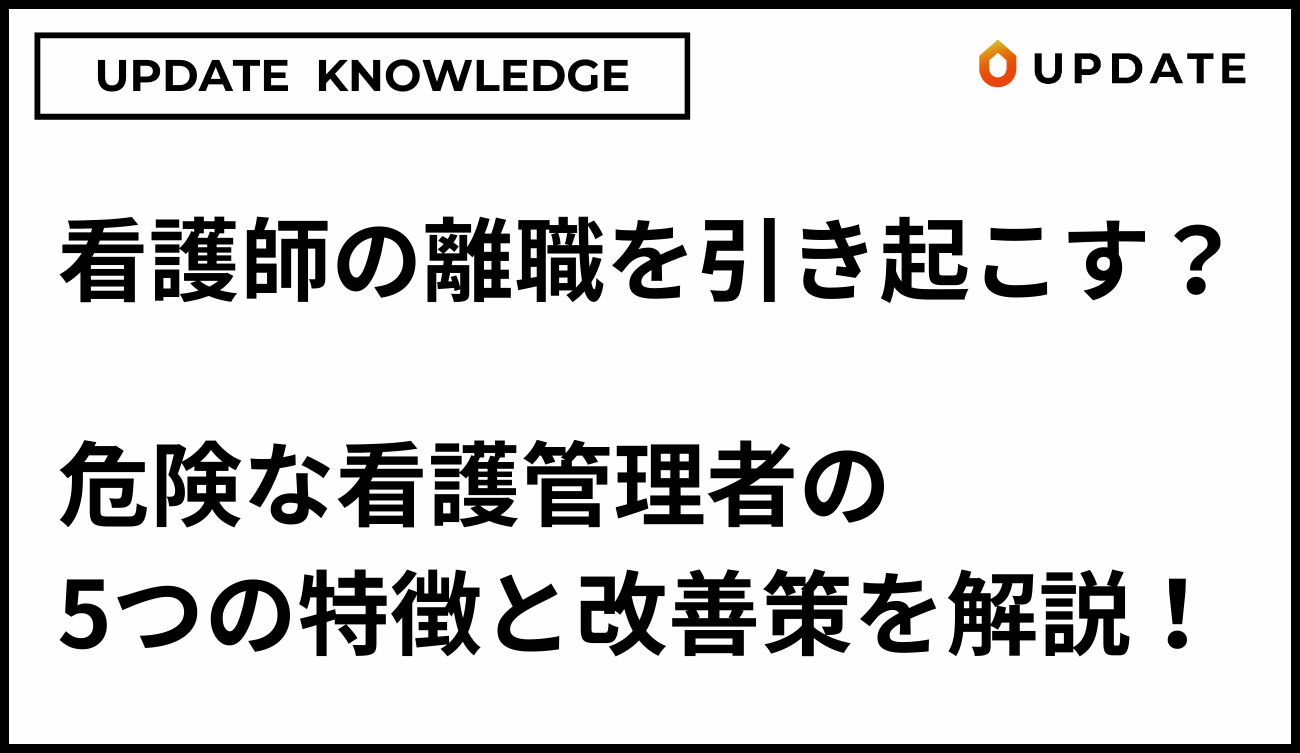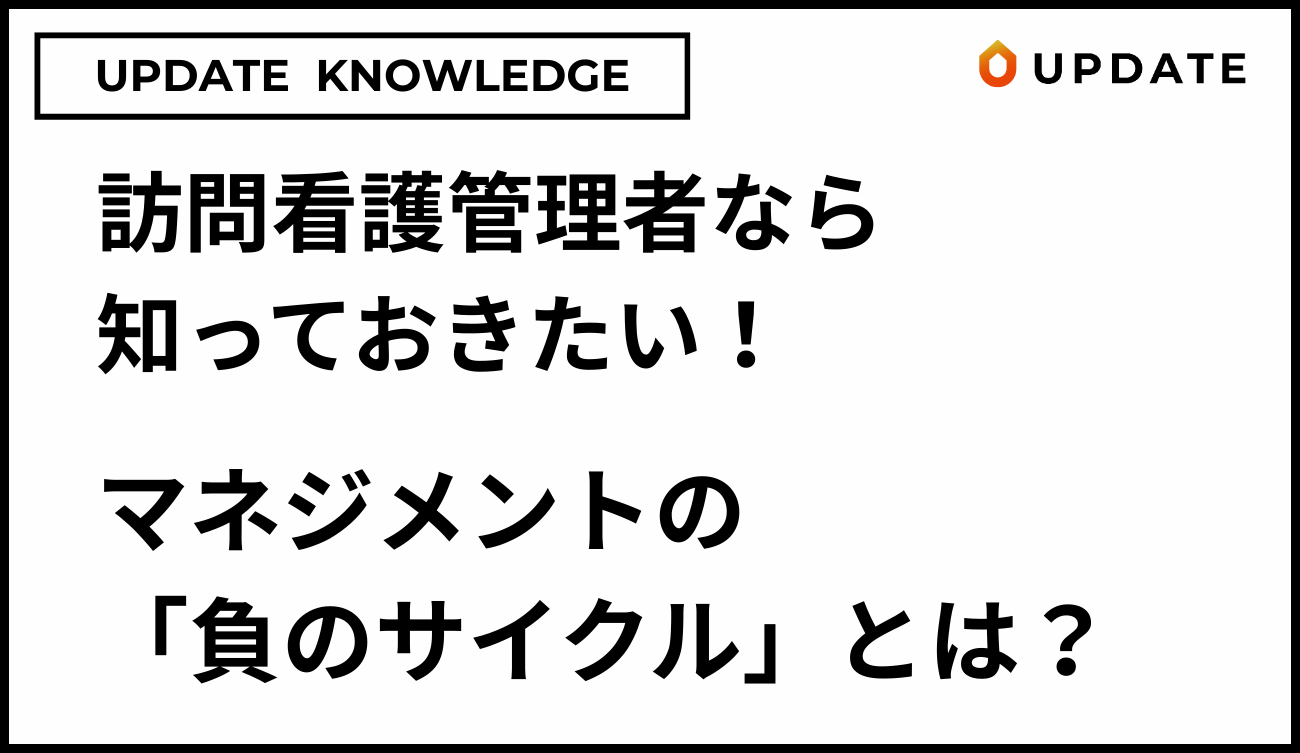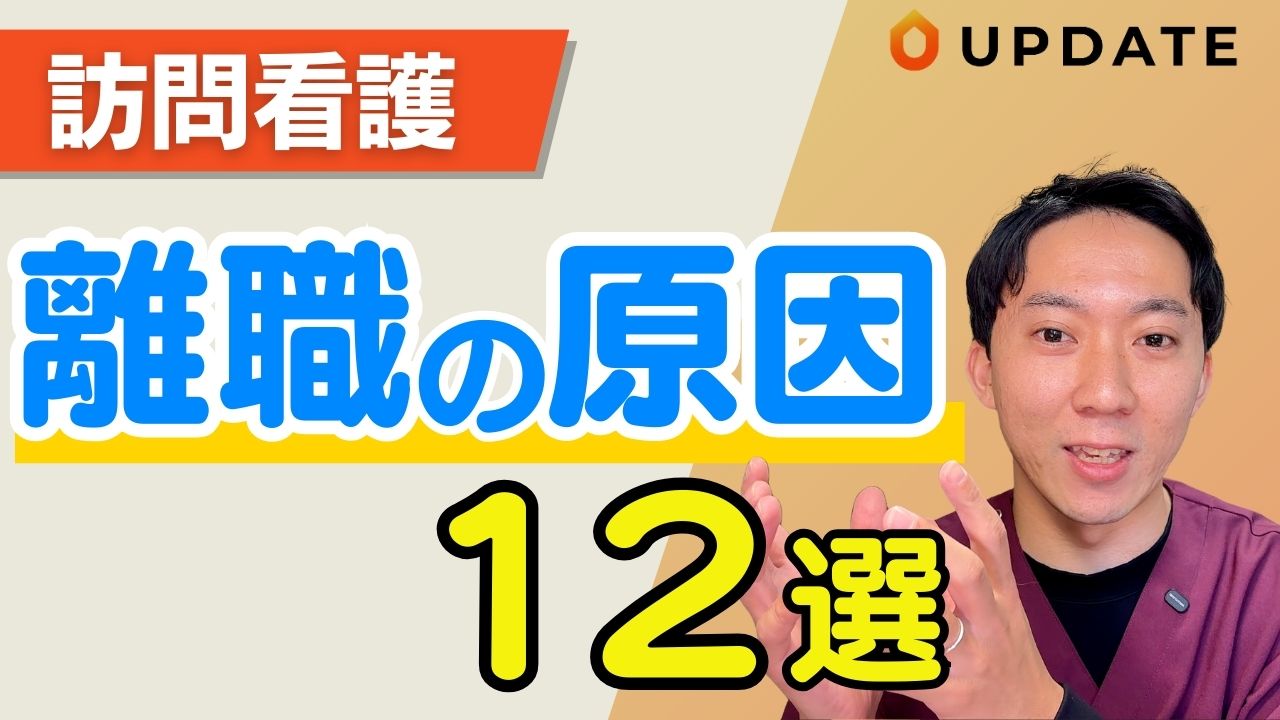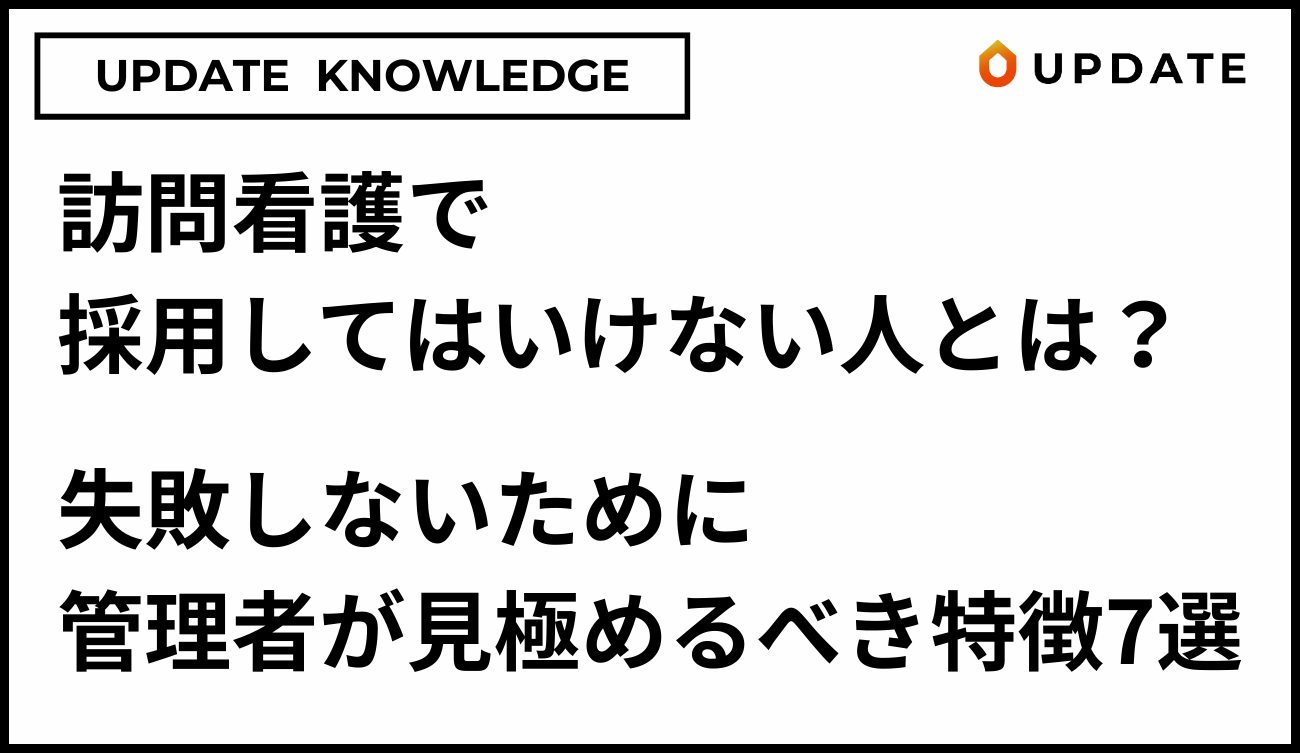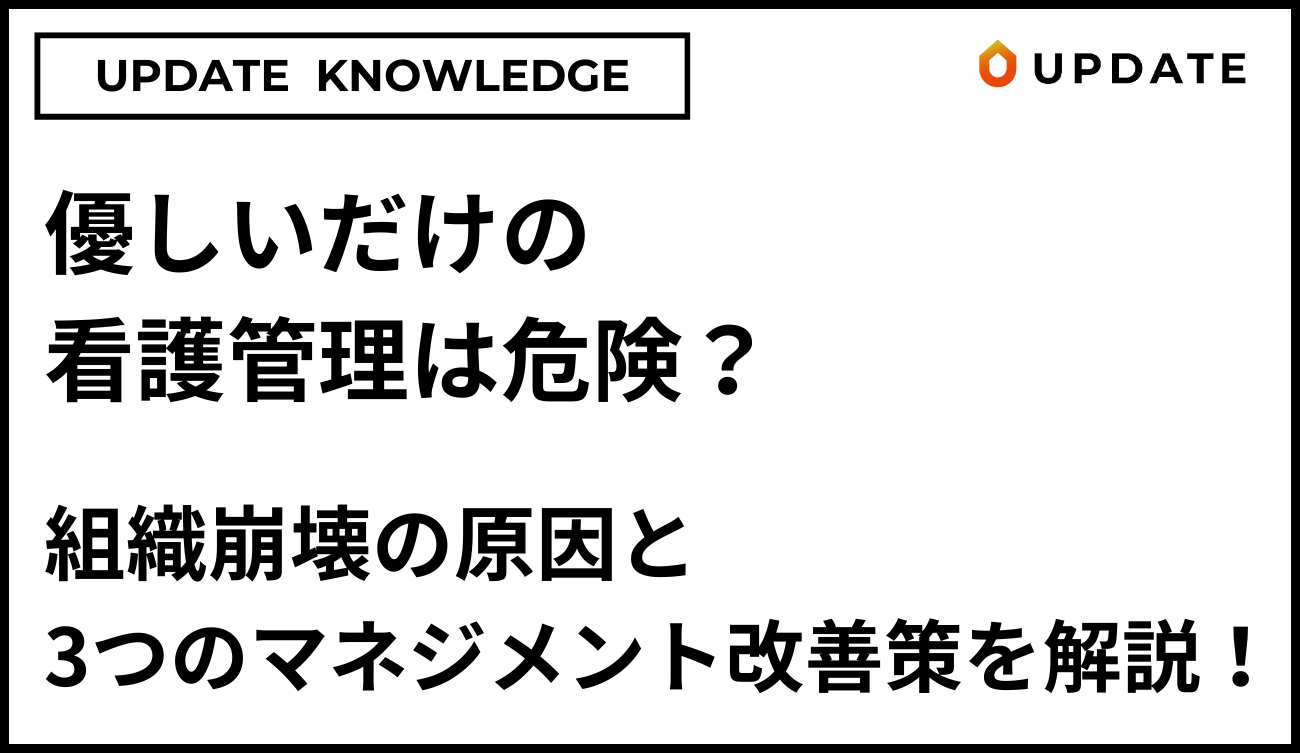訪問看護ハラスメント対策ガイド|管理者が取るべき実践策

訪問看護の現場では、利用者様やご家族の言動が意図せずハラスメントとなり、看護師の安全とサービス継続に影響する事例が増えています。管理者が迅速に実態を把握し、組織全体で対策を講じることが、職員の離職防止と質の高いケア提供を両立させる鍵です。本記事では、最新の業界動向と厚生労働省指針を踏まえ、現場に即した具体策を体系的に整理しました。
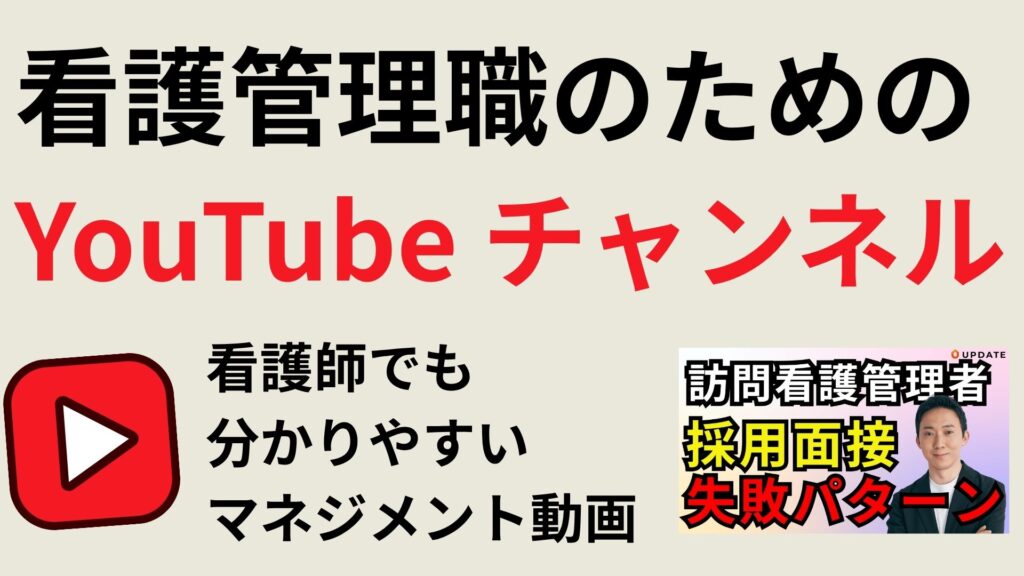
目次
訪問看護におけるハラスメントの現状

まずはハラスメントがどのような形で発生し、背景に何が潜むのかを整理しましょう。被害に遭った職員が声を上げにくい状況を理解することで、管理者は潜在リスクを具体的に把握でき、次の対策ステップが明確になります。ここで示す典型的事象と反応を踏まえた上で、ステーションとして優先順位を定める基礎情報を共有してください。
身体的な攻撃と背景
叩かれたりお茶や水をかけらえる、持参した血圧計や体温計を投げつけられ破損するといった行為は暴行障害に該当する重大事象です。管理者は「ご高齢で、これまでの性格もあるから仕方ない」などと済ませる反応が職員に生じやすい点に注意し、身体疾患や認知機能低下による拒否的反応と暴力を切り分けて評価する体制を整備する必要があります。
さらに訪問計画段階でリスク評価シートを作成し、二人体制や訪問時間短縮など複数の選択肢を持たせることで先回りした安全確保を図りましょう。こうした記録は発生時の証拠となり外部支援要請の際にも説得力を高めます。継続モニタリングで症状変化と攻撃性の関連を医師へ報告し治療調整も促進可能です。
精神的な攻撃と背景
「下手くそ」「帰れ」といった大声や中傷は職員の自尊感情を損ない離職を招く重大リスクです。権利意識の高まりや長期関係で起こる意識の緩みが背景にあり、スタッフのケアや対応の統一が難しいことも要因となります。管理者はサービス契約時に行動規範を明示し過度な要求を線引きする姿勢を示すことが不可欠です。
さらに職員が明らかな攻撃的言動を受けた際はその場で退避を認める方針を徹底し、帰所後速やかに事実確認と感情ケアを実施します。組織として「一人で抱え込ませない」文化を醸成し記録共有とケース会議で学びに変える仕組みを作りましょう。適切な境界設定は利用者様の満足度維持にも寄与し双方の信頼関係を再構築できます。
性的言動と背景
身体接触の強要や卑猥な質問は被害者が恥ずかしさから相談をためらいやすく表面化しづらいのが特徴です。密室環境で入浴介助など直接触れるケアが多い訪問看護では誤解や依存が助長されるリスクがあります。管理者は契約書に性的言動に対する禁止事項を明記し、研修で具体例を共有して早期認知を促進してください。
発生時は性別を問わず速やかに同席者を追加し記録を残した上で利用者様やご家族へ行動の不適切さを説明し継続訪問の条件を再協議します。被害者のプライバシー保護と心理的サポートを最優先にし安心して報告できる相談体制を設けることが必要です。
その他のハラスメント
無許可撮影や訪問時間外の呼び出し、事務所前での待ち伏せは生活領域を侵害し深刻な精神的負荷を与えます。長期関与や好意の誤認が要因となりやすく、契約で定めた時間外対応範囲を曖昧にすると被害が拡大します。
管理者は面談記録に行動の履歴を残し、連続発生時はケアマネージャーや地域包括支援センターと協議し訪問方法を変更するなど環境面の調整を図りましょう。
行為が継続し改善が見込めない場合には契約解除や警察相談も選択肢として明示し職員を保護する姿勢を組織として示すことが大切です。この段階でも感情的対立を避け第三者を交えた説明で透明性を確保することが信頼回復につながります。毅然とした態度が再発防止の鍵です。
管理者が整える組織的な予防体制
ハラスメントを個々の判断に委ねると再発リスクは減りません。管理者は経営資源配分を含む組織的対応を定義し、誰が何をいつ行うかを明文化する必要があります。以下では方針策定から情報共有まで、運営基盤となる仕組みの構築手順を示します。ステーションの規模や訪問件数に左右されずに機能する再現性の高いプロセスを設計することがポイントです。
ハラスメント方針と行動規範の策定
組織のトップが「ハラスメントは許さない」と明文化し契約書や重要事項説明書へ反映することで職員と利用者双方に基準を示せます。宣言は感情的表現ではなく具体的行動例と禁止行為を列挙し違反時の対応フローを併記することが要件です。
管理者は策定プロセスに職員代表を参加させ現場実態に即した内容へブラッシュアップしながら納得感を高めましょう。この方針は毎年度見直し改訂を周知することで形骸化を防ぎ常に最新の指針として機能します。
利用者様には初回訪問前に書面で説明し同意を得ることでトラブル時の交渉基盤を確立できます。経営者自ら署名し組織文化への本気度を示す姿勢が信頼を高めます。
リスクアセスメントと記録フォーマット
定量化されたリスクアセスメントは優先度の高いケースを即座に抽出し対策資源を集中投下する判断材料となります。チェックリストには身体的暴力歴、服薬状況、認知機能、家族構成、住宅環境を盛り込み客観的スコアで可視化する設計が有効です。記録フォーマットは電子カルテやクラウド共有シートに統一し書式のばらつきを排除してください。
文字入力の手間を削減する定型文とプルダウンを活用することで現場負担を抑えつつ情報精度を確保できます。定期的なデータ集計で傾向を把握し予防策のアップデートに役立てましょう。案件レビュー会議でスコア変化を共有すれば全員が危険度を同じ尺度で理解できます。
関連記事:在宅看護アセスメントの書き方について大切なポイントを解説
情報共有と定期レビュー体制
ハラスメント情報は迅速性と機密性の両立が鍵です。毎週のケースカンファレンスで新規事象を共有し対応策と心理フォローの進捗を確認する仕組みを定めましょう。出勤前にスマートフォンで入力できる簡易報告フォームを用意すれば帰所を待たずに被害情報が集まります。
管理者は月次で内容を分析し外部研修や訪問手順の見直しなど組織的対策へ反映します。職員が「報告しても変わらない」と感じないよう改善策と成果を数値で掲示し透明性を保つことが継続的な協力を促進します。
「しっかり組織マネジメントの基礎を学びたい!」という方向けに、UPDATEでは『訪問看護特化の組織マネジメント基礎講座』を開催しています。無料の体験クラス動画もご用意してますので、興味のある方はぜひご覧ください。
無料体験クラス「組織に合わない言動を放置する悪影響と、効果的なフィードバック」
研修と教育で職員を守る

制度を整備しても現場が実践できなければ形骸化します。管理者は危険予測の観点とコミュニケーション手順を標準化した研修を体系的に実施し、職員の「学んだが使えない」を防ぎましょう。以下ではプログラム設計と効果測定の要点を示します。
初期研修で学ぶコンフリクト対応
新入職員には就業前研修として顧客対応と退避判断基準をセットで学習させましょう。動画教材で典型的ハラスメント事例を視聴した後、グループディスカッションで感情と対応策を言語化することで個別判断のばらつきを抑えられます。
研修後に行動観察シートを活用した実地同行評価を設定し合格基準を明確にすると早期定着が期待できます。内容は毎年アップデートし法改正や判例を反映することで継続的な学習文化を育みます。
関連記事:訪問看護の新人教育マニュアル|作成するメリットとOJTの進め方を解説!
メンタルヘルス支援とフォローアップ
ハラスメント経験後の心理的影響を軽視すると品質低下と離職が連鎖します。管理者は専門家との契約や臨床心理士の定期面談を整備し被害報告と同時にサポート予約が行えるワンストップ窓口を提供しましょう。
面談結果は要約のみ共有しプライバシー保護を徹底することが信頼確保の鍵です。加えてリフレッシュ休暇や配置転換の選択肢を提示し、復職支援プランを個別に作成します。回復度合いをストレスチェックで定量化し組織の支援効果を検証しましょう。
発生時の一次対応とエスカレーションフロー
被害が発生した瞬間、現場スタッフは感情の動揺と利用者様のケア責任の狭間で迷いがちです。あらかじめ決めた一次対応フローと連絡ラインを提示しておくことで職員は速やかに安全確保を優先できます。以下では具体的手順を段階的に整理します。
現場退避と安全確保
第一段階は無理をせず安全を確保することです。心身の危険を感じた際は、利用者やご家族に一言かけ、一度その場を離れるなどの対応を取りましょう。
退避後は管理者と相談を行い、代理のスタッフや複数名での訪問へ切り替え、また訪問中止の検討を行います。この際、看護師だけでなく、担当のケアマネージャーなどにも背景などをしっかりと共有しましょう。管理者は最優先で心理ケア面談と休憩時間を確保することで職員を守る姿勢を示すことが重要です。
記録と証拠保全
事実経過を詳細に残すことで組織防衛と再発防止の基盤が築けます。発生時間、場所、言動、身体的接触の有無を時系列で記入し写真や破損物の画像も添付しましょう。ハラスメントがあった直後は、対象スタッフが傷ついていることもあるため、状況確認は丁寧かつ慎重に行う必要があります。本人の記録業務が困難な場合は管理者などがヒアリングを行うようにしましょう。
管理者・外部連絡ライン
管理者は多層的なエスカレーションラインを描き一次対応が完了した時点で誰に何を報告するかを一覧化してください。ケアマネージャー、市区町村担当、警察相談窓口、保険会社、法務顧問など連携先を電話番号付きで掲示板に掲げると夜間当直者でも迷いません。
報告後は二十四時間以内にケース会議を開きケア継続可否と代替訪問者の調整を決めます。連携先のフィードバックを取りまとめ再発防止策に反映するPDCAを必ず実施しましょう。
外部機関との連携と保険・法的措置
組織内の力だけで解決できないケースでは外部資源の活用が不可欠です。行政や警察との協定を結び保険による補償を準備しておくことで被害時の経済的・心理的負担を大幅に軽減できます。以下では主要な連携先と活用ポイントを紹介します。
ケアマネージャーとの協働
利用者様に最も近い多職種連携パートナーがケアマネージャーです。ハラスメント事例の共有時にはケア計画にリスク評価欄を追加し訪問看護と居宅サービス全体で一貫した対応方針を策定しましょう。
情報共有などの対応が遅れることで、ケアマネージャーとの連携が取りにくくなることがあり、また他サービス関係者が二次被害に合う可能性があります。そのため、ハラスメント発生時は事業所内で対応方針を検討の上、早急にケアマネージャーに情報共有や対応相談を行いましょう。
警察相談と通報基準
身体的暴行やストーカー行為が繰り返される場合は警察の介入を前提とする姿勢が必要です。管理者は警察署生活安全課との事前相談を行い通報基準を協定書に明記しましょう。
110番通報に至る前に使用できる防犯アプリの導入や地域パトロール隊への情報提供も選択肢です。通報後は被害届提出の可否、証拠の提出方法、保護命令申立てまで法務顧問と連携し職員と利用者様双方の安全を守ります。この際も、ケアマネージャーなど関係する連携先とは丁寧な情報共有が必要です。
賠償責任保険の活用
ハラスメント対応により生じた器物損壊や訴訟リスクは経営リスクでもあります。訪問看護賠償責任保険の特約に「暴力行為対応費用保険金」が含まれているか確認し、足りない場合は加入を検討してください。
保険会社に事前のリスクマップを提出すると割引が適用される場合もあります。被害発生後は速やかに事故報告書を送り示談交渉を専門家に委任することで管理者の負担を軽減できます。
ステーション運営で継続的改善を回す

最後に、策定した各種対策を一過性で終わらせず組織の学習サイクルとして定着させることが成功の鍵です。数値指標を設定し振り返りと改善をルーチン化することで持続可能な安全文化を醸成できます。以下では回す仕組みを整理します。
KPI設定とモニタリング
安全文化の成熟度を測るには定量指標が不可欠です。月間ハラスメント報告件数、初期対応完了までの平均時間、研修参加率、被害後休職率などの指標を可視化しましょう。数値は悪化が早期警報となり改善策の効果を検証する指針となります。
また、管理者はマネジメントメンバーにも継続的にリスクを共有する姿勢を示すことで職員の安心感が高まります。
改善策のPDCA
数値を得た後は原因分析と対策立案を速やかに回す必要があります。ケース会議で抽出した課題を報告書に整理し担当と期限を設定して実行計画を策定しましょう。翌月の会議で成果と学びを共有し成功事例を標準手順書へ反映します。
複雑性の高いケースについてはケアマネージャーやヘルパーなど、サービスに関わる関係者も交えて対応の振り返りを行い、地域でハラスメントに対する対応力を上げていくことも重要です。
職員満足度と定着率向上
ハラスメント対応の目的は利用者への適切な関係性の維持と、安全で働きがいのある職場の実現です。職員満足度調査にハラスメント安全感項目を追加し匿名性を担保した上で定期的に実施しましょう。結果を共有し改善策を即時宣言することで対話文化が生まれます。
まとめ
ハラスメント対策は「現状把握・予防体制・教育・一次対応・外部連携・継続改善」の六本柱を一体で運用することが要点です。管理者が先頭に立ち職員と利用者様の安全を守れば、サービス品質と経営安定を同時に実現できます。
UPDATEでは『訪問看護マネジメントスクール』を提供しております。組織マネジメントでお悩みの方は、ぜひお問い合わせページよりお気軽にご相談ください。