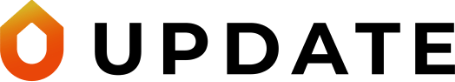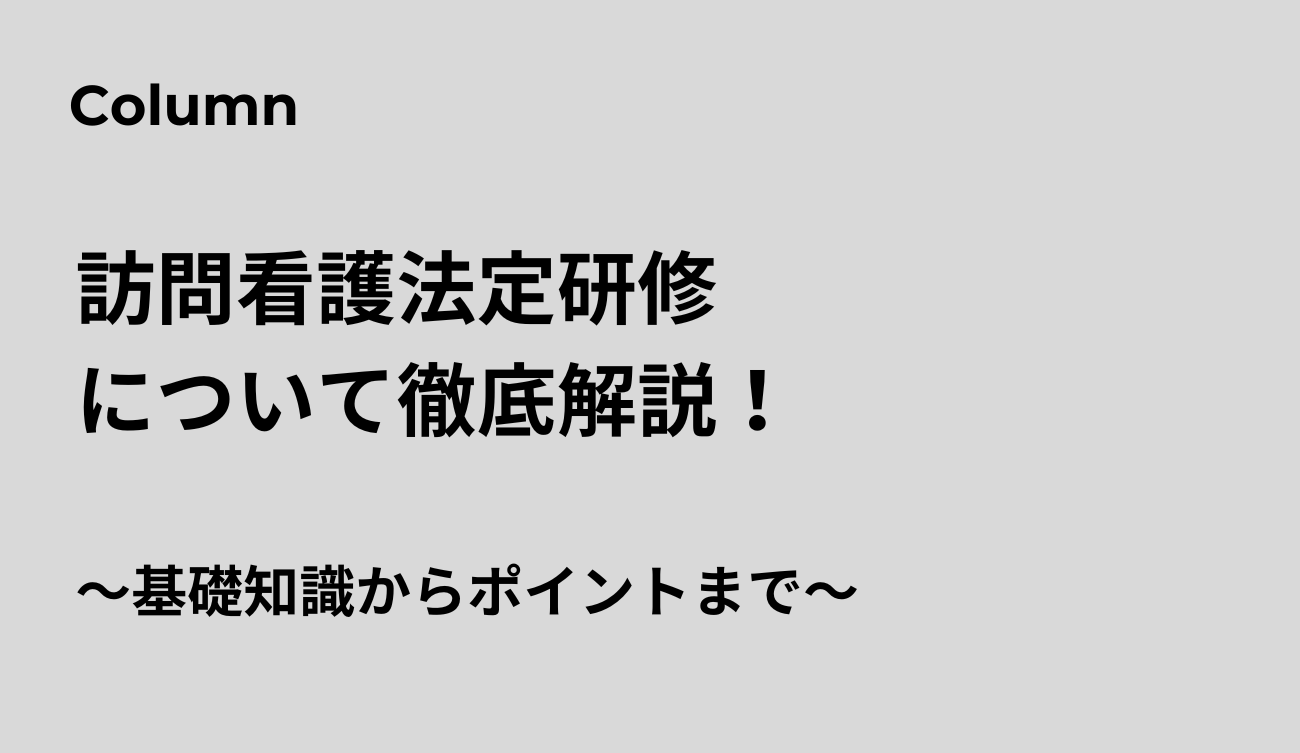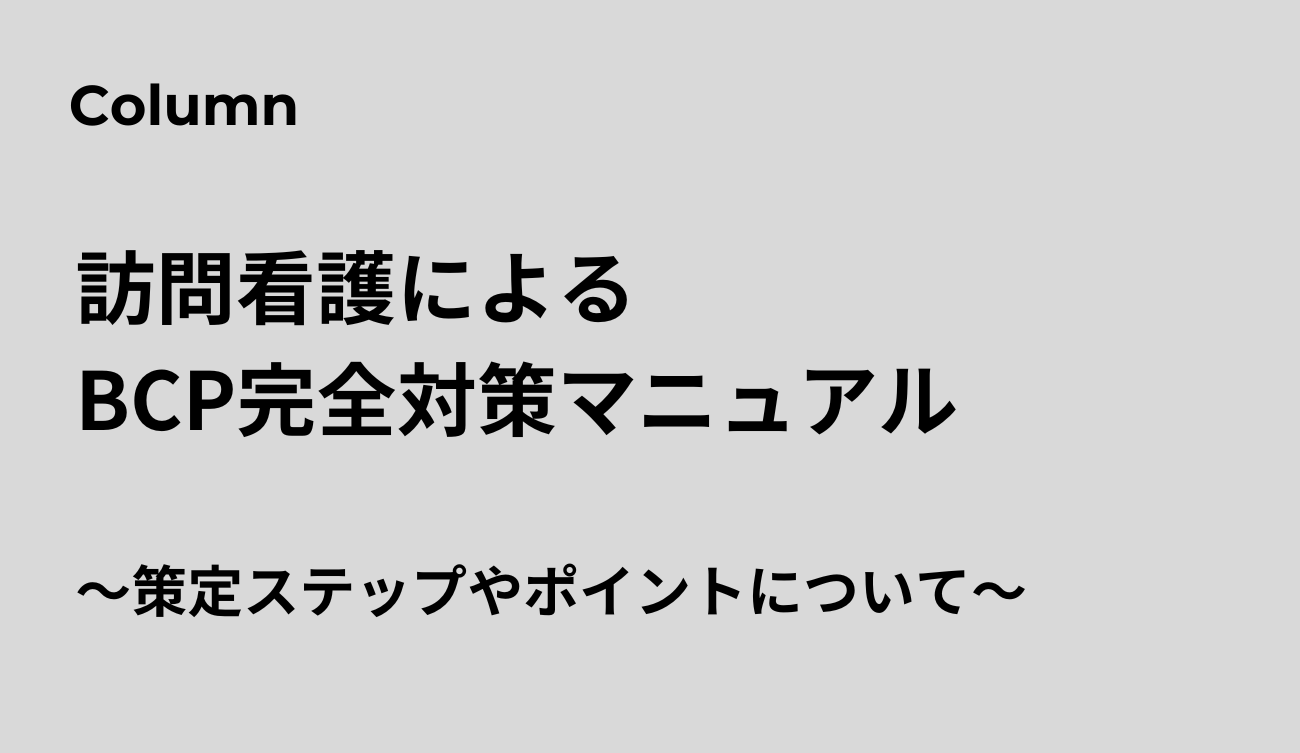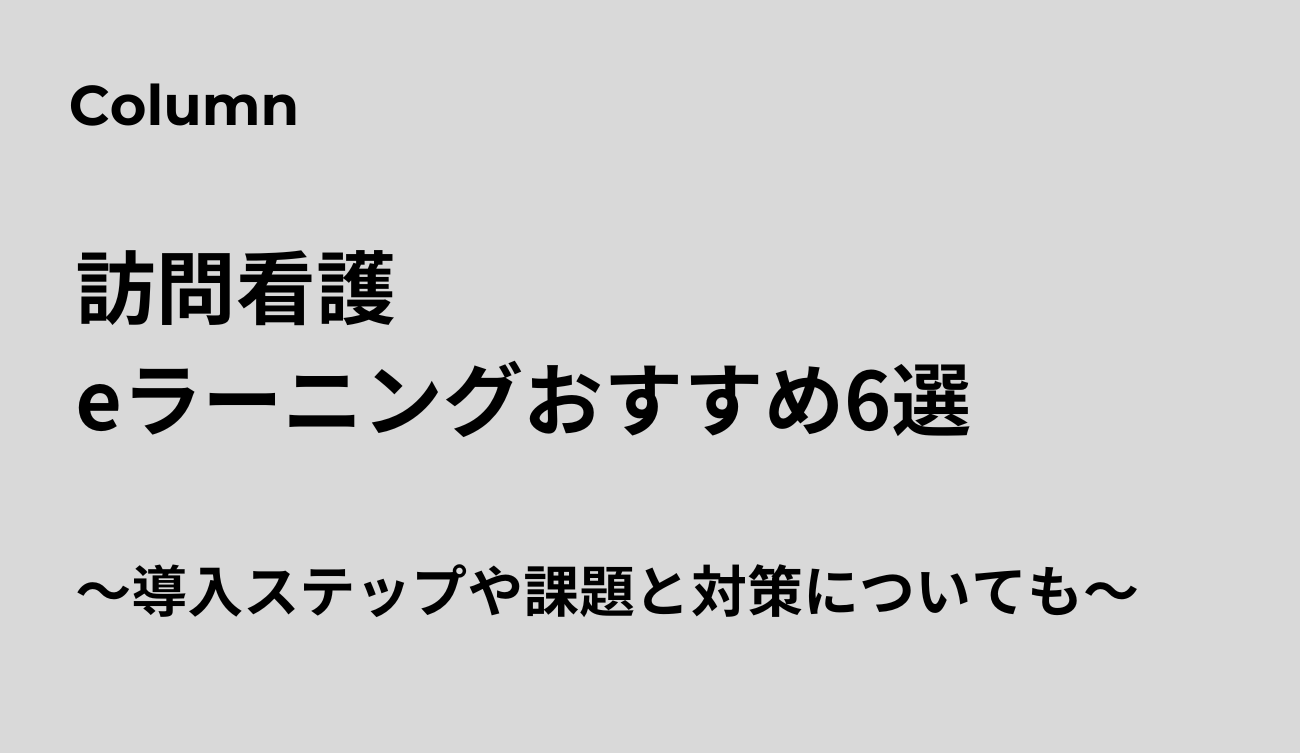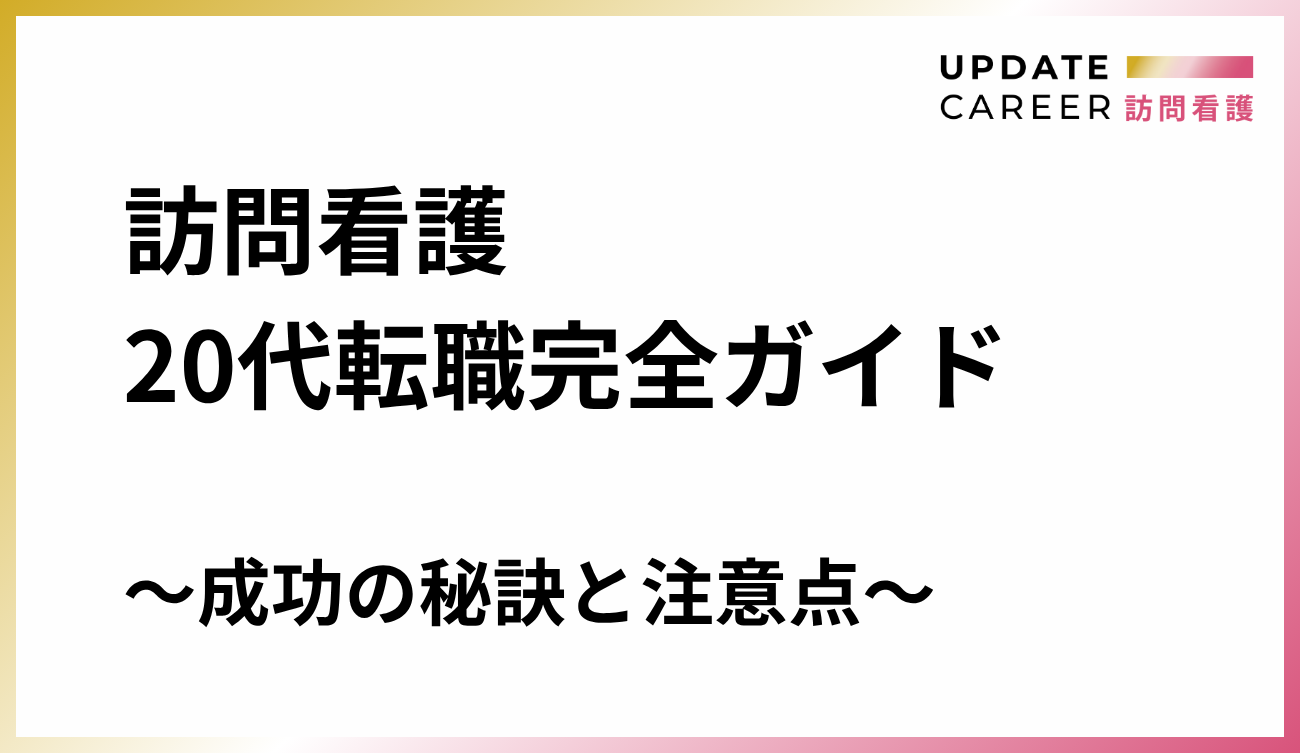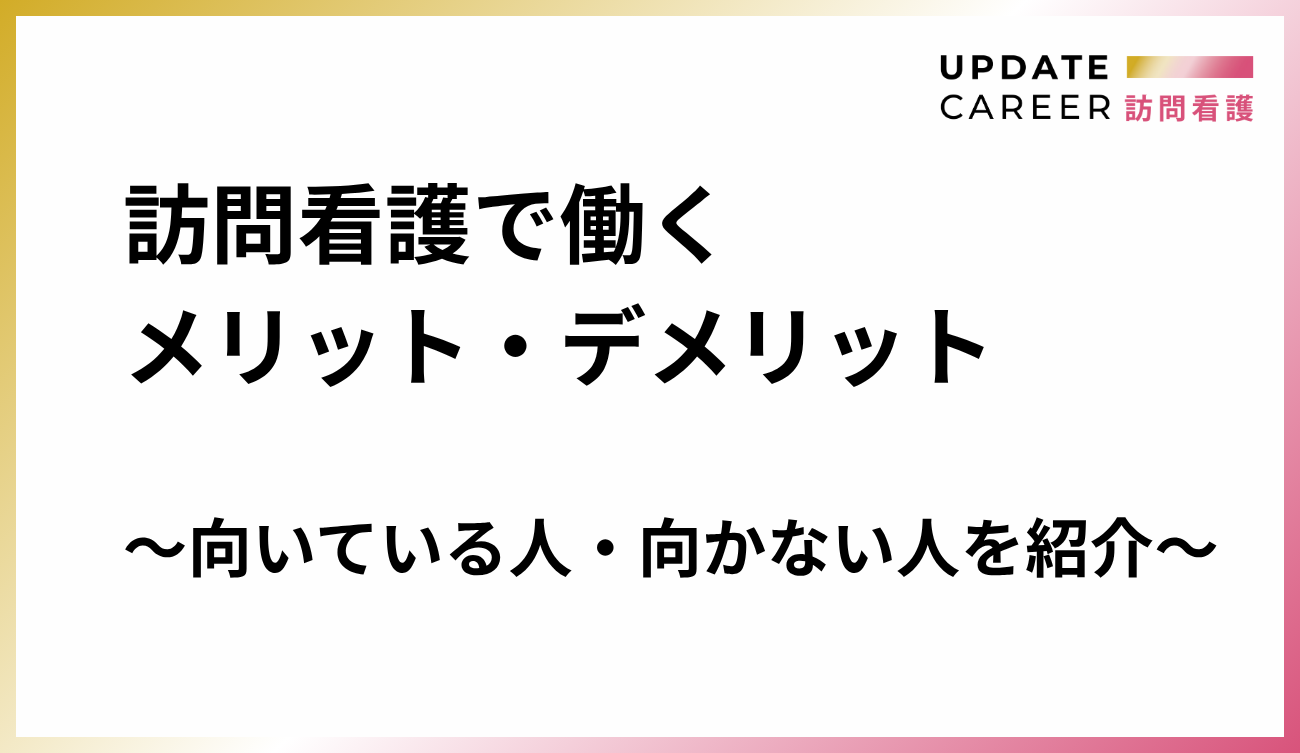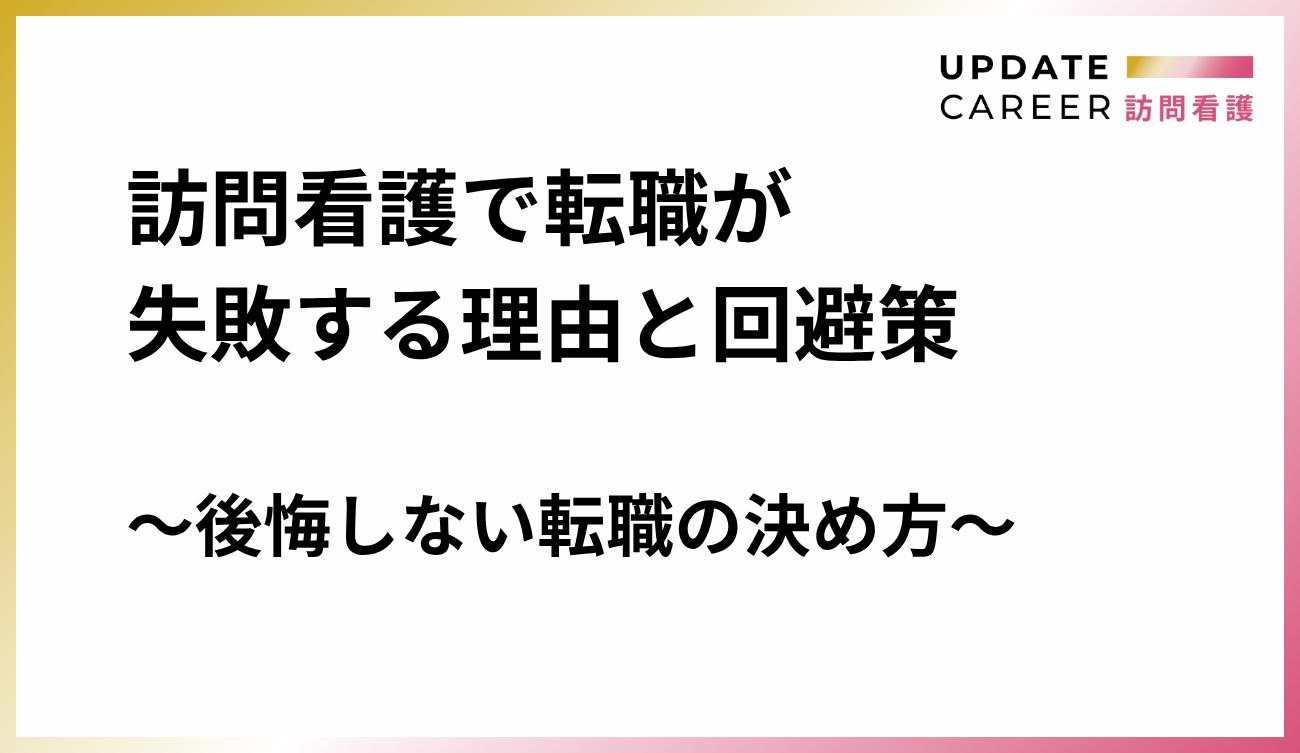訪問看護のコミュニケーションを円滑にする思考法【前編】話すべきこと・前提の認識を合わせる重要性
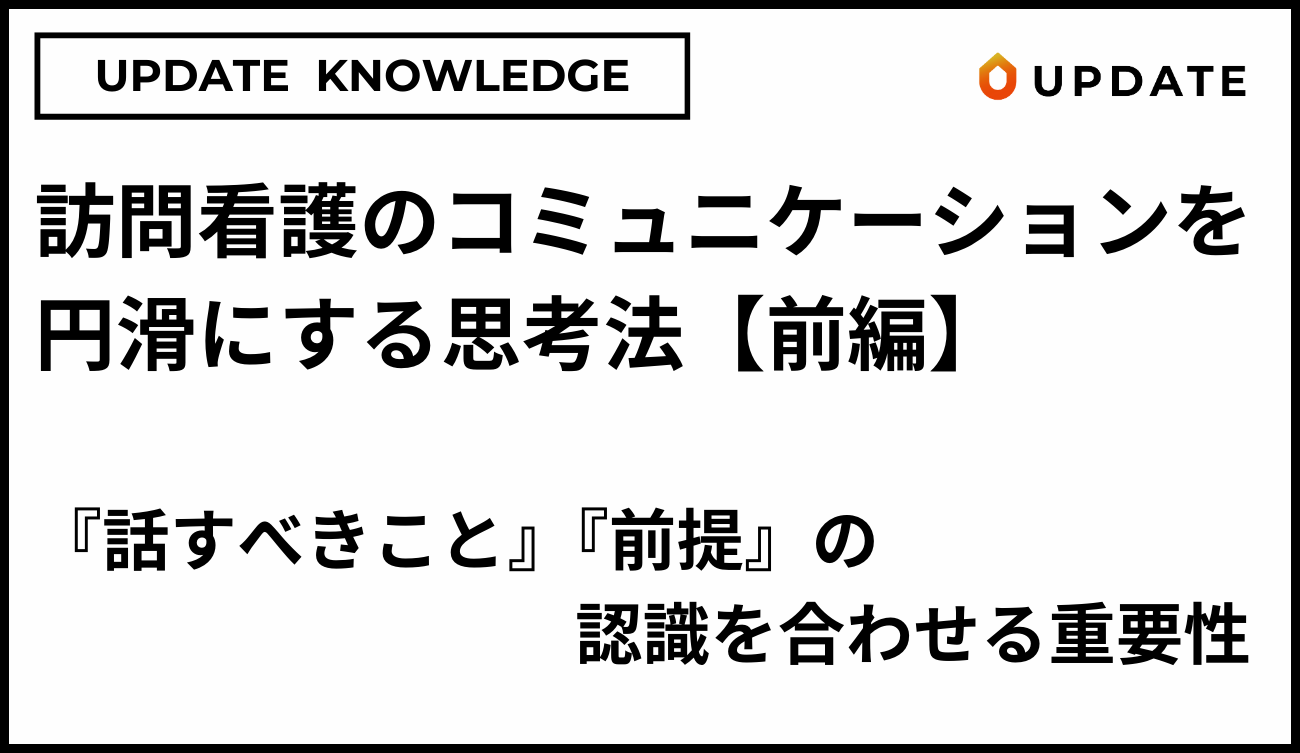
訪問看護のマネジメントにおいて、コミュニケーションの悩みは尽きないでしょう。管理者がメンバーに伝えたことがうまく伝わらない、メンバー間でのトラブルが発生し健全な組織運営ができないなど、訪問看護管理者は日々悩まされているのではないでしょうか?
この記事では、訪問看護ステーションを運営するなかで起こりがちなコミュニケーションの問題と、コミュニケーションを円滑にするための思考法について解説します。

目次
訪問看護事業所におけるコミュニケーションの問題は個人・組織の癖になる

訪問看護事業所におけるコミュニケーションの問題を放置すると、他責思考や意思疎通の敬遠など、個人・組織のよくない癖が定着してしまう恐れがあります。
ここでは、訪問看護管理者によくあるコミュニケーションの悩みと、コミュニケーションの問題を放置してしまった場合に起こりうるリスクについてみていきましょう。
訪問看護管理者によくあるコミュニケーションの悩み
訪問看護管理者・経営者にありがちなコミュニケーションの悩みとして、以下が挙げられます。
- 伝えたつもりなのに理解されていない・誤解が多い
- 漠然としたまま議論が終わり、課題解決が進まない
- スタッフ同士が議論でぶつかり、不健全に関係が悪化してしまう
- 立場が違う人が相手の場合、建設的な議論ができない
訪問看護事業所を運営するなかで、このような悩みを抱えることは少なくないでしょう。
組織全体を蝕む悪い癖が定着してしまうリスク
訪問看護事業所内で発生するコミュニケーションの問題を放置したままにすると、どのようなことが起こるでしょうか?考えられる状況として、以下が挙げられます。
- 「管理者が頼りない」とマネジメントや組織の信頼がなくなっていく
- 「あの人とは働けない」とスタッフ間の不仲が業務に影響し始める
- 異なる立場の相手を敵対視し、批判癖が付く
- 不健全な関係性になり、建設的な議論ができなくなる
このように、帰属意識の低下・他責思考・意思疎通の敬遠など、組織全体を蝕む悪い癖が定着してしまう恐れがあります。
コミュニケーション問題の原因は双方にあり
コミュニケーションの問題における原因は双方にあることが多く、どちらか一方にだけあるわけではありません。
コミュニケーションがうまく取れないという問題が発生した場合、相手を批判的に捉えてしまうこともあるかもしれません。しかし、こちらのコミュニケーション力が高ければ問題はそもそも起こらないか、解決しているはずです。
原因が相手にあると批判的に考えるのではなく、自分の伝え方・聞き方にも問題があるのではないかと疑ってみることが重要です。
マネジメントを担う管理者・経営者はこれらのことを踏まえ、組織の目標達成に向けて、スタッフ全体のコミュニケーションを活性化する責任があります。
組織におけるコミュニケーションを円滑にするためのテクニック

続いて、組織のコミュニケーションを円滑にするための考え方を解説します。
『演繹的思考・帰納的思考』を現場で使えるか
論理的に物事を考える際の基本的な思考法として、演繹的思考・帰納的思考を耳にしたことがあるかもしれません。
- 演繹的思考:一般論(ルール)を当てはめて結論を出す
- 帰納的思考:共通する要素から結論を出す
演繹的思考・帰納的思考について知っておくことは重要かもしれません。しかし、訪問看護の現場でこのような抽象的な概念に落とし込んで考える場面は少なく、なかなか使いこなせないという方もいるのではないでしょうか?
訪問看護において話が噛み合わない4つの原因と対策
そこでここでは、訪問看護運営におけるコミュニケーション問題の原因と対策について、わかりやすく噛み砕いて解説します。
コミュニケーションを取るうえで、話が噛み合わない原因は以下の4点が考えられます。
- 『話すべきこと』の認識がズレている
- 『前提』がズレている
- 見ている『論点』がズレている
- 自分視点での伝え方をしている
これらの原因のうち、今回は『話すべきこと』の認識のズレ・『前提』のズレと、その対策について解説していきます。
訪問看護における円滑なコミュニケーション思考①『話すべきこと』の認識を合わせる

訪問看護事業所内でのコミュニケーションを円滑にするための対策として、まずやるべきは、『話すべきこと』の認識を合わせることです。
『話すべきこと』の認識のズレている例
『話すべきこと』がズレている例として、ある訪問看護事業所における教育MTGの場面を考えてみましょう。議題は『最近入職した若手〇〇さんの教育について』です。
話し合っている5人のメンバーは、以下のように発言しました。
Aさん:「〇〇さん、この前利用者さんから怒られてかなり凹んでましたね。」
Bさん:「何度も同じ失敗をしている。どうしたらよいんだろう?」
Cさん:「同期もいないし、フォロー環境を整えないといけませんね。」
Dさん:「研修に行かせてみましょうか?」
Eさん:「課題が自分で把握できていないから、しっかりフィードバックした方がいいですね!」
5人のメンバーそれぞれが、若手スタッフの教育について真剣に考え意見を伝えているつもりでも、論点がズレており話が噛み合わなくなっていきました。
それぞれが『話すべきだと思ってたいこと』は以下です。
Aさん・Cさん:「メンタル状況とフォローアップをどうするべきか?」
Bさん・Dさん:「自ら課題を把握して改善しないことにどう対応すべきか?」
Dさん :「ケア提供時の課題とその改善方法をどうすべきか?」
同じようなことを話しているようで、話していることは大きくズレていたことがわかります。話が噛み合わなくなり、お互いを批判的に捉えてしまったり、建設的な議論ができずに会議が終わってしまったりすることもあるでしょう。
このような事例は、訪問看護の現場でよくみられるのではないでしょうか?
『話すべきこと』の認識のズレがないか確認する
会議の初めに、『話すべきこと』について共有し、参加者の間で認識のズレがないか確認することが重要です。
話す前に『話すべきこと』について認識合わせをする
漠然とした議題だけでは、それぞれの視点から意見をしてしまい話が噛み合わなくなる恐れがあります。具体的にどのようなことを話し合うべきか・決めるべきかという認識を擦り合わせてから会議を始めるのが有効です。
話し合いの前に、『話すべきこと』について、会議に参加しているメンバーそれぞれの視点を共有するとよいでしょう。出てきた意見の中から、具体的な『話すべきこと』について認識を合わせていきます。
全員が見える場所に『話すこと』を書いておく
今何を話しているのかを、メンバー全員が見ている議事録やホワイトボードに書いて共有することも『話すべきこと』の認識を合わせる一助となります。
オンライン上で話す場合には、話している具体的な議題について示したスライドを画面共有しながら議論するとよいでしょう。
BIG WORDの取り扱いに注意する
BIG WORDとは、具体的に何を指しているか曖昧な言葉のことを指します。抽象的なため、議論の妨げになったり、浅い理解のまま議論が終わってしまったりすることがあります。
具体例として、教育の場面でベテラン看護師が「”看護師として”その姿勢はよくない」「”責任感”がない」などと若手看護師に伝えたとします。これらの発言には具体性がないため、言われた若手看護師は思考停止してしまいます。反論・議論がしにくく、改善につなげることが難しいでしょう。
このほか、「負担」「現場は・・・」「会社は・・・」「経営は・・・」「営業を強化」などの抽象的な言葉がBIG WORDとして挙げられます。
これらの言葉を使うこと自体は問題ありませんが、具体性に欠けることでコミュニケーションの妨げになっていないか確認することが重要です。
UPDATE 訪問看護マネジメントスクールでは、訪問看護運営におけるコミュニケーション対策について、さらに詳しく解説しています。教科書的でない実践的な内容を学ぶことができ、管理者や経営者との交流もできます。詳しく学びたい方はぜひ内容をご覧ください。
訪問看護における円滑なコミュニケーション思考②『前提』のズレに気づく

訪問看護事業所におけるコミュニケーション対策として2つ目に紹介するのは、『前提』のズレに気づくことです。
『話すべきこと』の認識が合っていても、人によって前提とするものが異なると、話が噛み合わなくなることがあります。
『隠れた前提』とは?
同じことを話しているつもりでも、実は相手と前提がズレており、話が噛み合っていないことに注意が必要です。相手が育ってきた環境やこれまでの経験に基づき、自分とは異なる前提のもとで発言している可能性があります。
相手の発言が理解できない場合、このような『隠れた前提』を探ることで状況を打破できるかもしれません。『隠れた前提』がないかという意識を持って相手と接したり、相手に背景となる考え方を直接聞いてみたりすることが重要です。
前提がわかれば異なる意見も理解できる
話が噛み合わない時に、相手の発言が理解できずに苦しむこともあるでしょう。そのような時に相手を批判的に見てしまうと、建設的な議論ができなくなったり、不健全な関係性になってしまったりする恐れがあります。
相手の発言の裏にある背景を探り、『隠れた前提』に気づくことができれば、お互いの異なる意見を理解できる場合があります。
まとめ:訪問看護ステーション全体で話すべきこと・隠れた前提の認識合わせよう

本記事では、訪問看護事業所におけるコミュニケーションの問題と、コミュニケーションを円滑にする思考法について解説しました。
組織内のコミュニケーションを円滑にするためには、『話すべきこと』の認識を合わせ、『隠れた前提』のズレに気づくことが大切です。
マネージャーはこれらの点を意識し、チーム全体に浸透させることで、組織のコミュニケーション力を向上できるでしょう。
株式会社UPDATEでは、「実践的なマネジメントを学べば、医療はもっと良くなる。」というビジョンのもと、訪問看護ステーション運営に必要な知識が体系的に学べるマネジメント講座を実施しています。
訪問看護マネジメントの経験者による、実践的な内容を体系的に学べるのが特徴です。資料や体験クラスも用意していますので、具体的な内容を知りたい方は、以下のバナーからサービスページをご覧ください。

.png)