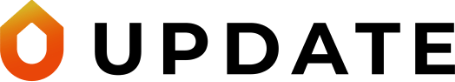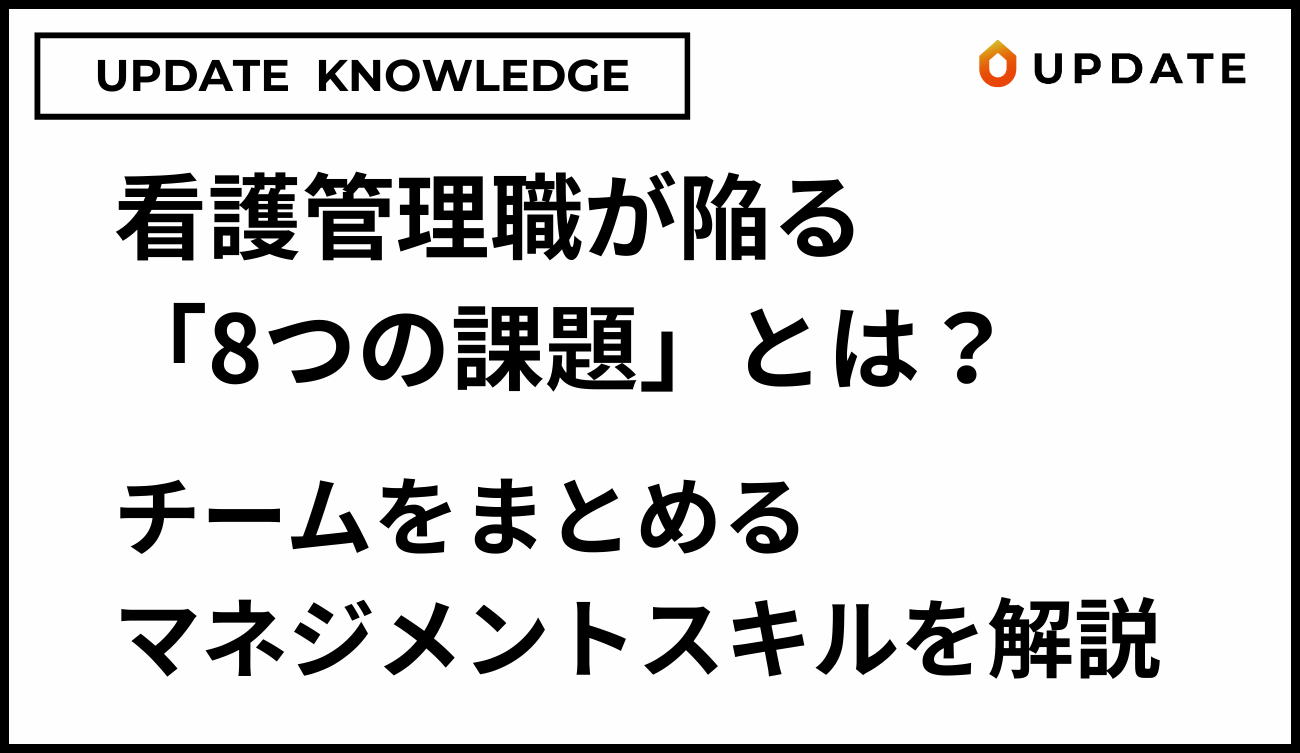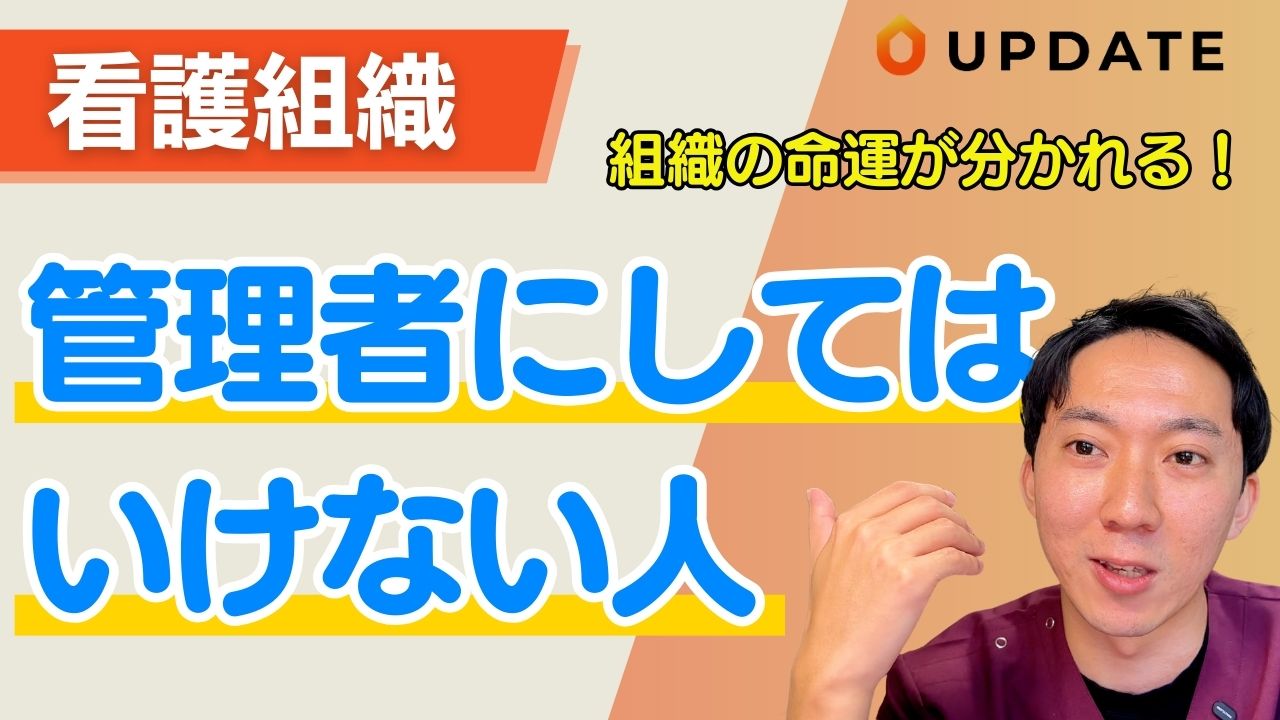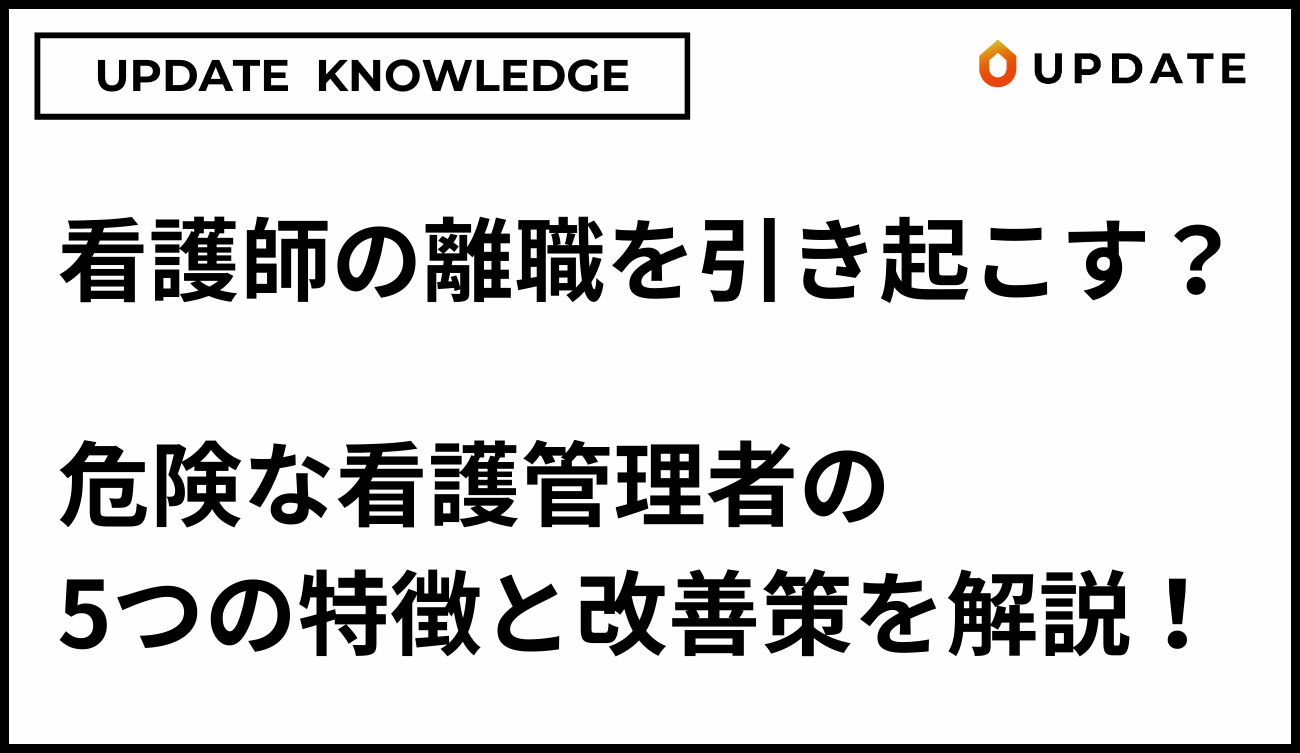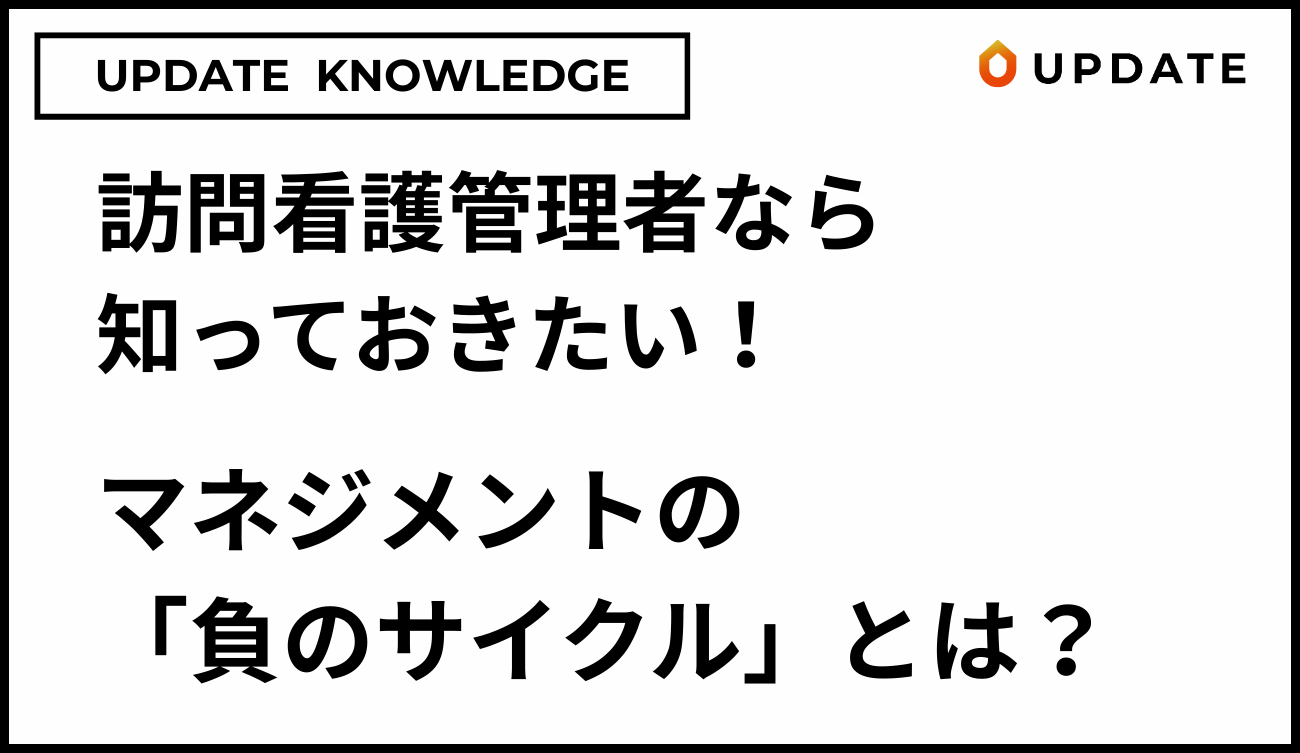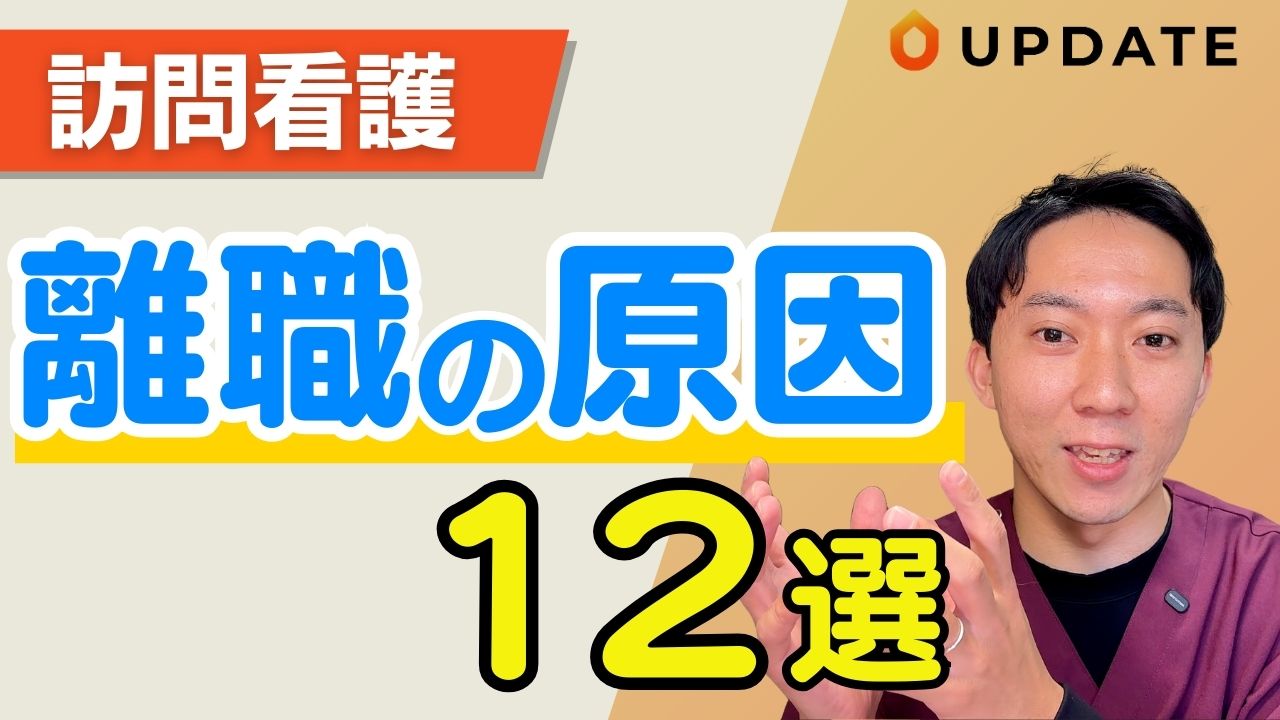訪問看護管理者が知るべき「目標設定」と「フィードバック」5つのポイントを徹底解説!
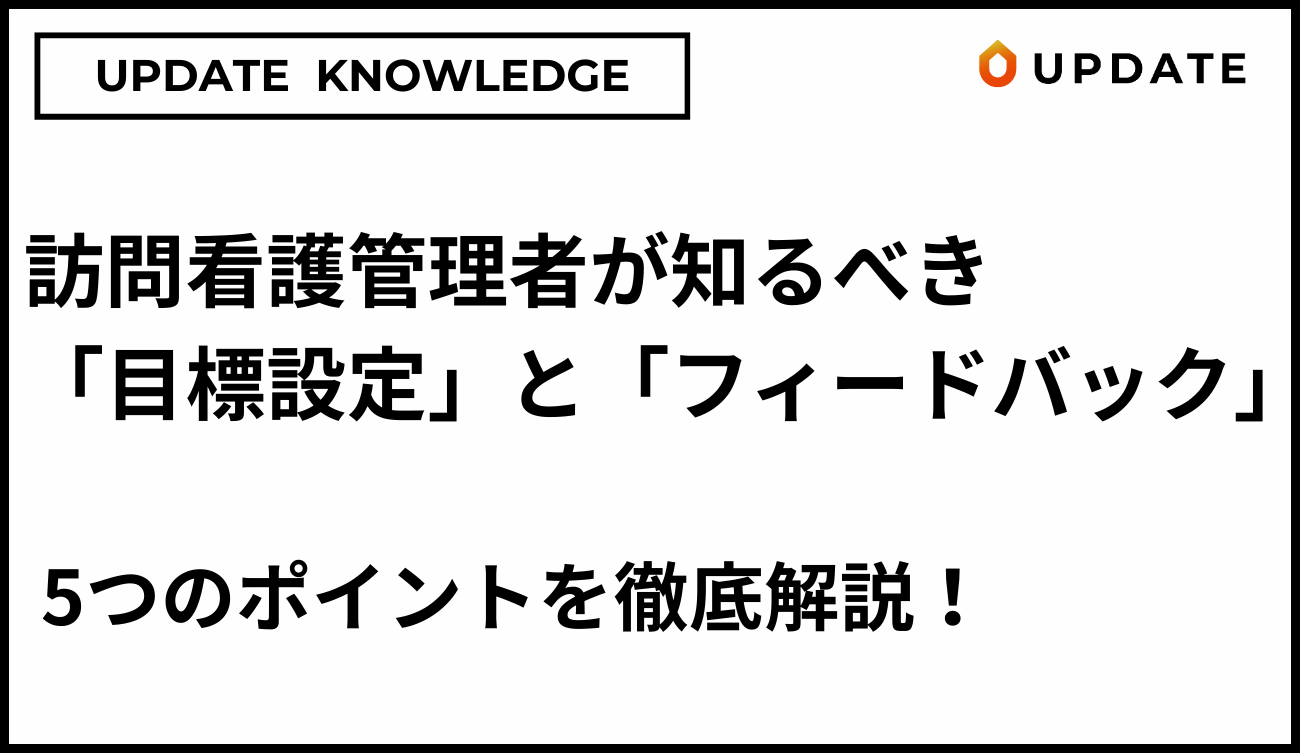
訪問看護の現場では、スタッフの成長や組織の発展のために「目標設定」と「フィードバック」が欠かせません。しかし実際にはうまく機能せず、悩んでいるマネージャーも多いでしょう。
「組織の期待とスタッフの希望が合わない」
「目標を立てても、途中で形骸化してしまう」
などの課題を抱える組織は少なくありません。
本記事では、このような課題を解決し、効果的な目標設定とフィードバックを実現するためのポイントを解説します。
組織と個人がともに成長できる仕組みづくりのヒントを、具体例とともにご紹介します。ぜひ最後までお読みください。
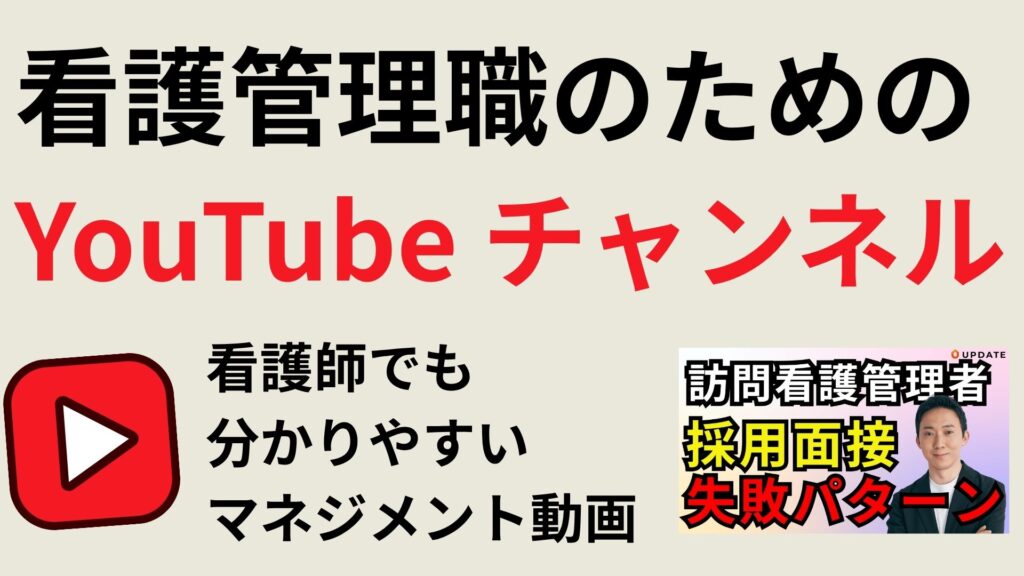
株式会社UPDATE 代表取締役(看護師・保健師・MBA) ケアプロ訪問看護ステーション東京にて新卒訪問看護師としてキャリアスタート。その後、訪問看護の現場・マネジメント経験の他、薬局や訪問看護運営するスタートアップ企業で40拠点・年商65億規模の経営を行い、上場企業へのグループインを実現。現在は医療職マネジメント人財を育成するためマネジメントスクールを運営中。
■経歴
2013年 慶應義塾大学 看護医療学部 卒業
2013年 ケアプロ株式会社入社
2019年 株式会社UPDATE(旧:ヘルスケア共創パートナー株式会社) 創業 代表取締役(現職)
2021年 GOOD AID株式会社 取締役(事業譲渡により退任)
2023年 セルフケア薬局 取締役(吸収合併により退任)
2023年 まちほけ株式会社 代表取締役(事業譲渡により退任)
■得意領域
医療系事業の組織マネジメント
教育体制構築
採用戦略・体制構築
教育体制構築
新卒訪問看護師の育成
管理職の育成
■保有資格・学位
看護師
保健師
経営学修士(MBA)
目次
訪問看護における目標設定・フィードバックの悩みと課題

訪問看護の現場で目標設定する際、以下の点で悩むことはありませんか?
- 自ら進んで動いてくれる人が少ない
- 立てた目標がなし崩しになってしまう
- 組織の期待と個人の希望が擦り合わない
- フィードバックにより起こる摩擦を避けようとして、うまく伝わらない
- 抽象度の高い目標を掲げてしまい、達成しにくい
などの問題を抱えるマネージャーは少なくありません。
これらの問題を解決するための3つの課題として、
- 共通目的の不在
- やさしさ主義
- 数値拒絶
が挙げられます。上記の課題を克服し、効果的な目標設定とフィードバックにつなげるためのポイントを一緒に学んでいきましょう。
訪問看護における目標設定・フィードバックの重要性

目標設定やフィードバックすることは、どのような意味があるのでしょうか?本章では、組織や個人における目標設定・フィードバックの重要性について解説します。
「仕事をこなすだけ」では成長が停滞しやすい
目標を設定していなくても、一定の成果を得るだけなら、業務をこなしていれば実現可能です。
訪問看護では、各スタッフが出勤し1日4〜6件訪問し、クレームなく業務を終えるだけでも一定の成果を出すことができます。日々の仕事をこなすだけでも、組織運営が成り立つでしょう。
しかし、日々の仕事をこなすだけでは、組織・個人のさらなる成長は期待できません。現状維持を目指していては、長期的には衰退に向かう可能性もあります。
組織や個人の成長を促し、チーム全体の成果を最大化させるのはマネージャーの使命です。
そのためにマネージャーがやるべきことは以下の4つが挙げられます。
| 業務遂行 | 質を保ちながら成果を出すための業務管理を行う |
| 人の活用 | 適材適所な人事配置・チームやプロジェクトづくり |
| 人材育成 | より高い成果を出せる人材を育てる |
| 組織連携 | 部署間の連携や他職種との連携 |
これらの4つの視点で組織をマネジメントすることが重要です。
組織は紆余曲折を経て成長する
組織の成長は常に右肩上がりとは限りません。成長が著しいと思える組織でも、直線的に成長するわけではなく、上昇と下降を繰り返しています。
スタッフがさまざまな理由で退職したり、人間関係の衝突があったりと、組織にとってマイナスな事象があると組織の成果が一時的に下がることもあるでしょう。
このように、組織は紆余曲折を経て成長するのが一般的です。
組織・個人が成長できる仕組みが必要
紆余曲折しながら成長する組織がある一方で、現状維持を目指している組織はどのような経過を辿るのでしょうか?
組織にとって避けられないトラブルやスタッフの退職など、ネガティブな事象が起こると、一時的に組織全体の成果が下がります。できるだけ楽をしたいと考えて、惰性で仕事をするスタッフがいると、業務の質が下がることもあるでしょう。
よって日々の仕事をこなすだけでは、長期的には現状維持どころか、組織のレベルが下がることが懸念されます。上記の点から、目標設定やフィードバックを行い、組織・個人が成長するための仕組みづくりが必要です。
「しっかり組織マネジメントの基礎を学びたい!」という方向けに、UPDATEでは『訪問看護特化の組織マネジメント基礎講座』を開催しています。無料の体験クラス動画もご用意してますので、興味のある方はぜひご覧ください。
無料体験クラス「組織に合わない言動を放置する悪影響と、効果的なフィードバック」
訪問看護の目標設定・フィードバックでよくある4つの例

続いて、訪問看護における目標設定やフィードバックの場面でよくある4つの例について紹介します。
例①:唐突に「何がやりたいの?」と聞いてしまう
メンバーに対し、唐突に「〇〇さんは何がやりたいの?」と聞いてしまうことはありませんか?マネージャーから漠然と何をやりたいか突然問われたメンバーは、どのように回答すべきか困ってしまう場合があります。
メンバーは、単に自分がやりたいことについて回答すればよいのか、よりよい組織運営のためにすべきことを答えるべきなのか悩んでしまうでしょう。
例②:数値目標だけを設定してしまう
数値目標ばかりを設定してしまい、メンバーが負担に感じることもあるでしょう。
例えば、「事業所での売上として、〇〇円を目指しましょう」「単独で〇〇件訪問できるようになりましょう」などの数値目標を掲げることはありませんか?
具体的な数字を入れて、評価しやすい目標を立てることは大切です。しかし、数値目標ばかりでは、メンバーにとって達成しなければならないノルマのように感じてしまう可能性があります。
例③:チャレンジ志向がメンバーにとって負担になっている
メンバーに対し、マネージャーが「もっとチャレンジングな目標を立ててみよう」と声をかける場面もあるかもしれません。このような声かけに対しメンバーの反応が薄い場合、メンバーにとっては負荷になっている可能性があります。
少しハードな目標を立てると、勉強会の主催者を任されたり、仕事量が増えたりすることも考えられます。ほかのメンバーとの業務量の偏りが生まれることもあるでしょう。
すると、勉強熱心なメンバーでも、より高い目標を立てる意欲を失ってしまうかもしれません。
例④:メンバーが望む以上の成長を期待してしまう
メンバーが望むレベルを超えた成長を、マネージャーが期待してしまう例もあるでしょう。
メンバーは「一定以上の経験を積んだので、そろそろ落ち着きたい」と考えていることもあります。また、さらなる成長が報酬や評価に直結するわけではないなら、現状のレベルで仕事を頑張りたいと考えているメンバーもいるでしょう。
訪問看護の目標設定・フィードバック5つのポイント

目標設定・フィードバックするうえで、押さえておきたいポイントは以下の5つです。
- 共通目的と具体的ゴールを設定する
- 目標設定のための要素を整理する
- 誰が見てもわかる具体的な行動計画を立てる
- フィードバックは瞬発力と波及性を重視する
- 人事評価と連動させる
続いて、一つひとつ詳しく解説します。
共通目的と具体的ゴールを設定する
組織が成果を出すためには、共通目的をもつだけでなく、具体的なゴール設定も重要です。組織の理念やビジョンに沿って、事業所の目標や個人目標などを具体的に設定することで、チームが一丸となり、成果を出しやすくなるでしょう。
ここでは、共通目的や具体的ゴールを立てるうえで注意すべきポイントを解説します。
個人のやりたいこと基準では組織目標を達成できない
個人の「やりたい」か「やりたくない」かを基準に立案した目標を達成しても、組織の目標は達成できません。また、目標が妥当であるかを判断する基準がないと、マネージャーや個人の主観による、漠然とした目標が設定される場合もあります。
組織目標をトップがまず示すことが重要
トップダウンで決めることがよくないことだと思っているスタッフは少なくありません。しかし実際には、組織目標をトップダウンで決めた方がよい場面もあります。
マネージャーが組織目標を示したうえで、個人の成長や役割などの目標を擦り合わせることが重要です。チーム全体の目標を達成したうえで、個人としても成長するための目標立案を目指しましょう。
目標設定のための要素を整理する

目標設定するときは、場当たり的に目標を立てるのではなく、求める要素を決めておくことが重要です。例として、以下の4つの要素に沿って整理してみるとよいでしょう。
| 成果目標 | 組織から求められる成果達成に関する指標 |
| 行動目標 | 業務に取り組むうえでの役割などに応じた目標 |
| マネジメント・フォロワーシップ目標 | 組織の一員として、チームマネジメントに参画するための目標 |
| Value・スタイル実現 | Valueを体現するために目指す目標 |
行動目標の例として、「採用担当者のみならず、メンバーも一丸となって良い仲間を集める」という目標が挙げられます。
あるスタートアップ企業ではこの目標を掲げ、メンバーが新規採用者や見学者が職場に来た際、事業所の入り口にウェルカムボードを置いて歓迎しました。結果的にメンバーの行動は、ある新規スタッフが入職を決める一因となったそうです。
このように、その場の雰囲気ではなく、組織が求める要素を話し合ったうえで具体的な目標を立てましょう。
誰が見てもわかる具体的な行動計画を立てる
目標を立てる際は、誰が見ても同様に評価できるよう、具体的に立案することが重要です。抽象度が高いと、評価する人によって解釈のズレが生じ、適切な評価ができない場合があります。目標と結果を振り返ったとしても、改善のためのヒントが得られにくいでしょう。
具体的に立案するポイントとして、一つの目標ごとに以下の3つの点を明確にすることが重要です。
- 納期(いつまでに)
- 水準や状態(どのくらい)
- 具体的行動(どのように)
特に、数値化が難しい定性的な目標に関しては、具体的行動(アクションプラン)に注力しましょう。
フィードバックは瞬発力と波及性が重要

フィードバックにおいては、時間を置かずに伝えることや、チームに波及させやすいタイミングを逃さないことが大切です。続いて、現場でありがちなパターンについて解説します。
パターン①:伝えるタイミングが遅れる
フィードバックは瞬発力が重要です。現場でありがちなパターンとして、伝えるタイミングが遅れてしまうことが挙げられます。
タイミングが遅れると、ポジティブなことは効果が薄まるでしょう。一方、ネガティブなことは「なぜ今さらもち出すのか」と反発心が増す可能性があります。
そのため、良いことも良くないことも、できるだけ速やかに伝えることを意識しましょう。
パターン②:伝える場面が効果的でない
チームへの波及性を考えずに伝えてしまい、効果的なフィードバックができていないパターンもあるでしょう。一対一でフィードバックするのではなく、チーム全体に向けて伝えることも重要です。
マネージャーからのフィードバックは、組織全体に影響を与えるメッセージとなります。メンバーの良い行動・望ましくない行動を、ロールモデルとして他の人にも認知させると、チーム全体に浸透していきます。
意図的にメッセージを伝えることで、組織文化をつくる一助となるでしょう。
効果的なフィードバックの場面
フィードバックするのに効果的な場面として、以下の5つが挙げられます。
- 個別に直接賞賛する
- 日報や社内SNSで賞賛する
- 定期的な1on1ミーティングで定点観測する
- MTGやカンファレンスでのよい例として賞賛する
- オリエンテーションや会社説明で事例として話す
このように、フィードバックの機会は個別面談だけではありません。チャンスをみつけ、組織の模範となる言動があれば、小さなことでも伝えることが重要です。
訪問看護ステーション運営に必要な知識が体系的に学べるマネジメント講座では、このほかネガティブな事象をフィードバックする際のコツについても詳しく解説しています。
訪問看護における実際の事例を交えながら解説しており、より実践的な知識を学べるのが特徴です。無料体験クラスでは、本記事に関連する「ネガティブな事象へのフィードバック手法」について解説しています。詳細を知りたい方は、ぜひ講座ページをご覧ください。
人事評価との連動
実績を出したら、しっかりと評価することが大切です。評価がない目標は形骸化してしまいます。
また人事評価と連動させ、昇給できる仕組みづくりだけでなく、言葉で賞賛する仕組みを作ることも重要です。例えば、「〇〇(企業・組織名)AWARD」をつくり、組織内で活躍した個人や部署を表彰する機会をつくるのも一例としてよいでしょう。
まとめ:適切な目標設定とフィードバックが個人・組織の成長を促し、文化を醸成する

訪問看護における目標設定とフィードバックは、単なる業務遂行のためだけでなく、組織の成長や文化づくりに影響を与える重要な要素です。適切な仕組みを整え、メンバーが主体的に成長できる環境をつくることが、訪問看護ステーションの成長につながります。
株式会社UPDATEでは、「実践的なマネジメントを学べば、医療はもっと良くなる。」というビジョンのもと、訪問看護ステーション運営に必要な知識が体系的に学べるマネジメント講座を実施しています。
訪問看護マネジメントの経験者による、教科書的でない内容を学べるのが特徴です。マネジメントの悩みを解決しながら、運営に必要な知識や考え方を定着させることが可能です。
資料や無料体験講座も用意しています。具体的な内容を知りたい方は、以下のバナーからサービスページをご覧ください。