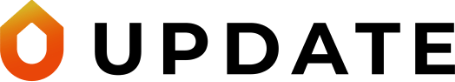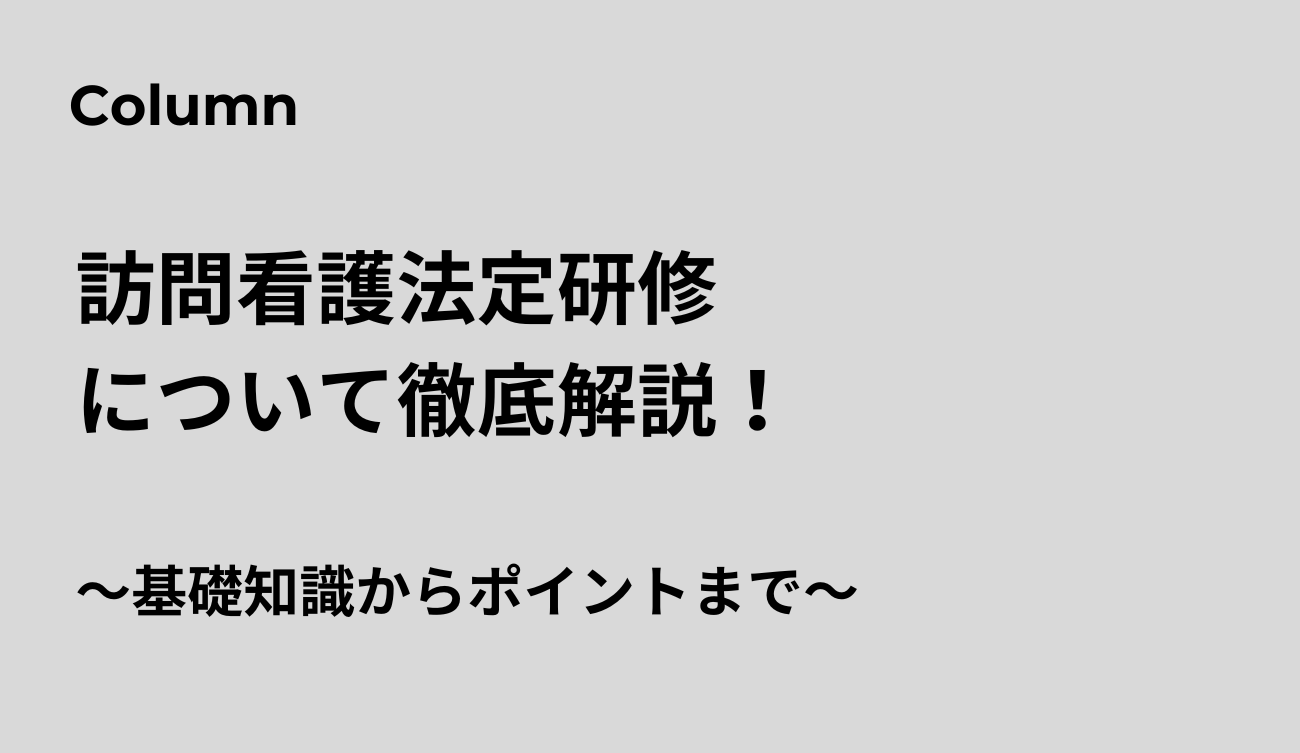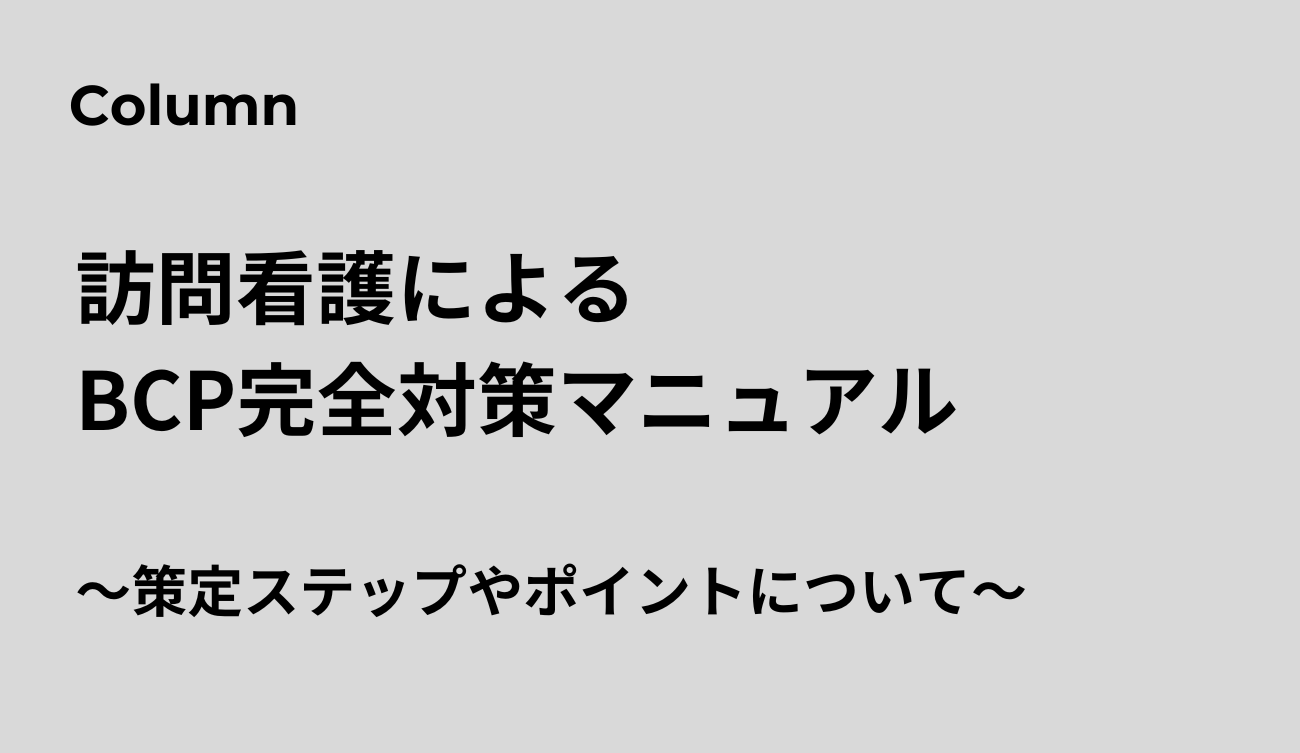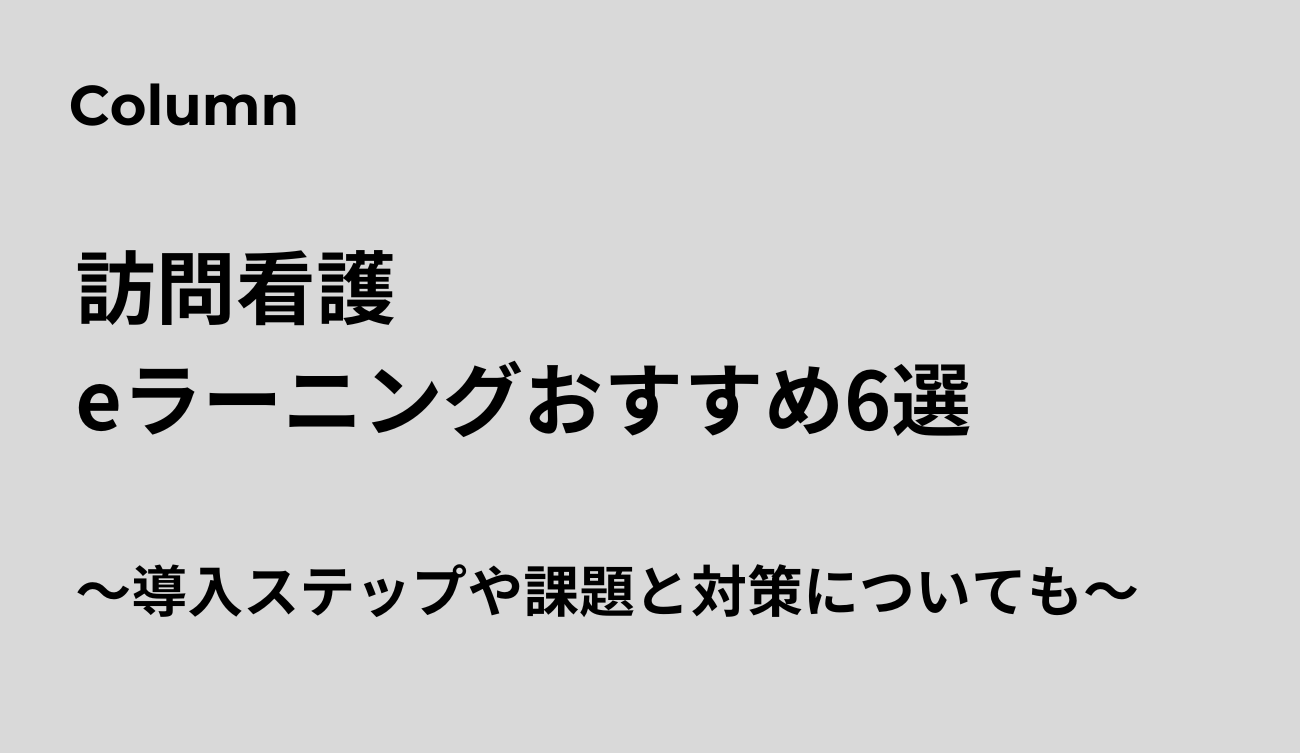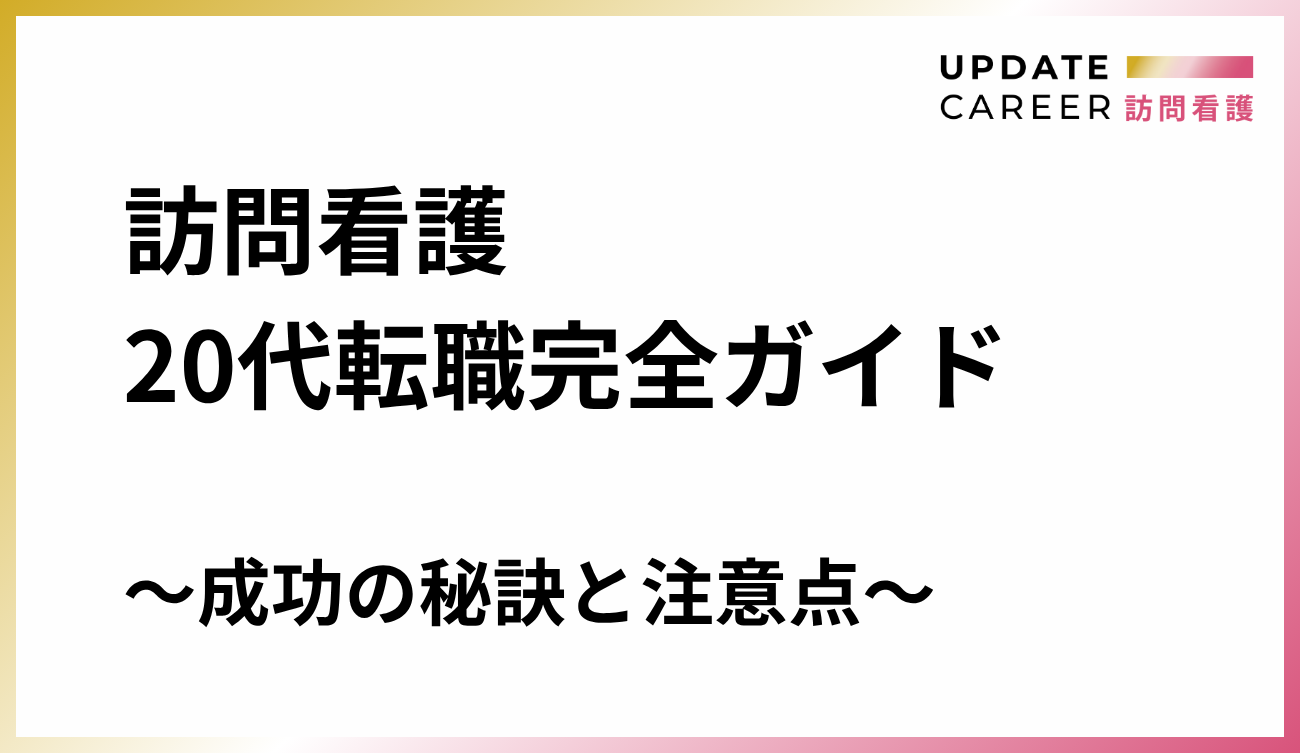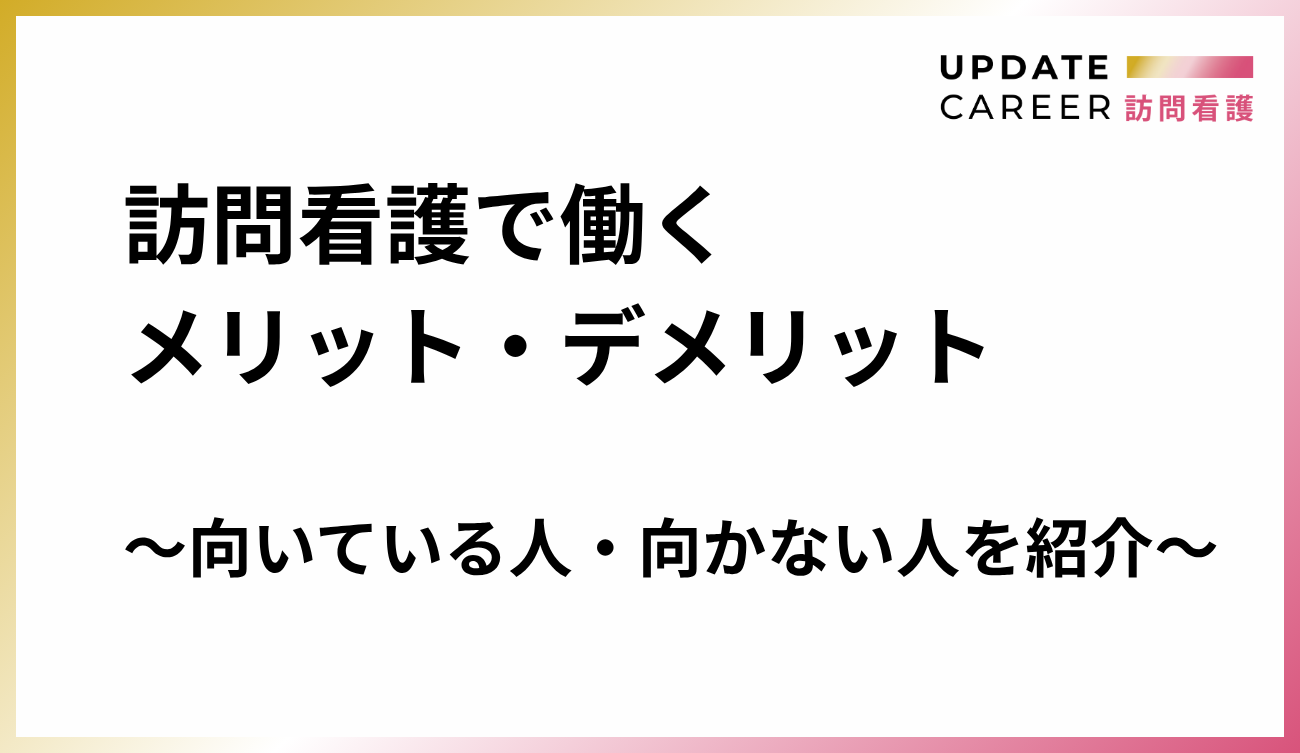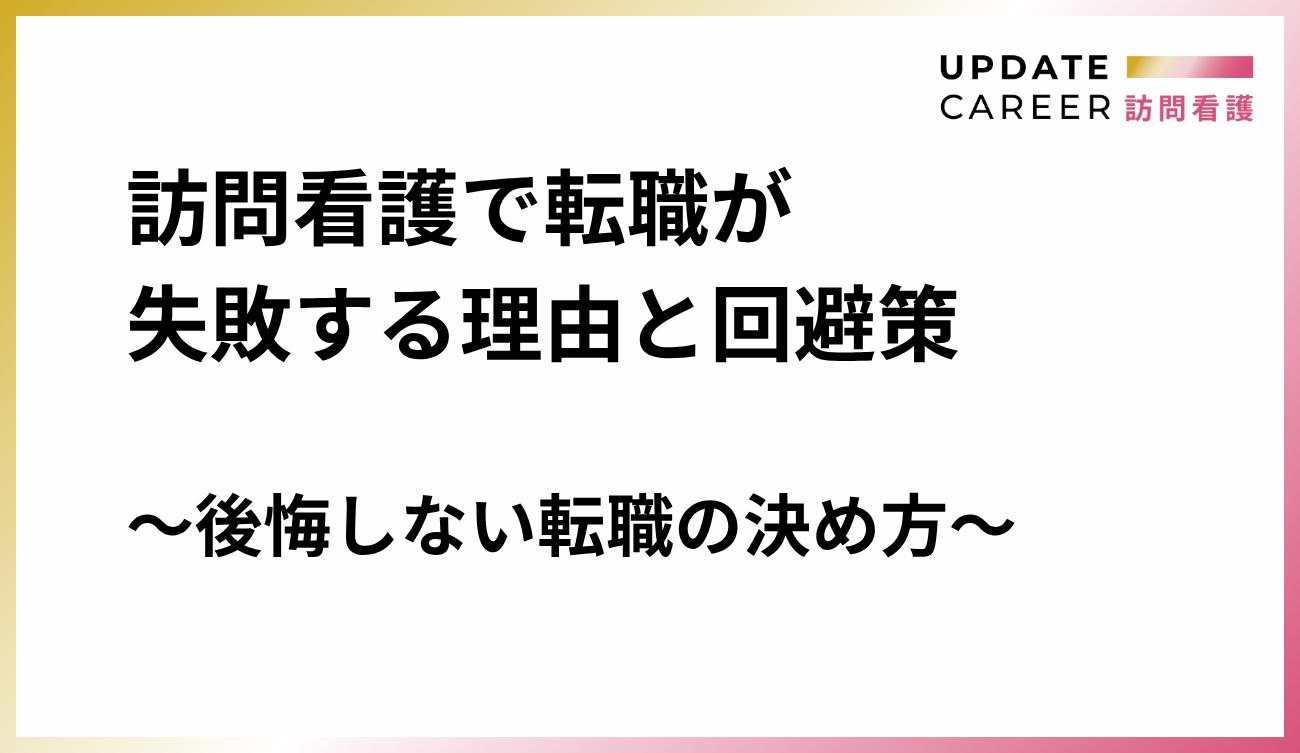訪問看護に介護保険が適用される条件とは?医療保険との違いについて解説!
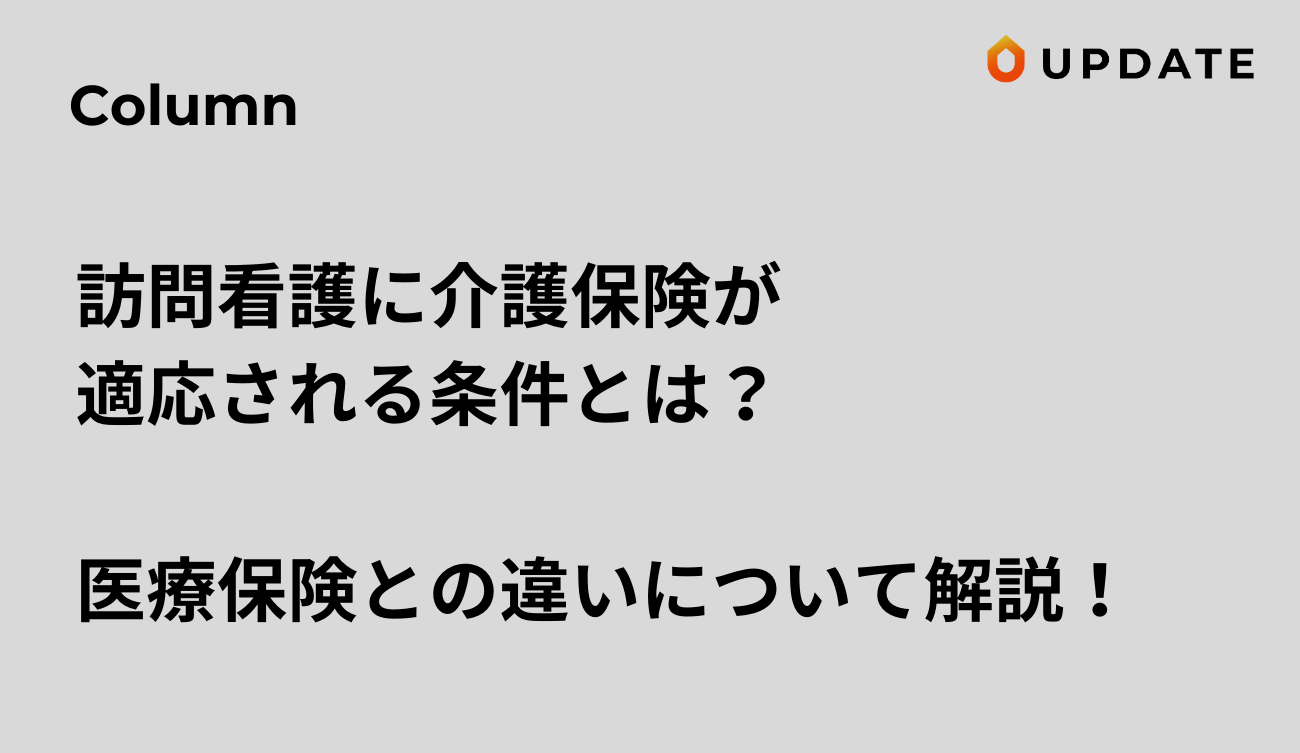
訪問看護は、医療的なケアと生活の支援の両方に対応する大切なサービスです。しかし、訪問看護の利用に際しては、介護保険と医療保険のどちらが適用されるのか、その違いや条件を正しく理解することが大切です。
本記事では、訪問看護では介護保険と医療保険の適用条件や優先順位を詳しく解説し、利用者様やご家族が安心して訪問看護サービスを受けるためのポイントを紹介します。

訪問看護ステーションの位置づけ

訪問看護ステーションは、医師の指示に基づき、利用者様のご自宅に訪問して医療ケアや日常生活のサポートを行う事業所です。訪問看護は医療的ケアの一環として行われるため、医療保険や介護保険の制度に則って提供されます。特に介護保険が適用される場合は、訪問看護ステーションが大切な役割といえるでしょう。
医師や病院と連携しながら、利用者様が住み慣れた自宅で安心して療養生活を送れるようサポートします。看護師をはじめとする専門スタッフが、病状の観察、服薬管理、リハビリテーション、医療機器の管理などを行い、利用者様やそのご家族の負担軽減を図るのが特徴です。
また、訪問看護ステーションは、利用者様の生活に寄り添い、医療と介護の橋渡し的な存在として、地域医療の中で大切な役割を果たしています。そのため、介護保険を活用して訪問看護を利用する際には、訪問看護ステーションの役割と機能を理解しておくことが大切です。
訪問看護ステーションの現状
訪問看護ステーションは、地域社会では大切な役割を果たしており、年々その需要が高まっています。日本は高齢化社会が進行しており、在宅医療や介護サービスのニーズが拡大しています。
こうした背景から、訪問看護ステーションは、病院やクリニックと並ぶ大切な医療・介護インフラとして注目されているでしょう。特に、医療と介護の連携を促進する役割が強調され、地域包括ケアシステムの一翼を担う存在として位置づけられています。
訪問看護ステーションの役割
訪問看護ステーションの役割は多岐にわたります。具体的には以下のような役割を担っています。
- 医療処置の提供
- 健康管理とアドバイス
- リハビリテーション支援
- 家族のサポート
医療処置の提供や健康管理、リハビリテーション支援、家族のサポートなどを行います。看護師がご自宅を訪問し、必要な医療処置や服薬管理を行うとともに、健康状態を把握し、適切なアドバイスの提供をするのも役割の一つです。
また、リハビリを通じて日常生活の自立を支援し、ご家族には介護方法の指導や精神的なサポートを行います。地域の医療機関や介護サービスと連携し、安心して在宅療養ができる環境を整えます。
関連記事:訪問看護の仕事内容とは?具体的な業務と役割について解説
訪問看護ステーションの課題と展望
現状、訪問看護の利用は増加傾向にありますが、看護師の人材不足が深刻化している点が課題となっています。そのため、ICT(情報通信技術)を活用した遠隔看護システムの導入や、訪問看護ステーション同士の連携強化が進められています。今後は、より利用者様が安心して在宅療養を行えるよう、訪問看護の役割はさらに必要となるでしょう。
また、訪問看護ステーションは、医療と介護の両面から利用者様とご家族を支える大切な存在です。地域の医療機関や行政と連携し、包括的なサポートを提供するために、今後もその役割は拡大していくことが期待されています。
訪問看護では医療保険か介護保険が適用される

訪問看護では、利用者様の状態や必要とするケアの内容によって、医療保険と介護保険のどちらが適用されるかが異なります。これにより、利用者様のご家庭の負担額やサービスの提供内容にも違いが生まれます。適切な保険制度を理解し、スムーズにサービスを利用できるようにすることが大切です。
介護保険が適用されるケース
要支援・要介護認定を受けた65歳以上の方や、特定疾病により要支援・要介護認定を受けた40歳以上65歳未満の方は、公的介護保険の適用を受けることができます。これは、高齢者や特定疾病を抱える方の生活を支援するための制度であるためです。
例えば、初老期における認知症や末期の悪性腫瘍などの特定疾病が原因で要介護認定を受けた場合、訪問看護は介護保険の適用対象となります。このように、対象者の条件を満たせば、訪問看護を公的介護保険で利用することが可能です。
医療保険が適用されるケース
訪問看護では、年齢や健康状態に応じて医療保険が適用される場合があります。これは、介護保険の対象外となる方の医療的ケアを支援するためです。
例えば、40歳未満の方や、16特定疾病以外の40歳以上65歳未満の方、要支援・要介護認定を受けていない65歳以上の方は、医療保険の適用を受けることができます。さらに、終末期や特別訪問看護指示書が発行された場合も医療保険の対象となります。このように、一定の条件を満たせば、訪問看護を医療保険で利用することが可能です。
訪問看護による介護保険と医療保険の違い
訪問看護を利用する際、介護保険と医療保険では、適用条件や提供される支援の内容に大きな違いがあります。利用者様がどちらの保険を活用するかは、状態や疾患の種類、必要なケアの内容によって決まるため、両者の違いを把握しておくことが大切です。
具体的には、対象者、自己負担額、利用上限、提供されるサービス内容が異なり、これらを理解することで、適切なサービスをスムーズに選ぶことができます。
対象者
訪問看護サービスの対象者は、自宅で療養を必要とし、主治医が訪問看護の必要性を認めた方です。これは、自宅での療養を支えるための制度であるためです。
例えば、介護保険では要支援・要介護認定を受けた65歳以上の方や、40歳以上65歳未満で16特定疾病に該当する方が対象となります。一方、医療保険では要支援・要介護認定を受けていない65歳以上の方や、40歳以上65歳未満で16特定疾病に該当しない方が対象となります。このように、対象者の年齢や疾病の有無によって適用される保険が異なります。
自己負担額
介護保険では、利用者様の負担額は原則1割から3割に設定されています。負担額は、利用者様の所得状況によって変わるため、経済的な負担を抑えながら訪問看護を利用できる点が特徴です。医療保険も同様に1割から3割の負担となります。
利用上限
介護保険では利用回数に制限がなく、支給限度額の範囲内であれば必要に応じて訪問看護を受けることができます。ヘルパーなどの他サービスと支給限度額の調整が必要なため、ケアマネージャーと都度調整を行いましょう。一方、医療保険では原則として週1〜3回の訪問が上限ですが、特定疾患がある場合や特別訪問看護指示書が発行された場合は週4回以上の利用が可能です。
サービス内容
介護保険は、日常生活のサポートや健康管理、リハビリテーションを中心に提供され、利用者様が在宅で快適に生活できるようなケアが行われます。医療保険の場合は、点滴やカテーテル管理、創傷の処置など、医療的ケアを主体としたケアが中心となるのが特徴です。特に、医療処置が必要な方には、医療保険の訪問看護が大切な支えとなります。
利用までの流れ
訪問看護を開始するには、まずかかりつけ医に相談し、訪問看護が必要かどうかを確認するのが一般的な流れです。介護保険を利用する場合は、ケアマネジャーが必要な手続きを進め、ケアプランを作成します。医療保険を利用する際は、医師の訪問看護指示書が不可欠です。
その後、訪問看護ステーションが具体的なケアの内容や訪問スケジュールを調整し、正式に訪問看護サービスが開始されます。
関連記事:特別訪問看護指示書とは?退院直後の発行の場合いつまでが指示期間?
訪問看護で介護保険と医療保険の併用は可能?

訪問看護では、利用者様の状態や必要とするケアの内容に応じて、介護保険と医療保険が適用されますが、両者を同時に併用することはできません。それぞれの保険には適用条件や優先順位が定められており、利用する際はその基準に従う必要があります。
介護保険と医療保険の併用はできない
介護保険と医療保険は、同じサービスに対して同時に適用することはできません。訪問看護を受ける際は、利用者様の状態に応じてどちらの保険が優先されるかが決まります。
例えば、要介護認定を受けている方が在宅療養をしている場合、原則として介護保険を活用します。しか、介護保険が適応となる方でも、状況に応じて医療保険の対象者となる場合は医療保険が適応となります。
介護保険と医療保険の優先順位について
訪問看護では保険の優先順位は、利用者様の状態や治療の目的によって判断されます。利用者様がどのような状態にあるのか、またどのようなケアが必要かによって、介護保険が適用されるのか、医療保険が優先されるのかが異なります。訪問看護を利用する際は、この優先順位のルールを理解しておくことが大切です。
要介護認定を受けている場合
要介護認定を受けている場合、訪問看護の利用には原則として介護保険が適用されます。これは、介護保険が高齢者や特定疾病を抱える方の在宅支援を目的としているためです。例えば、65歳以上で要支援・要介護の認定を受けている方や、40歳以上65歳未満で特定疾病による要介護認定を受けている方は、訪問看護を介護保険で利用することができます。
ただし、厚生労働大臣が定める疾病に該当する場合は、要介護認定を受けていても医療保険が適用されます。このように、訪問看護の保険適用は、要介護認定の有無だけでなく、疾病の種類によっても変わるため、事前に確認が必要です。
要介護認定を受けていない場合
要介護認定を受けていない場合、基本的には医療保険が適用されます。医師が訪問看護の必要性を認めた40歳未満の方や、16特定疾病に該当しない40歳以上65歳未満の方、要支援・要介護認定を受けていない65歳以上の方は、基本的に医療保険の対象となります。
医療保険が適用されるサービスには、創傷処置、点滴、カテーテル管理、緊急時の対応など、医療的ケアが中心となる支援が含まれます。また、入院後の退院支援として、在宅での医療的ケアが必要とされる場合にも医療保険が適用されるのが一般的です。
こうした状況では、医師の指示に基づき、訪問看護ステーションが計画的にケアを行い、利用者様の健康状態が安定するようサポートします。訪問看護の利用にあたっては、どの保険が適用されるのかを事前に確認し、ケアマネジャーや訪問看護ステーションと密に連携することが大切です。
適切な保険の選択を行うことで、利用者様やご家族の負担を軽減し、安心してケアを受けることが可能になります。
まとめ
訪問看護では、利用者様の状態に応じて介護保険または医療保険が適用されます。要介護認定を受けている場合は、日常生活の支援が中心の介護保険が基本です。一方、がん末期や特定疾患など医療的ケアが主体となるケースでは医療保険が優先されます。
要介護認定がない場合は医療保険が適用されることが多く、特に65歳未満の特定疾患や急性期の治療時に利用されます。保険の選択は訪問看護ステーションやケアマネジャーと相談し、最適な制度を活用することが大切です。
UPDATEでは、「訪問看護マネジメントスクール」を行っています。ご興味がある方は、ぜひ無料の体験クラス動画もご視聴いただければ幸いです。

.png)