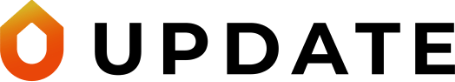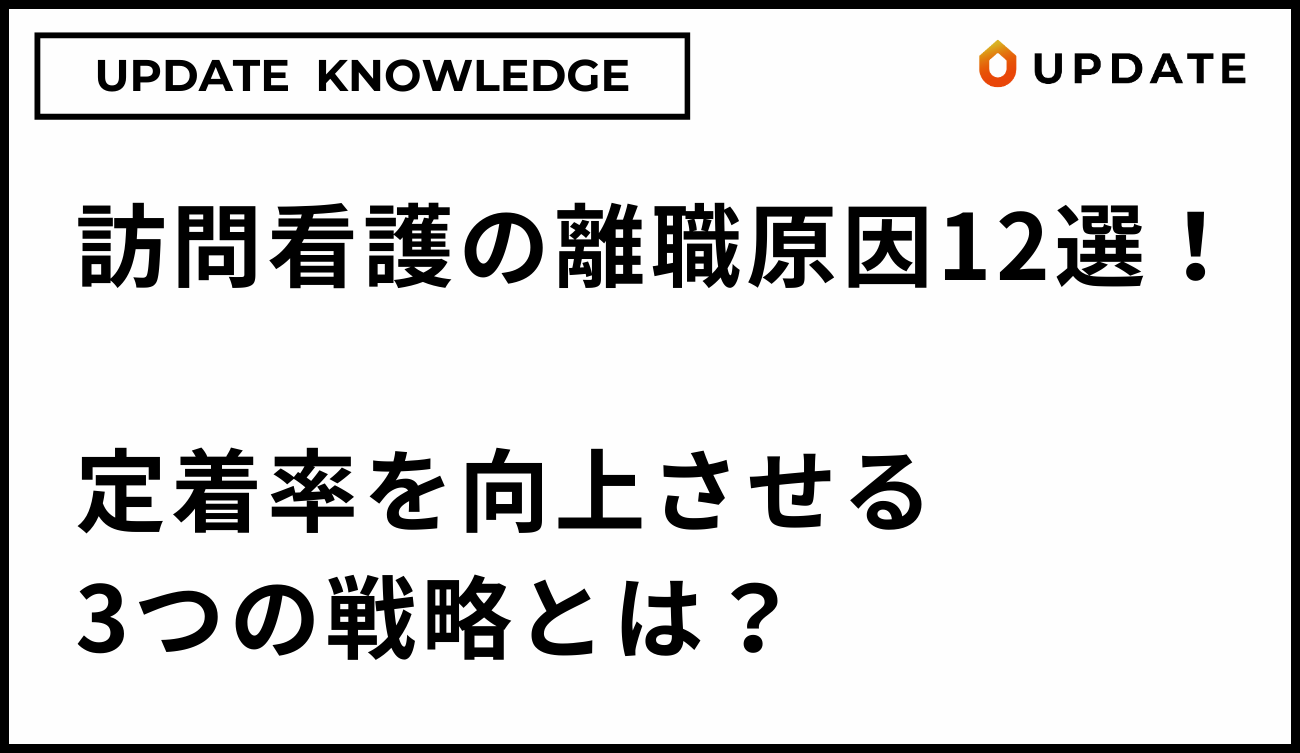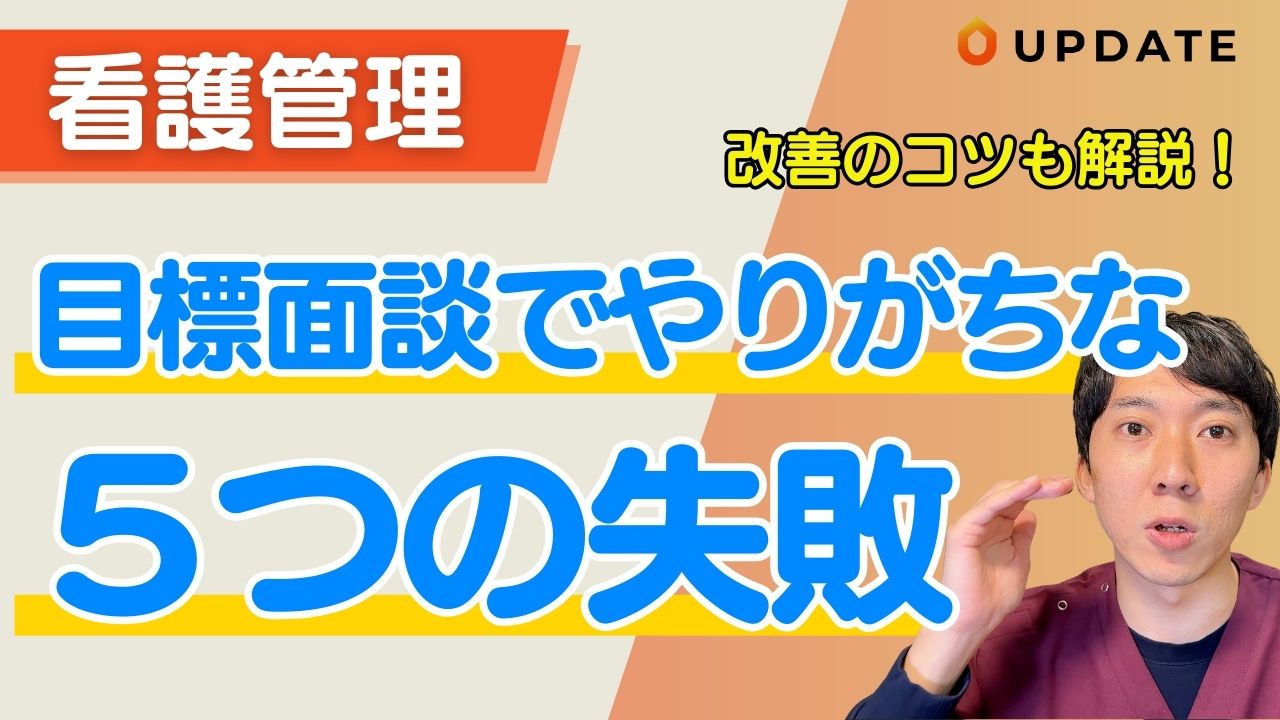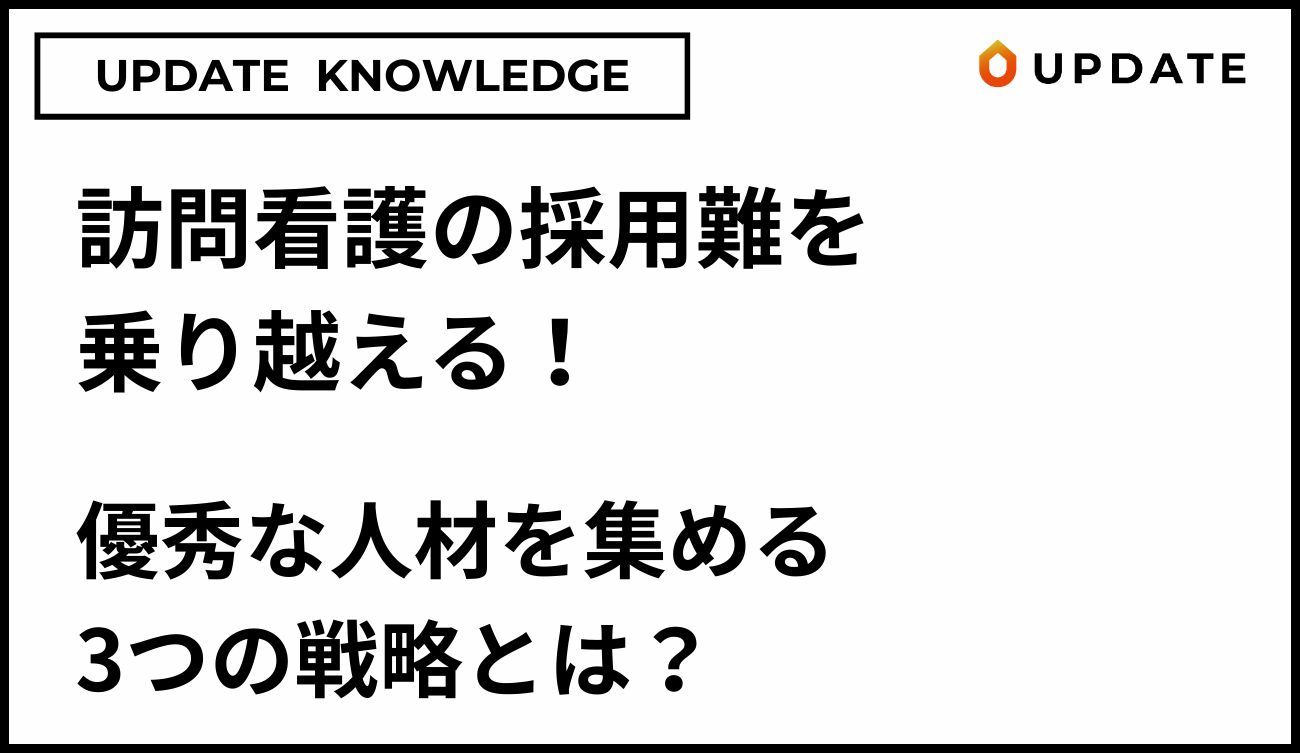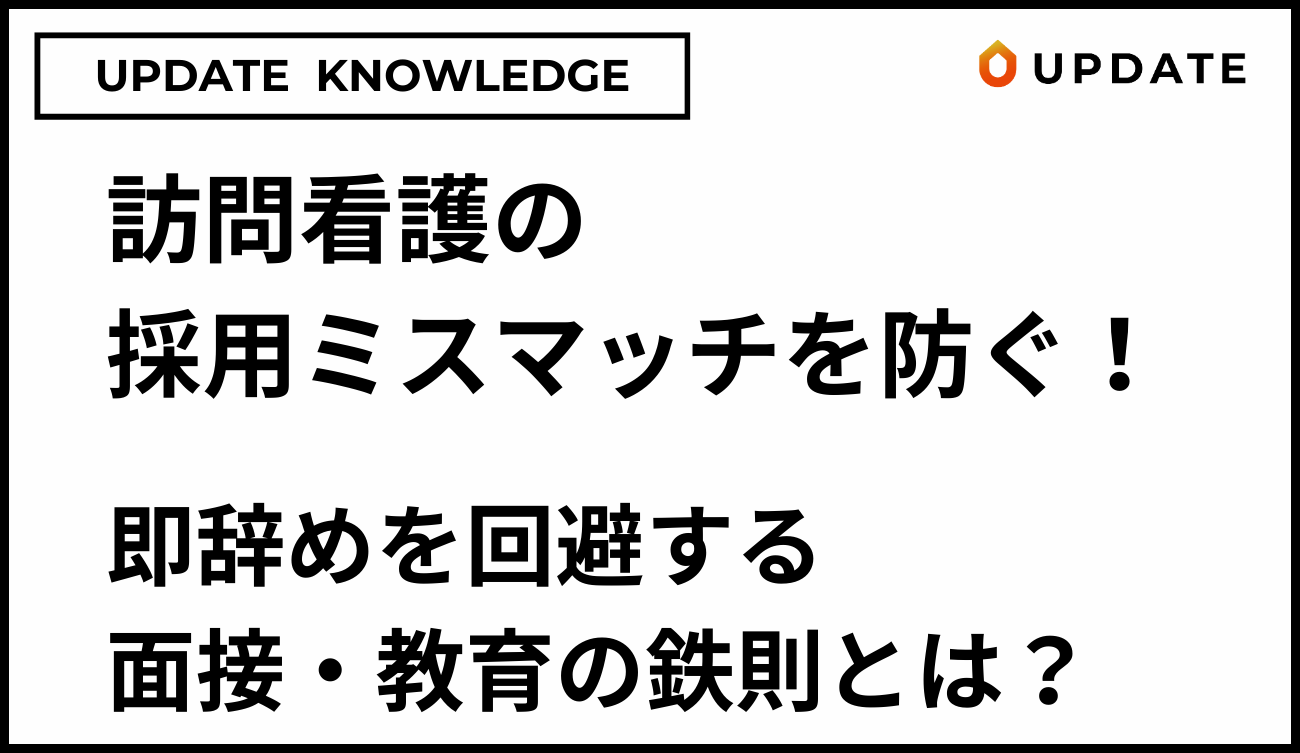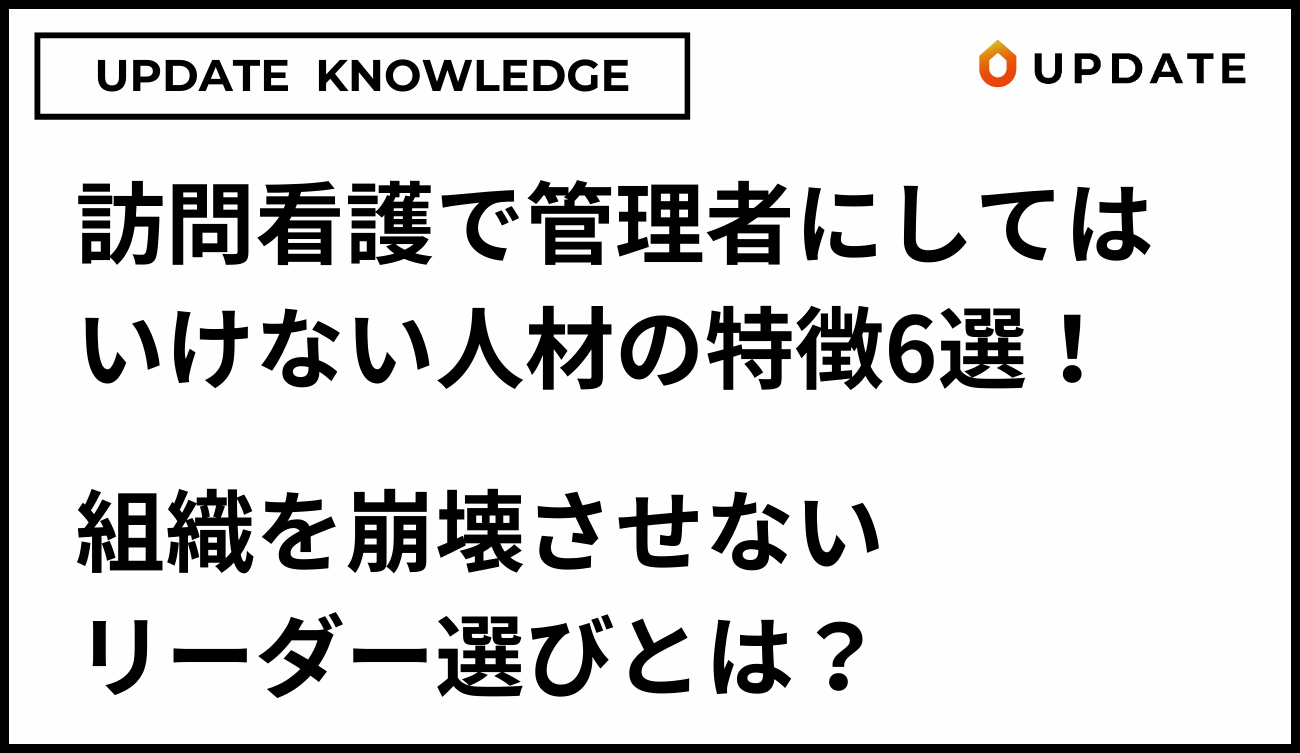訪問看護の医療保険適用条件について詳しく解説!介護保険との違いについて
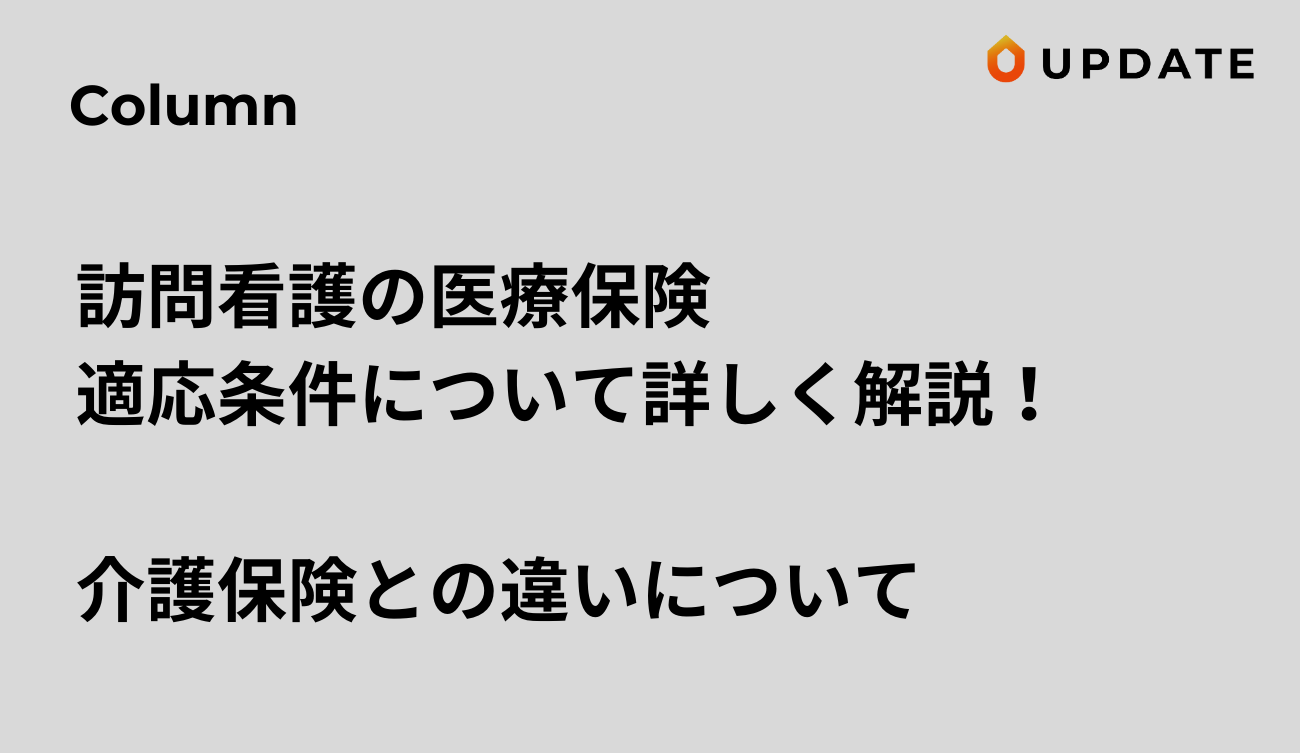
訪問看護を利用する際、医療保険や介護保険の適用条件を理解することはとても大切です。特に、訪問看護では、利用者様の症状や状態に応じた保険制度が適用され、費用負担や受けられるサービスが異なります。
本記事では、訪問看護による医療保険の具体的な適用条件やサービス内容、さらに介護保険との違いを詳しく解説します。利用者様やご家族が安心して訪問看護を利用できるよう、保険制度の正しい理解が大切ですので、ぜひ参考にしてください。
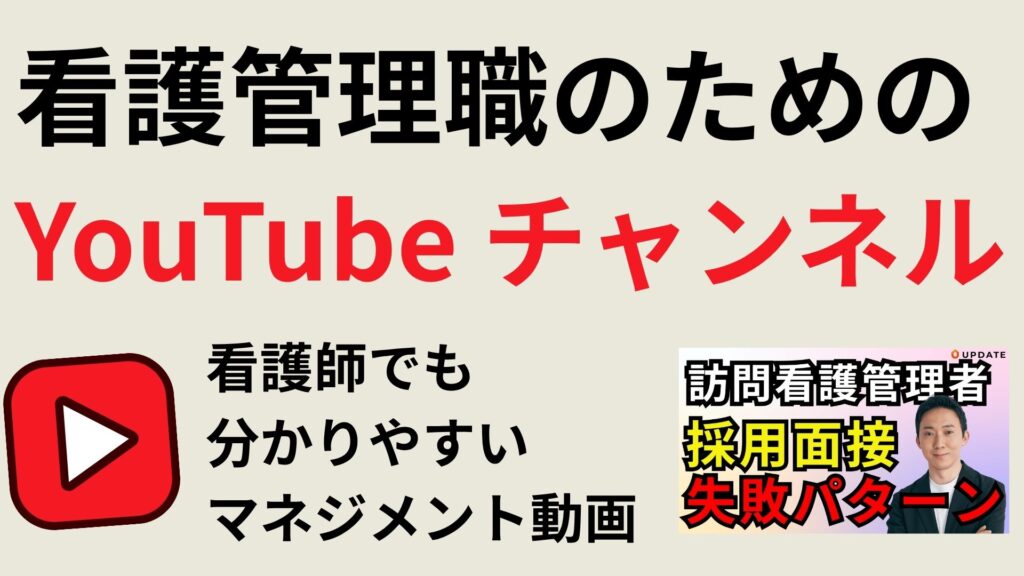
目次
訪問看護で利用できる保険の種類

訪問看護を利用する際には、保険の種類によって費用の負担や手続きが大きく異なります。はじめに、訪問看護で利用できる保険を詳しく解説します。
医療保険
医療保険は、主に医療的ケアが必要とされる利用者様が訪問看護を受ける際に適用される保険制度です。訪問看護ステーションを通じて、医師の指示に基づいた医療的ケアが行われる場合に利用できます。
【医療保険が適用される主な条件】
- 65歳以上で医師が訪問看護の必要性を認め、かつ要支援・要介護認定を受けていない
- 40歳以上65歳未満の方で、16特定疾病に該当しない
または該当していても要支援・要介護認定を受けていない場合 - 40歳未満の方で、医師が訪問看護の必要があると判断した場
【医療保険でカバーされるサービス】
- 生活の相談及び支援
- 医療的ケア
- 症状の管理及び看護
- リハビリテーション
医療保険は、1回90分程度の訪問が1日1回、週に3回までなどといった上限があります。
介護保険
介護保険は、要介護認定を受けた高齢者が、日常生活の支援や健康管理を目的として訪問看護を受ける場合に適用されます。医療的なケアが主な目的ではなく、生活の質を維持・向上させるためのケアが中心となる点が特徴です。
【介護保険が適用される主な条件】
- 65歳以上で、介護保険において要支援または要介護の認定を受けている場合
- 40歳以上65歳未満で、16特定疾病に該当し、かつ要支援・要介護認定を受けている場合
【介護保険でカバーされるサービス】
- 健康状態の観察と助言
- 服薬管理や指導
- 日常生活での介助やアドバイス
- 家族への介護指導
介護保険を利用する場合、訪問看護は「介護サービス計画(ケアプラン)」に基づいて実施されるため、事前にケアマネジャーに相談し、適切な訪問看護計画を立てることが必要です。
両者の違いを理解し、ご自身やご家族の状況に最適な保険を選択することで、訪問看護をより安心して活用できます。
医療保険と介護保険は併用できない
訪問看護では、医療保険と介護保険の併用は基本的にできません。これは、要支援や要介護の認定を受けている場合、原則として介護保険が優先される仕組みになっているためです。
ただし、異なる診断名で訪問看護を受ける場合や、それぞれの保険の適用時期が異なる場合、また末期がんなどの特定の難病を抱えている場合には、医療保険と介護保険の併用が可能になることもあります。
訪問看護で医療保険が適用される年齢別の条件

訪問看護による医療保険の適用条件には、利用者様の年齢や健康状態が深く関係します。加えて、医師の診断や指示が大切な判断基準となるため、これらの条件を十分に理解し、最適な保険制度を選択することが訪問看護を効果的に利用するためのポイントとなります。
40歳未満
訪問看護において、40歳未満の方は医療保険の適用対象となります。これは、医師が訪問看護の必要性を認めた場合に限られ、介護保険の適用はありません。
40歳以上65歳未満
40歳以上65歳未満の方が訪問看護を利用する際、医療保険の適用を受けるには一定の条件があります。これは、医師が訪問看護の必要性を認めたうえで、16特定疾病に該当しない、または該当していても要支援・要介護認定を受けていない場合に限られます。
さらに、介護保険第2号被保険者でないことも条件となります。これにより、必要な医療的支援を受けながら、自宅での療養を継続することが可能になります。
65歳以上
65歳以上の方が訪問看護を受ける際、医療保険の適用を受けるには条件があります。それは、医師が訪問看護の必要性を認め、かつ要支援・要介護認定を受けていないことです。
この条件を満たしている場合、医療保険を利用して自宅での適切なケアを受けることが可能です。要支援・要介護認定を受けると、原則として介護保険が優先されるため、訪問看護の利用にあたっては、保険の適用範囲を確認することが重要です。
訪問看護で医療保険が適用される疾患条件
特掲診療料の施設基準等に定められた疾病を持つ方は、医療保険による訪問看護の対象となります。週4日以上の訪問や、2つの訪問看護ステーションの併用が認められており、1日の訪問回数には制限がありません。ただし、訪問回数によって加算費用が異なる場合があります。
【対象となる疾患】
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患
・進行性核上性麻痺
・大脳皮質基底核変性症
・パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がII度又はIII度のものに限る)
- 多系統萎縮症
・線条体黒質変性症
・オリーブ矯小脳萎縮症
・シャイ・ドレーガー症候群
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフイー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷または人工呼吸器を使用している状態及び急性増悪期の場合
訪問看護で医療保険が適用される範囲
訪問看護を医療保険で利用する際には、訪問時間、訪問回数などの利用範囲に関する制約があります。これらの基準を理解し、計画的に利用することで、訪問看護の効果を最大限に引き出すことができます。
支給限度額は介護保険のみ
訪問看護を利用する際、医療保険と介護保険では支給限度額の考え方が異なります。医療保険には月間の支給限度額が設定されておらず、利用回数に制限はありますが、必要に応じた訪問が可能です。
一方、介護保険では支給限度額が決まっており、その範囲内で訪問看護を利用する必要があります。限度額を超えた場合は自己負担が発生するため、他の介護サービスと調整しながら計画的に利用することが重要です。
訪問時間
訪問看護の訪問時間は、医療保険の適用を受ける場合、1回あたり30分から90分の範囲で設定されます。多くのケースでは60分程度の訪問が一般的です。
厚生労働大臣が定める特定の疾病に該当し、長時間のケアが必要な場合には、週1回に限り90分を超える訪問が認められることもあります。訪問時間は、利用者の病状や必要な支援内容に応じて調整され、適切なケアが提供されるよう考慮されています。
訪問回数
訪問看護における医療保険の適用では、原則として1日1回、週3回までの訪問が認められています。ただし、厚生労働大臣が定める特定の疾病に該当する場合や、特別訪問看護指示書が発行されている場合は、週4日以上の訪問が可能です。
また、1日に複数回訪問する場合には、難病等複数回訪問加算の対象となることがあります。訪問回数によって基本療養費が変わるため、適切な回数での利用が求められます。
利用者様から回数を増やしてほしいと言われた場合
訪問看護の回数は、利用者様の健康状態やケアの必要性に応じて柔軟に見直しが可能です。回数の増加を希望する際は、医師やケアマネジャーへの相談が必要です。医療保険と介護保険のどちらを利用しているかによって、対応方法が異なります。
医療保険の場合
医療保険では、訪問看護の回数は医師の指示や看護の必要度に基づいて決定されます。そのため、利用者様が「もっと訪問回数を増やしてほしい」と希望された場合でも、医師の診断や治療方針、看護アセスメントの上での必要性を基に検討される必要があります。
必要に応じて、医師に訪問回数の再評価を依頼することが可能です。状況に応じて医師が訪問回数の見直しを判断し、指示書が再発行される場合もあります。利用者様の健康状態や医療的なニーズに応じた柔軟な対応が求められます。
関連記事:特別訪問看護指示書とは?退院直後の発行の場合いつまでが指示期間?
介護保険の場合
介護保険を利用する場合は、訪問看護の回数はケアマネジャーが作成するケアプランに基づいて決定されます。利用者様が訪問回数の増加を希望された場合は、ケアマネジャーと訪問看護ステーションが連携し、利用者様の状況に応じたプランの見直しが行われることになります。
ケアプランの変更には、利用者様やご家族の意向を踏まえたうえで、必要に応じて主治医の意見を取り入れることが大切です。
UPDATEでは『訪問看護特化の組織マネジメント基礎講座』を開催しています。無料の体験クラス動画もご用意してますので、興味のある方はぜひご覧ください。
無料体験クラス「組織に合わない言動を放置する悪影響と、効果的なフィードバック」
訪問看護における医療保険のルールについて

訪問看護を医療保険で利用する場合には、一定のルールや基準が設けられています。利用者様の症状や体調に応じて、適切な訪問時間や回数が定められ、それに基づいて訪問看護が提供される仕組みです。これらのルールを正しく理解し、適切に活用することで、訪問看護の効果を最大限に引き出すことができます。
一訪問90分まで
医療保険を利用する訪問看護では、1回の訪問時間は原則として90分以内と決められています。これは、効率的に必要な医療ケアを行うための基準であり、90分の範囲内でケアや指導が完了するよう計画されます。利用者様の健康状態や病状に応じて、訪問看護ステーションは効率的なケアを行うためのスケジュールを組み立てられるでしょう。
90分を超える訪問が必要な場合は、医師の指示や訪問看護ステーションの判断により、例外的に対応が検討されることがあります。特に、状態が急変した場合や集中的な医療ケアが必要と判断された場合には、医師の判断に基づき、より長時間の訪問が認められるケースがあります。
長時間訪問の指示があった場合
長時間の訪問指示があった場合は長時間訪問看護加算となり、特別なケアが求められる利用者に対し、1時間30分以上の訪問看護を行うことで適用される加算です。対象となる利用者様の要介護(要支援)度に応じて、介護と介護予防の長時間訪問看護加算がそれぞれ設定されています。
例えば、気管カニューレの使用や、在宅自己導尿指導管理のケースでは、長時間の訪問が適切とされることがあります。
このような長時間訪問が必要となる場合は、訪問看護ステーションが事前に医師やケアマネジャーと綿密に連携し、適切なケアプランが策定されます。計画的な訪問スケジュールの作成や、ご家族との情報共有が不可欠となり、利用者様が安心して在宅療養を続けられるように配慮されます。
関連記事:訪問看護の多職種連携の必要性とは?看護師の役割や課題を解説!
まとめ
訪問看護で医療保険の利用には、訪問時間や回数に関するルールが存在します。重度の疾患や急な状態悪化時には、長時間の訪問が必要とされ、医師や訪問看護ステーションが連携して対応します。利用者様の症状や状況に応じた柔軟な計画が大切であり、事前に医師やケアマネジャーとの連携が不可欠です。
UPDATEでは、訪問看護での実践的なマネジメントが学べる『訪問看護マネジメントスクール』や『企業内研修』を提供しております。 経営や組織運営に関してお悩みの方は、ぜひお気軽にお問合せください。より良い訪問看護の運営をサポートいたします。