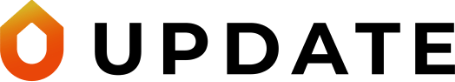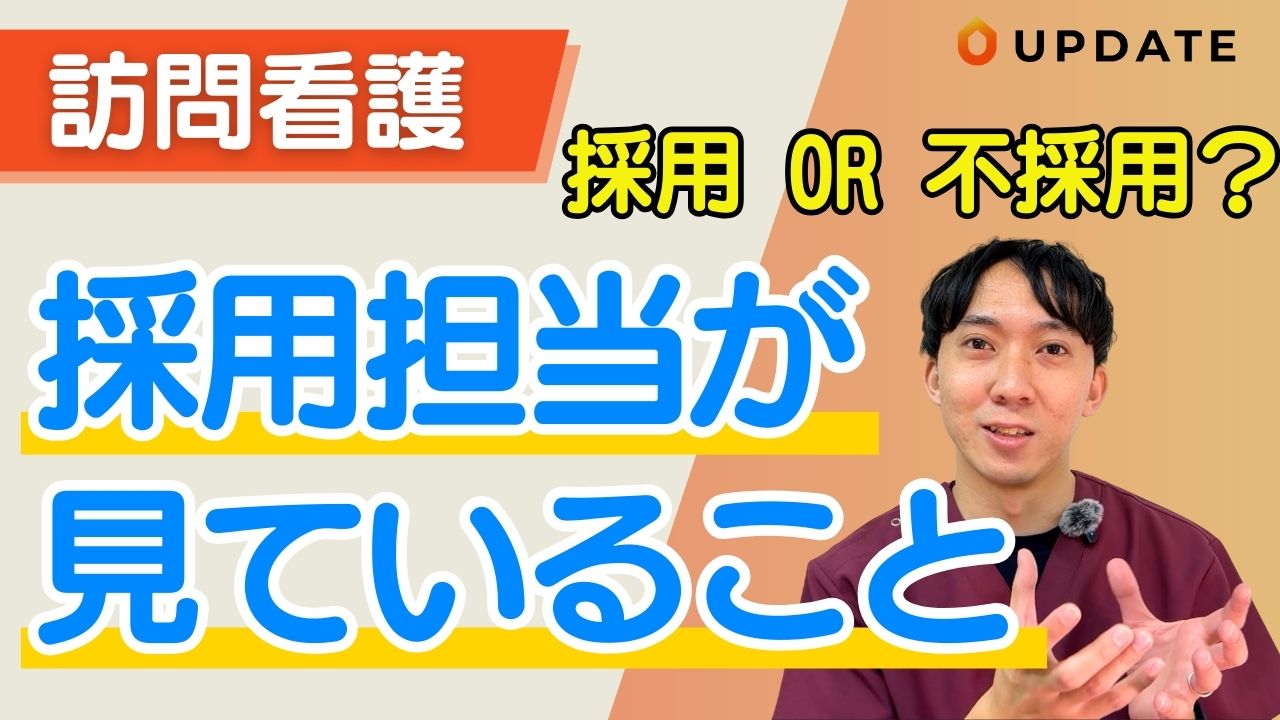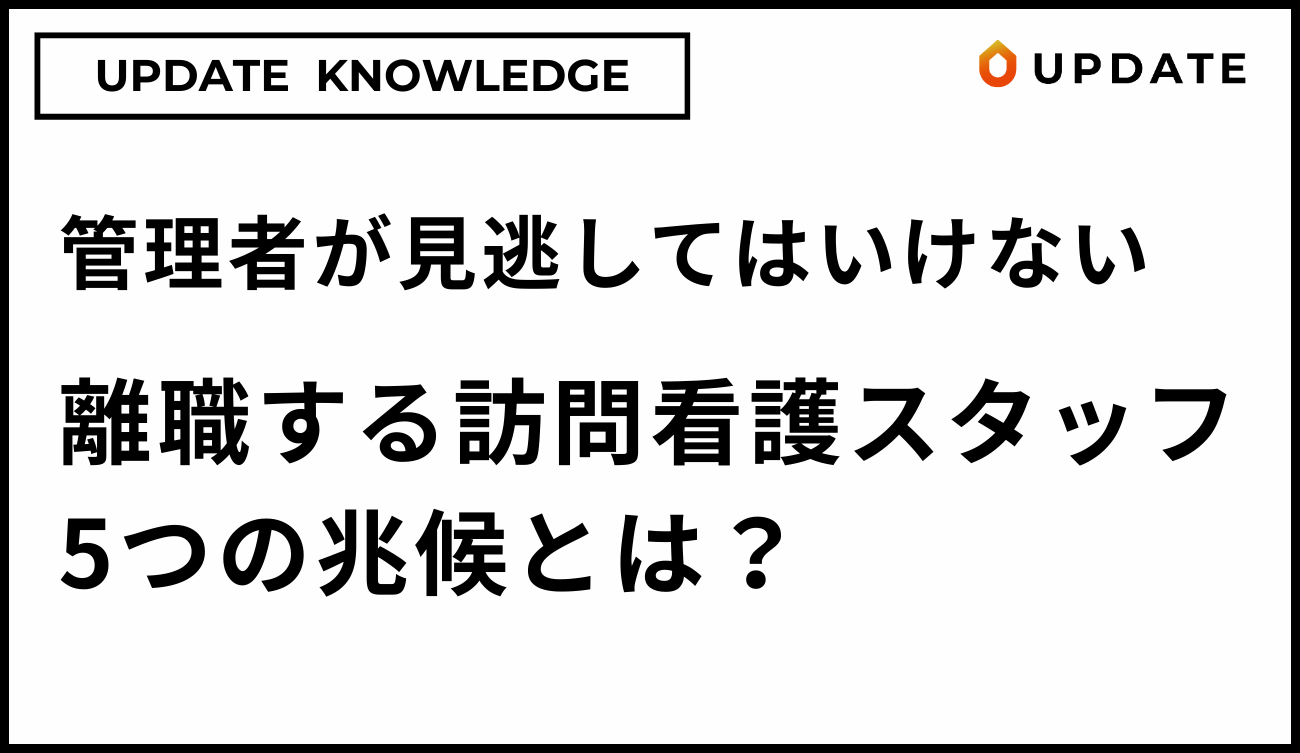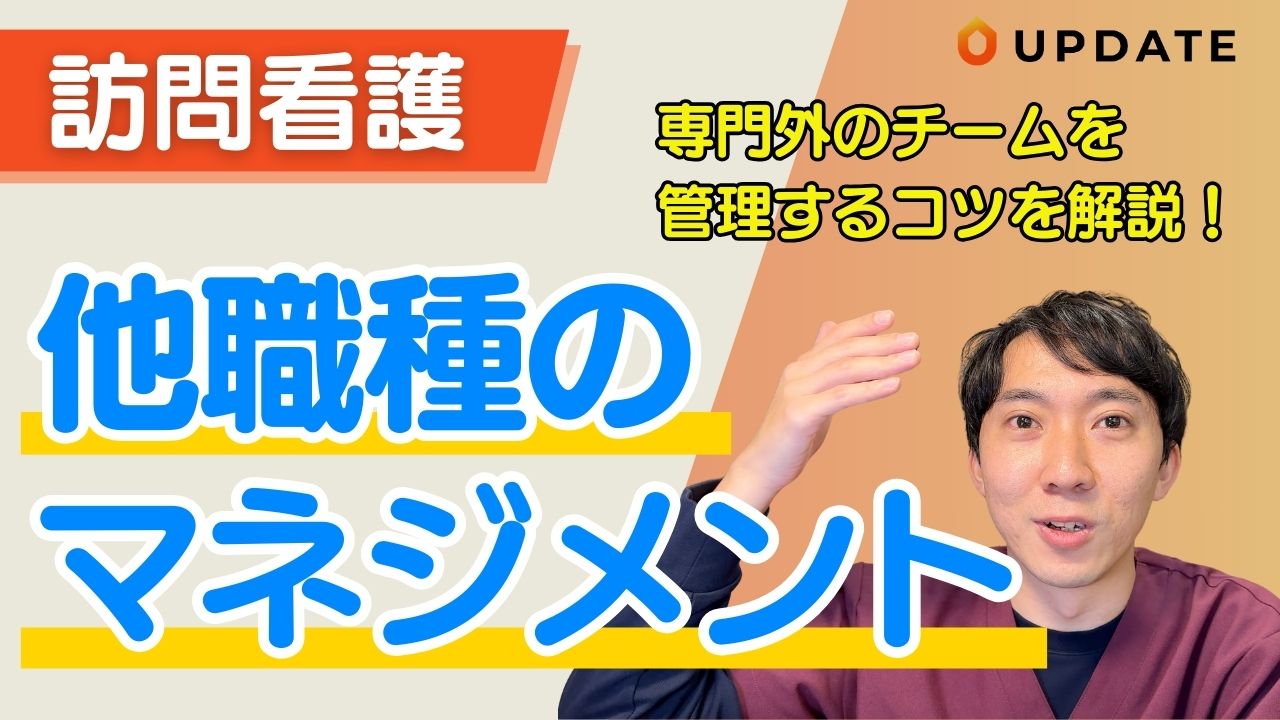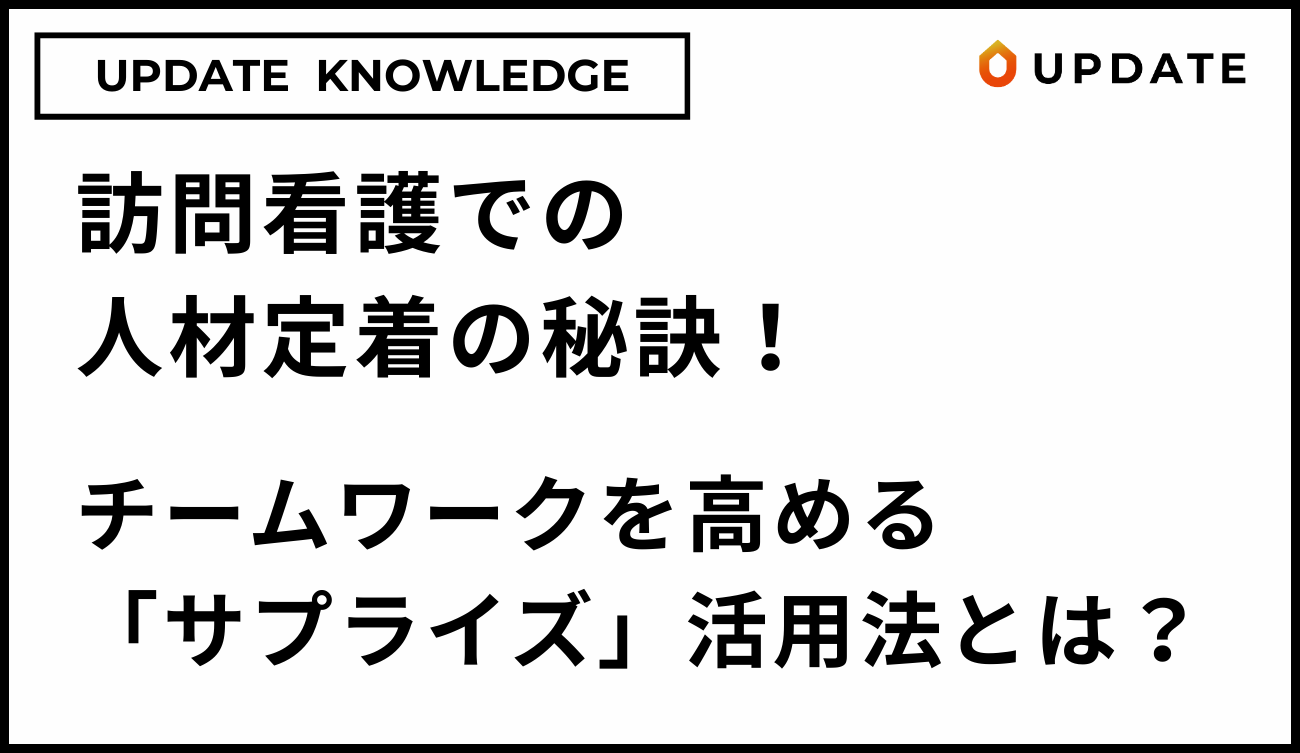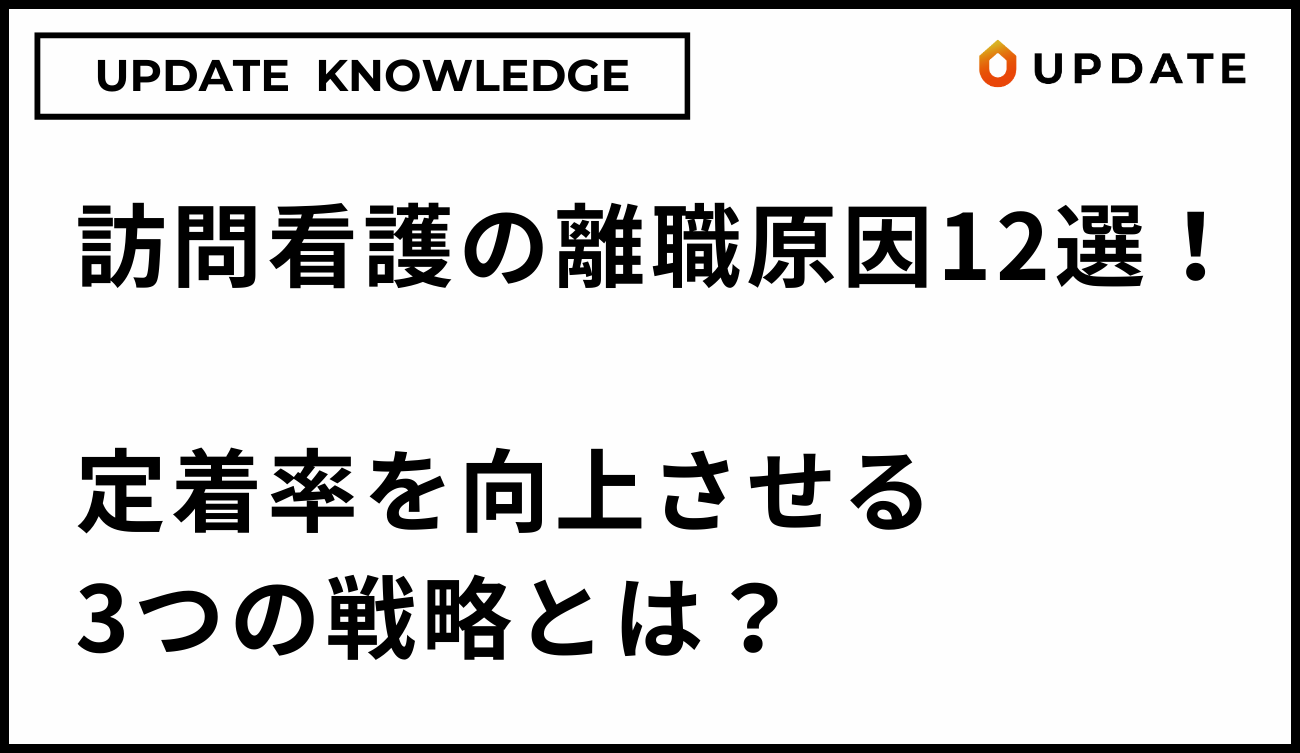在宅看護アセスメントの書き方について大切なポイントを解説
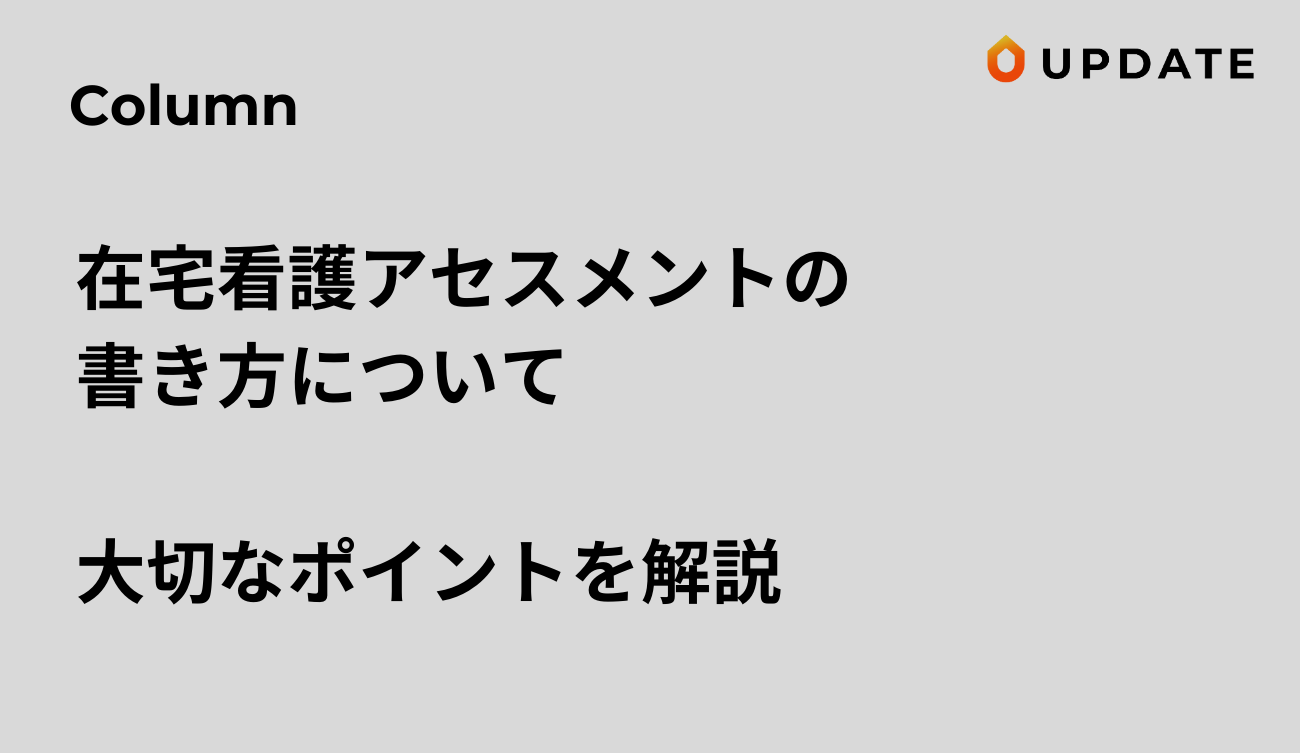
在宅医療では、利用者様が住み慣れた自宅で安心して療養生活を送るために、的確なアセスメントが大切です。病院とは異なり、在宅看護では家族の支援や生活リズム、住環境などの要素が密接に関わるため、幅広い視点での評価が求められるでしょう。
利用者様の健康状態はもちろん、日常の行動パターンや心身の変化を把握することで、最適なケアの提供が可能になります。本記事では、在宅看護アセスメントの具体的な手順や大切なポイントを詳しく解説します。
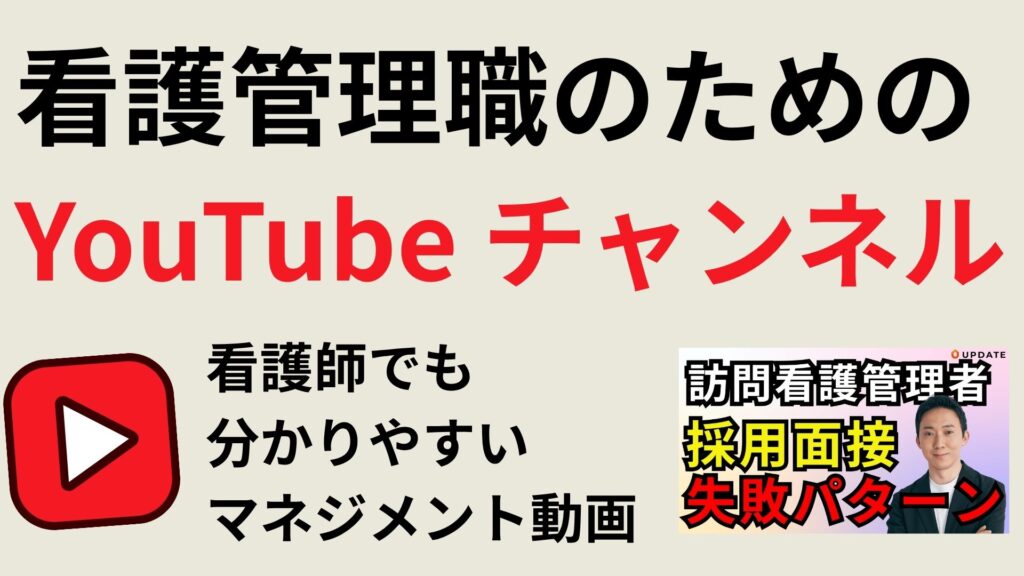
株式会社UPDATE 代表取締役(看護師・保健師・MBA) ケアプロ訪問看護ステーション東京にて新卒訪問看護師としてキャリアスタート。その後、訪問看護の現場・マネジメント経験の他、薬局や訪問看護運営するスタートアップ企業で40拠点・年商65億規模の経営を行い、上場企業へのグループインを実現。現在は医療職マネジメント人財を育成するためマネジメントスクールを運営中。
■経歴
2013年 慶應義塾大学 看護医療学部 卒業
2013年 ケアプロ株式会社入社
2019年 株式会社UPDATE(旧:ヘルスケア共創パートナー株式会社) 創業 代表取締役(現職)
2021年 GOOD AID株式会社 取締役(事業譲渡により退任)
2023年 セルフケア薬局 取締役(吸収合併により退任)
2023年 まちほけ株式会社 代表取締役(事業譲渡により退任)
■得意領域
医療系事業の組織マネジメント
教育体制構築
採用戦略・体制構築
教育体制構築
新卒訪問看護師の育成
管理職の育成
■保有資格・学位
看護師
保健師
経営学修士(MBA)
在宅看護アセスメントとは

在宅看護アセスメントとは、在宅医療や訪問看護では利用者様の健康状態や生活状況を評価し、適切なケアを提供するための不可欠なプロセスです。病院とは異なる環境であるため、利用者様の住環境やご家族との関わり、日常生活の動線など多岐にわたる要素を考慮する必要があります。
適切なアセスメントが行われることで、利用者様が安全かつ快適に療養生活を送れる環境が整い、必要な支援や介入が効果的に行えるようになります。
病院と在宅看護の違い
病院では、医師や看護師が24時間体制で利用者様の状態を管理し、医療機器や検査機能が充実しています。一方、在宅看護では、利用者様の生活空間での看護が基本となり、限られた時間内で的確なアセスメントと介入を行う必要があります。利用者様のご家族や介護者がケアの担い手となることが多く、その役割や負担も考慮した支援が大切です。
また、在宅環境では利用者様が生活の主体であるため、日常生活に支障をきたさないケアの計画が求められます。例えば、入浴や食事、排泄などの行動を見守りつつ、利用者様が自立した生活を送れるように支援する視点が欠かせません。そのため、利用者様の価値観や生活のこだわりにも配慮する必要があります。
在宅看護アセスメントの重要性
在宅看護アセスメントは、利用者様の健康状態の把握だけでなく、家庭環境や介護者の状況を理解するために欠かせません。利用者様が抱える健康課題や生活上の不安を見つけ出し、最適なケア計画を立てるための重要なステップとなります。
アセスメントを通じて、利用者様の疾患管理や再発予防のための具体的なケア方法を策定し、適切な医療的ケアの調整や福祉支援につなげることができます。また、利用者様のQOL(生活の質)向上を目指し、本人の意思を尊重しつつ柔軟なサポートを行うためにも、的確なアセスメントが求められるでしょう。
さらに、訪問看護師が利用者様の身体的な症状だけでなく、精神的な負担や社会的な課題にも目を向けることで、包括的な支援が可能となります。これにより、利用者様が安心して在宅療養を続けられる環境づくりが進められます。
在宅看護のアセスメント頻度
在宅看護のアセスメントは、利用者様の健康状態や生活環境の変化に応じて柔軟に行うことが大切です。訪問のたびに基本的な健康状態のチェックを行い、異常の兆候や利用者様の訴えに耳を傾けることが求められます。特に、慢性疾患の管理や終末期ケアでは、症状の変化に敏感に対応するため、こまめなアセスメントが欠かせません。
アセスメントの頻度は、利用者様の健康状態やリスクの程度によって異なります。例えば、急性症状が見られる利用者様や退院直後の利用者様には、頻回のアセスメントが必要です。一方、状態が安定している利用者様には、定期的な訪問に加えて必要に応じた緊急対応が効果的です。
また、利用者様の生活環境や家族構成が変化した際も、アセスメントを通じて支援内容の見直しが求められます。これにより、利用者様の安全確保やご家族の負担軽減につながる最適なケア計画が実現します。
在宅看護アセスメントの4つの視点
在宅看護アセスメントは、利用者様の健康状態を多角的に評価することで、より適切なケアが実現します。特に重要な4つの視点に注目することで、利用者様のQOL向上や病状の安定に繋がる具体的な支援が可能です。
身体状況の視点
身体状況の視点では、利用者様の全身状態を把握し、健康管理の方針を立てるために大切です。具体的には、体温、血圧、脈拍、呼吸状態などのバイタルサインのチェックが基本となります。
また、皮膚の状態や褥瘡(じょくそう)の有無、関節の動きや筋力の変化なども確認が必要です。特に、在宅では感染症のリスクが高まるため、早期発見と迅速な対応が求められます。定期的な観察を行い、身体機能の維持・向上に向けた介入を行うことが不可欠です。
心理状況の視点
心理状況の視点では、利用者様の感情や精神状態を理解することが大切です。利用者様が抱える不安や孤独感、ストレスの要因を把握し、精神的なサポートを提供することで、QOLの向上が期待できます。
特に、慢性疾患や終末期ケアでは、利用者様のメンタルケアが大切です。リラックスできる環境づくりや、利用者様が自分の気持ちを話しやすい関係性の構築が効果的なサポートに繋がります。
生活環境の視点
生活環境の視点では、利用者様が安全に快適に生活できる環境が整っているかを評価します。住環境のバリアフリー化、転倒防止のための配置の見直し、福祉用具の活用などが必要です。また、ご家族の協力体制や介護者の負担も考慮し、サポートが必要な場合は地域の介護サービスや医療機関と連携を図ることが効果的です。
社会や家族環境の視点
社会や家族環境の視点では、利用者様を取り巻く社会的なネットワークや家族の役割が大切です。利用者様が地域社会と適切に関わりを持てるか、孤立していないかを確認することが不可欠です。
介護負担の偏りや家族間のコミュニケーション不足が問題となるケースも多いため、必要に応じて地域の支援団体や相談窓口の活用を促すことで、利用者様と家族双方の負担を軽減する効果が期待できます。
SOAPを使った書き方のポイント

在宅看護アセスメントの記録では、SOAP形式が広く用いられています。SOAPとは、主観的情報(Subjective)、客観的情報(Objective)、評価考察(Assessment)、計画(Plan)の4つの要素から構成され、情報整理と正確な記録に役立ちます。
主観的情報(Subjective)
主観的情報は、利用者様やご家族が訴えた症状や感情、生活の中での気づきを記録します。具体的には「頭が痛い」「食欲がない」「夜眠れない」などの利用者様自身の言葉が含まれます。
これらの情報は、利用者様の状態やニーズを正確に把握するために欠かせません。利用者様の感情面の変化にも着目し、心理的な支援が必要かどうかも評価することが大切です。
客観的情報(Objetive)
客観的情報は、看護師が実際に観察し、測定した事実に基づく情報です。具体的には、体温や血圧、脈拍、皮膚の状態、傷の治癒状況などが挙げられます。視診、触診、聴診、検査データなどを活用して、できるだけ具体的な数値や状況を記載することが大切です。利用者様の状態変化が把握しやすく、ケアの方向性が明確になります。
評価考察(Assessment)
評価考察では、主観的情報と客観的情報をもとに、利用者様の健康状態の評価や今後のケアの方針を記録します。例えば「脱水のリスクが高い」「疼痛が強まりつつある」「心理的ストレスが蓄積している可能性あり」などの具体的な評価が求められます。利用者様の課題やリスクを明確にすることで、より的確なケアに繋げることができます。
計画(Plan)
計画では、評価考察に基づいて実行するケアの内容やタイミングを記録します。例えば「1日2回の水分補給を促す」「疼痛緩和のためのポジショニングを実施」「カウンセリングの導入を検討」などが該当します。具体的で実行しやすい計画を立てることで、チーム内での情報共有や介入の精度が向上します。
UPDATEでは『訪問看護特化の組織マネジメント基礎講座』を開催しています。無料の体験クラス動画もご用意してますので、興味のある方はぜひご覧ください。
無料体験クラス「組織に合わない言動を放置する悪影響と、効果的なフィードバック」
アセスメントに役立つ理論
アセスメントに役立つ理論とは、利用者様の健康状態や生活環境を的確に評価し、最適なケア計画を立てるための指針となる枠組みのことです。特に在宅看護では、利用者様の身体的・精神的側面だけでなく、家庭環境や生活リズムなどの要素も大切な評価ポイントとなります。
11の機能的健康パターン|マージョリー・ゴードン
マージョリー・ゴードンが提唱した「11の機能的健康パターン」は、利用者様の健康状態を包括的に評価するための理論です。これには、健康管理、栄養代謝、活動・運動、認知・知覚、睡眠・休息などの視点が含まれ、利用者様の健康課題を多角的に捉えるのに役立ちます。
これにより、単に病状を把握するだけでなく、利用者様の生活リズムや社会的関係、精神状態に対する理解が深まるでしょう。
例えば、食事に関しては「栄養バランスが取れているか」「食事の時間が安定しているか」などの視点でチェックできます。また、活動・運動では「日中の活動レベル」や「夜間の睡眠状況」などを記録し、利用者様の健康維持のための具体的な支援が可能となります。
14の基本的欲求|ヘンダーソン
ヘンダーソンが提唱した「14の基本的欲求」は、人間が健康を維持するために満たすべき基本的なニーズを示しています。これには、呼吸、食事、水分補給、排泄、睡眠、清潔保持などの要素が含まれ、利用者様の生活の質を向上させるための視点として大切です。
例えば、呼吸では「酸素吸入が必要か」「呼吸のリズムに異常がないか」を確認し、清潔保持では「入浴や清拭が定期的に行われているか」などの観察が不可欠です。これらの視点を用いることで、利用者様の健康管理に必要なケアが具体化し、効果的な介入が可能となります。
アセスメント力を向上するために大切なこと

在宅看護アセスメントの質を高めるには、日々の業務での意識と工夫が大切です。アセスメントスキルを磨くために、以下の4つのポイントを意識することが効果的です。
小さな変化に気づく
利用者様の状態は日々変化します。特に在宅看護では、病院に比べて医療スタッフが利用者様のそばにいる時間が限られるため、細かな変化に気づくことが大切です。
例えば、「食事量が減っている」「顔色が悪くなった」「歩行時に足の運びが重そう」などの微細な変化を見逃さないようにすることで、早期対応が可能になります。利用者様の日常生活を観察する際には、生活リズムや行動のパターンに着目し、健康状態の変化に素早く対応できるスキルが求められます。
関連記事:訪問看護で求められるスキルとは?経験者が直面する課題について解説
多職種の連携で視野を広げる
在宅看護では、医師や理学療法士、薬剤師、介護福祉士など、多職種との連携が欠かせません。各専門職が持つ視点を取り入れることで、利用者様の健康課題を多角的に捉え、より効果的なケアにつなげることができます。
例えば、リハビリテーションの観点から「利用者様の関節の動きが悪くなっている」と指摘があれば、早期の対応で悪化を防ぐことができます。多職種の意見を積極的に取り入れ、情報を共有することで、より正確なアセスメントが可能です。
専門知識のアップデートをする
医療や看護の現場では、日々新しい治療法やケアの技術が進化しています。より質の高いアセスメントを実践するためには、最新の知識を習得し続けることが不可欠です。
例えば、在宅での医療機器の使用方法や、新たな疼痛管理の方法など、実践に活かせる情報の収集が求められます。専門書の読書や勉強会の参加、最新の学術研究の確認などを通じて、知識をアップデートする姿勢が欠かせません。
他者からのフィードバックを受ける
自らのアセスメントの精度を高めるためには、他者からの意見やフィードバックを積極的に受け入れることも大切です。
上司や先輩看護師、医師からのアドバイスを活かすことで、視点の偏りや見落としを防ぎ、アセスメントの質を向上させることができます。また、同僚と定期的にケースカンファレンスを行い、互いの視点を共有することで、より多角的な気づきや知見を得る機会が増えます。
まとめ
在宅看護アセスメントは、利用者様の健康状態や家庭環境、家族の関わりなどを総合的に評価することが大切です。小さな変化の見逃しを防ぐためには、細やかな観察力と情報収集が欠かせません。また、医師や介護職との密な連携を図ることで、より質の高いケアが実現します。利用者様が安心して在宅療養を継続するためには、的確なアセスメントが不可欠です。
UPDATEでは、訪問看護の実務に特化した「訪問看護マネジメントスクール」や「企業内研修」を実施しております。経営や組織運営に関するお悩みがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。訪問看護のより良い運営を目指し、皆様をサポートいたします。