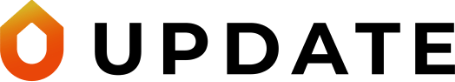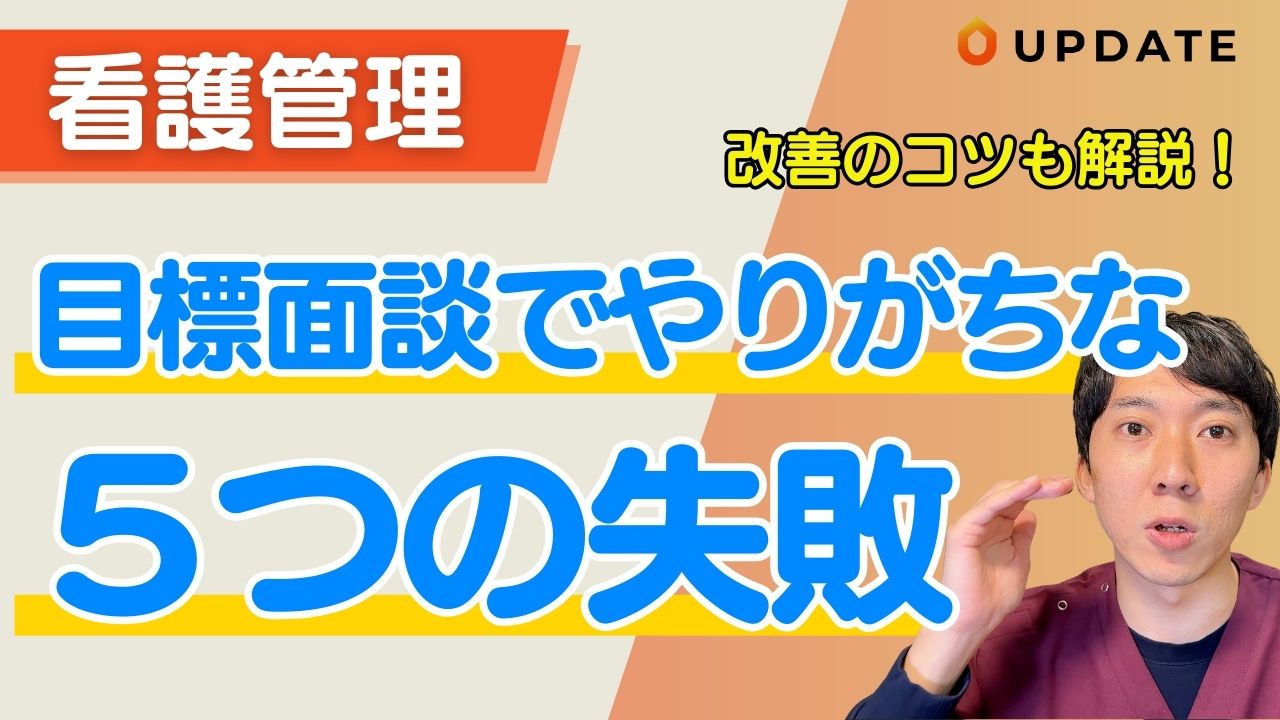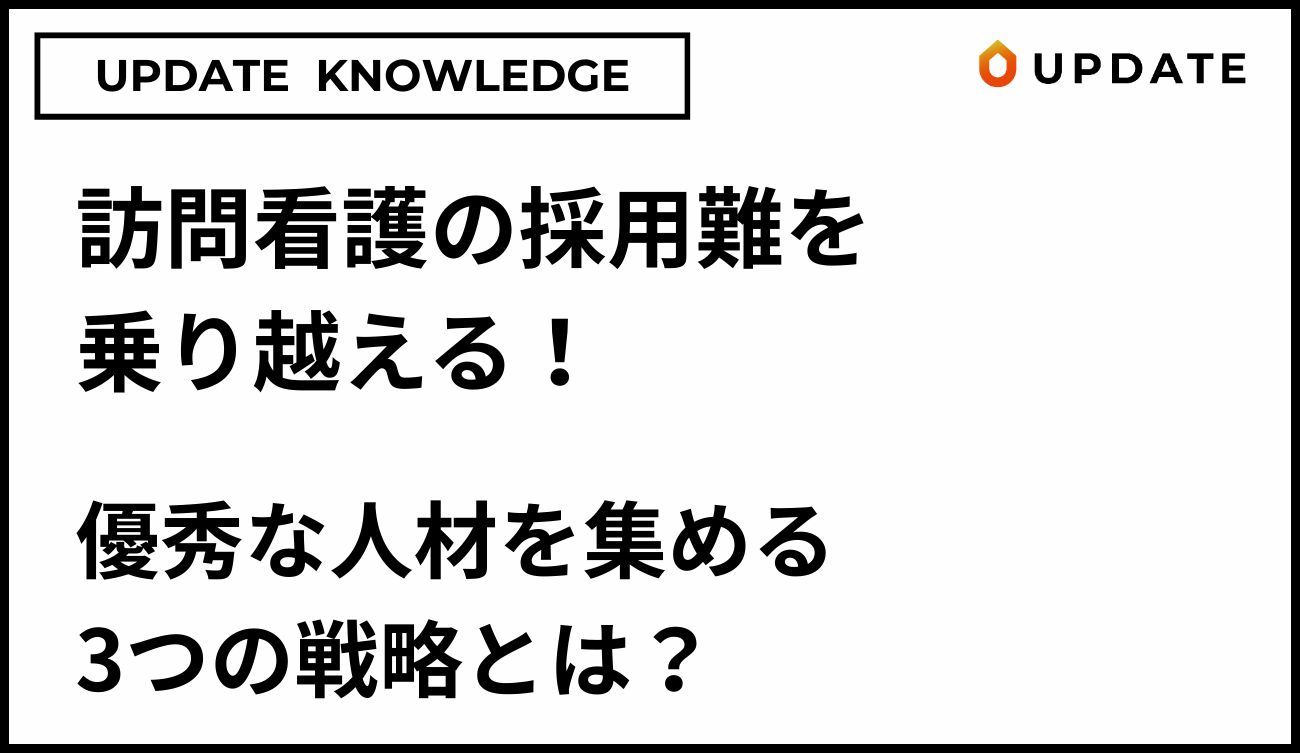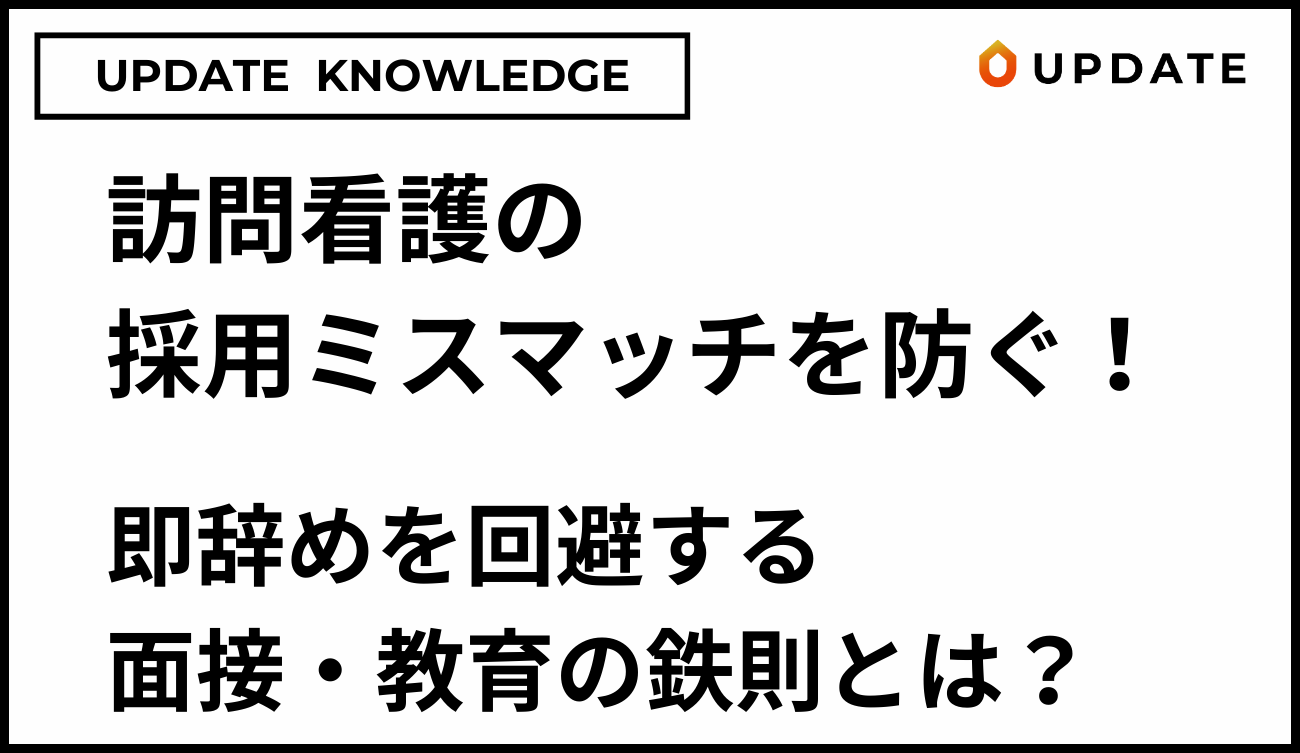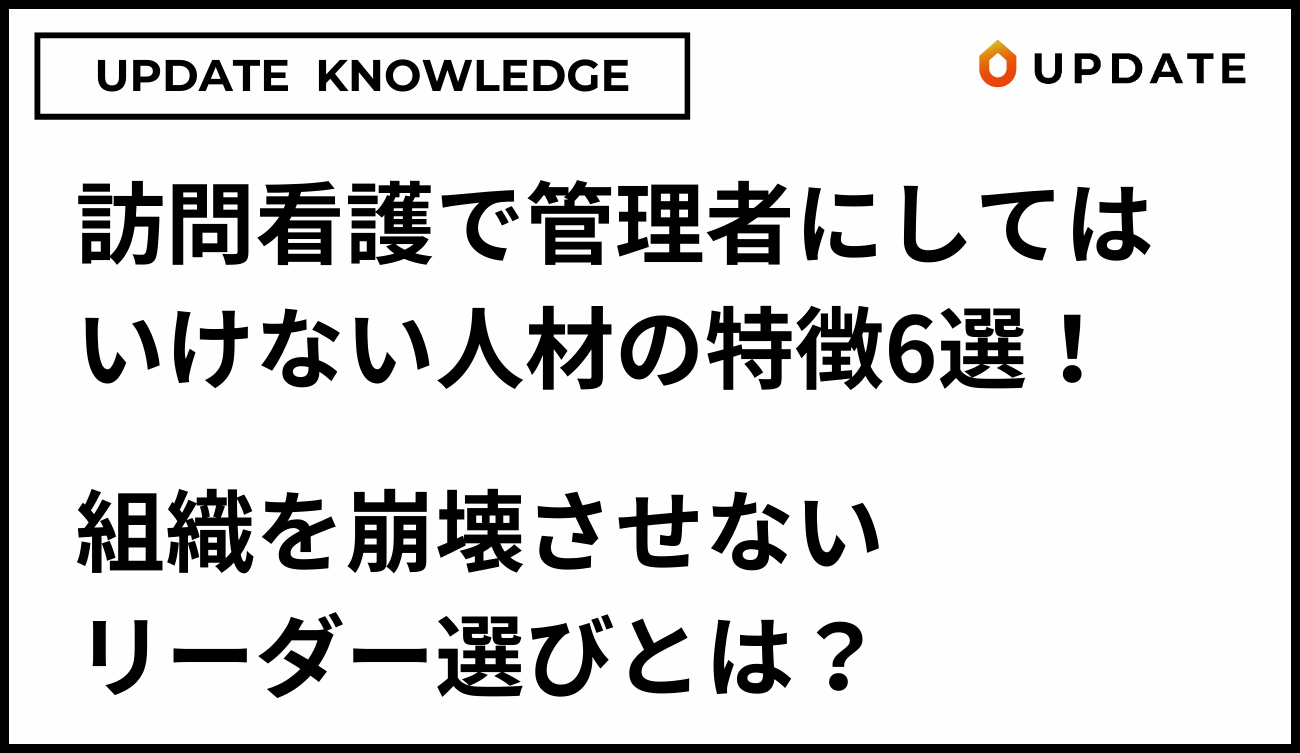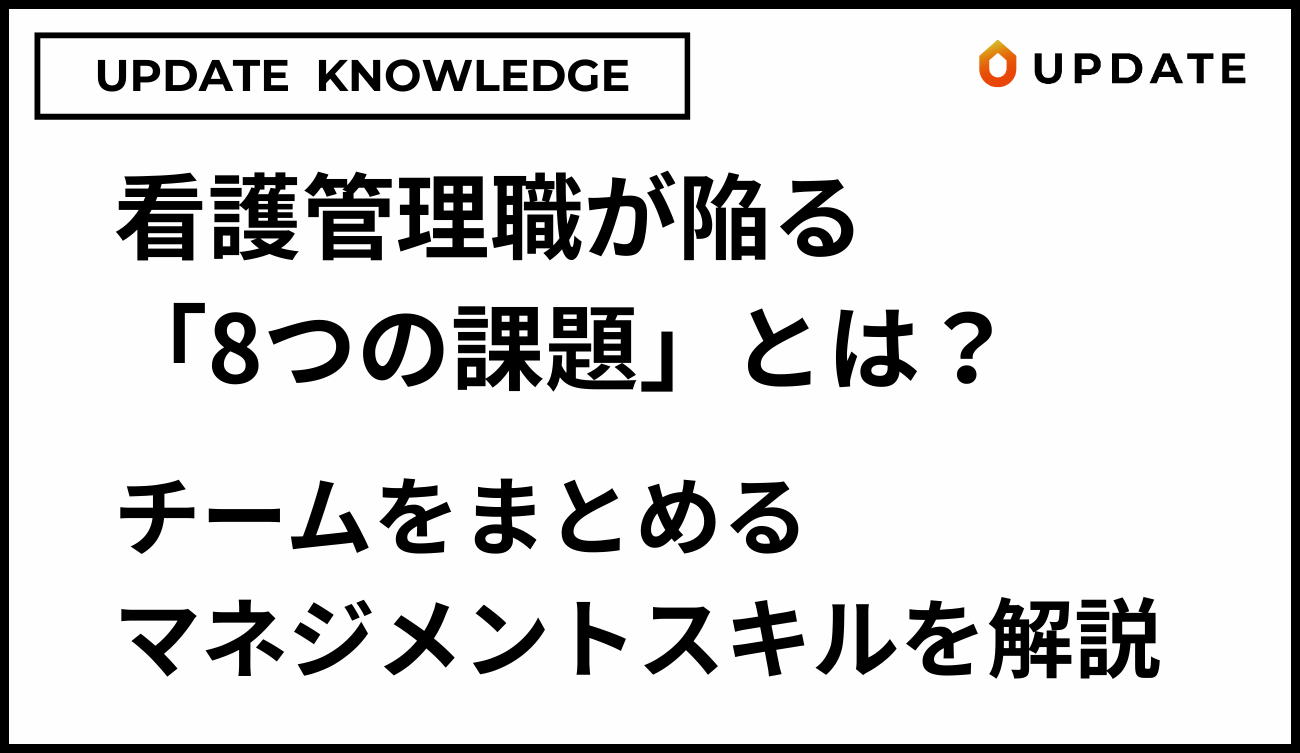【違反事例あり】訪問看護ステーションの開設基準「人員・設備・運営」を徹底解説!
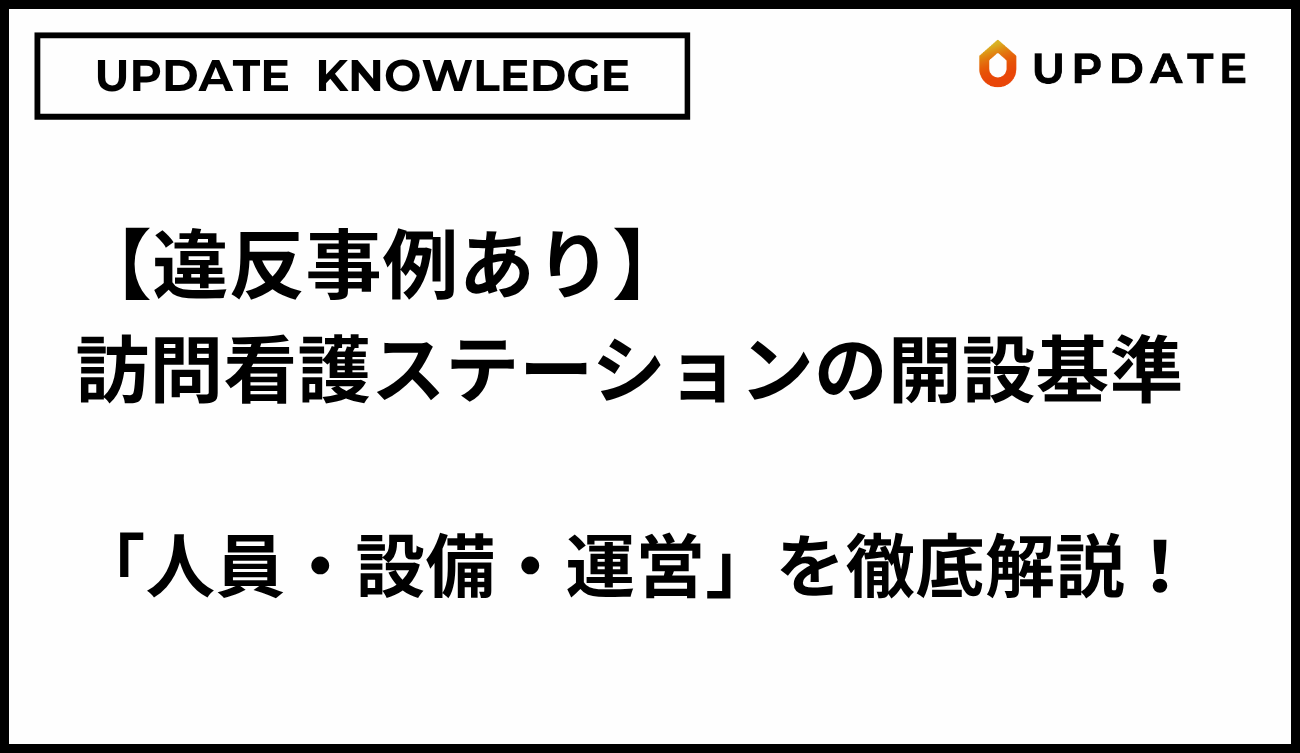
訪問看護ステーションを運営するためには、厚生労働省によって定められた基準を満たす必要があります。訪問看護事業所の開設基準は、以下の3つに分かれています。
『人員に関する基準』
『設備に関する基準』
『運営に関する基準』
本記事では、それぞれの基準の詳細と、訪問看護ステーションで実際にあった事例について解説します。
これからステーションを立ち上げる方、運営している事業所が各基準を満たしているか不安な方は、ぜひ最後までお読みください。
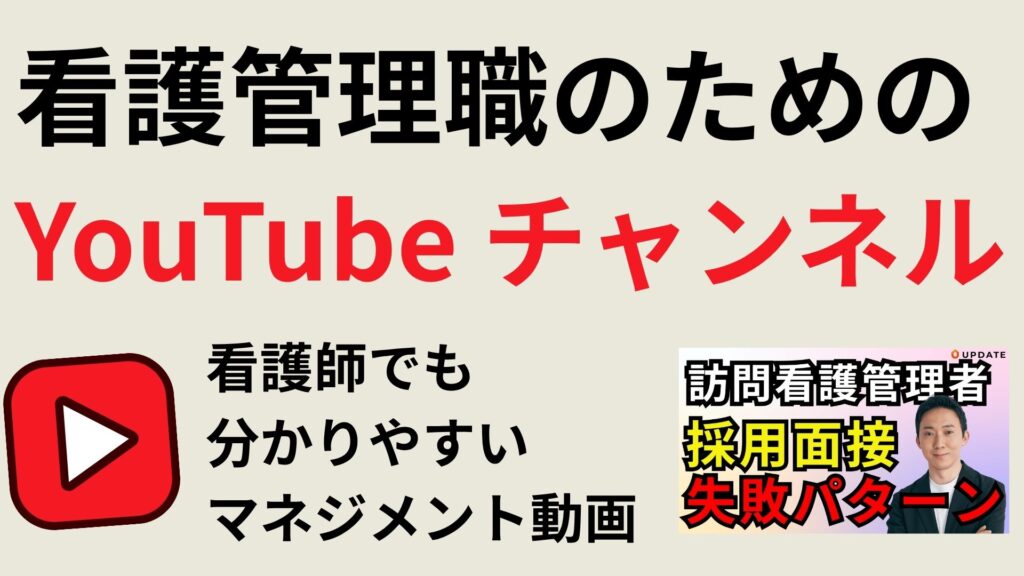
目次
- 1 訪問看護ステーションの「人員に関する基準」とは?
- 2 訪問看護ステーションの「人員基準」に関する指摘事例
- 3 訪問看護ステーションの「設備に関する基準」とは?
- 4 新規立ち上げ時の具体的な確認点
- 5 訪問看護ステーションの「設備基準」に関する指摘事例
- 6 訪問看護ステーションの「運営に関する基準」とは?
- 6.1 サービス提供困難時の対応
- 6.2 居宅介護支援事業者等との連携
- 6.3 利用料等の受領
- 6.4 指定訪問看護の基本取扱方針
- 6.5 指定訪問看護の具体的取扱方針
- 6.6 主治医との関係
- 6.7 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成
- 6.8 同居家族に対する訪問看護の禁止
- 6.9 緊急時等の対応
- 6.10 運営規程
- 6.11 記録の整備
- 6.12 内容及び手続の説明及び同意
- 6.13 提供拒否の禁止
- 6.14 受給資格等の確認
- 6.15 要介護認定の申請に係る援助
- 6.16 心身の状況等の把握
- 6.17 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助
- 6.18 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供
- 6.19 居宅サービス計画等の変更の援助
- 6.20 身分を証する書類の携行
- 6.21 サービスの提供の記録
- 6.22 保険給付の請求のための証明書の交付
- 6.23 利用者に関する市町村への通知
- 6.24 勤務体制の確保等
- 6.25 業務継続計画の策定等
- 6.26 衛生管理等
- 6.27 掲示
- 6.28 秘密保持等
- 6.29 広告
- 6.30 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止
- 6.31 苦情処理
- 6.32 地域との連携等
- 6.33 事故発生時の対応
- 6.34 虐待の防止
- 6.35 会計の区分
- 6.36 管理者の責務
- 7 訪問看護ステーションの運営基準に関する指摘事例
- 8 まとめ:法令を守って適切な運営を!経験者と伴走し失敗を回避しよう!
訪問看護ステーションの「人員に関する基準」とは?

訪問看護の運営に関する基準は『指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について』の第60条から第61条(準用を除く)によって定められています。
看護師等の員数
指定訪問看護事業者は、次に掲げる指定訪問看護事業所の種類の区分に応じて、看護師等の員数を置くことが定められています。
| 指定訪問看護ステーションの区分 | 看護師等の員数 |
|---|---|
| 病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所 | ・看護職員が常勤換算方法で、2.5人以上となる員数 ※このうち1名は、常勤であること ・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は実情に応じた適当数 ※配置がなくてもよい |
| 病院又は診療所である指定訪問看護事業所 | 指定訪問看護の提供に当たる看護職員を適当数置くべきもの |
※「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法。
管理者
指定訪問看護事業者は、訪問看護ステーションごとに常勤の管理者を配置しなければならず、また管理者は原則保健師か看護師でなければならないことが定められています。また、適切な訪問看護を行うために必要な知識・技能を有するものでなければならないことも定められています。
訪問看護ステーションの「人員基準」に関する指摘事例
これらの基準は法令でさだれられたもののため、正しく実施をしないと行政からの指導を受けたり、悪質な場合は行政処分を受ける可能性があります。
ここでは、実際にあった訪問看護ステーションの「人員基準」に関する指摘事例をご紹介します。
| 看護師等の員数 | ・保健師、看護師又は准看護師を常勤換算で2.5人以上確保していない ・訪問看護ステーションにおいて月ごとの勤務表を作成していない |
| 管理者 | ・管理者とされたものが非常勤であった |
UPDATEの【訪問看護管理者研修】基礎から学ぶ組織マネジメント講座では、ステーションの立ち上げ期から成長期のお悩みまで、さらに詳しく学べます。現場のリアルな悩みを解決でき、頼られる管理者への一歩を踏み出せます。
「しっかり組織マネジメントの基礎を学びたい!」という方向けに、【訪問看護管理者研修】基礎から学ぶ組織マネジメント講座を開催しています。
今なら無料の体験クラス動画や特別プレゼントもご用意しています。
あなたもぜひお受け取りください。
訪問看護ステーションの「設備に関する基準」とは?
訪問看護の運営に関する基準は『指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について』の第62条(準用を除く)によって定められています。
設備及び備品等
指定訪問看護事業の設備基準等には以下の2点が法令で定められています。
- 事業の運営を行うために必要な広さを持つ専用の事務所を設けること
- 訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えること
新規立ち上げ時の具体的な確認点
指定訪問看護の新規申請を行う際に、よく設備基準について確認される点についても解説します。
事務室

訪問看護ステーションの事務所は以下の2つのいずれかを満たすことが必要です。
- 運営に必要な広さを有する専用の事務室を設けていること
- 他の事業の事務所と兼ねる場合、必要な黒さの専用の区画を有し区画が明確であること
相談スペース
相談スペースについては以下の2点を満たす必要があります。
- 新規申し込みの受付や相談を行えるスペースを事業所内に設けること
- パーテーションなどによって個人情報保護の観点に配慮すること
手指洗浄場所の設定

同一敷地内にある他の事業所・施設と併用する場合は、以下の2点を満たすことが必要です。
- 定期的な清掃・消毒などの感染予防を取ること
- 他事業所・施設と供用の状況を確認し適切にしようすること
※不特定多数が利用する場合は不可のことが多い。
電話の設置
携帯電話ですが、業務でFAXを使用するため、事務所の固定電話は基本的に必須です。
介護事業以外の他の事業所や施設等との共用は、秘密保持の観点で不可の場合が多いため注意しましょう。
個人情報保護のための設備
以下の設備を設けるようにしましょう。
- 鍵付き書庫(書類などの格納)
- パソコンのセキュリティー対策
訪問看護ステーションの「設備基準」に関する指摘事例
訪問看護の設備基準等は、新規開設時に写真や現地調査などがあるため、運用のおける指摘事例はほとんどありません。
しかし、開設時に申請していた内容と実際の事業所の使い方が異なる場合は、指導の対象となることがありますのでご注意ください。
▼これから事業所を立ち上げる方は、ぜひ以下の記事も参考にしてください。
『訪問看護ステーションを立ち上げるには?開設に必要な手続き・準備を初心者向けに徹底解説』

訪問看護ステーションの「運営に関する基準」とは?
訪問看護の運営に関する基準は『指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について』の第63条から第73条(準用を除く)によって定められています。
サービス提供困難時の対応
訪問看護事業者は利用者の病状や対応エリアなどを鑑みてサービス提供が行えない場合、医師や居宅介護支援事業者に連絡を行う必要があります。また、他社の訪問看護事業所を紹介するなどの対応を講じなければならないことが定められています。
居宅介護支援事業者等との連携
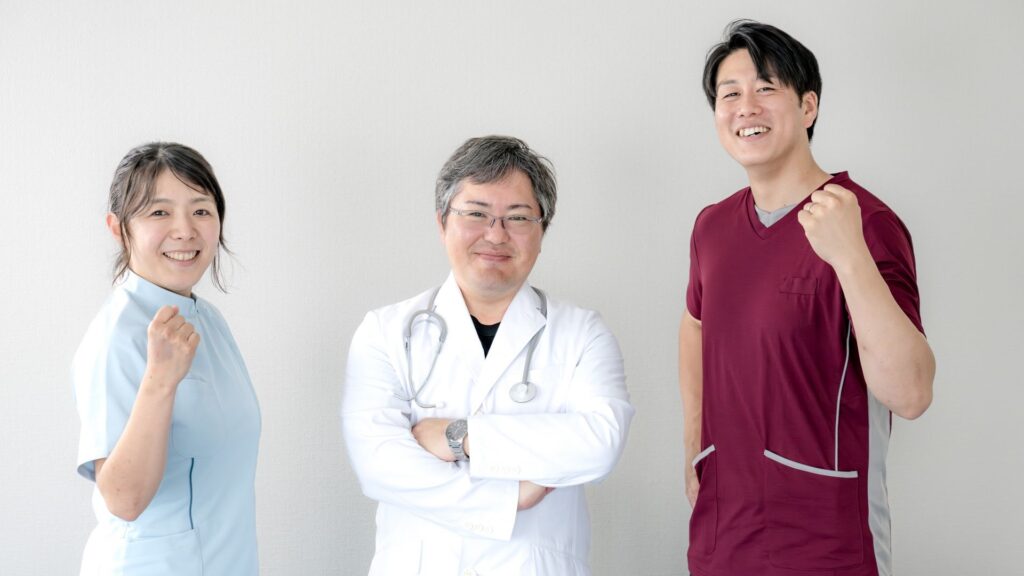
訪問看護事業者は、居宅介護支援事業者と密接な連携をしなければならないことが定められています。また、サービス終了時には、利用者やその家族に対して適切な指導を行い、医師や居宅介護支援事業者に情報提供などの連携を行うことが定められています。
利用料等の受領
訪問看護事業者は、訪問看護を提供した利用者から利用料(自己負担分)を受領することが定められています。また、通常の事業実施の地域以外にて訪問看護を行う場合には、それに要した交通費の支払いを受けることができる旨も記載されています。
指定訪問看護の基本取扱方針
訪問看護は、利用者の要介護状況の軽減や悪化防止に向けて目標設定を行い、計画的に実施しなければなりません。また自ら質の評価を行い、その改善を図らなければならない旨も定められています。
指定訪問看護の具体的取扱方針
訪問看護の提供にあたり、以下が定められています。
- 主治医との連携・訪問看護計画書に基づき、利用者の心身機能の維持回復のため適切に行うこと
- 利用者や家族に対し、療養上必要な事項を理解しやすいように説明すること
- 緊急やむを得ない場合の除き、身体拘束等を行ってはならないこと
- 身体拘束等を行う場合は、方法・時間・心身の状況・やむを得ない理由を記録すること
主治医との関係

訪問看護事業所の管理者は、主治医の指示に基づき適切な訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければなりません。
また、サービス提供にあたっては主治医による指示を文書で受け(訪問看護指示書等)、主治医に訪問看護計画書・訪問看護報告書を提出して連携を行わなればならない旨なども定められています。
訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成

看護師は、利用者の希望、主治医の指示および心身の状況を踏まえ、療養上の目標や具体的なサービス内容を記載した訪問看護計画書を作成しなければならないことが定められています。
また、以下についても定められています。
- 居宅サービス計画等が作成されている場合は、その内容に沿って作成すること
- 主要な事項は利用者や家族に説明し同意を得ること
- 利用者に交付すること
- 訪問日、提供した看護内容等を記録した訪問看護報告書を作成しなければならないこと
- 管理者は訪問看護計画書や訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導や管理を行なうこと
同居家族に対する訪問看護の禁止
看護師等が、その同居家族である利用者に対して訪問看護を提供してはならないことが定められています。
緊急時等の対応
看護師等は、訪問看護を提供している時に李商社の病状に急変等が生じた場合、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医への連絡を行い指示を求めるなどの必要な措置を講じなければならないことが定められています。
運営規程
訪問看護事業者は、事業所ごとに次に掲げる事業所の運営に関する規定を定めておかなければならないことが定められています。
- 事業の目的と運営方針
- 従事者の職種、員数及び職務の内容
- 営業日および営業時間
- 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の金額
- 通常の訪問エリア
- 緊急時等における対応方法
- 虐待の防止のための措置に関する事項
- その他運営に関する重要事項
記録の整備
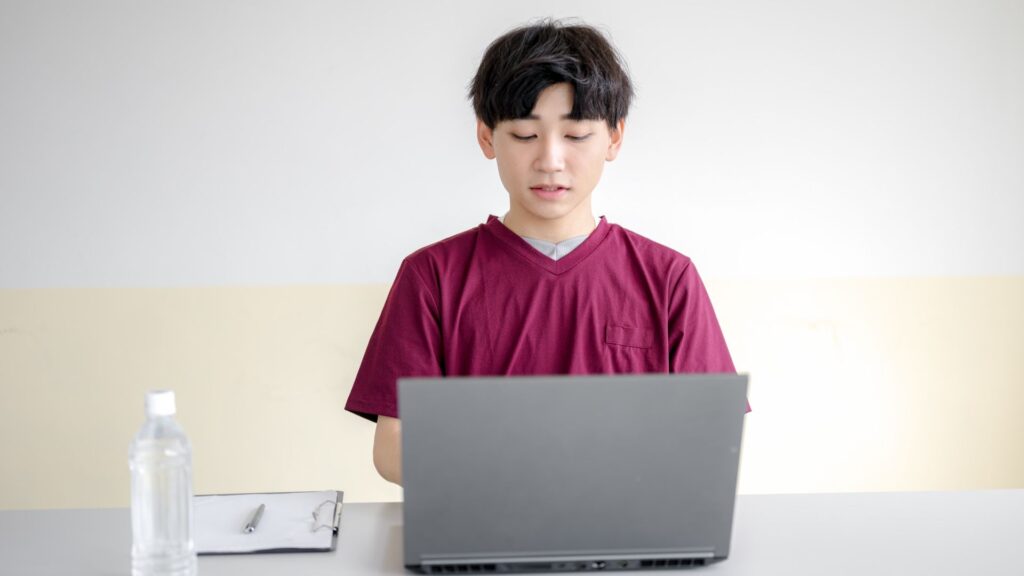
訪問看護事業者は、従事者・設備・備品および会計に関する記録を整備しておかねばならず、その完結日から2年間補完しなければならないことが定められています。
- 主治医による指示の文書
- 訪問看護計画書
- 訪問看護報告書
- 提供したサービス内容等の記録
- 身体拘束等の態様及び時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由の記録
- 市町村への通知に係る記録
- 苦情の内容等の記録
- 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
内容及び手続の説明及び同意
訪問看護事業者は、訪問看護サービスの提供の開始に際し、あらかじめ利用者・家族に対して運営規定の概要など重要事項について文書を交付して説明し、同意を得る必要があることが定められています。
また、文書の交付を電磁的方法にて行ってもよいことが定められています。
提供拒否の禁止
正当な理由なく指定訪問看護の提供を拒んではならないことが定められています。
受給資格等の確認
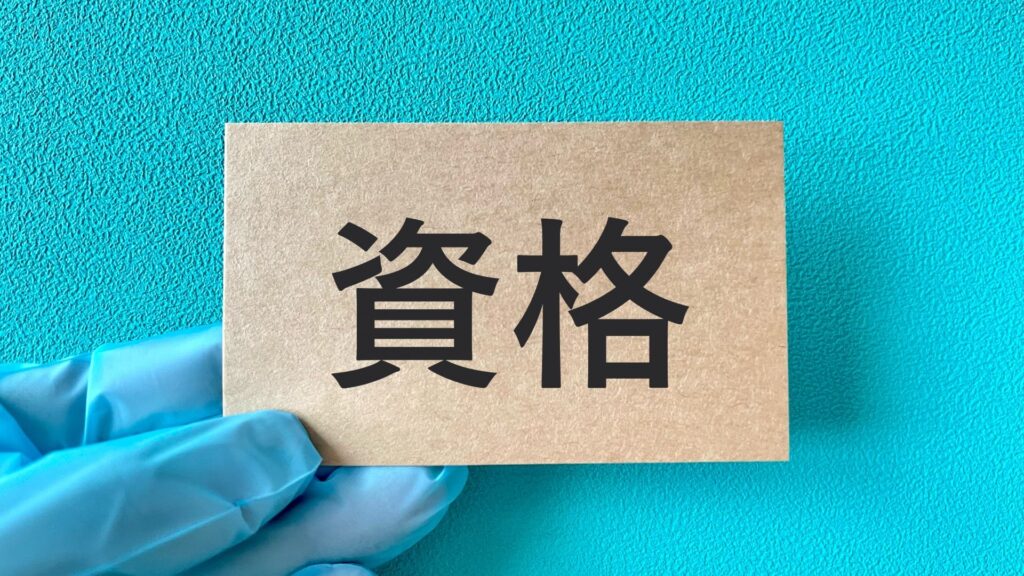
訪問看護事業者は、訪問看護の提供を求められた場合は、被保険者証で被保険者資格、要介護認定の有無・要介護認定の有効期間を確かめることが定められています。
また、被保険者証に認定審査会意見の記載がある場合は、それに配慮してサービスの提供を務めなければなりません。
要介護認定の申請に係る援助
訪問看護事業者は、訪問看護の提供開始の際に、要介護認定を受けていない場合は、申請が既に行われているかを確認する必要があります。
また、申請が行われていない場合、利用者の意志を踏まえて速やかに申請が行われるように援助することが定められています。
心身の状況等の把握
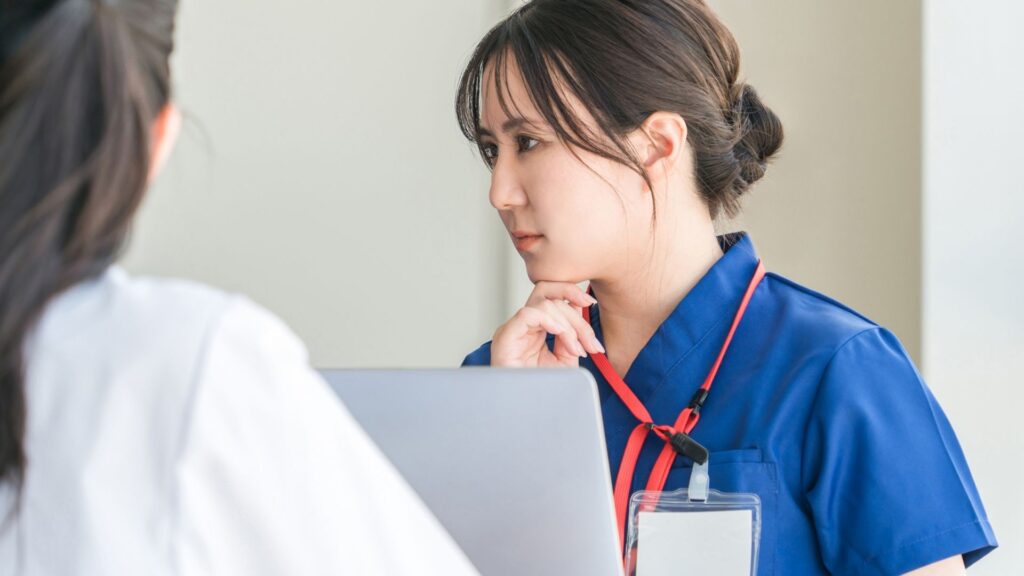
訪問看護事業者は、訪問看護の提供にあたって居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議を通じて、以下の把握に努める必要があります。
- 利用者の心身の状況
- 病歴やおかれている環境
- 他の保健医療サービス・福祉サービスの利用状況
法定代理受領サービスの提供を受けるための援助
訪問看護事業者は、必要な利用者に対し法定代理受領サービスを受けることができる旨を説明し、援助を行わなければならないことが定められています。
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供
訪問看護事業者は、居宅サービス計画に沿ったサービス提供をしなければならないことが定められています。
居宅サービス計画等の変更の援助
利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、居宅介護支援事業者への連絡や必要な援助を行わなければならないことが定められています。
身分を証する書類の携行
訪問看護事業者は、従業員に身分を証する書類を携行させて、初回訪問時や求められたときに提示すべき旨を指導しなければならないと定められています。
サービスの提供の記録

訪問看護を提供した際には、訪問看護の提供日・サービス提供内容・居宅サービス費の額等を利用者の居宅サービス計画書に記載しなければならないと定められています。
また、利用者や家族から申し出があった場合には、その情報を文書などにより提供しなければならない旨も定められています。
保険給付の請求のための証明書の交付
法定代理受領サービスに該当しない訪問看護に係る利用料の支払いを受けた場合には、提供したサービス内容、費用の額その他必要な事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならないと定められています。
利用者に関する市町村への通知
訪問看護事業者は、以下の場合に遅れることなく意見を添えて市町村にその旨を通知しなければならないと定められています。
- 正当な理由なしに訪問看護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められる時
- 偽りやその他不正な行為によって保険給付を受けたり、受けようとしている時
勤務体制の確保等
利用者に対し適切な訪問看護を提供できるよう、事業所ごとに従業員の勤務体制を定めておかねばならないことが明記されています。
また事業所ごとに所属している職員によってサービスを提供すること、従業員の資質の向上のために研修の機会を確保すること、職場での各種ハラスメント等の防止のための処置を講じなければならないことも定められています。
業務継続計画の策定等
感染症や非常災害の発生時における訪問看護の提供継続のために「業務継続計画」を策定し、必要な措置を講じなければなりません。
また、従業員に周知するとともに、必要な研修・訓練を実施すること、定期的に見直しを行うことも定められています。
衛生管理等

従業員の清潔の保持・健康状態について必要な管理を行わなければならないことが定められています。また、以下についても定められています。
- 事業所設備や備品の衛生的管理に努めること
- 6か月に1回、感染防止に関する委員会を開催すること
- 指針を整備し、感染対策の研修を行うこと
掲示
見やすい場所に、運営規定の概評・勤務の体制・利用者のサービス選択に必要な重要事項を掲示しなければならないことが定められています。
秘密保持等

従業員は、正当な理由なく、その業務上知りえた利用者や家族の情報を漏らしてはならないことが定められています。
また、事業者は、従業員が秘密を漏らすことのないよう必要な措置を講じるとともに、サービス担当者会議等で個人情報を用いる場合は利用者や家族の同意をあらかじめ文書により得ておかねばならないことが定められています。
広告
広告を行う場合は、その内容が虚偽・誇大なものであってはならないことが定められています。
居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止
事業者は、居宅介護支援事業者やその従業員に、利用者に対して特定事業者のサービスを利用させることを代償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならないことが定められています。
苦情処理

事業者は、利用者や家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付ける窓口を設置するなどの措置を講じなければならないことが定められています。
また苦情を受け付けた場合には、その内容を記録し、市町村からの質問や紹介・調査に協力するとともに、必要な改善を行わなければならないことが定められています。
地域との連携等
事業者は、提供した訪問看護サービスに関する利用者からの苦情に関する市町村等による事業に協力するよう努めなければならないことが定められています。
また、事業所と同一建物に居住する利用者にサービス提供を行う場合には、同一建物に居住する利用者以外にもサービス提供を行うよう努めなければならないことも定められています。
事故発生時の対応
訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村・利用者の家族・利用者に係る居宅支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないことが定められています。
また、事故の状況や処置の記録、賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行わなければならないことも定められています。
虐待の防止
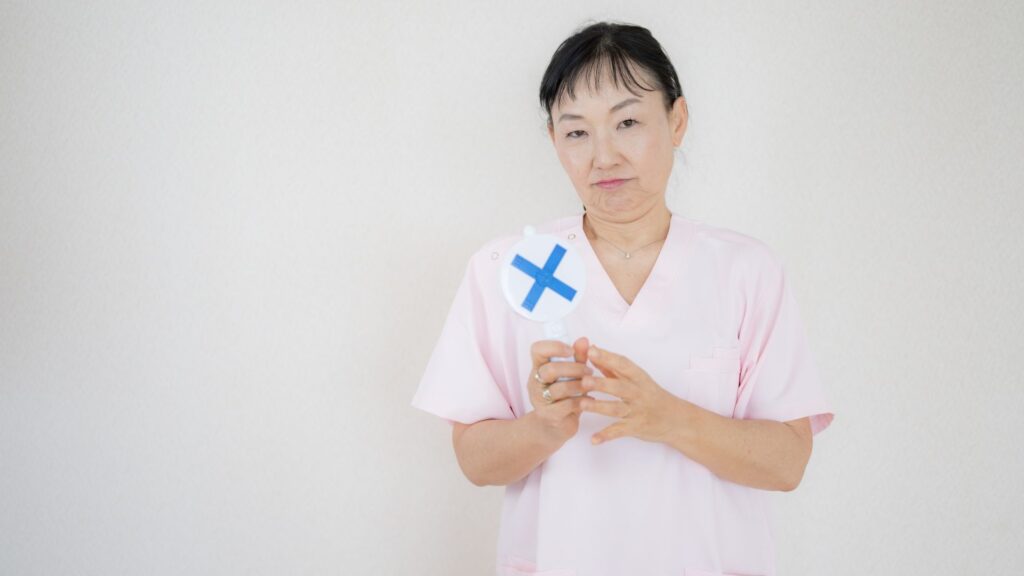
事業者は、虐待の発生や再発防止のために、委員会の定期開催と内容の周知、指針の整備、定期的な研修開催、担当者の配置を行わなければならないことが定められています。
会計の区分
事業者は、訪問看護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問看護事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならないことが定められています。
管理者の責務
事業所の管理者は、従業員の管理や利用申し込みに係る調整・業務の実施状況の把握・その他の管理を一元的に行うものとすることが定められています。
また従業員に、規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うことも定められています。

訪問看護ステーションの運営基準に関する指摘事例
これらの基準は法令で定められたもののため、正しく実施しないと行政からの指導を受けたり、悪質な場合は行政処分を受ける可能性があります。
ここでは、実際にあった訪問看護ステーションの「運営基準」に関する指摘事例をご紹介します。
| 勤務体制の確保等 | ・職員の雇用の事実が不明瞭(雇入れ通知書を整備していない) ・常勤換算を行うに当たって必要な労働条件が不明瞭 - 常勤の賞金が勤務すべき時間数を、修行規則等に明確に規定していない - 個々の職員の勤務時間が不明瞭 ・作成した勤務表が不適切 |
| 管理者 | ・管理者とされたものが非常勤であった |
| 運営規定 | ・通常の事業の実施地域について、客観的に特定できない規定をしている ・指定訪問看護のサービスと明確に区分されている介護保険外サービス利用料等について、指定訪問看護の運営規程で規定している ・利用料その他の費用の額を、運営規程に規定していない |
| 利用料等の受領及び領収書 | ・通常の事業の実施地域内において、交通費を徴収していた ・通常の事業の実施地域内において、夜間緊急訪問に要した交通費を徴収していた |
| 主治の医師との関係 | ・サービス提供開始後に、主治医からの指示書の交付を受けていた ・主治医からの指示を文書で受けることなく、訪問看護を行っていた ・訪問看護の内容が主治医の指示書の内容と相違している |
| 訪問看護計画及び訪問看護報告の作成 | ・訪問看護計画書を作成せずに訪問看護を行っている ・訪問看護計画書が、居宅サービス計画の内容と相違している ・訪問看護計画書の内容が不十分である |
| 秘密保持等 | ・従業者の守秘義務についての取り決めを徹底していない ・個人情報の使用に関する同意を明確にしていない(利用者の個人情報の同意(利用者が同意)と家族の個人情報の同意(当該家族が同意)を区別していない |
| 苦情処理 | ・事業所への苦情対応の措置を、利用者に明確に周知していない(重要事項説明書の事業所の苦情相談窓口を記載していない等) ・外部機関(保険者、国保連)の苦情相談窓口を記載していない |
| 事故発生時の対応 | ・事故の状況、事故に際して講じた処置について記録していないため、事故の詳細・事故発生時の事業所の対応・再発防止策等が不明確 ・事故発生に係る報告を、保険者に対して行っていない |
| 記録の整備 | ・当該利用者の契約終了の日から2年間保存していなかった |
UPDATEの【訪問看護管理者研修】基礎から学ぶ組織マネジメント講座では、さらに現場の課題を掘り下げ、解説しています。現場の悩みを直接相談できたり、他の管理者の方と交流したりしながら、訪問看護のマネジメントについて詳しく学べます。
一人で悩みを抱え込まず、持続可能なステーション運営を一緒に目指しましょう。
「しっかり組織マネジメントの基礎を学びたい!」という方向けに、【訪問看護管理者研修】基礎から学ぶ組織マネジメント講座を開催しています。
今なら無料の体験クラス動画や特別プレゼントもご用意しています。
あなたもぜひお受け取りください。
まとめ:法令を守って適切な運営を!経験者と伴走し失敗を回避しよう!

訪問看護ステーションの開設基準は、法令として厚生労働省が定めている重要な決まり事です。事業所を立ち上げる方や運営中の方はしっかり遵守しましょう。
特に法令は文章の読み解きが難解で、分量も多く理解しきれないまま訪問看護ステーションを立ち上げてしまうこともあるでしょう。実は法令に違反しており、行政から指摘をされるというケースも少なくありません。
このような事態を防ぐには、一人で解決しようとせず、訪問看護ステーションの立ち上げ経験者に頼るのがおすすめです。私たちUPDATEでは、訪問看護の現場・管理・経営を10年以上経験した代表小瀬が、訪問看護ステーションの立上げ支援をしております。
また、【訪問看護管理者研修】基礎から学ぶ組織マネジメント講座では、訪問看護管理者としてのマネジメントを体系的に学べます。少人数制のクラスでは、現場でのリアルな悩みをその場で質問し、解決できます。
実際に受講した方からは、
「モヤっとする現場の悩みを解決できた」
「組織の適切な配置や役職採用での注意点がわかった」
「メンバーへのフィードバック方法や関わり方がわかった」
などのお声も多数!
受講者満足度は94.6%と、高評価をいただいています。
尽きない課題を一つひとつ解決させ、人材が定着する事業所を育てたいと願う管理者の方へ。
ぜひ無料体験講座をご覧ください。今なら特別プレゼントもお配りしていますので、この機会をお見逃しなく!

<参考文献>