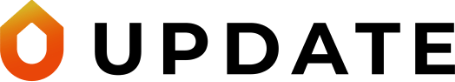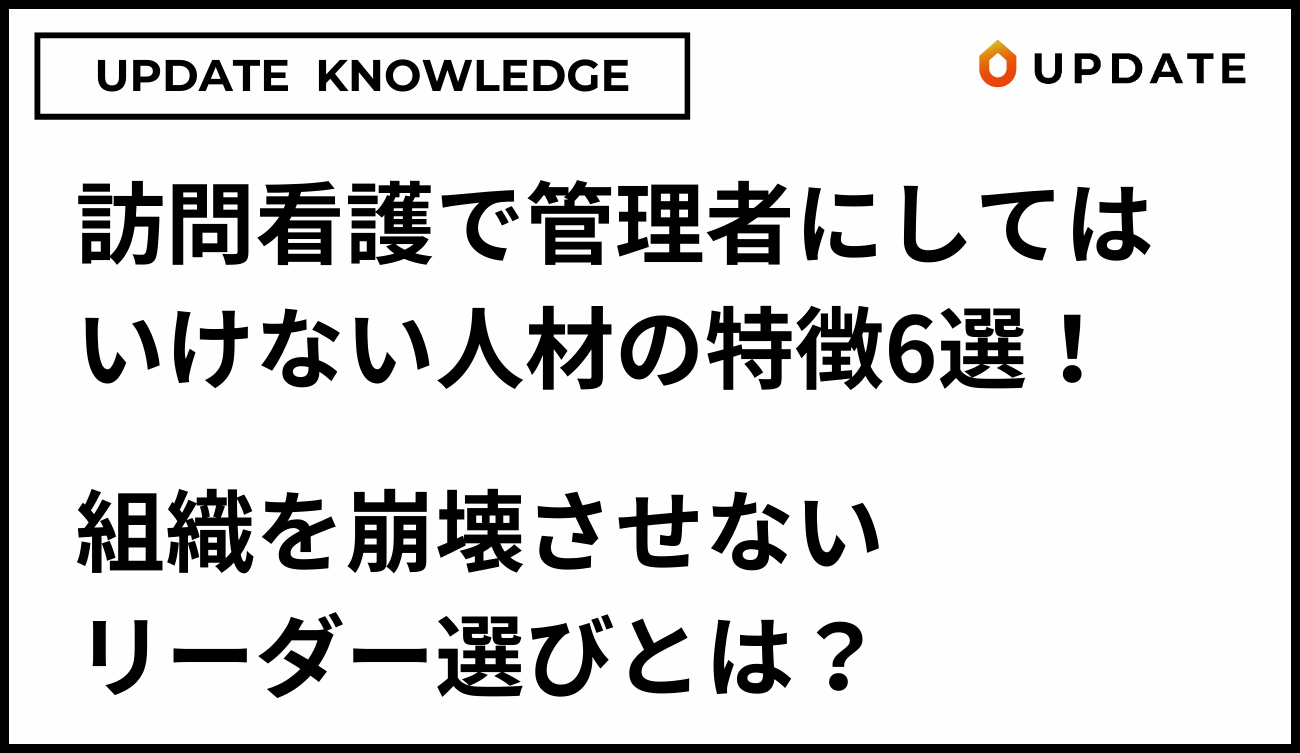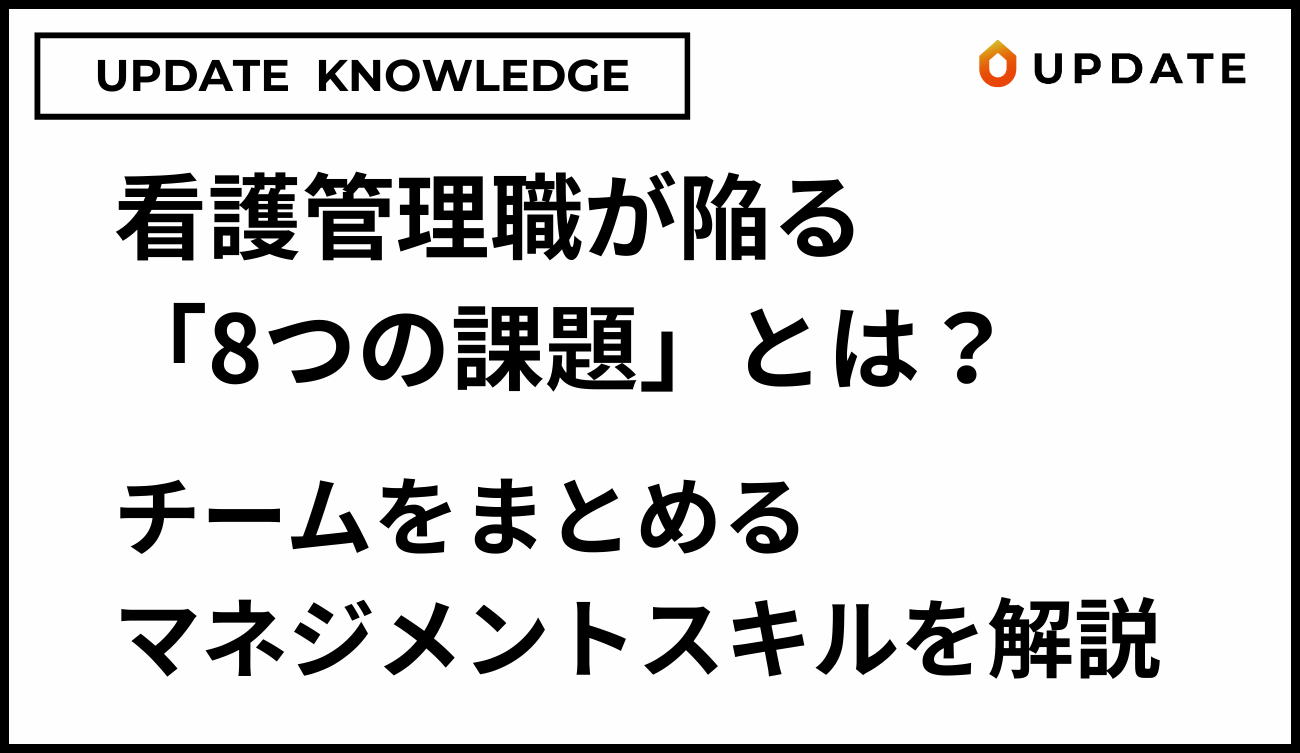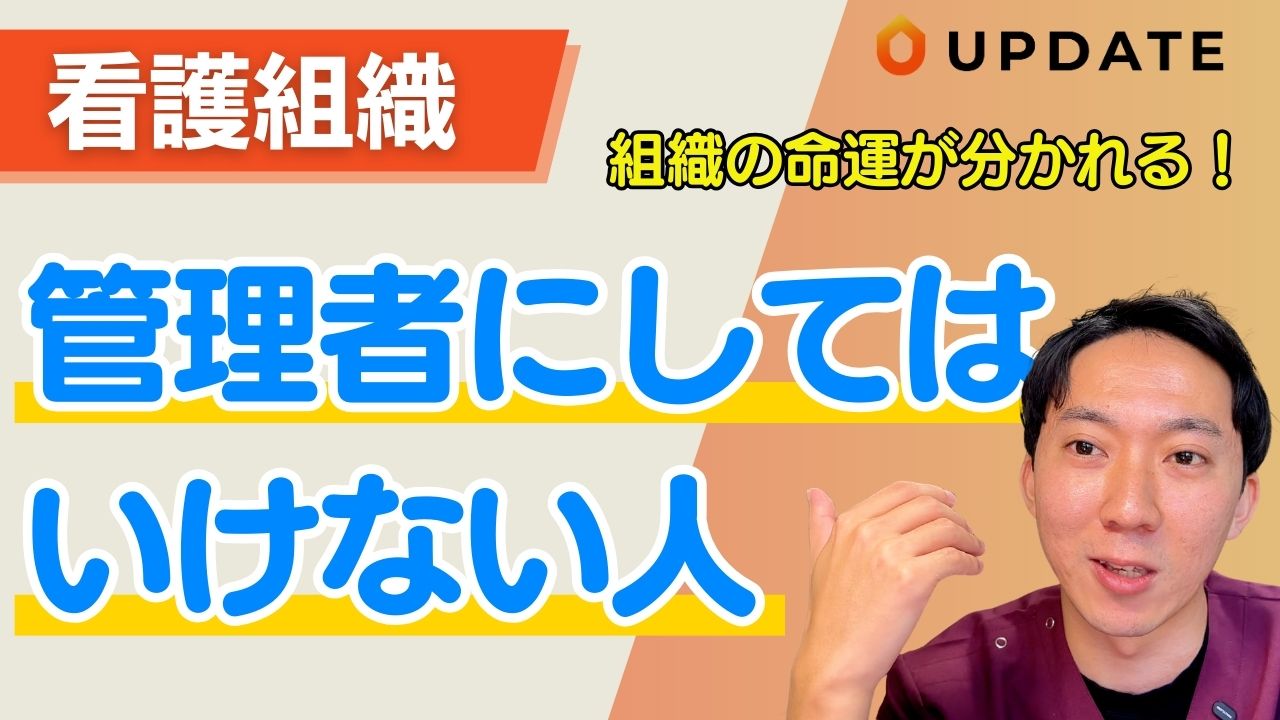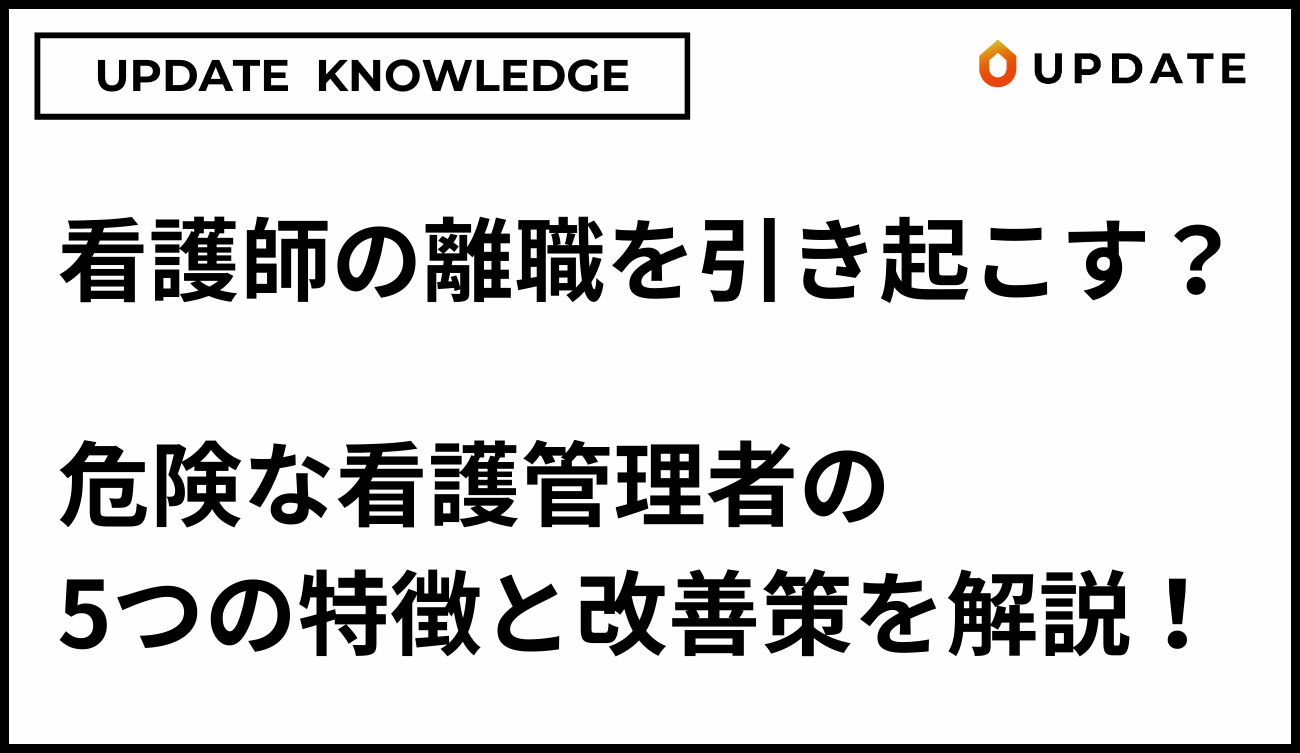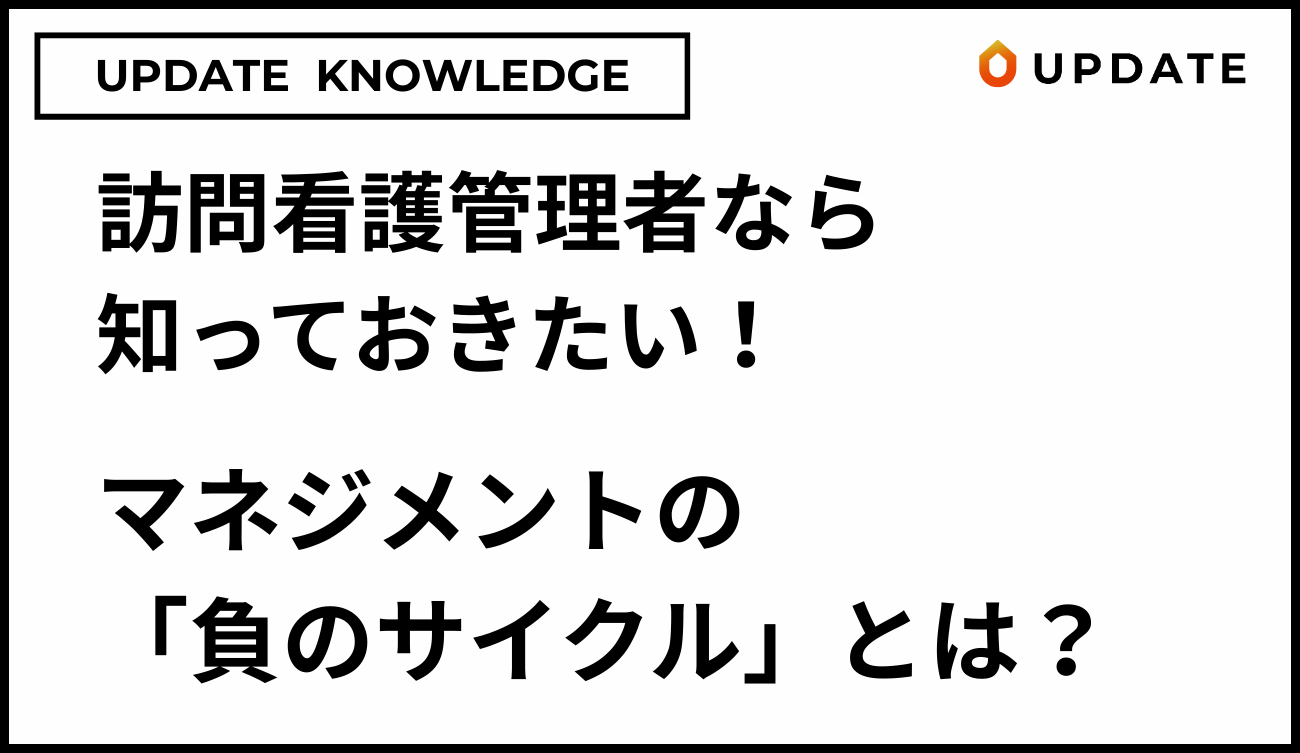新人訪問看護師の「つまずき5選」転職後の悩みを解決するヒントを徹底解説!
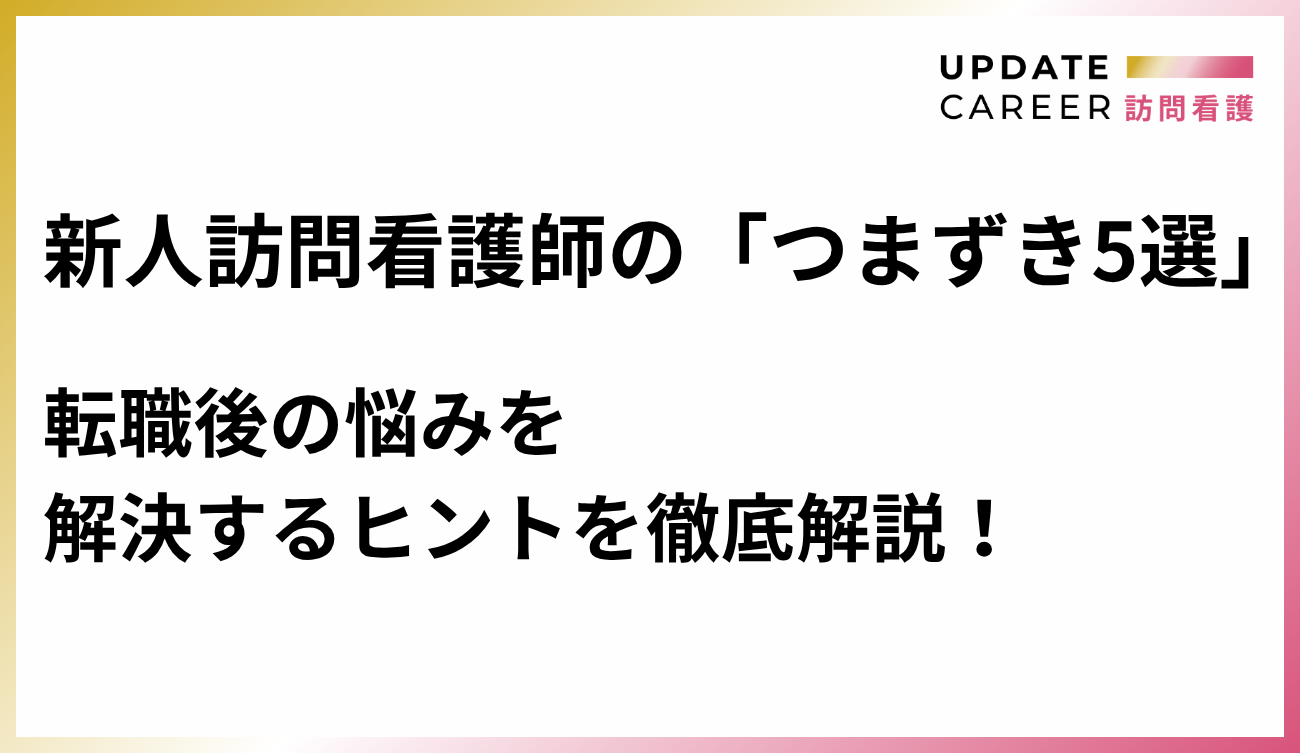
病院から訪問看護へ転職したものの、
「ギャップがあって、なかなか慣れない」
「半年経っても、まだ一人で訪問するのが不安」
「利用者さんからの拒否を受けて、自信がなくなった」
などの悩みを抱えていませんか?
訪問看護の現場は利用者さんの暮らしの中にあるため、病棟とは前提がまったく異なります。特に最初の半年は、自分の看護に自信が持てず、つまずきやすい時期といえるでしょう。
本記事では、そんな新人訪問看護師が特につまずきやすい5つのポイントを整理します。
また、あなたの心を軽くするためのヒントを、具体例を交えてわかりやすくご紹介します。
訪問看護師として自信を持って働きたい方や、もっと成長したい方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
新人訪問看護師のつまずきポイント5選とは?

病院から訪問看護に転職して半年ほどは、病院との違いに戸惑い、壁にぶつかりやすい時期といえます。
新人訪問看護師が特につまずきやすいポイントは、以下の5つです。
- 情報がない問題:検査値・情報がそろっておらず、判断に迷う
- 拒否をされる問題:利用者さんとの距離感がつかめない
- 関係者との連携トラブル:他職種(ケアマネ・ヘルパーなど)連携に慣れていない
- 処置屋止まり問題:利用者さんの生活全体を支える視点が身につかない
- 看護業務だけをやりたい問題:訪問以外の調整業務にやる気がでない
上記の5つは、多くの新人訪問看護師が通る成長のプロセスです。
この記事では、5つのつまずきポイントを打開するために必要な、視点を変えるヒントを紹介します。
考え方を少し変えるだけで、悩みは驚くほど軽くなり、訪問看護師としての力がぐっと伸びていくでしょう。
悩みや不安な気持ちがあるときは、一人で抱えるより、頼れる人に話してみることが大切です。
UPDATEでは、訪問看護を12年以上行ってきたスタッフが、あなたの不安やお悩みをお伺いします。現場で抱える問題を解決し、あなたらしく輝けるようサポートします。
現時点では転職を検討していなくても、無料で利用できます。
「まずは聞いてほしい」という方も大歓迎ですので、以下のバナーよりお気軽にご相談ください。

新人訪問看護師のつまずき① 情報がない問題

検査値や記録がそろっている病棟とは異なるため、訪問看護に慣れるまでは不安を感じやすい傾向があります。
訪問看護の場合、情報が少ない状態から観察を始めることを理解しましょう。
新人訪問看護師はなぜ戸惑うのか?
新人が情報不足に戸惑うのは、病棟と訪問看護で判断材料の前提がまったく違うためです。病棟ではカルテや検査値が揃っており、そこから状態を把握できます。
しかし訪問先では、生活環境の中から必要な情報を自分で拾い上げる必要があります。このギャップが、「何を基準に判断すればよいのか分からない」という不安につながる場合があります。
特に新人訪問看護師は、訪問時に何から見ればよいのか迷ったり、検査データのない状態でアセスメントすることに抵抗を感じたりするでしょう。
これは能力の問題ではなく、生活を評価する経験がまだ少ないだけです。誰もが通る自然なプロセスとして捉えましょう。
視点を変えるヒント:生活の変化に気づく
情報が少ない状況は不安の原因ではなく、生活の変化への洞察力を育てる場と捉えることが大切です。
訪問看護では、数値よりも昨日との違いや普段のズレを見つけることがアセスメントの中心になります。新人のうちからこの視点を意識しておくと、訪問看護師としての基礎力が着実に身に付けられるでしょう。
たとえば、いつもなら玄関まで迎えに来てくれる利用者さんが今日は来ない、表情が曇っているなど、生活の小さな変化が体調悪化のサインになることがあります。
いつもと違う動作や表情に気づき、異変を察知できると、病棟とは違う深さのアセスメントができるようになります。
新人訪問看護師のつまずき② 拒否される問題

訪問看護に慣れていない新人ほど、利用者さんから「訪問を拒否されてしまう」「距離を置かれてしまう」と悩む傾向があります。
これは看護師として正しいことをしたいという思いが強いほど起こりやすい現象です。
なぜ利用者さんから拒否されるのか?
拒否が起こる背景には、病棟と訪問看護の関わり方の前提の違いがあります。
訪問では利用者さんの生活の場に入るため、看護師の言動が、相手にとっては生活に踏み込みすぎていると思われる恐れがあります。
たとえば、食事制限を厳しく伝えてしまう、家の物を断りなく使ってしまい元に戻さないなどが挙げられます。
特に新人訪問看護師ほど、「正しい看護をしなければ」と思う気持ちが強く、意図せず利用者さんの生活リズムを乱してしまう点に注意が必要です。
視点を変えるヒント:関わり方を見直す機会と捉える
利用者さんから拒否されてしまった時は、関わり方を見直すチャンスと捉えると気持ちが軽くなります。訪問看護では、医療的に正しいことよりも、生活に寄り添う姿勢の方が関係を築きやすいでしょう。
たとえば、食事制限を一方的に伝えるより、無理なく続けられる方法を一緒に考えてみるのはいかがでしょうか?また、家の物に触れるときは必ず一声かけ、きちんと元の場所に戻すなど、細やかな配慮が安心感を生みます。
相手の価値観に目を向けると、拒否の理由が見えやすくなります。利用者さんの生活リズムに合わせる姿勢を意識するだけで関係性は変わり始めるでしょう。
「まずは悩みを聞いてほしい」「転職は検討していないけど、話だけ聞いてみたい」というあなたへ。UPDATEキャリアでは、訪問看護経験のある看護師に、無料で何度でも相談できます。ぜひ今すぐ、お気軽にご連絡ください。
新人訪問看護師のつまずき③ 関係者に嫌われる問題
多くの新人訪問看護師が戸惑うのが、ケアマネさんやヘルパーさんとうまく関係が築けないという問題です。
訪問看護は多職種との連携が欠かせません。コミュニケーションをとる際の言葉選びや伝え方によって、印象が大きく変わります。
病棟とは違い、自分がいない時間のケアをどう支えるかという視点が求められるため、最初はギャップに悩むのも当然です。
なぜ関係者間でのトラブルが起こるのか?
多職種連携の壁が生まれる背景には、専門職ごとに前提が違うという構造があります。
病棟では看護師同士で価値観が似ていますが、訪問看護ではケアマネ・ヘルパー・リハビリスタッフなど、それぞれが異なる視点で利用者さんを支えています。
この違いを理解しないまま関わると、押しつけがましくなったり、距離を置かれたりすることがあります。
たとえば、短いノート記録だけでは相手に意図が伝わらず、連携が途切れてしまうことがあります。また、看護師目線の『こうするべき』をそのまま伝えると、ケアマネ側からは非現実的と捉えられるケースもあります。
トラブルは、前提のズレから起こることがほとんどです。まずは立場による視点の違いに気づくことが、関係改善の一助となるでしょう。
視点を変えるヒント:情報共有方法を工夫する
多職種との関係づくりのコツは、自分が見ていない時間を想像しながら情報を共有することです。
訪問看護は一日に訪問できる回数が限られており、家でのほとんどの時間を支えるのは家族やヘルパーさん、そしてケアマネさんの調整です。
この前提を理解したうえで連携すると、情報の伝え方が変わってくるでしょう。
たとえば、連絡ノートに短く書くだけでは伝わらない場合、張り紙やチェックリストなどの視覚的に伝わる工夫を加えると共有の精度が上がります。また、専門用語は必ず補足し、相手にとってわかりやすく、やる気が高まる表現で伝えることが有効です。
また、他職種スタッフと直接対面で話せるタイミングを大切にすると、お互いの考えがより伝わりやすくなるのでおすすめです。
「どう伝えれば相手が動きやすくなるか」を軸にすると、医療目線だけでは見えなかった課題が明確になるでしょう。
新人訪問看護師のつまずき④ 処置屋止まり問題

訪問看護に慣れないうちは、処置だけをして帰る仕事になりやすく、そこから成長が止まったように感じてしまうことがあります。
病棟では、担当患者の情報が常にそろっている環境ですが、訪問看護では次の訪問までの時間をどう支えるかの視点が欠かせません。
このギャップが埋まっていないと、訪問が単発の作業になり、やりがいも感じにくくなってしまいます。
なぜ訪問看護師としての成長が止まるのか?
処置中心の訪問になってしまう背景には、訪問看護で求められる役割の広さに気づきにくいことが挙げられます。新人ほど、いかにミスなく処置を終えられるかに気を取られて、生活全体を支える視点が抜けやすくなります。
たとえば、処置は問題なく完了したのに、次の訪問で状態が悪化していたという経験をしたことはありませんか?これは、多くの新人訪問看護師が通る道です。処置そのものが悪いのではなく、訪問後にどう生活が続いたかを見据える視点が十分でないために起こります。
視点を変えるヒント:ケアのバトンをつなぐ
処置屋止まりから抜け出す第一歩は、訪問看護は点ではなく、面で支える仕事という視点を持つことです。訪問が終わった瞬間から、次の訪問までの数日〜1週間をどうサポートするかが、訪問看護の本質ともいえます。
たとえば、次のような行動を意識してみましょう。
・ヘルパーに今日の変化や注意してほしいポイントを共有する
・家族に症状悪化のサインを一つだけ伝え、気づいたら連絡してもらう
・小さな変化があった場合、早めに管理者や医師へ相談しておく
上記のような『バトンをつなぐケア』が、利用者さんの生活を守るうえで欠かせません。
さらに、次回訪問までの7日間をイメージしながら申し送りを行うと、「いま必要な調整は何か」「どの職種に伝えるべきか」が見えやすくなるでしょう。
新人訪問看護師のつまずき⑤ 看護業務だけやりたい問題

訪問看護を始めてしばらくは、調整や事務作業が多く、看護の仕事に集中できないことに戸惑いを感じやすい傾向があります。
役割が明確な病棟では看護に専念しやすい一方で、訪問看護は小規模チームのため、看護以外の業務もチームを支える一部として求められます。
この認識のギャップが負担になり、モヤモヤを抱える原因になるのです。
狭い看護の定義に縛られてしまう原因とは?
新人訪問看護師が「看護だけをやりたい」と感じる背景には、病棟での役割分担が強く影響しています。
病棟では役割が細かく分かれ、看護師は看護に集中できる環境が整っています。
同じ感覚のまま訪問看護で働くと、調整や報告、電話対応などの業務を看護以外の仕事と捉えてしまいやすく、負担感につながります。
たとえば、訪問後にケアマネや家族へ共有し、必要に応じて医師に連絡するという流れについて考えてみましょう。病棟では、それぞれの担当が分かれている業務です。
慣れないうちは、「なぜ自分がこんなに調整役をするのか?」と疑問を抱きやすいのも無理はありません。
視点を変えるヒント:「調整」も看護の役割と考える
在宅医療の現場では、看護師だけで利用者さんを支えているわけではありません。看護の役割には、多職種の力をつなぎ、調整することが含まれます。
あなたが訪問以外の時間での調整・報告・共有をすることで、
・家族が安心して対応できる
・ヘルパーさんが悪化のサインに早く気付ける
・医師が次の診察で必要な判断材料を得られる
など、利用者さんとその家族の生活を守ることにつながるでしょう。
この視点を持てると、『看護ではない仕事』だと思っていた業務が、生活を支える看護として意味を持ち始めます。
訪問看護師の成長に必要な3つのマインドセット

訪問看護では、最初の半年間に多くのつまずきを経験しますが、これは誰もが通る成長プロセスです。
ここでは、その壁を乗り越えるために大切な3つの心得を紹介します。これらの視点を押さえれば、日々の訪問を通して成長を感じられるでしょう。
- つまずきを「成長のきっかけ」と捉える
- 一人で抱え込まず、チームや管理者に共有する
- 「何が違うのか」を言語化する
新人訪問看護師だからこそ見える違和感や気づきは、利用者さんを支えるうえで非常に大切なヒントになります。ぜひ今日からこれらのマインドセットを取り入れてみてください。
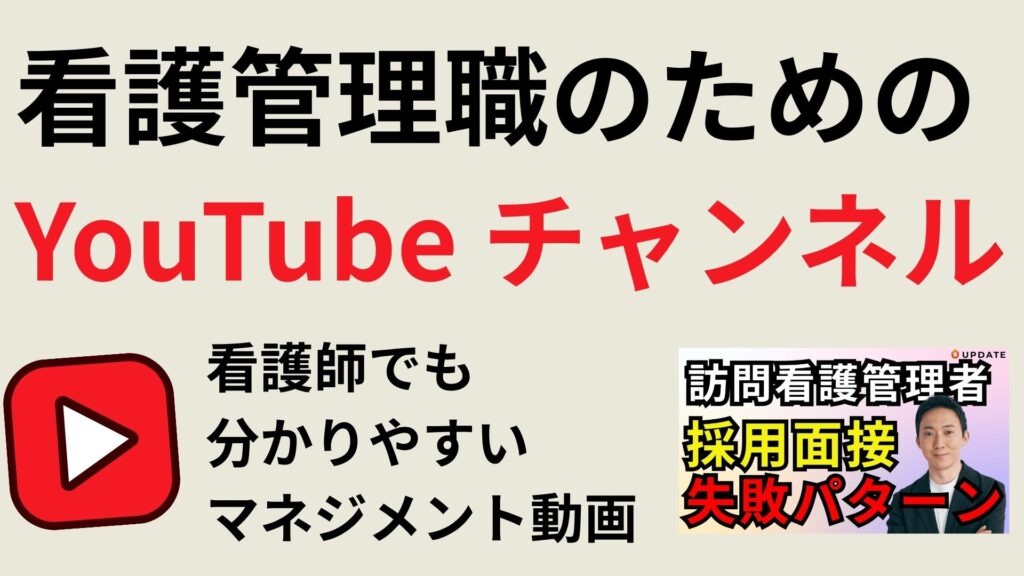
まとめ|つまずきの先に訪問看護師としての成長がある

訪問看護でつまずきを感じるのは、あなただけではありません。病棟とは環境も役割も大きく違うため、悩みや戸惑いが生まれるのは当然です。
今回紹介した5つの壁も、多くの新人訪問看護師が通る成長の入り口であり、経験を重ねることで乗り越えられます。
とはいえ、「自分の場合はどう解決したらいい?」「職場ではなかなか悩みを打ち明けにくい」などと、一人で悩むことも少なくないでしょう。
徐々に不安が大きくなり、「自分は訪問看護に向いていないのでは?」と感じてしまうこともあるかもしれません。
UPDATEでは、訪問看護の現場経験者が、そんなあなたのお悩みに寄り添います。
いつでも何度でも無料で相談できるので、あなたが自信を取り戻せるまで伴走します。ご希望に合わせて、あなたのキャリアや価値観に合ったステーション探しもサポート可能です。
「転職を決めているわけではないけれど、先が見えずモヤモヤする」
「相談できる人がいないので、悩みを聞いてほしい」
そんな気持ちで利用していただくこともできます。
ひとりで抱え込まず、ぜひ以下のリンクより、お気軽にご相談ください。
あなたのペースで、なりたい訪問看護師像を一緒に目指していけるよう、サポートします。