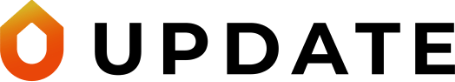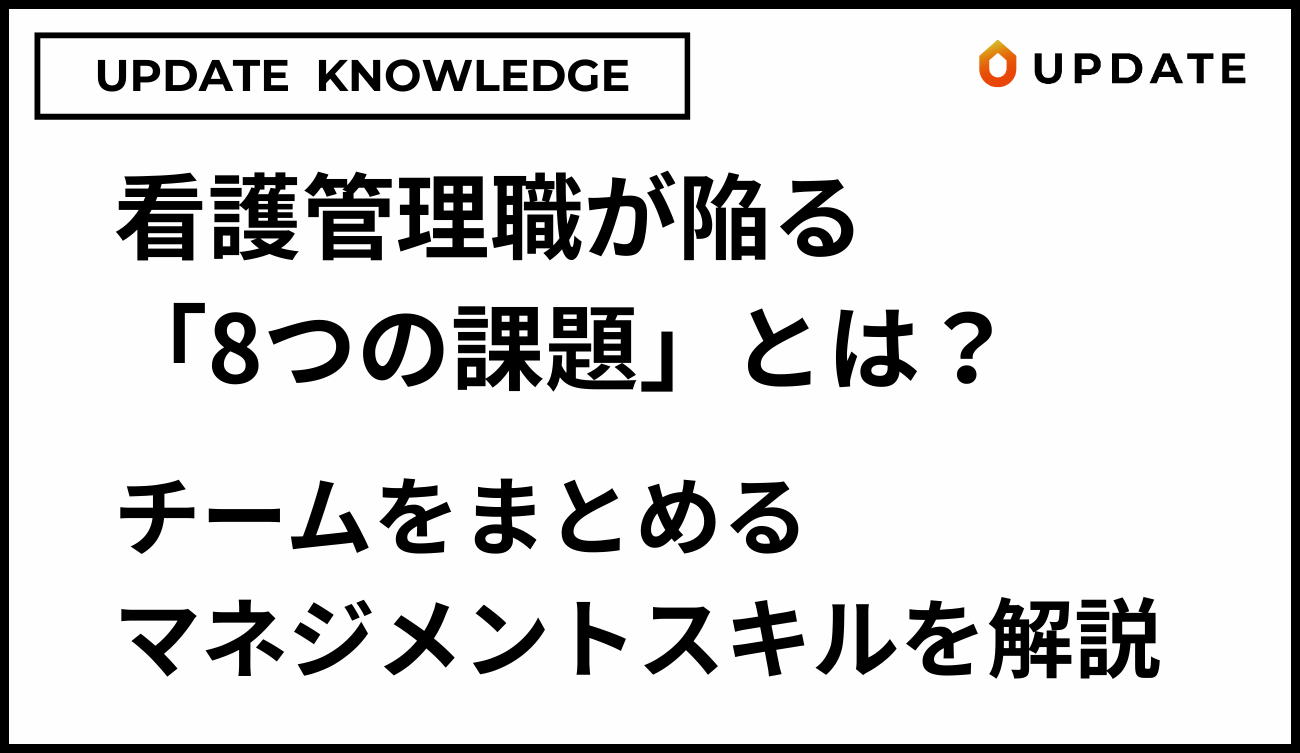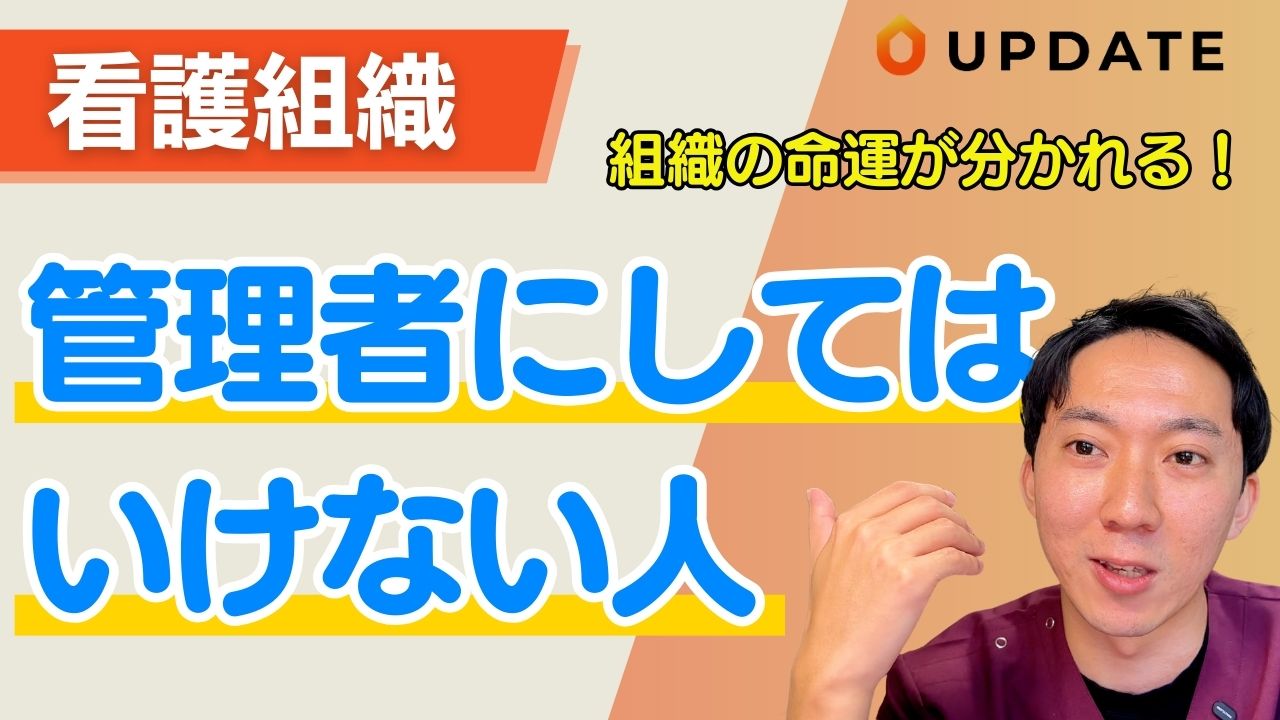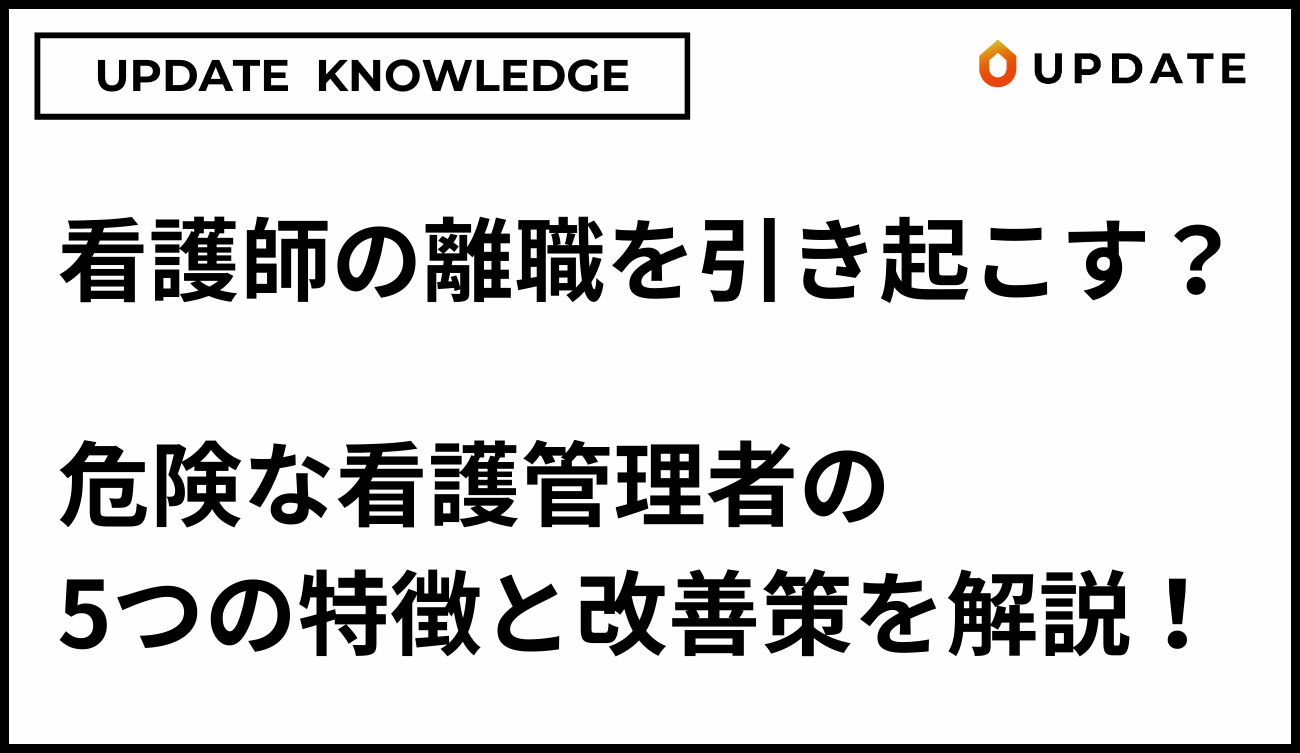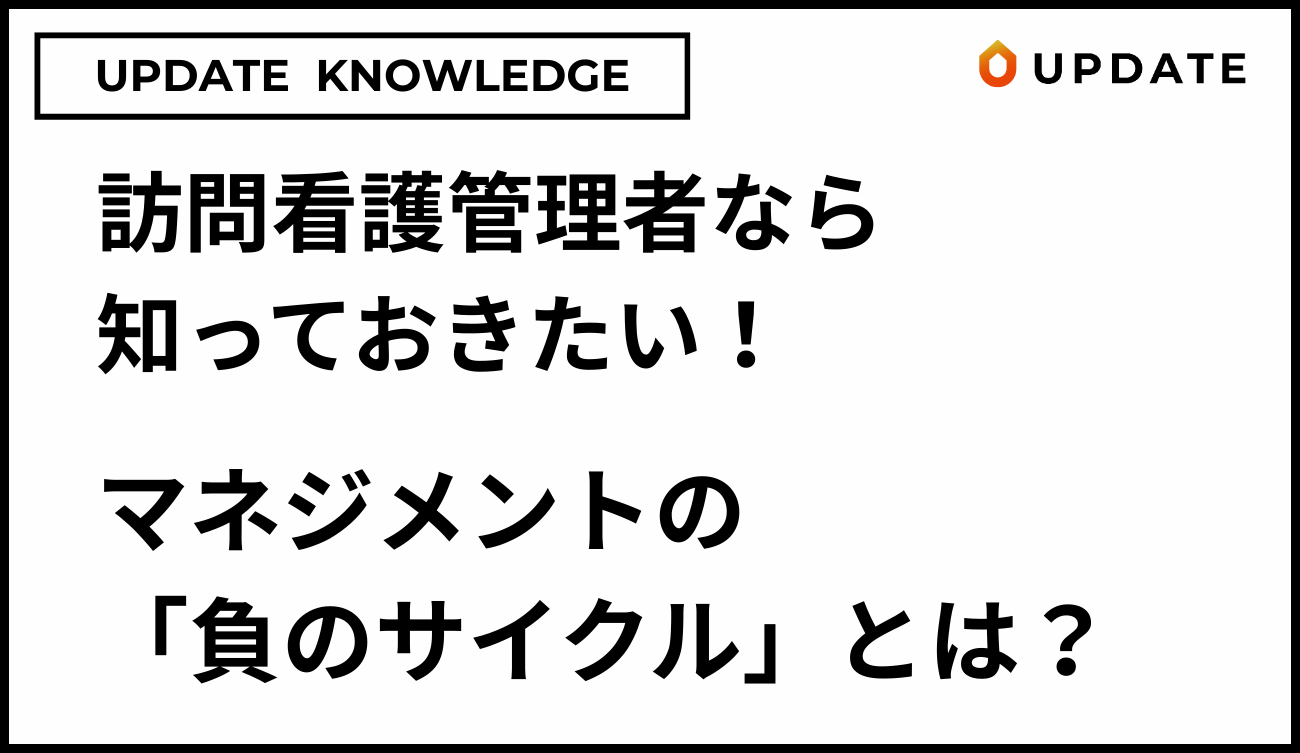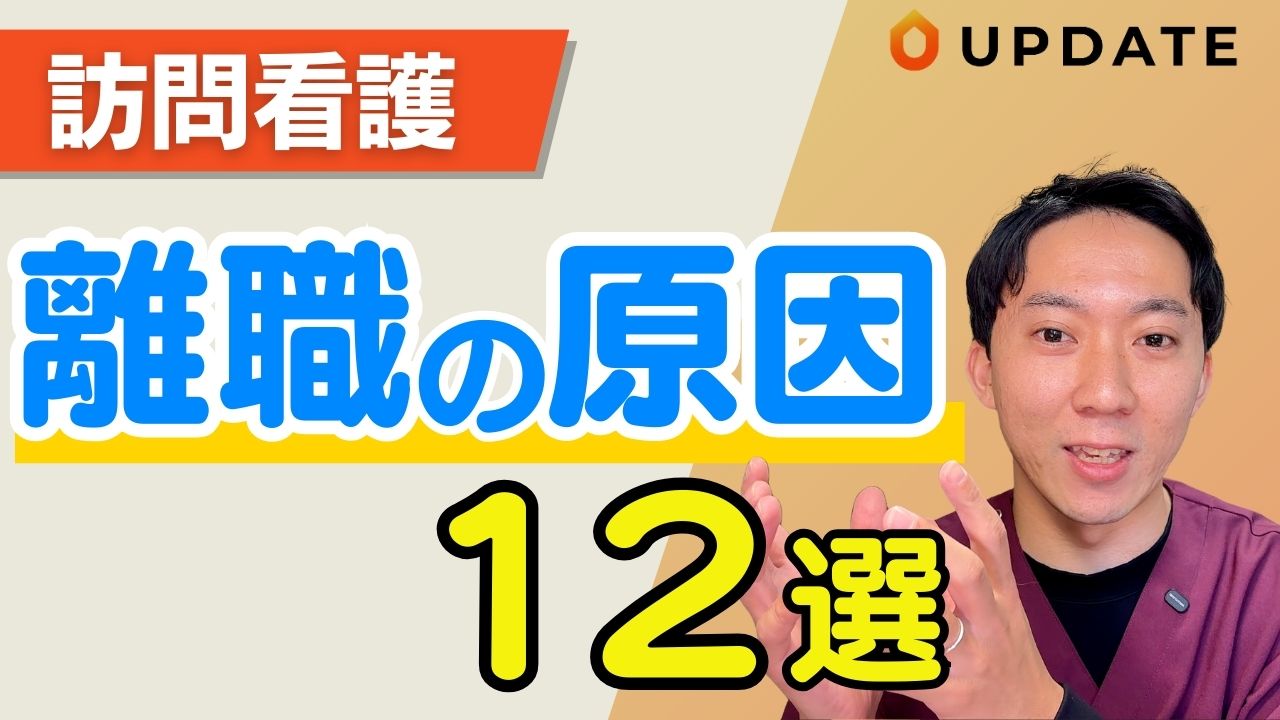【訪問看護の管理者必見】新人がつまずきやすい5つの壁と対応策を解説!
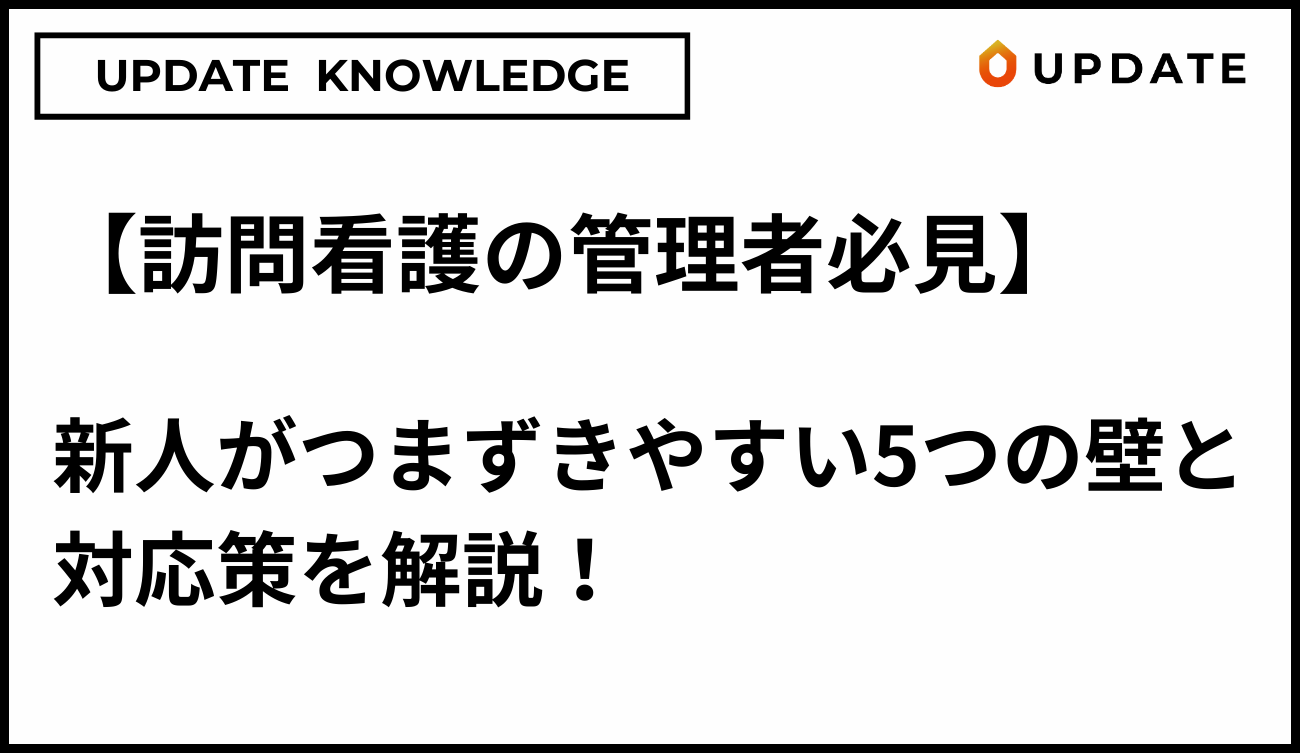
新人訪問看護師を受け入れたものの、
「病院とのギャップに戸惑い、なかなか現場に馴染めていない」
「利用者さんとの関わりに苦戦し、自信をなくしている」
そんな新人を前に、どう支援すべきか悩んだ経験はありませんか?
なかには、半年以上経っても一人訪問に不安が残り、同行が外せないケースもあるでしょう。
訪問看護は暮らしの場で行われるため、病棟とは求められる視点が異なります。
そのため、新人が最初の半年でつまずくのは、珍しいことではありません。管理者や教育担当が適切にフォローし、乗り越えられるよう支援することが大切です。
そこで本記事では、新人訪問看護師がつまずきやすい5つのポイントを管理者の視点で整理します。
また離職を防ぎ、現場で自信をもって活躍できるようになるための支援策を、具体例とともに紹介します。
- 新人が伸び悩んでいる
- 教育体制を見直したい
- 定着率を高めたい
そんな思いをお持ちの管理者の方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
訪問看護で最初につまずきやすい5つのポイント
訪問看護の役割や判断基準は、病棟とは大きく異なります。そのため、訪問看護へ転職して半年間は、経験値にかかわらず、ほとんどの新人が壁にぶつかります。
特に、新人訪問看護師がつまずきやすいポイントは次の5つです。
- 情報が少なく判断に困る:検査値・経過情報がそろわず、判断に迷う
- 拒否される問題:利用者さんとの距離感がつかみにくい
- 関係者との連携トラブル:ケアマネ・ヘルパーなど他職種との連携に慣れていない
- 処置屋止まり問題:生活全体を捉えられず、処置中心の関わりになってしまう
- 看護業務だけをやりたい問題:訪問前後の調整業務に意欲が湧かない
上記の問題は、ほぼすべての新人が通る成長のプロセスです。
これらを管理者が適切に支援しないまま放置すると、離職や早期挫折につながる恐れもあります。新人が育ちやすく、辞めにくい組織をつくるためには、管理者がどのように新人と関わるかが重要です。
株式会社UPDATEでは、訪問看護管理者向けに、訪問看護に特化した『基礎から学ぶ組織マネジメント研修』を開催しています。
新人がやりがいを感じられ、定着しやすい組織をつくるヒントを得たい方は、ぜひ以下のバナーから詳細をご確認ください。

新人訪問看護師の壁①情報が少なく判断に困る
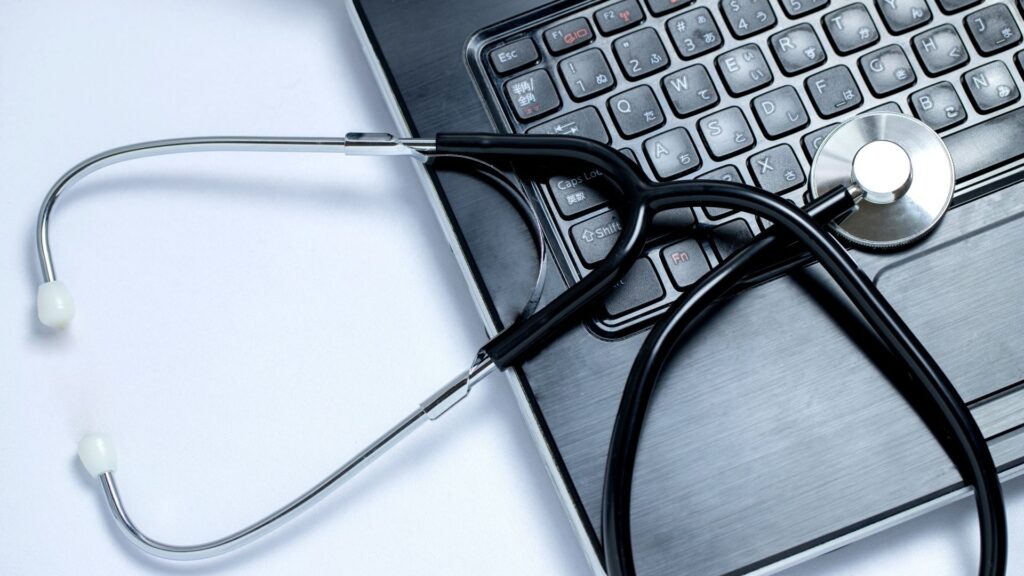
病棟では検査値や記録がそろっているため、判断に必要な材料を容易に確認できます。
一方、訪問看護は情報が不足した状態から観察を始めることが前提のため、新人ほど強い不安を抱えやすいでしょう。
管理者がこのギャップを理解しておくことで、教育のポイントが明確になります。
新人が情報不足でつまずく理由
新人が戸惑う最大の理由は、病棟と訪問看護で「判断材料の集め方」が根本的に異なることです。
病棟ではカルテ・検査値・経過記録がそろい、それをもとに状態を把握できます。
しかし訪問先では、生活環境の中から必要な情報を自ら拾い上げ、統合して判断する必要があります。
このギャップによって、
- 何から観察すれば良いのかわからない
- 数値がない状態で判断することに不安を感じる
- 「基準がつかめないまま訪問する」ことにストレスを抱える
などの状況が生まれます。
管理者が促すべき考え方:生活の変化を捉える
情報が少ない状況は、訪問看護ではむしろ成長を促す重要な学びの機会になります。
「昨日との違い」「普段の様子からのズレ」を捉えることがアセスメントの核心です。この視点を早い段階で身に付けさせることで、新人の成長スピードは大きく変わるでしょう。
たとえば、
- いつもなら玄関まで来る利用者さんが来ない
- 表情が普段より固い
- 動作がゆっくりになっている
- 部屋の様子がいつもと違う
などの小さな変化が、体調悪化や生活の困りごとの初期サインになることがあります。
管理者がこうした「生活の観察ポイント」を日頃から言語化し、新人と共有できると、
訪問看護ならではのアセスメント力が育つでしょう。
新人訪問看護師の壁② 距離感がつかめない

訪問看護は人の生活の中に入るため、利用者さんとの距離の取り方が病棟とは大きく異なります。そのため新人は、どこまで踏み込んでいいのかわからず、関わり方に戸惑いを覚えることもあります。
そして利用者から少しでも拒否的な態度をとられると、自分が受け入れられていないように感じ、必要以上に落ち込んでしまうこともあります。
新人が距離感につまずく理由
訪問では利用者さんの生活の場に入ります。その際、看護師の言動が、利用者さんにとって生活に踏み込みすぎていると思われることもあります。
特に新人訪問看護師ほど、正しい看護をすべきであると考え、意図せず利用者さんの生活リズムを乱してしまいやすい点に注意が必要です。
具体的には、
- 食事制限を厳しく伝えてしまう
- 家の物を断りなく使ってしまい元に戻さない
などの例が挙げられます。
利用者さんとの心地よい距離感を保つには、食事制限を一方的に伝えるより、無理なく続けられる方法を一緒に考えるのが望ましいでしょう。
また家の物に触れるときは必ず一声かけ、きちんと元の場所に戻すことで、利用者さんが安心してケアを受けられます。
管理者が促すべき考え方:徐々に距離感をつかむ
距離感をつかめない問題は、新人がまだ生活の場での関わり方に慣れていないだけの話です。過度に落ち込む必要はなく、誰もが通る段階だと管理者が伝えることが、新人の安心につながります。
新人には、「焦らず、まずは信頼の土台を作ること」「拒否は必ずしも個人への否定ではないこと」を丁寧に伝える必要があります。
同行訪問の際には、指導者が自然な声かけや立ち位置を見せるだけでも、新人にとって貴重な学びとなります。
「しっかり組織マネジメントの基礎を学びたい!」という方向けに、UPDATEでは『訪問看護特化の組織マネジメント基礎講座』を開催しています。無料の体験クラス動画もご用意してますので、興味のある方はぜひご覧ください。
新人訪問看護師の壁③他職種との連携に戸惑う

訪問看護では、ケアマネジャー・ヘルパー・リハ職など、さまざまな職種と連携しながら利用者を支えます。
病棟とは連携の仕組みもコミュニケーションの前提も異なるため、多くの新人は「どう関わればよいか」が分からず戸惑います。
小さなすれ違いが積み重なると、自信を失ったり、関係づくりに苦手意識を持ってしまったりすることもあるでしょう。
そのため管理者は、新人がつまずきやすい背景を理解し、適切にフォローできる体制を整えることが求められます。
新人が連携につまずく理由
新人が多職種連携で壁を感じる背景には、それぞれの専門職が大切にしている視点が異なるという構造があります。
病棟では看護師同士で価値観や優先順位がそろっています。
一方で訪問看護では、生活全体を調整するケアマネ・日常動作を支えるヘルパー・身体機能を見るリハ職など、それぞれが違う軸で利用者を支えています。
この視点の違いを理解せず、看護師としての正解だけを伝えてしまうと、意図が正しく届かなかったり、押しつけに感じられたりします。
管理者が促すべき考え方:情報共有を工夫する
多職種と良い関係を築くためには、相手がその後どう動くかを想像しながら情報を共有することが重要です。
家族やヘルパー、ケアマネは、看護師よりも長く利用者さんと関わるため、その前提を踏まえた伝え方が求められます。
たとえば、訪問看護でよく活用される『連絡ノート』に、連絡事項を端的に書くだけでなく、少しの工夫を加えてみましょう。
簡単なメモやチェックリストを加えたり、専門用語の補足説明をしたりすると、読んだ相手が「次に何をすればいいか」が分かりやすくなります。
また、他職種と対面で話せる機会を大切にするよう促すことも効果的です。直接顔を合わせることで、互いの背景や意図が伝わりやすくなります。
連携の目的は、情報を渡すことではなく、自分がいない時にも相手が動きやすい状態をつくることです。
この視点を新人が持てるようになれば、多職種との連携はもっと円滑になり、訪問看護師としての自信にもつながるでしょう。
新人訪問看護師の壁④生活者の視点が抜けている

病棟経験が長い新人ほど、処置こそが看護という意識が抜けにくい傾向があります。
つい手技に意識が偏ってしまい、訪問看護で求められる生活全体を支える視点とのギャップに戸惑うことも珍しくありません。
訪問看護では、単に処置をして帰るのではなく、次の訪問までの時間をどう支えるかの視点が欠かせません。生活者としての視点が不足すると、訪問が単発の作業になり、やりがいも感じにくくなります。
新人が処置中心になってしまう理由
病棟では、点滴・創処置・清潔ケアなどの医療行為が看護の中心であることから、生活環境の評価は優先度が下がってしまう傾向にあります。
そのため訪問看護に転職すると、環境や生活の背景に目を向けるという発想への切り替えがうまくできない場合があります。「処置を適切に終えた=訪問看護業務が完了した」と捉えてしまう新人は少なくありません。
管理者が促すべき考え方:生活者としての視点をもつ
まず、処置そのものは目的ではなく、生活を支えるための手段だと新人に伝えることで、理解が深まりやすくなります。
たとえば褥瘡処置なら、処置をして帰るだけではなく、生活に隠れている褥瘡発生原因を一緒に考えることが重要です。寝る姿勢やクッションの使い方や食事の量、服薬状況など、生活全体に原因が隠れていることも多いためです。
指導者は、新人との同行訪問時に次のことを問いかけるとよいでしょう。
「この処置の背景に、生活面で気になることはある?」
「家族が症状悪化に気づいてもらえるよう、伝えるべきことは?」
「自分がいない間に注意してほしいポイントを他職種にどう伝える?」
これらの問いかけにより、処置中心の視野から生活全体へ、新人の意識を広げるサポートができます。利用者さんが生活者であるという視点をもち、処置という点ではなく、看護という面で支えるという意識をもつことが重要です。
新人訪問看護師の壁⑤訪問業務以外に意欲が湧かない

新人の多くは「看護がしたい」という思いが強く、記録・連絡・調整などの訪問以外の業務に抵抗感を抱きやすくなります。
業務量の見通しが立たないことや、優先順位の判断に慣れていないことが負担となり、気持ちが落ち込んでしまうケースもあります。
訪問自体は順調でも、周辺業務でつまずき、全体として自信をなくしてしまう新人も少なくありません。
管理者は、この業務構造の違いが新人の不安を生みやすいことを把握し、丁寧なサポートを行うことが大切です。
新人が調整業務につまずく理由
病棟では、医療者同士が同じ場所にいるため、調整や記録はチームの中で自然と分散され、個人の判断負担は大きくありません。
一方訪問看護では、訪問計画・記録・連携・スケジュール管理など、一つひとつの業務を自分で組み立て完結させる必要があります。
そのため新人は
- どこから手をつけていいか分からない
- 時間内に終わらない
- 訪問以外の仕事が多くて気が重い
と感じてしまうケースがあります。
管理者が促すべき考え方:調整も看護の一部である
調整業務や書類仕事は、訪問看護の質を左右する大切な役割です。このことを新人に伝えると、訪問業務以外の仕事への捉え方が大きく変わるでしょう。
正確な記録があれば他職種との連携がスムーズになり、早めの情報共有が利用者の生活の安定につながることも実感しやすくなります。
また、管理者が一緒に優先順位を整理したり、業務の流れを視覚化したりするだけで、新人の負担は格段に軽くなります。
周辺業務も「生活全体を支えるために行う仕事なのだ」と実感できたとき、抵抗感は薄れ、やりがいにもつながるでしょう。
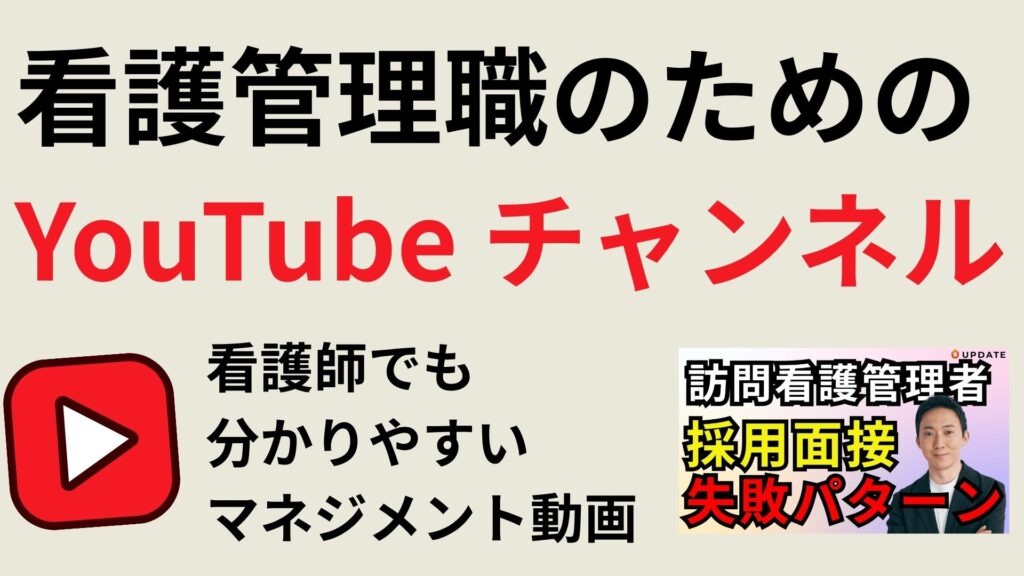
まとめ:新人のつまずきは管理者の関わり方で大きく変わる
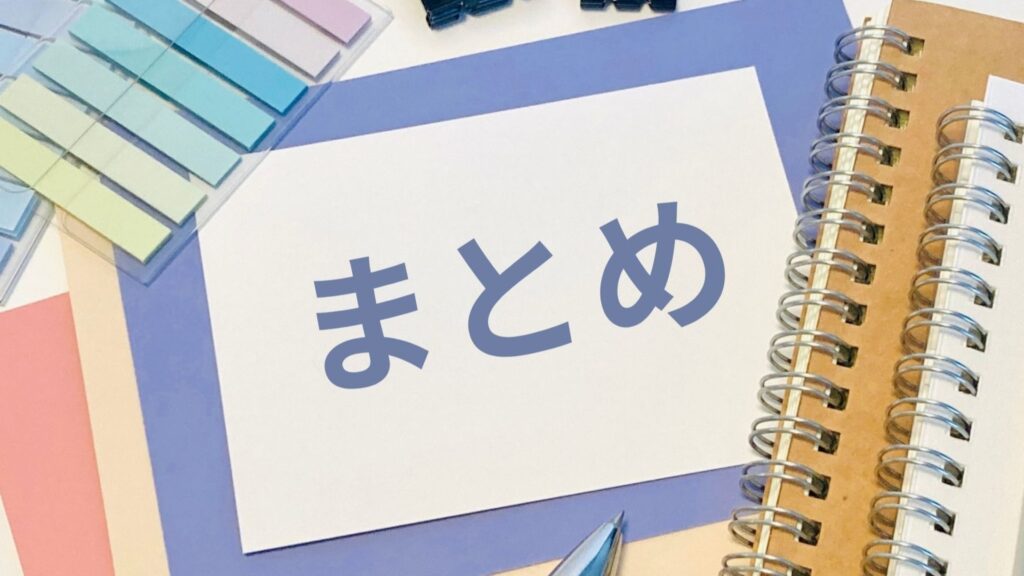
新人訪問看護師が感じる戸惑いや不安は、決して本人の能力の問題ではなく、病棟との環境差から生まれる自然な反応です。
情報の少なさに迷い、利用者との距離感に悩む。そして多職種連携でつまずき、生活者視点とのギャップに戸惑い、訪問外業務に負担を感じる・・・。
これらは、多くの新人が必ず経験するプロセスであり、適切なフォローがあれば確実に乗り越えられます。
そして、新人がこれらの壁を乗り越えるスピードや自信の育ち方は、管理者の関わり方によって大きく変わります。
新人の視点を理解し、適切な声かけや教育のポイントを押さえれば、現場の雰囲気が良くなり、定着率向上にも役立つでしょう。
一方で、
「問題の原因は理解できたけど、どう仕組み化すればいいのか分からない」
「自力では限界を感じている」
と一人で悩む管理者の方もいらっしゃるかもしれません。
そんなあなたにこそ、組織全体で新人を育てる仕組みづくりが必要です。
訪問看護に特化したマネジメントを学ぶことで、現場の課題がひとつひとつ整理され、新人からベテラン、管理者まで全員が安心して働ける環境へと変わっていきます。
そこで株式会社UPDATEでは、
新人が育ちやすく、辞めにくい組織をつくるための『基礎から学ぶ組織マネジメント研修』を開催しています。
管理者の判断軸がクリアになり、職場のコミュニケーションが整うため、あなた自身も孤独から解放されるでしょう。
「管理者としてやりがいを感じたい」
「教育体制を整えて、スタッフを定着させたい」
「ステーションの全員が安心して働ける組織にしたい」
そんなあなたの願いを、一緒に仕組みで解決していきます。ぜひ以下のバナーより、詳細をご覧ください。
今なら1万円相当の無料体験講座もプレゼントしています。この機会にあなたもぜひ、以下のリンクよりお受け取りください。

サービス利用者の声をご紹介します!