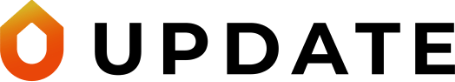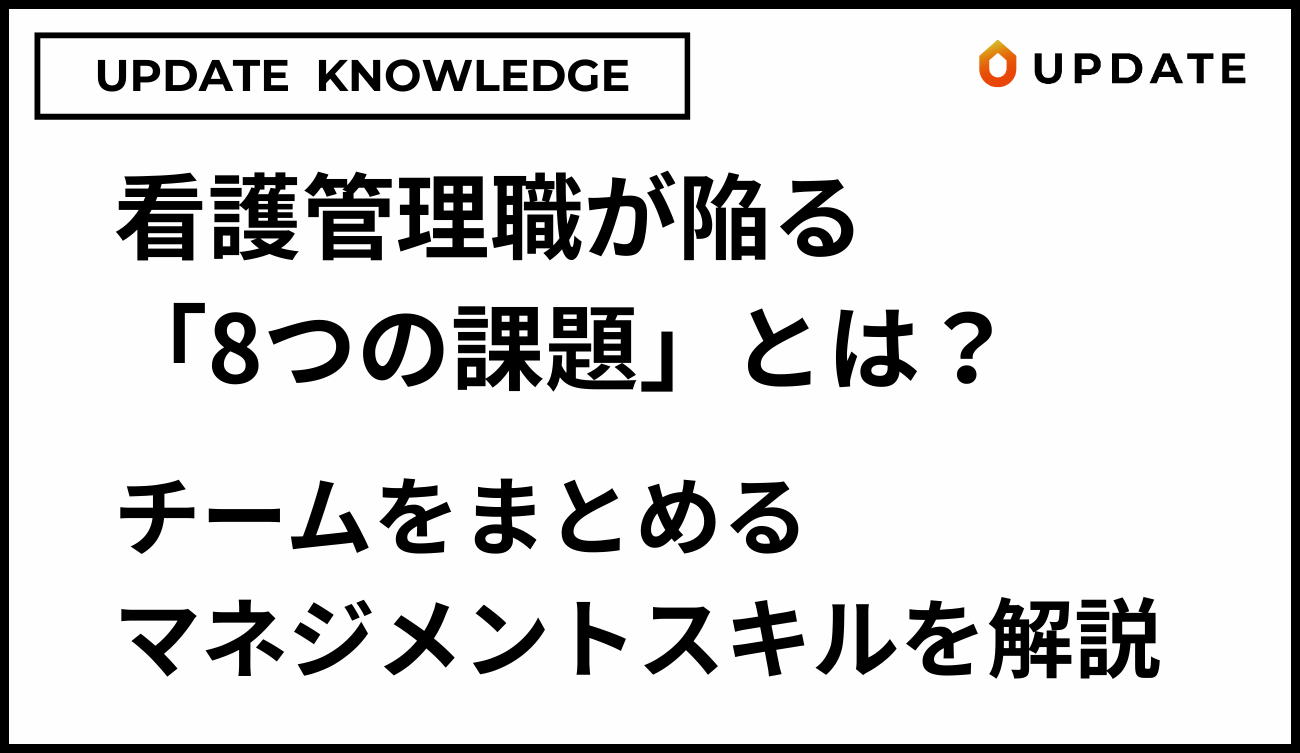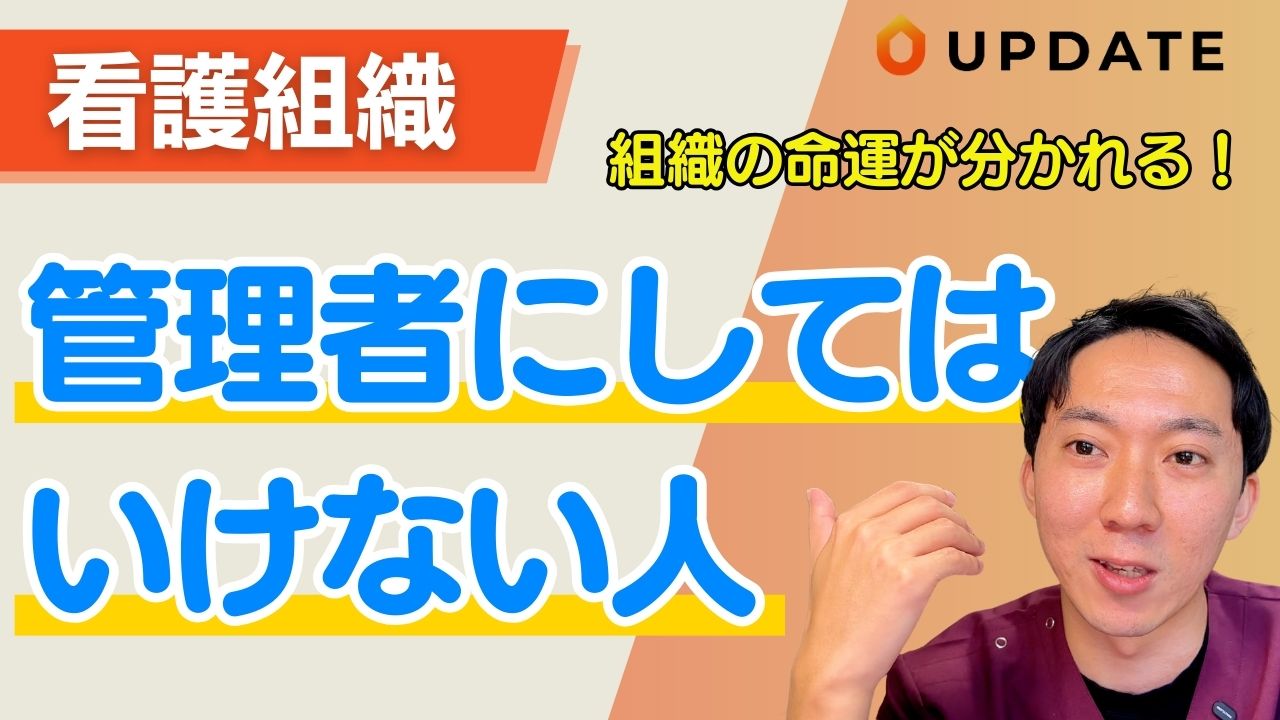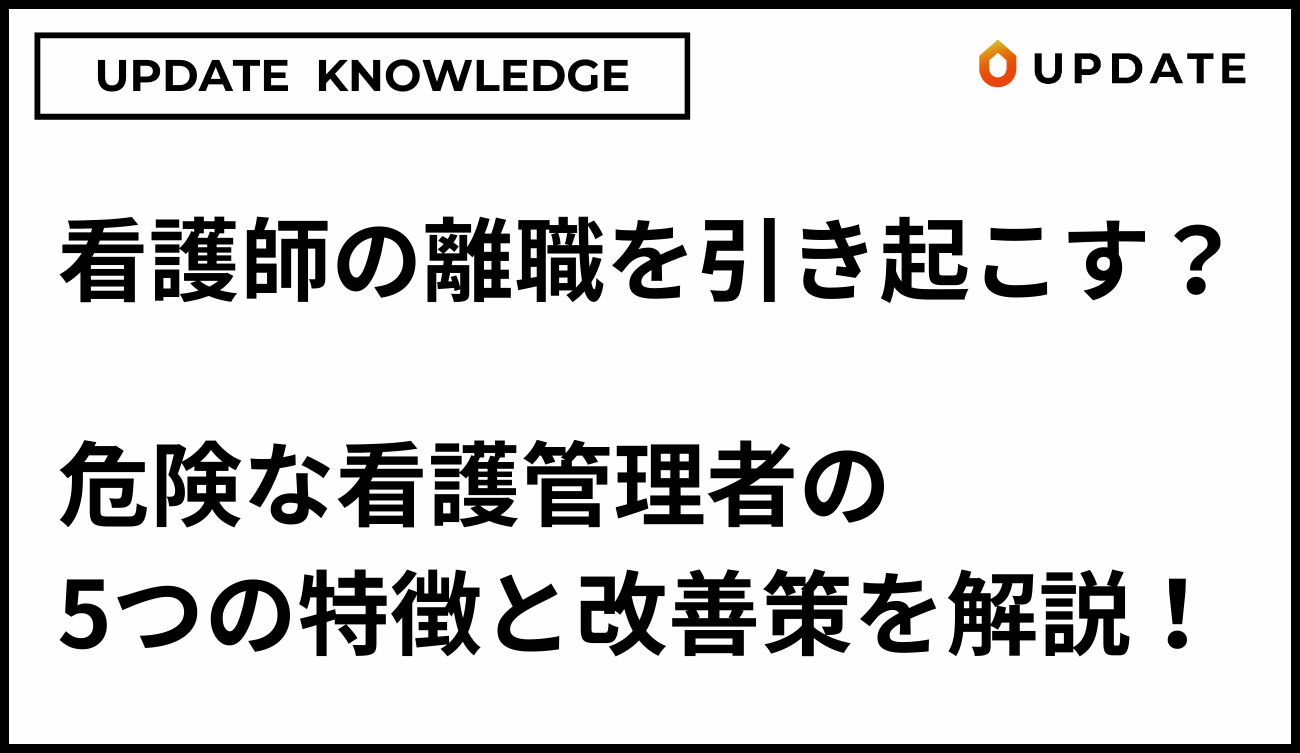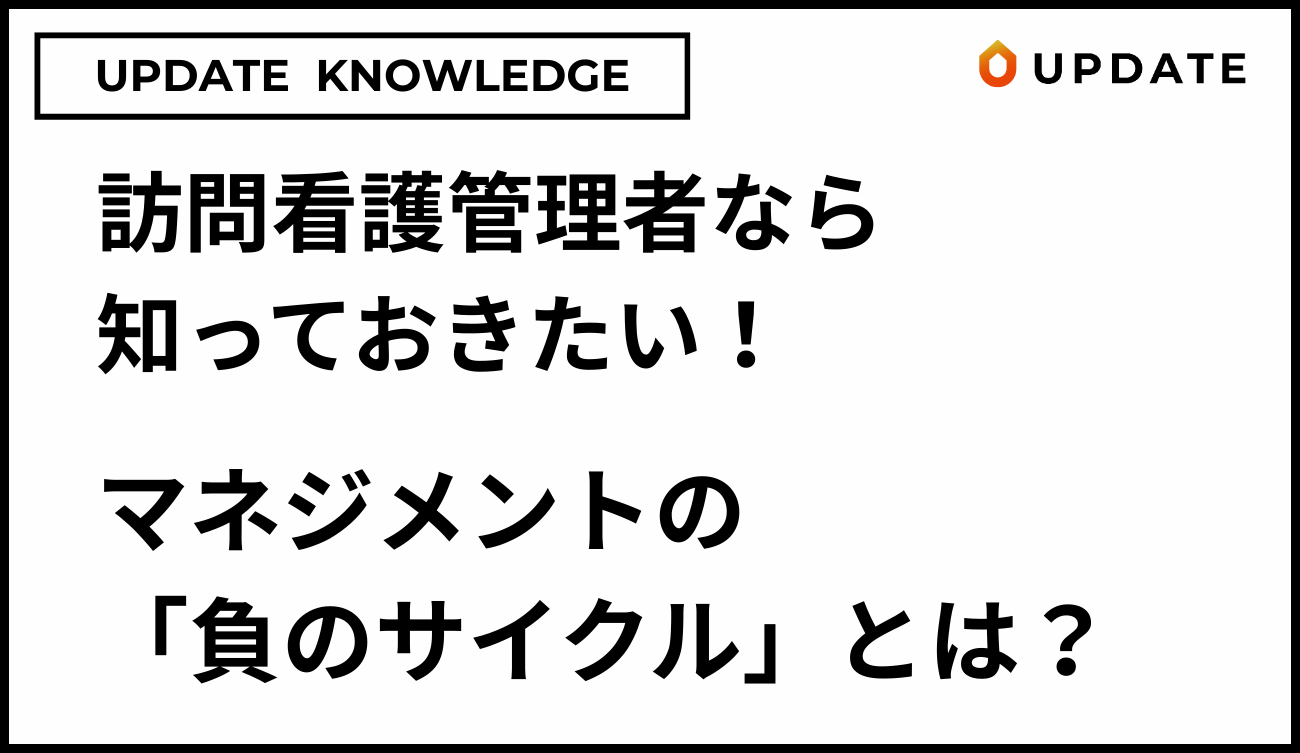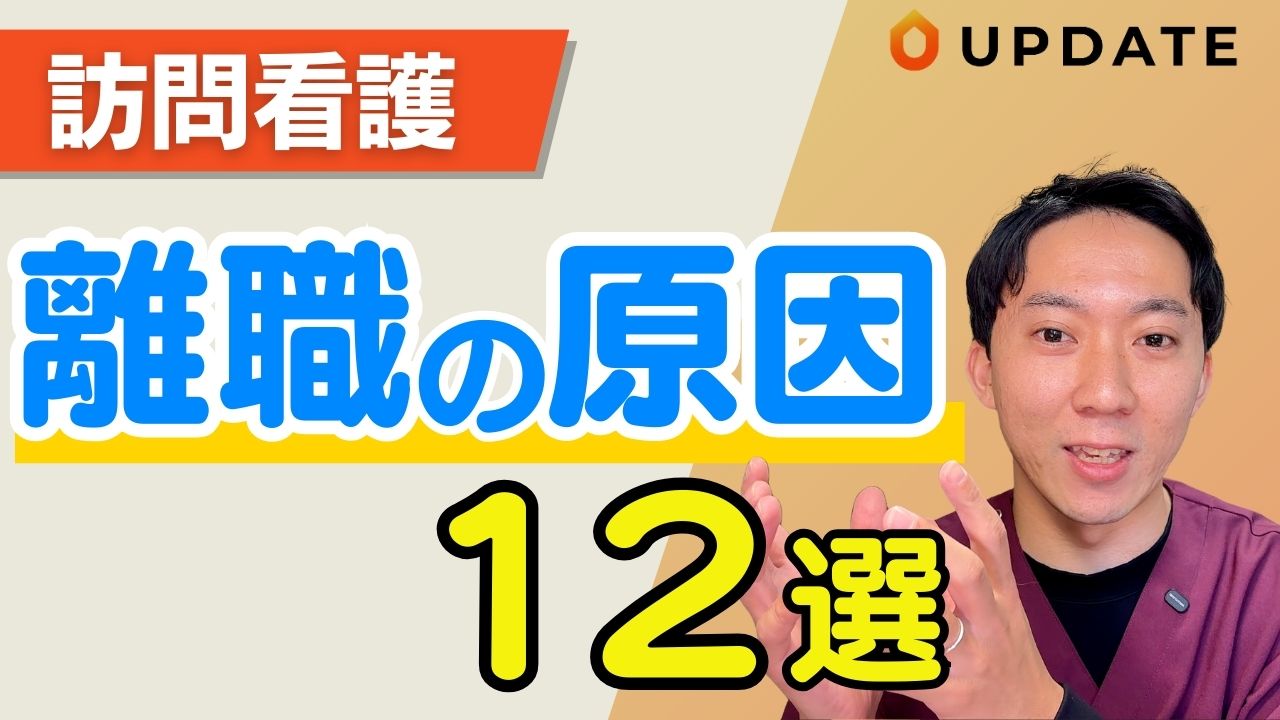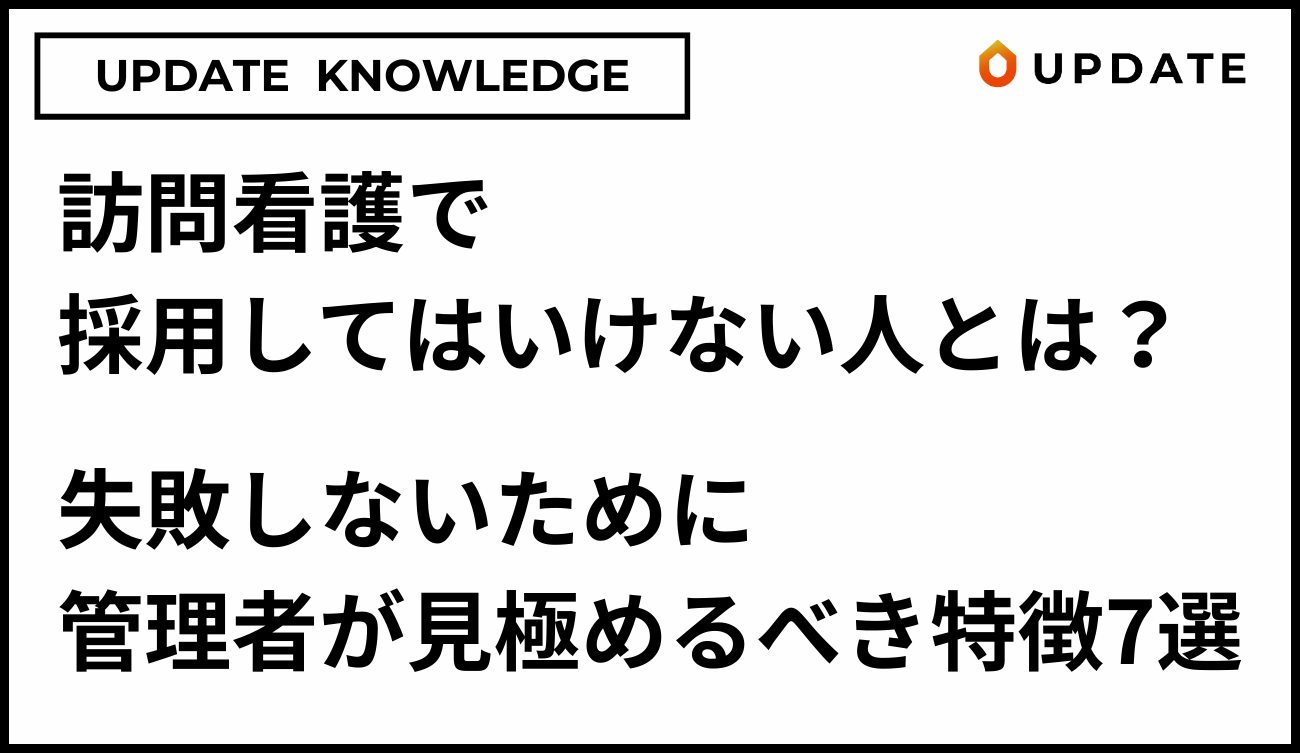訪問看護ステーションでのコミュニケーションを改善するには?管理者に必要な4つの思考法を徹底解説!
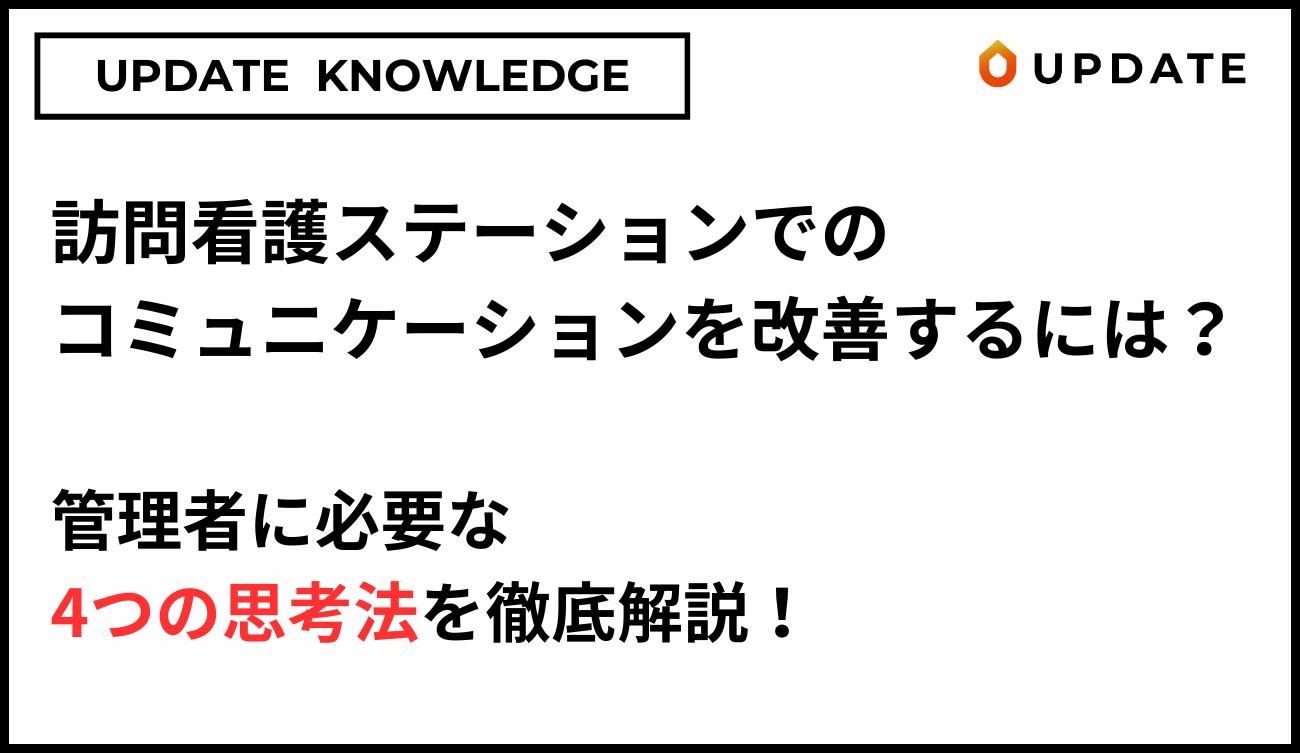
訪問看護の現場では、コミュニケーションに悩む場面が少なくありません。
スタッフの誤解やすれ違いが積み重なれば、組織全体に不信感が広がり、離職やチームの機能低下につながる場合もあります。
そこで本記事では、訪問看護ステーションでよくあるコミュニケーション問題や、管理者が意識すべきコミュニケーション改善のための4つの思考法を解説します。
この記事を読めば、今日から現場のコミュニケーションを改善するための考え方や、具体的な行動がわかるでしょう。
訪問看護事業所内でのコミュニケーションに悩む管理者の方は、ぜひ最後までご覧ください。
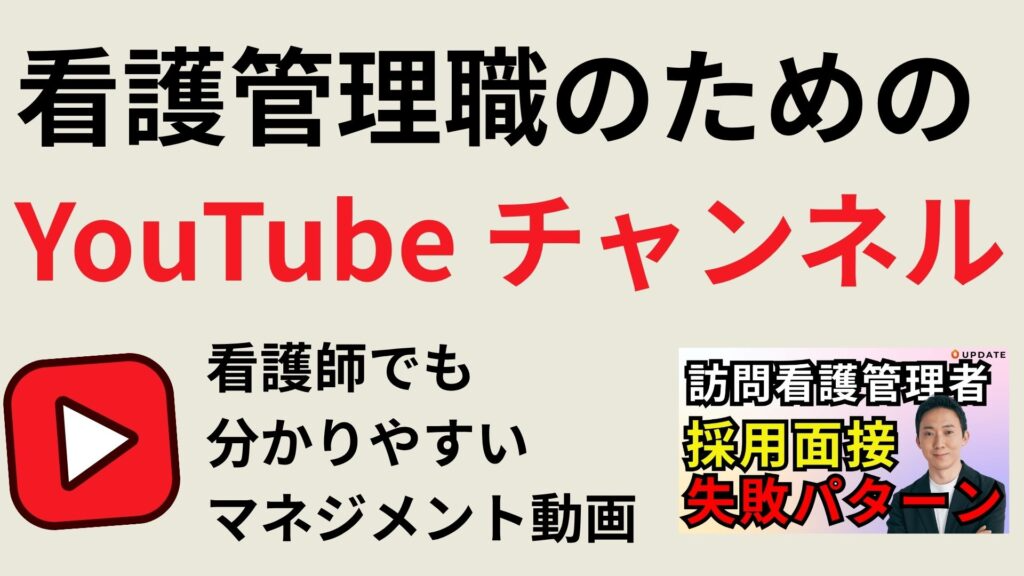
目次
訪問看護で管理者が抱えるコミュニケーション問題
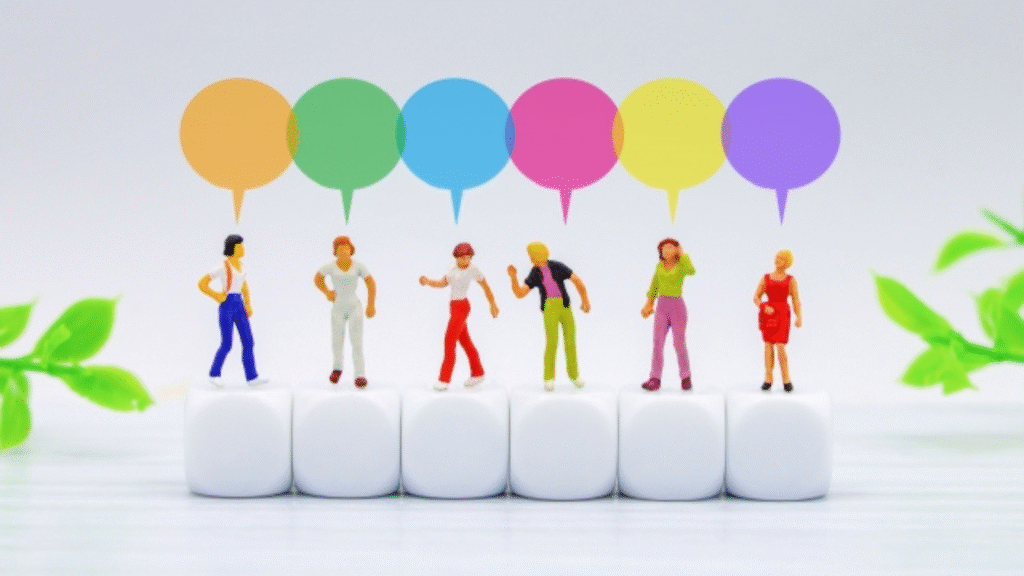
訪問看護ステーションの管理者にとって、コミュニケーションの問題は日常的に直面する大きな課題です。
利用者宅での業務が中心となる訪問看護では、スタッフ同士が常に顔を合わせて仕事をしているわけではありません。
ちょっとした行き違いや、伝えたつもりの一言が、誤解や摩擦を生む可能性があることに注意が必要です。
特に、管理者は組織全体を見ながら情報を共有したり、方向性を示したりする役割を担っています。
スタッフとのコミュニケーションが噛み合わないと、チーム内の動きがバラバラになり、現場の混乱につながる恐れがあります。
よくある現場でのコミュニケーションの問題は、以下のとおりです。
- 「伝えたつもり」が誤解され、指示が正しく届かない
- 会議が漠然として終わり、課題が前に進まない
- スタッフ同士が衝突し、関係性が不健全になる
一見すると小さな行き違いに見えますが、積み重なれば業務効率や職場の雰囲気に大きな影響を与える可能性があります。
訪問看護のコミュニケーション問題を放置すると?
チームにおけるコミュニケーション問題を「少しの誤解だから大丈夫」「自然に解決するだろう」と放置してしまうと、問題はどんどん深刻化してしまう点に注意が必要です。
コミュニケーションのズレは、人間関係の不信感につながり、放っておくと組織全体が悪循環にはまりこんでしまいます。具体的には、以下のような状態を生むリスクがあります。
- 組織や管理者への信頼が薄れ、頼られなくなる
- 批判的・他責的な態度が常態化する
- スタッフの不仲や不信感が、離職につながる
例えば、管理者の指示が曖昧で伝わらないと、スタッフは「自分たちで判断しよう」と動き始めます。
しかし各自が勝手に判断すれば、方向性がバラバラになり、責任の所在もあいまいになってしまうかもしれません。
すると、「誰が悪いのか?」という非難が始まり、チームはどんどん分断されていきます。
つまり、単なる会話の食い違いが、最終的にはステーション運営そのものを揺るがすケースも少なくありません。
そのため、早い段階で改善策を講じる必要があります。これらの問題を解決する糸口として、訪問看護に特化した組織マネジメントを学ぶのがおすすめです。
「しっかり組織マネジメントの基礎を学びたい!」という方向けに、UPDATEでは『訪問看護特化の組織マネジメント基礎講座』を開催しています。無料の体験クラス動画もご用意してますので、興味のある方はぜひご覧ください。
無料体験クラス「組織に合わない言動を放置する悪影響と、効果的なフィードバック」
訪問看護のコミュニケーション問題の4つの原因

訪問看護の現場で発生するコミュニケーションの問題の原因は、次の4つに整理できます。
- 話すべきことの認識がズレる
- 隠れた前提の違いに気づかない
- 論点が整理されないまま議論が進む
- 相手視点を欠いた伝え方をしてしまう
いずれも普段の現場でよくあることですが、繰り返されるうちにスタッフのやる気を削ぎ、管理者への信頼を損なう可能性があります。この4つを意識して改善できれば、組織全体の会話力は格段に向上するでしょう。
ここで忘れてはならないのは、コミュニケーションの問題は一方だけに原因があるわけではないことです。
相手を批判的に捉えるのではなく、「自分の伝え方や聞き方に、改善の余地はないか?」と振り返る姿勢が欠かせません。
管理者・経営者はこうした前提を踏まえたうえで、組織の目標達成に向けてスタッフ全体のコミュニケーションを活性化していく責任があります。
しかし多くの管理者は、問題をどうにかしたいと思いつつも、解決するための糸口がみつからずに悩んでいるのではないでしょうか?
そのような訪問看護の管理者・経営者に向け、株式会社UPDATEでは【訪問看護特化】基礎から学ぶ組織マネジメント研修を開催しています。
訪問看護に特化した組織マネジメント研修を受講すると、次の変化が期待できます。
- クレームや連携ミスが減り、落ち着いた職場環境になる
- 人材が定着し、「働き続けたい」と思える組織に変わる
- 管理者が孤独から解放され、判断に自信がもてる
今なら、無料体験講座や特典もご用意しています。
事業所のコミュニケーション問題やマネジメント課題をクリアし、頼られる管理者になりたいとお考えの方は、ぜひ今すぐバナーをクリックしてお受け取りください。

訪問看護のコミュニケーションを改善する4つの思考法

続いて、先ほどの4つの問題を解決するための思考法を解説します。
それぞれ、現場で起こりがちな失敗パターンと、現場でできる改善アクションに分けて具体的にご紹介します。
ご自身の組織の状況と、照らし合わせながらご覧ください。
思考法1. 話すべきことのズレを意識する
訪問看護の現場でよくあるのが、会議や打ち合わせで真剣に話しているのに、話がかみ合わないという状況です。
管理者は「教育方針を決めたい」と思っていても、スタッフは新人のフォロー体制を話したり、ケア提供の課題改善を語ったりと、それぞれが別のテーマを口にすることがあります。
このように、話すべきことの認識がズレたまま会議が進むと、結論が出ないまま時間だけが過ぎてしまいます。さらに、結局誰も何を決めたのかわからず、会議そのものへの不満や不信感が生じてしまうかもしれません。
現場で起こりがちな失敗パターンとして、以下が挙げられます。
- 議題が曖昧で各自が別のテーマを話す
- 決めることが不明確で会議が空回りする
- 議事録や合意形成の仕組みが弱い
これらの対策として有効なアクションは、以下のとおりです。
- 会議冒頭に「話すこと・決めること」について共有する
- ホワイトボードや画面共有で、議題を可視化する
- BIG WORDを具体化して、曖昧さをなくす
会議のスタート時点で「何を話し、何を決めるのか」を明確にすることが、ズレを防ぎ、生産的な議論につながります。
思考法2. 前提のズレを意識する
同じ言葉を使っていても、スタッフによって受け止め方が異なることがあります。
これは、立場や経験の違いによって隠れた前提がずれているからです。
個々の経験や立場で前提が違うことや、同じ言葉でも解釈が異なることを認識し、前提を共有してから議論を進める必要があります。
そのためには、以下のアクションを取り入れるとよいでしょう。
- 「なぜそう思う?」と背景を聞く習慣をもつ
- 経験や立場を翻訳してチームに共有する
- 前提を可視化し、異なる意見を理解する
前提の違いに気づけると、相手の意見の背景が理解でき、衝突ではなく協働につなげることができます。
思考法3. 論点のズレを意識する
議論がかみ合わない理由のひとつは、論点が整理されないまま進んでしまうことです。
現場で怒りがちなパターンとして、論点がズレたまま話し合いを進めてしまい、論点が網羅できないケースがあります。
また、メンバー間の主張がぶつかると、個人の主張が強くなる傾向があります。
それぞれの望む結論に向かってメリットやデメリットを主張してしまったり、自分の意見をより強く主張してしまったりするなど、論点の偏りが生じる場合もあるでしょう。
これらを予防するために、以下の3つを意識してみましょう。
- 自分と反対の立場を想定して考える
- 「相手の立場なら何が気になるか?」を意識する
- 論点を広げて考える時間と、結論を導く時間を分けて整理する
論点を整理しながら議論することで、参加者全員が納得できる結論に近づきやすくなります。
思考法4. 相手視点を意識する
管理者として伝えたいことを意識していても、それを相手視点で伝えられなければ、誤解や不満を生む場合がある点に注意が必要です。
現場で起こりがちな失敗パターンとして、相手の知識や立場を考えず、相手の知りたい順序を無視して説明してしまう場合が考えられます。
また、自分の結論ありきで話を進めてしまい、建設的な議論ができないパターンもよくあります。
以下の行動を取り入れると、相手視点を意識したコミュニケーションになるでしょう。
- 相手が理解しやすい順序に並べ替える
- 立場ごと(上司・同僚・部下)に伝え方を変える
- 相手の関心や制約を踏まえて整理する
相手の立場に寄り添った伝え方をすれば、共感や信頼を得ながら円滑にコミュニケーションを取れるでしょう。
まとめ:訪問看護のコミュニケーションは4つの思考法で円滑になる

訪問看護の現場でコミュニケーションを改善するには、以下の4つの思考法を取り入れるとよいでしょう。
- 話すべきことのズレをなくす
- 隠れた前提の違いに気づく
- 論点を整理して進める
- 相手視点で伝える
管理者がこれらを意識して習慣化することで、組織全体の会話力が高まり、課題解決のスピードも飛躍的に上がります。
株式会社UPDATEの【訪問看護特化】基礎から学ぶ組織マネジメント研修では、4つの思考法をさらに掘り下げ、実践的な内容に落とし込んで解説しています。
少人数制の講義では、訪問看護の現場・管理・経営を10年以上経験してきた講師に、現場のお悩みを相談できます。また、同じお悩みを抱えている管理者の方との交流も可能です。
本研修を受講後には、尽きない組織の課題を解決し、頼られる管理者になって、笑顔で活躍できるでしょう。
受講者満足度は94.6%と、高い評価をいただいています!
実際に受講した方からは、
「モヤっとする現場の悩みを解決できた」
「組織の適切な配置や役職採用での注意点がわかった」
「メンバーへのフィードバック方法や関わり方がわかった」
などのお声も多数いただいています。
今なら無料体験講座(約10,000円)や特別プレゼントもご用意しています。ぜひ以下のバナーをクリックしてお受け取りください。
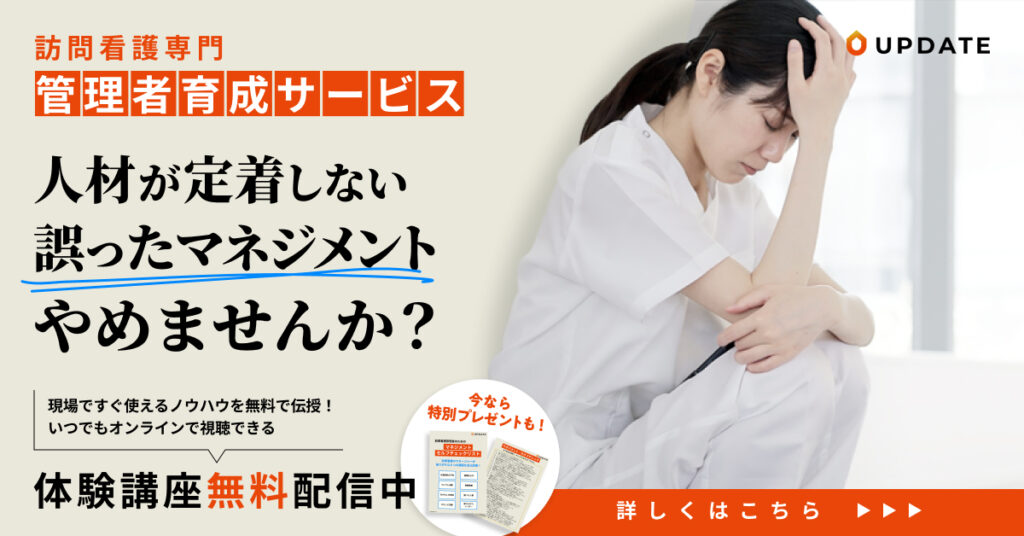
サービス利用者の声をご紹介します!